
なんと!サブリース二重契約の罠
「これで無事に契約完了です。」
ハンコを押し続けて、晴れて2017年6月から大家デビューを果たす。
ハンコを押すまでのあらすじは下記に記載している。
晴れて大家デビュー、気になる収支は?
購入後の収入と支出は下記の通り。
・収入
家賃(サブリース):76,000円
・支出
返済(1.65%金利):71,183円
管理費:8,500
振込手数料:440円
正真正銘、「4,123円」の赤字である。
さらに追加で、年1回の固定資産税「65,400円」が発生する。
結果、年間の収支は単純計算で「114,876円」の赤字である。
※49,476円(4,123円×12か月)+65,400円
「全然儲かってないじゃないか」という声が聞こえてきますがその通りである。
当時、購入を前向きにした魔法の2つの合言葉がある。
それは、「節税」と「生命保険変わり」である。
実はこの言葉は不動産営業の謳い文句でそれぞれ落とし穴がある。
節税の罠
確かに経費などにより赤字になれば還付金を受けられるが、初めから赤字を見越しての購入は投資とは呼べない。
私の場合も上記の赤字と減価償却費を確定申告で計上して2~3万円程度の還付金は得られた。
しかし、投資としては失敗としか言えない。
生命保険変わり
確かに自分自身が死亡した場合、残りのローンが”チャラ”になるというのは生命保険として役立つ。
しかし、条件としては物件を保有している間だけである。
仮に、保有期間中に金利が高騰し、赤字が拡大して物件を保有出来なくなったとする。
すると、売却せざるを得ず、売却額と残りローンを差し引き、赤字の場合補填する必要が生じる。
その後、死亡したとしても全く保険は下りない。
私の場合、保険は未加入のため、売却後は保険は何も下りないというリスクがある。
起死回生の一手
私自身、そんな状況を見て見ぬふりをし続けていたわけではない。
時は2019年末、購入先に電話をかけて「サブリースの解約」を申し出た。
実はサブリース契約というのは、借主である先方にとってかなり有利な契約である。
なぜなら、一般の賃貸契約と同様、借主の権利が保護されるためである。
実際に住んでおらず、転貸している先方が保護される法律に疑問はあるがそれがこの国の決まりである。
契約期間は5年だが途中解約
電話をして当時の担当者に取り繋ぐように依頼した。
しかし、知らぬ間に挨拶もなく営業部から異動していた。
完全なる「売り逃げ」状態である。
仕方なく、別の担当者と話すことに。
私:「5年で契約していたサブリース契約を解約したいのですが。」
先方:「分かりました。途中解約なので月額家賃1ヶ月分が発生しますがよろしいですか?」
なんと、あっさり解約できることに拍子抜けしたが裏があった。
私:「分かりました。76,000円を支払うので請求書をお願いします。」
先方:「承知しました。あと、契約書にも記載ありますが、弊社も転貸主に転貸しております。」
私:「えっ!?どういうことですか? 転貸主が転貸主に転貸ですか?」
先方:「そうです。弊社も○○社とサブリース契約を結んでいます。そちらは解除は難しいと考えます。」
完全なる私の負けである。
先方の戦略かもしれないが、私自身、契約書を読んでいた時にそこまで入念に確認出来ていなかった。当時、いくつか読んでいた本にもそんなリスクの記載はなかった。
サブリース契約を一つ解除はしたが。。。
とりあえず、先方とは話をつけて、一つ目のサブリース契約は解除した。
結果、家賃は86,000万円にアップして、収支は「4,798円」の黒字転換。
収支は下記の通り。
・収入
家賃(サブリース):86,000円
・支出
返済(1.73%にアップ):72,042円
管理費:8,500
振込手数料:660円
難攻不落のサブリース契約
たまたま空室になった時に、所有物件の賃貸情報をネットで確認すると月額家賃「98,000円」で募集中であった。
実は、新築購入時は月額家賃「91,000円」だった物件が4年経って「7,000円」も賃貸価格が上昇していた。
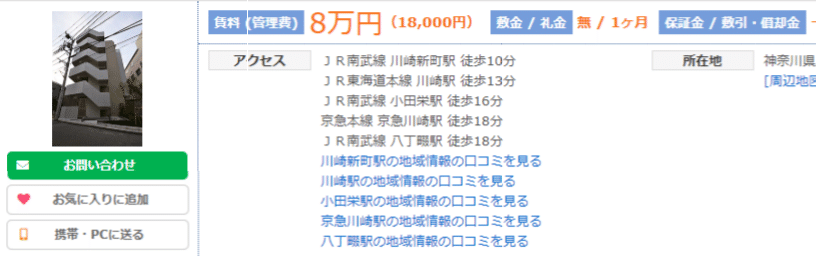
背景として、川崎は開発が進み人気が増えて賃貸需要が増している。
しかし、サブリース契約の下ではそんな恩恵は全く受けられない。
現在、サブリース契約を締結してようやく4年が経過しようとしている。
契約は5年契約であり、半年前に通知すれば解約可能と記載がある。そのため、2021年の終わりには解約通知書を準備する心づもりである。
教訓:これからワンルームマンションを買う方へ
現在、アパートに対する銀行融資はさらに絞られている。
一方で、ワンルームマンションは未だにサラリーマンに対して融資が出やすい環境。
背景としては「耐用年数」が挙げられる。
木造アパートの場合、耐用年数は税法上22年であり、サラリーマンが融資の組める金額内の物件のほとんどが耐用年数を超えている。
一方で、マンションは47年のため、耐用年数以内の物件は市場に溢れている。そのため、ワンルームマンションの方が、耐用年数内であり、融資金額も比較的少ない。
結果、サラリーマンとしての信用も相まって銀行も稟議書を通しやすい。
もし、マンション投資に可能性を感じるのであれば、私のような失敗だけは避けて頂きたい。
特に、収支が赤字になる物件やローン期間が40年を超える物件には手を出さないように注意頂きたい。
現在、45年ローンやガン保障特約など、銀行も追加でサービスを拡充している。罠がどんどん増える現状に危機感を覚える。
それでもアパートを買ったのはなぜ?
次回はそんな失敗を踏まえて、2019年末に購入した1棟アパートについて下記に記載しているので一読頂けると嬉しいです。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
