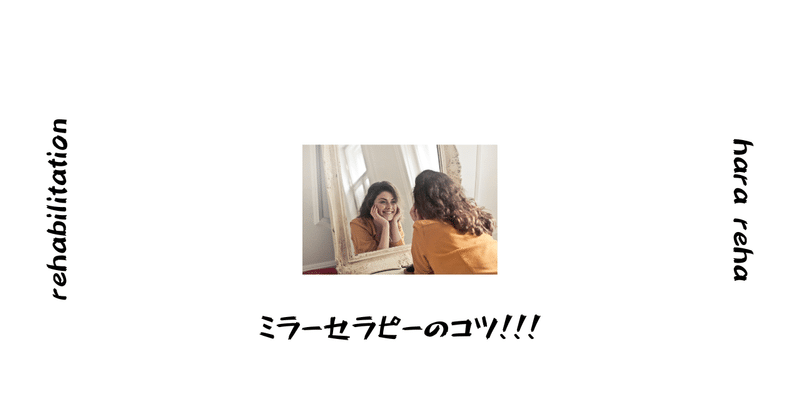
脳卒中後遺症のリハビリ[ミラーセラピーの実践]
お疲れ様です。はらリハです。
本日は…
「脳卒中後遺症者の治療:ミラーセラピー」について解説します。
運動麻痺の改善を目指す、当事者とその家族、セラピストに向けて投稿します。
運動麻痺に対するリハビリ手段の一つとして取り組んでみて下さい。
作業で紡ぐ上肢機能アプローチ | 書籍詳細 | 書籍 | 医学書院 (igaku-shoin.co.jp
脳卒中後の運動機能を改善するためのミラー療法 - PubMed (nih.gov)
脳卒中後のミラー療法を行う方法は?メタアナリシスからの証拠 - PubMed (nih.gov)
重度の上肢機能障害を有する慢性脳卒中生存者におけるミラー療法:ランダム化比較試験-PubMed (nih.gov)
はじめに(ミラーセラピーとは?)
ミラーセラピー:ミラー(鏡)/セラピー(治療法)
言葉の通り、鏡を使った治療をミラーセラピーといいます。
これは、鏡に映る麻痺足の手足が動いていると脳を錯覚させて、運動イメージの促通を狙うことで運動麻痺の改善を目指す治療手段の1つです。
ミラーセラピーの特徴として、
① 重度の麻痺〜軽い麻痺の方まで幅広い症状の方に有効
② 自主トレで活用が可能
があげられます。
脳卒中後遺症のリハビリで重要なのは「質が高く/集中し/感じる」課題を反復練習することで、この要素を兼ね備えているのがミラーセラピーです。
つまり、「やらないよりやった方がいいよ!!!」ってことです。
しかも、世界中で効果のあるリハビリと実証、報告もされているので、ぜひ取り組みましょう。
◯ やるべき良い理由[その1(エビデンスが高い)]
手のリハビリで有名なのは…
□ CI療法
□ 課題指向型訓練
□ 電気刺激
□ ミラーセラピー
であり、この4つは世界的に有効であると報告が多い手のリハビリです。
詳しく説明すると…
[ミラーセラピーのエビデンスについて]
・米国の心臓/脳卒中学会ガイドライン2016年には、エビデンスレベルA(強い推奨)と示している。
・コランレビュー2021年(医学論文のシステムティック・レビューを行う国際的団体のコクランが作成しているもの)では、51〜79歳の脳卒中患者567名に対してミラーセラピーを実施した結果、上肢運動機能、日常生活活動、疼痛、半側空間無視に対して有効な効果があったと報告されている。
竹林祟
◯ やるべき理由 [その2(誰でも出来る/効果がある)]
ミラーセラピーは運動パフォーマンスと運動機能を高める効果が期待できます。
ここの2つの用語は、
☑︎ 運動パフォーマンス
コップを持つ、パソコンやスマホを操作など、実際に何かを行うこと
☑︎ 運動機能
指が伸びる、手首が動く、肘が伸びるなど、単純な関節運動のこと
の意味を持ち、どちらも手の機能を良くするには重要なことです。
【ミラーセラピーは運動機能を向上させる可能性がある】
実際には運動を行わないにも関わらず、運動をイメージすることで皮質脊髄路と呼ばれる脳と手を繋ぐ神経路の反応を増大させることが明らかになっています。
※ 専門的には皮質脊髄路の興奮性の増大といいます。
ミラーセラピーは、鏡を利用して非麻痺側で運動を行い、その際に投影された鏡面上の非麻痺側を観察することで、麻痺側上肢が動いているように感じる錯覚を利用した治療法です。
Ram-achandranらによって、ミラーセラピーは上肢切断者の幻肢痛の治療法として報告され、Altschulerらによって脳卒中患者に応用されて以降、現在まで多くの研究成果により有効性が示されました。
実際には、麻痺側の運動を行わないが、ミラーセラピーを行うことで、
□ MEP amplitudeが増強する(MEP とは脳の運動中枢を直接電気刺激して、手足の筋肉の筋電図を調べて運動機能を調べる方法で、そのMEPの反応する振幅のこと)することや、
□ MEP latemcyが短縮する(流れるまでの時間や潜伏時間のこと)
といった皮質脊髄路の興奮性が変化することも明らかになっている。
発症からの時期としても…
錯覚に個人差はあるも、コクランレビュー(医学論文のシステムティック・レビューを行う国際的団体のコクランが作成しているもの)においても急性期(発症から2週間以内)〜慢性期(6ヶ月以上)にわたる脳卒中患者の運動機能障害に対する有効性が示されています。
ミラーセラピーの実践
◯ 頻度
□ 1回あたり30〜60分以上
□ 週3〜5回
□ 1ヶ月以上
◯ 効果をUPさせるコツ
□ 物品操作をするパターン/しないパターン
物品あり:積み木を積む課題など
→運動パフォーマンスを向上させる効果は有効ではない △
→運動機能を向上させる ◯
物品なし:単純なグーパーや手首の上げ下げなど
→運動パフォーマンスを向上させる効果がある ◯
→運動機能を向上させる ◯
□ 麻痺した手を動かすパターン/動かさないパターン
これは、どちらでも運動パフォーマンスと運動機能に有効である
□ なるべき大きい鏡を使う
まとめると…
・物品なしの運動が望ましい
・麻痺側は動かさなくても、動かしても良い
・鏡は大きい方が望ましい
◯ 作成方法
下記の動画がとてもわかりやすいのでオススメです。
おわりに
ここまで読んで頂きありがとうございます。
はらリハでは、自費リハビリを受けたいが、金銭的に難しい方に向けて、有料の自主トレメニューを販売しています。
根本的な問題は『脳』と捉え、それを解決するに「脳と手足を繋ぐ神経」を回復させる必要があり、そのためには「脳の可塑性」が重要になります。
ここでは…
『脳の可塑性を考慮した自主トレーニングメニュー』を作成しています。
回復を諦めていない方、身体の動きが伸び悩んでいる方、新しいリハビリを体験したい方に向けた記事です。
興味のある方は、たった500円で体験できるので、ぜひご利用下さい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
