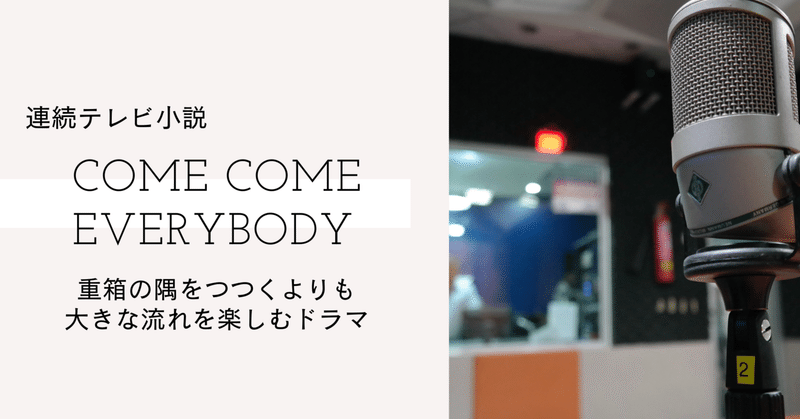
「カムカムエヴリバディ」-重箱の隅をつつくよりも、大きな流れを楽しむドラマ-
三部構成
「カムカムエヴリバディ」が終わりましたね。
戦前から戦後、そして現代と、ヒロインが次々と交代していくというのが目新しい枠組みでした。
そもそも、NHKの朝ドラは、最初の1週、または2週で幼少期を描き、それからは、
1.地方における未成年時代で、ご当地の文物を紹介しつつ、家業(第一次産業が多め?)について描かれて、
2.大人になると上京(または上阪)して、都会で生活、新しい環境での苦労と成長を経由し、
3.なんだかんだで実家(地元)に戻って、これまでのキャリアを活かした地域再生や振興に従事
という流れは、特に現代(戦後)を舞台にすると定番。
上京(or上阪)がないと、どうにもお話が一箇所で留まって変化がないし、また最後の「地元へ帰郷」がないと、NHKの受信料対策という面も多分にあるであろう朝ドラにおいては必要不可欠の展開でして、もし、「都会に出た娘は、地元では仕事もないし、娯楽もないしで、戻って来ませんでした。田舎に残った両親は寂しい老後を過ごしました」という、「東京物語」的なリアリティを、田舎在住の視聴者の多くが望んでいるはずもなく、こういうオチになるのは致し方なし。
(「ひよっこ」では、主人公は帰郷しなかったけど、その代わり父親が戻ってましたね)
通常の朝ドラも、「三部構成」になることは多いわけで、ならば、いっそ主人公を交代してしまおうという発想は、奇手というよりは一つの進化なんでしょう。
脇役な英語
ドラマ放送前に、「ラジオ英会話にまつわる親子三代の物語」と聞いて、「英語を武器にして、その時々、女性が自立していく、または女性がたくましく生きていく物語なんだろうなぁ」と予測していましたが、しかし、実際に始まってみると、なかなか英語は登場せず、朝ドラ的お約束の「家業」、今作に関しては、和菓子屋についてが長らく語られて、不思議な感じというか、既視感というか。
徐々にラジオが登場し、初恋の相手があらわれて、英語に親しむようになるけれども、物語としては、色恋の展開や成就がメイン。
「主人公」と、その「ヤンチャな幼馴染」と、「幼馴染の知的な兄貴」による三角関係って、ベタだなぁ~と思いながらも、盛り上がったのは事実です。
その過程において、「英語」が橋渡しとなるけど、二人を結びつける契機であり、ラブロマンスの小道具に過ぎない。
太平洋戦争が激化し、恋人は戦死、実家は空襲で喪失、辛うじて生き残った父親も病死(衰弱死?)、一週間の放送でバタバタ死んでいき、戦後になって、ようやく英語を活用する場面が出てきて、「英語を使って、自活していくのかな? GHQ占領期で、日常会話が不自由でない程度に英会話が出来るなら、十分働けるだろうなぁ」と思ったら、家業の和菓子屋再建に望みを託すという流れで、またしても英語は背景に押しやられてしまう。
そして、第二部、深津絵里さんが演じる高度経済成長期の「るい編」になると、ラジオは時々活用されるけど、「英語」は出てこなくて、とりあえずジャズ対決。
それが終わったら、土地勘のない大阪から京都に居を移して、回転焼き屋を始める。
またしても、和菓子屋。
三部の、より現代に近い「ひなた編」では、子供時代に、やんわりと英語にまつわる話も出てきたけど、深入りすることなく、主流は時代劇に関するエピソード。
後半、彼氏に振られたあたりから、ようやく英会話に打ち込むようになり、それが彼女の人生を、新しいステージに移行させる。
彼氏の成功を自分の人生と重ね合わせていた受け身な人生から、自らの努力で自己実現を勝ち取るというわけで、この物語において、ようやく「英語」に意味が宿った箇所ですが、その契機が「失恋」というのは、リアルと言えばリアルですが、ちょっと脱力。
そして、ラスト20話くらいで、「英語」「野球」「ジャズ」「和菓子」「時代劇」「ラジオ」といった、三代で登場した要素が、これでもか! と渾然一体、怒涛の展開でした。(それにしても、「るい」の歌唱力というアビリティーは、突然の発動・・・・)
最終的には、「ラジオ」と「英会話」が、メインとなっていましたが、あくまでも、「最終的」。
初代の安子にとっては、英語はラブロマンスの小道具で、それが成就されると、アメリカ逃亡へのジャンプ台。
二代目るいは、母への郷愁のバロメーター。
三代目ひなたで、英語に限らず、外国語習得で得られるであろう職業選択の広がりや、異文化交流が描かれるようになりました。
けれども、「深く掘り下げられていたか?」と問われると、「そうでもないかな」というのが正直な感想です。
三代に渡って
三代に渡って描かれたということで、「あの人が、こんな所で、また出てきた」とか、「あの人の子孫が、こんなことしているんだ」とか、「実は、子供時代に会っていたんだ」といったお約束だけど楽しいギミックも満載で、時に、「うわぁー、ネタ切れだ」と見透かされてしまう朝ドラもある中で、普通なら半年かけて描かれる「女の一生」が、二ヶ月で消化しなくてはいけないので、展開が早くて、一般的には好評だったのかな?
ただ、物語の最大の見せ場だった、親子の別離が、どうにもこうにも強引だったと感じたのは、僕だけ?
そして子煩悩だった初代の安子が、子供を捨てるようにしてアメリカに渡って、その後、没交渉というのも。
その他にも、三代、それぞれ独立性を強めたせいなのか、二代目のるいも、これまで育ててくれた岡山の家を出ると、住所すら教えていなかったというのは、いくらなんでも冷たすぎるのでは?
「それくらい母親との別離がトラウマとして残っていたから」と言えるのかもしれないけど、その旦那、錠一郎は、戦災孤児だったところを拾われて、音楽で食えるくらいの腕前にしてくれたのに、育ての親が亡くなっているのも知らなかった様子。
なんぼズボラでも、年賀状のやり取りくらいしなよ・・・・。(るいと錠一郎が結婚して以降、物語上、クリーニング屋は、まったく登場する機会はなかったけど、どうやらやり取りくらいはあったみたいだし。京都と大阪だから、語られないだけで、行き来があっても当然だよね)
ドラマティックにしよとするばかりに、ちょっと無理があるなぁーと思うところでした。
そしてヒモな錠一郎
「トランペットを吹くこと以外に能がない」と言ってしまえば、それまでだが、そのトランペットが吹けなくなってからのヒモ状態が長く、「イケメン無罪なのか?」と疑問に思いながら見てましたが、「ピアニストになる」と決めたら、けっこうあっさりとプロになれて、オイオイ。
(なら、ピアニストをしながら、トランペットへの復帰も努力してれば、良かったのでは?)
「旦那が外で稼いで、妻は内で家庭を守る」という保守的な価値観へのアンチテーゼとして描かれているわけでもなく、そもそも、旦那は「主夫」としてもダメダメ、お母さんが稼ぎ頭で家事もやっているけど、それに対して、別段、父親は居心地悪そうにしているわけでもなく、母親も現状に満足しており、子供たちも不思議に思っていないという、ほのぼの家族として描かれているわけで、「社会風刺」や「文明批評」、「現代批判」が盛り込まれていれば、即、良作・傑作に結びつくわけではないにしても、せっかく3つの時代の女性を描くというのに、メッセージ性が薄いということろが、朝ドラと言えば朝ドラなんでしょうけどね。
それでも、三代目ひなたについては、結婚・出産はなくて、仕事を持ったバリバリに自立している女性というエンド。
現代的ではあるけれども、ラストシーンでは、「幼少期に出会っていた外人(城田優氏)が、実は、今のビジネスパートナーでした」で、なんとなくラブロマンスを想起させる流れ。
ここらへんを、素直に楽しむのが正解なドラマだったんだなぁと、改めて思う最後でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
