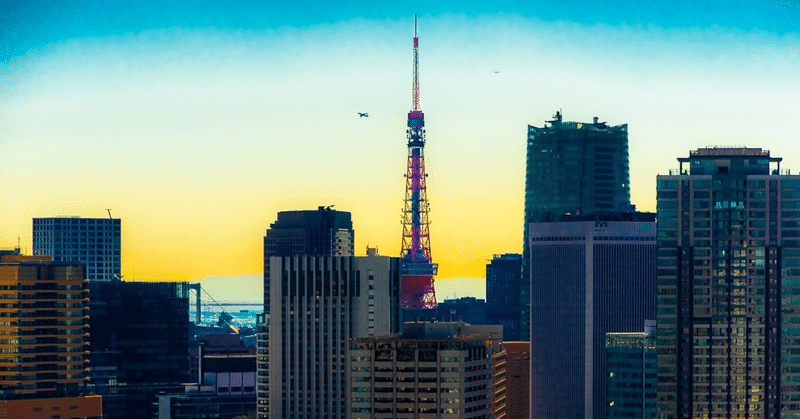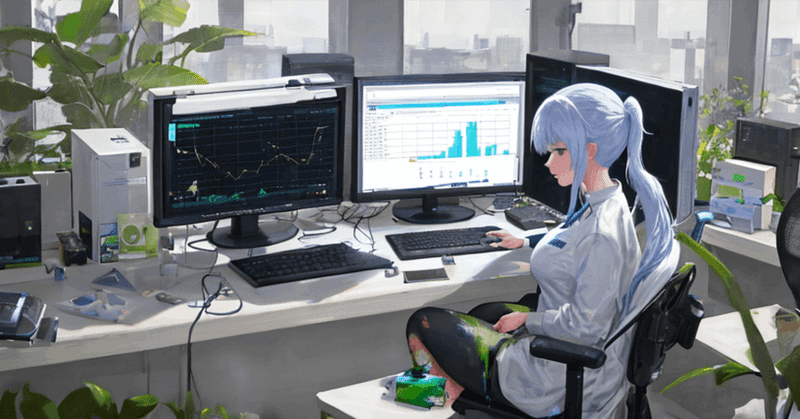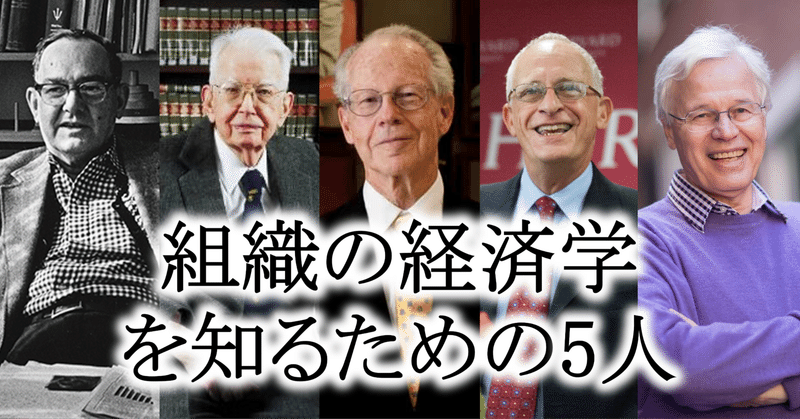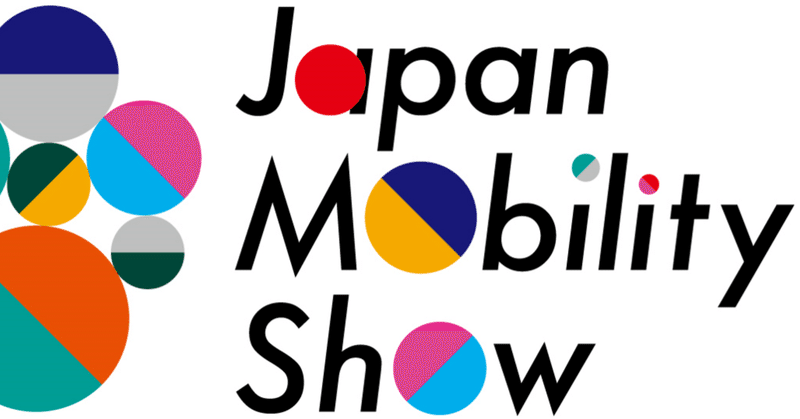#企業

1972年~1985年のCPI、GDP成長率、企業と家計の民間の資金繰りを示す経済指標を確認しスタグフレーションで起きていた現象と足元の経済指標を比較して アメリカ経済はスタグフレーションなんだ!論を検証して行きます。
noteの月額500円の有料読者募集しています。 1記事だと300円~500円が多いですがスタンダードプランだと月額500円で過去の2500以上の記事も含め全てが読めるプランとなるので1記事購入より月額500円のスタンダードプランがお買い得かと思います。 1972年~1985年のCPIの推移、GDP成長率、企業と家計の民間の資金繰りを示す経済指標を確認しスタグフレーションで起きていた現象と足元の経済指標を比較して アメリカ経済はスタグフレーションなんだ!論 を検証して
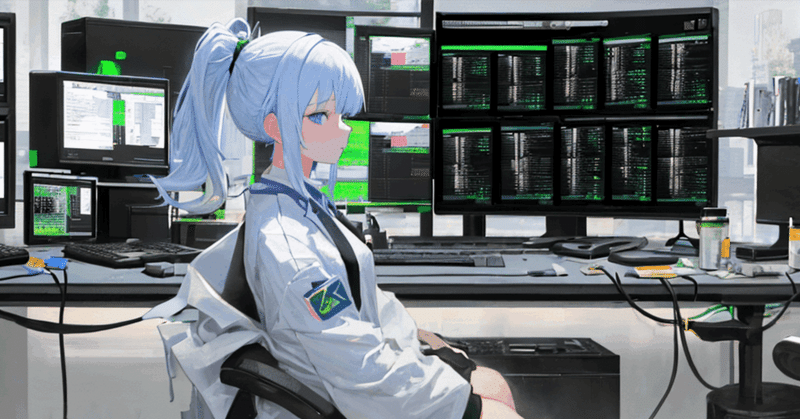
1970年~1985年のスタグフレーション入り時と過去1年の労働生産性、単位労働コスト、実質賃金、労働分配率のデータを比較しアメリカ経済がスタグフレーションに陥るのか?それともスタグフレーションとは真逆に経済成長の加速となっているのか?を分析して行きます。経済学の基本的な内容です。
経済学と金融理論、会計、マーケティング理論の知識をベースに記事を書いてます。 またニューヨークを拠点とした全米で上位1%に評価されているヘッジファンドの分析手法を参考にしてデータ分析し予想してます。 米国の経済学者やヘッジファンドの分析レポートも日々読んで参考にしてます。 noteの月額500円の有料読者募集しています。 1記事だと300円~500円が多いですがスタンダードプランだと月額500円で過去の2500以上の記事も含め全てが読めるプランとなるので1記事購入より
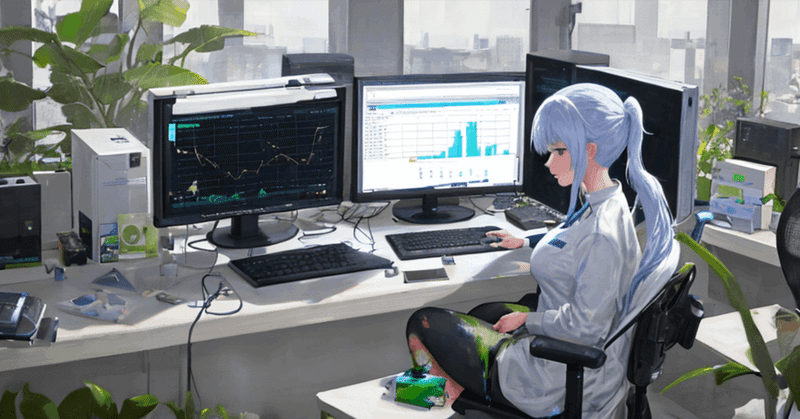
アメリカ企業の総資産、総負債、純資産、株式時価総額に対する負債比率の各データからアメリカ経済の現状と先行きを考えて行きます。アメリカ経済はリセッションに向かっているのか?それとも経済成長の加速に向かっているのか?を見て行きます。
経済学と金融理論、会計、マーケティング理論の知識をベースに記事を書いてます。 またニューヨークを拠点とした全米で上位1%に評価されているヘッジファンドの分析手法を参考にしてデータ分析し予想してます。 米国の経済学者やヘッジファンドの分析レポートも日々読んで参考にしてます。 私の記事はデータ分析と予想が中心で用語解説も交えながら進めてるので初めて株を取引する人でも直ぐに理解出来て予想は参考になると思います。 データの内容は個人投資家がほとんど見たことが無いか見ないデータ

アメリカ経済全体の企業や家計の資金繰りの状況が把握出来るマクロ経済のデータを確認しアメリカ経済の現状と先行きを考えて行きます。過去65年のデータからリセッション入りのタイミングが分かるデータでもあります。
noteの月額500円のスタンダードプランの読者募集しています。 1記事だと100円以上ですがスタンダードプランだと500円で過去の2200以上の記事も含め全てが読めるプランとなるので1記事購入より月額500円のスタンダードプランがお買い得かと思います。 経済学と金融理論、会計、マーケティング理論の知識をベースに記事を書いてます。 またニューヨークを拠点とした全米で上位1%に評価されているヘッジファンドの分析手法を参考にしてデータ分析し予想してます。 米国の経済学者や
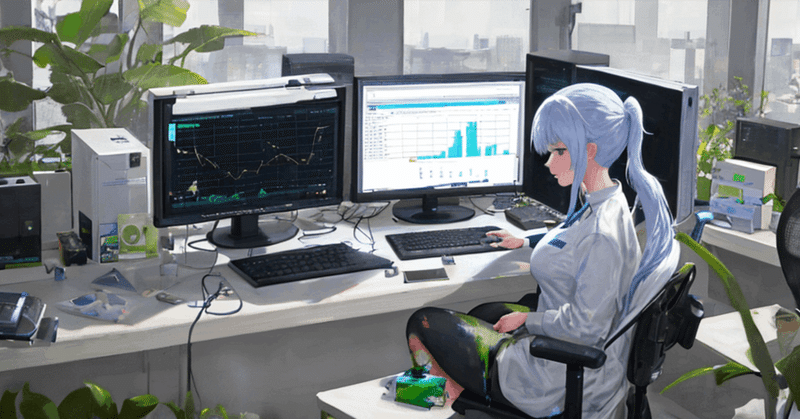
雇用統計の謎解きをデータから考えて行きます。アメリカの著名な経済学者の間でも話題となったポイントとなります。知ったかぶりしてお話出来る小話となります。
経済学と金融理論、会計、マーケティング理論の知識をベースに記事を書いてます。 またニューヨークを拠点とした全米で上位1%に評価されているヘッジファンドの分析手法を参考にしてデータ分析し予想してます。 米国の経済学者やヘッジファンドの分析レポートも日々読んで参考にしてます。 私の記事はデータ分析と予想が中心で用語解説も交えながら進めてるので初めて株を取引する人でも直ぐに理解出来て予想は参考になると思います。 データの内容は個人投資家がほとんど見たことが無いか見ないデータ

日本の債務バブルとバブル崩壊の過程に入っているリセッション入りをデータ分析して行きます。バブル形成と崩壊のメカニズムについて考えて行きます。また財政破綻や財政の持続性も考えています。
noteではS&P500、ナスダック、日経平均の終値をEPS、PER、益回り、金利、イールドスプレッド、経済学や金融理論などから独自に理論値を算出し 何%割高 何%割安 と日々分析し解説しています。 ドル/円は経済学の理論と過去30年のデータと通貨の価値の本質から独自に理論値を算出し毎月、月末のドル/円を予想しています。 経済学と金融理論、会計、マーケティング理論の知識をベースに記事を書いてます。 またニューヨークを拠点とした全米で上位1%に評価されているヘッジフ

アメリカ経済がリセッションに向かっているのか?それとも経済は成長が再加速に向かっているのか?を金融の7つのデータからデータ分析して行きます。
経済学と金融理論、会計、マーケティング理論の知識をベースに記事を書いてます。 またニューヨークを拠点とした全米で上位1%に評価されているヘッジファンドの分析手法を参考にしてデータ分析し予想してます。 米国の経済学者やヘッジファンドの分析レポートも日々読んで参考にしてます。 noteの月額500円のスタンダードプランの読者募集しています。 1記事だと100円となりますがスタンダードプランだと500円で過去の1300以上の記事も含め全てが読めるプランとなるので1記事購入よ