韓国現代文学と国際養子縁組
昨年の11月になりますが、コペンハーゲンのモダンアートギャラリーCharlottenborgで開催された韓国現代文学セミナーに行ってきました。
デンマークでも徐々に注目を集めている韓国現代文学ですが、まだ日本やアメリカほどではありません。韓国語翻訳者の数自体少ないと言われており、たとえばハン・ガン著『菜食主義者』は英語から、『少年がくる』はノルウェー語からの重訳です。原語から直接訳されているものには、ファン・ソギョン著『パリデギ― 脱北少女の物語』や、今回ご紹介する作家の一人シン・ギョンスクの『母をお願い』があります。
今回のセミナーは、テラポリス(Terrapolis)というデンマークのフェミニズム文学グループと、韓国文学翻訳院(Literature Translation Institute KoreaまたはLTI Korea)の共同プロジェクトによって実現したものです。そして、コペンハーゲン大学コリアンスタディーズの助教授であり、ジェンダーの視点から韓国の現代文学や映画を研究しているバーバラ・ウォールが司会を進行しました。当日は、韓国から4名の文学作家、そしてデンマークから2名の作家がゲストとして招かれ、嬉しいことに、観覧者全員には韓国作家4名の作品から抜粋された頁のデンマーク語訳が詰まった小さな文集が無料で配られました。デンマーク語への翻訳者は、同大学の韓国語講師と大学院生の3名です。
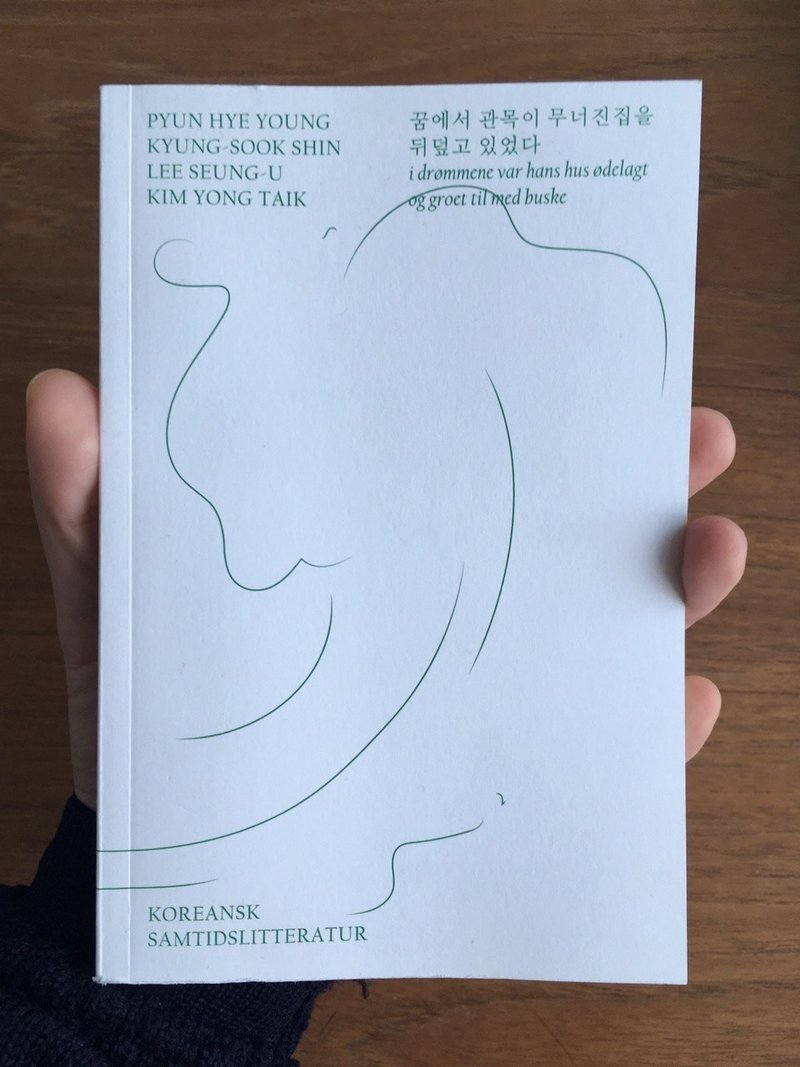
セミナーでは作家各自がそれぞれ抜粋箇所を朗読してくださいました。もちろん韓国語でですので、そのあと翻訳者がそれぞれデンマーク語で朗読していきます。
 右から司会のバーバラ・ウォール、ピョン・へヨン、翻訳者スィニ・ヘニングセン、キム・ヨンテク、翻訳者ルイーゼ・ヴェンデルボー、デンマーク人作家マヤ・リー・ラングヴァ
右から司会のバーバラ・ウォール、ピョン・へヨン、翻訳者スィニ・ヘニングセン、キム・ヨンテク、翻訳者ルイーゼ・ヴェンデルボー、デンマーク人作家マヤ・リー・ラングヴァ
当日朗読いただいた作品を、文集をもとに簡単にご紹介します。
ピョン・へヨン(1972年-)『ホール』, 訳/カン・バンファ(書肆侃侃房(韓国女性文学シリーズ5))
アメリカのシャーリイ・ジャクスン賞受賞作品。
交通事故後、病院で目を覚ます主人公オギ。事故時に同車していた妻は亡くなり、娘の死を悲しむ義母。事故で体が不自由になってしまったオギと、義母の奇妙な二人暮らしが始まります。
イ・スンウ(1959年-)『植物たちの私生活』, 訳/キム・スニ(藤原書店)
主人公は車で売春地区を徘徊して娼婦を選び、両足を失った兄が待っているモーテルに送るのですが、イ・スンウが朗読したのは、この兄弟がモーテル帰りに墓地を散歩する場面でした。兄を乗せた車椅子を押しながら二人で暗闇をゆっくりと静かに進んでいく様子が鮮明に描かれています。
シン・ギョンスク(1963年-)『離れ部屋』, 訳/安宇植(集英社)
舞台は1994年、作家となった32歳の「わたし」が、パク・チョンヒ政権の終焉が迫る1978年に田舎町で過ごした16歳の「わたし」を振り返ります。
キム・ヨンテク(1949年-)『ソムジン江』(『韓国現代詩小論集―新たな時代の予感』掲載, 土曜美術社出版販売)、『木』(2002年)未邦訳、他
ソムジン江が流れる農村で育ったキム・ヨンテクは、小学校の教職を経て1982年に詩人としてデビュー。農村、自然、家族を題材とした抒情詩が特徴的でした。
以上4名の作家が朗読したあと、韓国系デンマーク人の作家エヴァ・ティン (Eva Tind)とマヤ・リー・ラングヴァ (Maja Lee Langvad)が登壇し朗読しました。
エヴァ・ティン(Eva Tind): 1974年釜山生まれ
文学作家としてだけでなく、自分のエスニシティを題材として写真アートや映像を中心に手がける芸術家としても活動。HP: http://evatind.dk
ティンが朗読したのは2019年4月に出版された"Ophav"(意味: 原点、ルーツ)から抜粋した章でした。
あらすじ: ある家族が自分を、そしてお互いをさがしに世界を旅する物語。18歳になった娘のスイをひとりで育てたカイは、スイの独り立ちがきっかけで実存的危機に陥り、生きる意味を失う。韓国からの養子としてデンマークで育ったカイは自分のルーツには無関心で、インドへ自分探しの旅にでる。スイは幼い頃以来ずっと会っていなかった母親を訪ねにスウェーデンに向かい、その後祖父のいる韓国へ旅立つ。(参考: https://www.gyldendal.dk/produkter/eva-tind/ophav-50041/hæftet-9788702281392)
マヤ・リー・ラングヴァ(Maja Lee Langvad): 1980年ソウル生まれ
作家学校卒業後、アイデンティティ、養子縁組、デンマーク人らしさ、ゼノフォビアをテーマにした小論集『ホルガダンスケを探せ(注1)』(原題: Find Holger Danske)で2006年に作家デビュー。2007から2010年までソウルに滞在。滞在期間に海外養子制度を問題視する立場として現地の活動家やアーティストと交流。その後に刊行された『彼女は怒っている』(原題: Hun er vred)は、これまでデンマーク国内ではあまり疑問視されてこなかった韓国・デンマーク間の国際養子制度、養親と実親の権力関係、そして養子であることの複雑さに対する怒りと疑問を投げかけています。
ラングヴァが朗読したのは、これから刊行予定の本で、タイトルは未公開でしたが、韓国語が話せない作家と韓国語しか話せない実親が交わす、親子のぎこちないけれどどこか温かみを感じる会話がユーモラスに綴られていました。
 朗読するマヤ・リー・ラングヴァ
朗読するマヤ・リー・ラングヴァ
–
このセミナーを見つけた時、韓国現代文学と韓国系デンマーク人作家が書いた文学とのあいだにどのような繋がりがあるのだろうか? という疑問が湧きましたが、当日はそんなことなどすっかり忘れ、楽しく和やかな時間を過ごし、今まで知らなかった韓国文学にも触れることができました。一緒に行った友人も、私と同様にとても満足げでした。けれどもやはり疑問は消えず、二人とも韓国からの養子だから? そうだとしても少々無理がある構成ではないだかろうか…、などと考えていくうちに、デンマークでは韓国の海外養子制度がどのように捉えられているのか、どう議論されてきたのかを調べてみようと思いました。
まず、デンマークにはSporløsというドキュメンタリー番組があります(Sporløsとは「足跡/形跡がない」といった意味です)。何らかの理由で世界中から養子としてデンマークの家庭で育ち成人となった人たちが、自分のルーツを探す旅にでかけ、だいたいの人が実の親と感動の再会を果たします。日本の番組で無理やり似かよった例を挙げるとすれば、日本テレビの「嗚呼!バラ色の珍生!!」といったところでしょうか…。さて、Sporløsは2012年から2019年末まで放送されていたほどですから、ずいぶん好評だったのでしょう。
その反面、養子制度を美化し、単純化しすぎている、といった批判の声も少なくありません。たとえば、デンマーク養子制度シンクタンクTænketanken AdoptionのメンバーのひとりMichala Yun-Joo Schlichtkrullは、自分の生まれた土地、ルーツ、そして自分自身をも見いだすことによって「可哀想な」養子たちは幸せを得る、というステレオタイプなイメージを支えている、と厳しく批判し、また「養子」と「血のつながり」があまりにも当然のように関連づけられていることを疑問視しています。実際には韓国系デンマーク人が直面する外見による差別、養親側と実親側の権力関係の不均衡や経済的な依存関係などといった、血縁以上の複雑な問題があるからです(注2)。このような問題は、上記のエヴァ・ティンやマヤ・リー・ラングヴァといった作家たちによって、文学を通じて議論され始めました。
ラングヴァは作家デビュー後も、養子問題をメディアでとりあげ続けました。韓国の養子斡旋団体は、国外への養子縁組斡旋によって多大な利益を得ていることから、養子縁組の産業化が進んでいる事実を指摘しています(注3)。また、次のように言及もしています:
養子を迎えたい理由として「貧困な子どもや施設で育った子どもを救うため」というような人道主義的な理由が挙げられるが、もし本当に人道主義的なのであれば、障がいのある子や、ある程度成長した子どもを養子として受け入れるはず。しかし実際に好まれているのは乳幼児、そして障がいのない「健康な」子どもである。(2007年7月11日付JydskeVestkystenより)
さらには、養子縁組は養親になりたいひとたちの権利である、と言われているけれど、それは「権利」ではなく「特権」であり、つまりは「欧米の中流階級の白人が持つ特権」であるとも発言しています。
そして、デンマークでは同性愛のカップルには子どもを養子に迎える権利が強調される反面、実親が自分の生んだ子どもと暮らす権利があるかどうかについては誰も触れることがない、とも厳しく指摘しています。
養子を迎える権利を持つカップルは子どもを養育できる程度の経済的余裕があることを意味していますし、そういった意味ではラングヴァが言うような中流階級に当てはまるのかもしれません。ただ、エスニシティや肌の色と養子を迎える権利がどのように関係しているのかは彼女自身も触れておらず、私自身もすっきりとしませんが「欧米の白人がもつ特権」であるかどうかは議論の余地がありそうです。
この記事は2008年のものなので、ラングヴァの視点は今では変わっているかもしれませんが、これまであまり議論されてこなかった養子縁組の背景やタブーに敢えて踏み込み、デンマークで規範とされてきた考えを再検討する機会を与えた数少ない文学作家と言えるのではないでしょうか。
最後に、ラングヴァの韓国滞在経験をもとにした2作目『彼女は怒っている』(未邦訳)の一部をご紹介したいと思います。
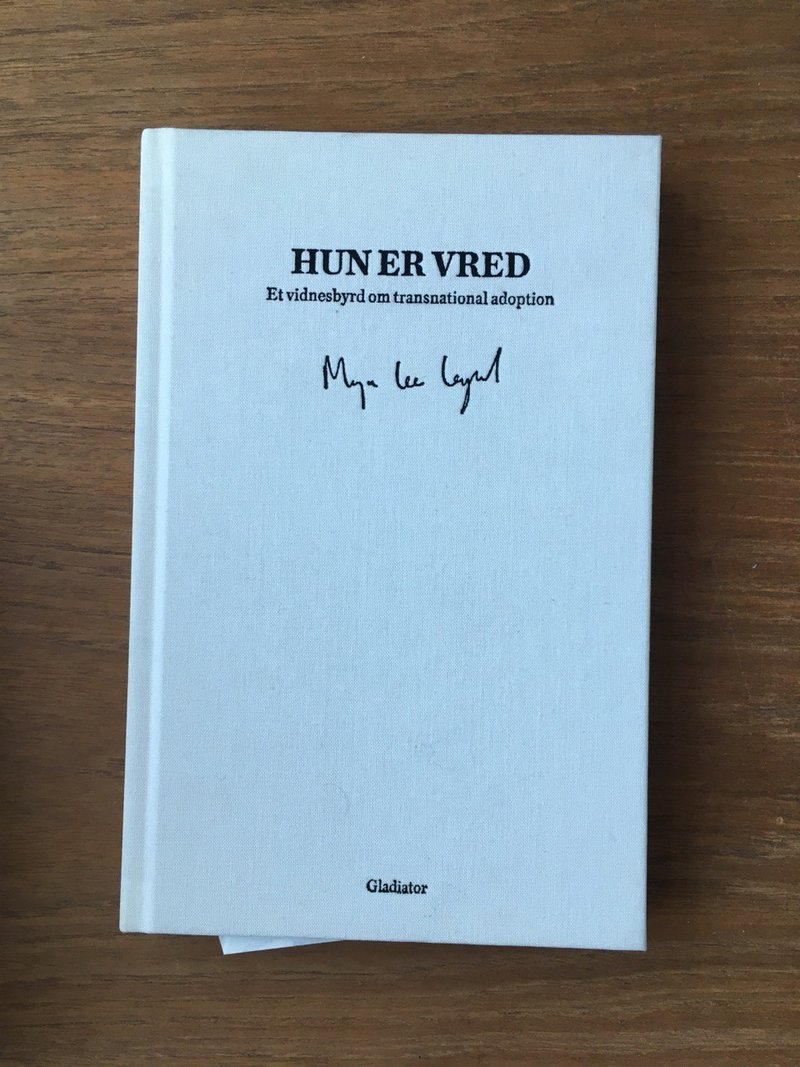
彼女は養父に怒っている。
彼女は養母に怒っている。
彼女は実母の存在を認めない養母に怒っている。
彼女は実父の存在を認めない養父に怒っている。
彼女は実父に怒っている。
彼女は実母に怒っている。
朝食に出してくれる白いごはんとキムチの代わりにパンと卵を要求すると、それを拒絶だと思い込む実母に怒っている。母の表情を見ればわかる。しかし彼女はトーストとスクランブルエッグを食べる。娘が自分と同じものを食べないことへの悲しさが、母の目にはっきりと映っている。
[…]
彼女は、もうこれ以上食べられないと言ってもご飯をよそい続ける実母に怒っている。
彼女は、自分が理解できない韓国語で話しかけ続ける実母に怒っている。
彼女は、自分と実母をさえぎる壁があることに怒っている。それは精神的な壁、言葉の壁、文化の壁、地理的な壁だったりする。
彼女は、実母について自分がほとんど何も知らないことに怒っている。
彼女は、実父について自分がほとんど何も知らないことに怒っている。
[…]
("Hun er vred" 2014 pp. 217-218)
(注1)ホルガダンスケとは: デンマークの伝説上の英雄。ちなみになぜ『ホルガダンスケを探せ』かといいますと、イギリスの絵本『ウォーリーをさがせ!』のデンマーク語版『ホルガをさがせ!』(Find Holger!)と掛け合わせたもので、周りと見た目がほとんど同じだけれど何かが異なるウォーリーと、多数派の白人のデンマーク人の集団に混じって存在する見た目の異なるラングヴァ自身を重ね合わせているのだと思われます。
(注2)http://www.taenketankenadoption.dk/2016/02/det-handler-om-roedder/
(注3)"ADOPTION: International adoptioner en industri" (2008年6月16日付Information)
(文責:種田麻矢)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
