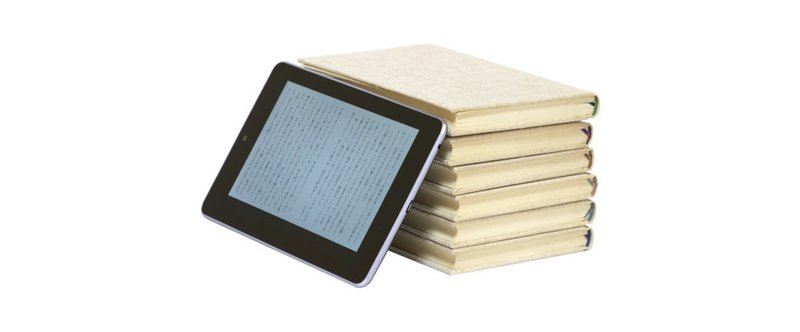
隘路に陥った経済学はどこへ向かおうとするのだろうか?──岩井 克人・鶴光太郎・小林慶一郎・中神康議・矢野誠・大橋 弘『経済学は何をすべきか』
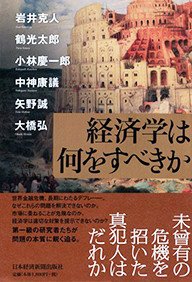
第2章「日本の経済論争はなぜ不毛なのか」(鶴光太郎さんと小林慶一郎さんの対談)の冒頭からこのような問いが発せられます。
「しっかりとした議論が戦わされていないのでないか、エコノミストの役割はどうなっているのか、経済学者と実際の政策決定者との間にコミュニケーションはできているのか」(鶴さん)
「経済学が政策に生かされない、あるいは政策につながらないことにも、二種類の要因があるように思います。一つは、経済学からいろいろな分析の結果が出て、ある程度正しいことが判断できる材料があるのに、それが政策の現場にうまく伝わらないという問題です。
もう一つは、何が正しいのかが学問の世界でもよくわかっていないという問題があります。デフレやインフレなどがその典型です」(小林さん)
なんとも正直な小林さんたちの対話ですが、確かにさまざまなメディアでエコノミスト、経済学者、経済政策通の政治家、官僚たちが入れ替わり立ち替わり登場して持論を述べていますが、かみ合わないままのことが多いようです。
具体的な提案(=診断)でも
「私はアベノミクスの議論を聞いていて以前から腑に落ちなかったのは、第三の矢が大事だと皆が言っているのですが、具体的には何をやればいいのか、大事だと言っている本人がわかっていないのではないかということです。私を含めて第三の矢が大事だとは言っているわけですが、こういうことをやれば生産性が上がるという具体策は、実はそんなに見えていないのではないかと思います」(小林さん)
というのが実情なのではないでしょうか。
さまざまな論者がいますが現在主流派と言われる人たちが前提としている、市場がもたらす効率性と安定性というものは確かなものなのでしょうか。
市場から〝不純物〟を取り除くことで純粋化すれば問題は解決するのでしょうか。
この効率性と安定性というものに正面から疑義を呈しているのがこの本の冒頭の岩井克人さんの一文です。
「効率性と安定性の二律背反は,資本主義の不都合な真実です。その不都合な真実を直視して経済政策をつくる。それが不均衡動学派の考え方です」
岩井さんはケインズの〝美人投票論〟をもとに、資本主義の本質である投機性を見落としてはならないと主張しています。
「生産活動にも金融活動にも投機があり、さらには貨幣こそが純粋な投機である。この三つの投機的な要素を内包しているという意味で、資本主義とは全面的に投機システム
であるのです。そして、投機とは本質的に不安定です」
この投機性というものは貨幣の出現によって強化され、純粋化され完成されたのでしょう。
市場至上主義という新古典派経済学がもたらした〝罪〟ともいうべきものがあります。
「一九八〇年代から始まったグローバル化は、「見えざる手」の働きに全面的な信頼を置く、新古典派的な経済学の壮大な実験でした。それは、資本主義をなるべく純粋にし、世界全体を市場で覆い尽くせば尽くすほど、経済の安定性も効率性もともに最大限に達成されるという理論でした。だが、この壮大な実験は壮大に失敗しました」
この失敗の責任はどこにあるのでしょうか。
さらにまたその実験の〝被害〟にあったのは誰だったのでしょうか。
国家間の格差拡大、国内での格差拡大、不安定な雇用・労働市場などはその実験の失敗がまねきよせたものではないでしょうか。
そして金融市場というものについて
「金融市場の発達は、結局フリードマンが提示したような牧歌的な市場ではなく、ケインズが想定した、プロが互いにしのぎを削って互いの予想を予想しあい、さらにその予想の予想の予想をしあうという美人投票的な市場を拡大するということにほかならないのです。その意味で、金融革命は、投機の活発化を通して、不安定性の増大をもたらすことになったのです」
この岩井さんの指摘は傾聴に値するものです。
私たちは市場の意味とそれがもたらすものだと考えた前提を疑うべきだったのです。効率性と安定性という神話を疑うべきだったのではないでしょうか。
経済学のイロハである需要と供給の均衡性はなにも公平性を保証するものではないと思います。結果として均衡性が現れたのにすぎません。そこを純粋化(理論化)することでえられたものは確かに多いと思います。けれどそれゆえに見落とした(捨象した)ものも多かったのではないでしょうか。
市場はなにもユートピアではありません。もちろん地獄でもありませんが、怪物なのは確かです。それは過去の恐慌史を振り返ればわかることだと思います。
「資本主義の健全な持続可能性のためには、新古典派経済学が生みだした自由放任主義思想と訣別しなければなりません。自由を守るためには、自由放任主義から解放されなければならない。この逆説こそ、今回の経済危機の最大の教訓であるでしょう」
この岩井さんの言葉をどのように生かし、実現していくかが私たちが取り組まなければならない最大の課題のように思います。
書誌:
書 名 経済学は何をすべきか
著 者 岩井 克人・鶴光太郎・小林慶一郎・中神康議・矢野誠・大橋 弘
出版社 日本経済新聞出版社
初 版 2014年2月7日
レビュアー近況:本日アップデートのMacOSアプリが起動せず、メーカーに問い合わせ。すると、サポートの方が野中のマシンを遠隔で操作して作業するという状況が続いてます。恥ずかしいファイル満載のデスクトップを延々晒す辱しめに、耐え難きを耐えています。
[初出]講談社BOOK倶楽部|BOOK CAFE「ふくほん(福本)」2015.07.10
http://cafe.bookclub.kodansha.co.jp/fukuhon/?p=3724
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
