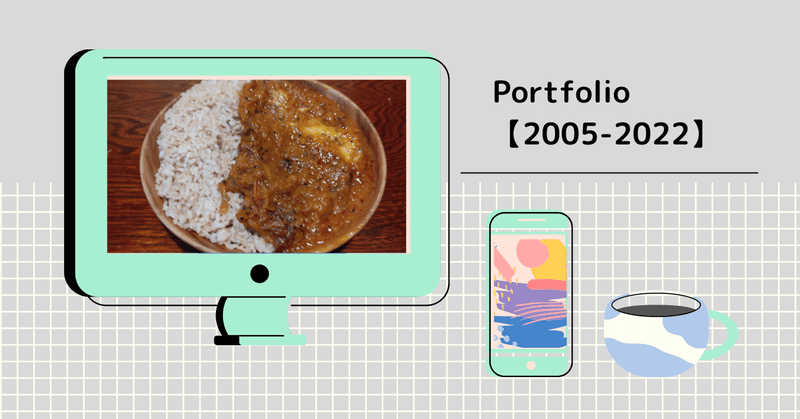
【2018-】Curry × Community【#スパイスカレー #コミュニティ】

なぜ、スパイスカレーなのか?
スパイスカレーを知ったきっかけは、お坊さん時代に知り合った友人がスパイスで作ったチキンカレーを食べさせてくれたこと。
それまで「カレーといえばカレールーから作るカレーがカレーだ」信者だった私は、当初「スパイスだけで本当にカレーができるのか?」と、友人が作っている姿を見てやや不安を感じたものだ。
いざ出来上がったカレーは、カレールーのカレーと比べて大変あっさりしている。しかし、カレーなのだ。あっさりしている分、しつこさがなくて、スルスルと口の中に入っていく。スプーンが止まらない。こんなことがあるのかと驚いた。
何でも、その友人がスパイスカレーを始めたのは、我が家のインドカレーというはてな匿名ダイアリーに出会ったのがきっかけだという。
私も読んでみた。
スパイスカレーを作りたくて作りたくてしょうがなくなった。
今読んでも、簡にして要、概ねスパイスカレー作りにおいて必要不可欠なことは全て上手にまとまっている。
そして、すっかりスパイスカレーにハマってしまった私は、気になったスパイスを手当たり次第大津屋で買い漁った。

約22種類。これだけあれば、チャイも作れるしタンドーリチキンもサブジも作れる。カレーもチキンはもちろん、マトンカレー、キーマカレーから、魚のカレー、サーグ(ほうれん草)カレーまで、何でも作れる。そして、今挙げたのは全て自分で作ってみた。どれも旨かった。
だが、スパイスカレーの魅力はそれだけではない。
ずっとスパイスカレーばっかり食べていると、その間だけは体の調子が整ってすこぶる調子がいいのである。身体の底から活力が湧いてくる感じとでも言おうか。
元々、スパイスには薬効効果があり、それゆえにインドではアーユルヴェーダという民間医学が発達している。それもまた、調べていくと奥が深くて興味深かった。仏教を学んでいるからこそわかる。インドは人を惹きつけてやまない、底なしの沼がある。
是非とも、この魅力をお寺の檀家さんたちにも味わってほしい。そう思って立ち上げたのカリー寺だった。

私がカレーを通して立ち上げることになった初めてのコミュニティである。ちなみに、この時点では、まだカレーの販売はしていない。
丁度、他宗のお寺界隈でも「お寺でカレー食べるって、インドつながりだし、なんかいいよね」ってことで始める寺が徐々に出てきた頃だった。2番煎じではあったが、やってみたら結構楽しかった。
ゆくゆくは勤めていた正養寺というお寺の恒例行事にしたかった。
その矢先、私自身が適応障害でうつ状態になり、働けなくなった私を両親が寺から追い出すという事件が発生した。寺から追い出されてしまった私は、アパートで生活保護を受給しながら暮らすことになって、現在に至る。
寺を追い出された後も、スパイスカレーは作り続けた。

カレーを食べている間は、自分がうつであることを忘れられた。今だから確信持っていえるが、スパイスカレーはうつに効くのである。医学的なエビデンスで言っているのではない。スパイスカレーを丁寧に作って、食べている時だけは、うつ状態で失われていたまともな味覚がちゃんと戻ってきてくれるのである。これは私が身をもって実感したことだ。だから、ダウナーな時のご馳走として、よくスパイスカレーを作った。
そして、カレーを作る様子をFacebookに上げていたところ、ちょうど最近知り合った同じ岩手県内は北上市の方が「私のスパイスカレーを食べてみたい」と声をかけてくれたのだ。
一つは、ワラタネスクエア。もう一つは、Neconoteさんだった。
目標・価値・実現方法
目標
みんなに美味しいスパイスカレーを提供する
カレーでしっかり売り上げを出す
カレーを通してコミュニティの輪を作り出す
提供したい価値
スパイスカレーという食を通して、みんなが笑顔になってくれる
自分も作ってみたいという同好の士が現れてくれる
流しのカレー屋がいる、ということがその地域の豊かさになる
実現方法
オペレーション:作り方が一通りわかっているだけでは、どこでもカレー屋が出来るようになるわけではない。「材料調達」「事前の仕込み」「注文を受けてからの調理」を区分けし明文化して、いかに各工程の作業を効率化するかを考えなければならない。目標提供人数が10人以上であれば大量調理になるし、それだけ手間も計り知れなくなる。
オペレーション作成にあたっては、僧侶になるための修行時代、50人程度の食を一手に担う食堂でチーフを任されていた経験が生かされた。コスト計算:材料のコスト(食材費)や仕込みのコスト(光熱費・人的コスト)はもちろん、接客を一人つけるかどうかといった当日の人的コストや、盛岡⇄北上間の移送コストも考えなければならない。
テイクアウト対策:そして、コロナ禍で忘れてはいけないのが、テイクアウト容器をどうするか、というコストである。通販に頼ってもよかったが、幸い盛岡には橋市という業務用に厨房器具を扱っている店が使い捨て容器を取り扱ってくれている。大概のテイクアウト容器はそこで揃えた。
予算と売り上げ見込みの算出:コスト計算をしっかりした上で、何にどれくらいお金がかかって、どれだけ売り上げれば元が取れるのかを数値で出す必要がある。
出店の記録
北上で最初に私が関わったのが、2021/02/23のワラタネ食堂だ。


スパイスカレーと自家焙煎コーヒーを提供するので忙しく、集まった人とゆっくり会話する暇もなかったのだが、久しぶりに大人数にカレーを振る舞った。材料費も多少頂いたが、大体トントンくらいで、粗利という粗利も存在しない、ただ「参加することに意味がある」回だった。
それからすぐ、同じ北上市内にあるNeconoteさんに「3/27にマルシェやるから出店しないか」とお声かけいただいて、今度は焼き野菜カレーで出店した。


テイクアウトも含めて、それなりに売れた。
更に1年後になるが、Neconoteさんにはまた声をかけてもらって、グリーンカレーを出させてもらったことがある。
この時は結局1万円ちょっとの赤字を出した。
思うように客足が伸びなくて、結局出店者の内輪で消費してもらったせいもある。ただ、それ以上に材料費が嵩んでしまって、よっぽど呼び込まない限り売れない状況に追い詰められていたということもある。
やって満足はしたが、手痛い失敗だった。
経験したこと
現実問題、商売としてカレー屋をやったらどうなるかをまざまざと経験した
カレー屋のみならず、飲食業をやるならどうやってオペレーションを効率的にこなすか、研究することができた
何より、自分のカレーを食べてもらって、喜んでもらって、それがきちんとお金になる仕組みを作ることの喜びと奥深さを知った
反省したこと
「おいしい」「キャッチー」だけで自ずと人が来るわけではない。ちゃんと宣伝にもコストをかけるのは大事
↑と重複するが、カレーがお金になる仕組みは作れたが、売り上げをきちんと伸ばす仕組みまで手が回っていなかった。だから、出店経験はあるものの、グリーンカレーで赤字を出すまで「どうやったらもっと売れるか」を考えずにここまできてしまった
カレーを通してコミュニティを開きたいと思いつつ、準備と調理で忙しくて、実際問題カレーでどこまで人とのつながりが生まれているのか、実感しきれていないところがある。「コミュニティを開きたい」ならそうで、本当はもうちょっと他にやりようがあるのではないか
成果
目標達成率
みんなに美味しいスパイスカレーを提供する(90%)
カレーでしっかり売り上げを出す(60%)
カレーを通してコミュニティの輪を作り出す(70%)
総括
食べてくれた人には「美味しい!」と言わせられる自信は少しずつついてきた。
あとは、しっかり売り上げを出せるように努力することと、もっと出店回数を増やしていくことだと思う。こればっかりは、場数を踏んでいくしかない。
何より、「カレー屋をやっていきたい!」のであれば、「自分のカレーは他所のカレーとココが違う!」という差別化=売れるカレーづくりも、追々やっていかなければいけなくなるだろうし、「コミュニティを作りたい!」ならカレーは凡庸でもいいからカレーを通した体験の設計に力を入れたい。さぁて、自分はどっちに一生懸命になりたいんだろうね? というところが未だ定まっていないのは、今後課題というか、向き合わなければいけないことなのだろうと思う。
今後の展望
カレー屋は今後もやり続けたいと思う。
それこそ、最近知り合った人が「コロナに効くカレー」「うつに効くカレー」を作って売りたいと言っているのを聞くと、スパイスカレーを売りたい人・食べたい人の需要がなくなることはないと思う。
また、カレー屋の他に、珈琲屋も私はやっている。
ワラタネ食堂では、カレーとコーヒーの両方を提供した。仲間がもう一人ついてくれれば、カレーとコーヒー、両方やれる気はしている。
あと、出来れば近いうちに「スパイスの栽培」にも着手したい。
丁度、私はコンポストをやっており、土づくりに関する知識と経験には蓄積がある。
ターメリックは無理でも、コリアンダー(パクチー)・チリペッパー(要は唐辛子)・クミン・にんにく・生姜くらいだったら東北の大地でも育ちはする。もちろん、玉ねぎとトマトは十分育つ。
そして、育てた野菜でカレーを作り、カレーを作る過程で出た生ゴミはまたコンポストにして土に還す。

この循環の仕組みをうまく回せるようになれば、売れるかは置いておいて間違いなく他のカレー屋と差別化ができるようになり、加えて各プロセスに人が加わることによって独特の体験を提供できるようになる。
ここまでの仕組みづくりを、私は死ぬまでにはやってみたいと思っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
