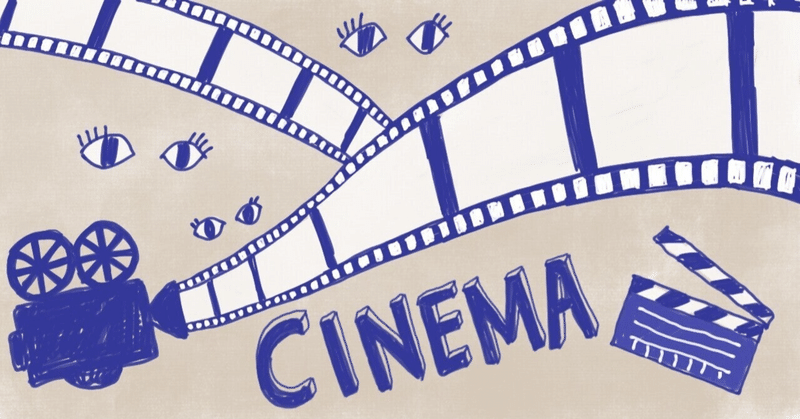
白石監督は、映画製作を楽しんでいました。
※「ほぼ日の學校 Advent Calendar 2021」18日目です。
映画って「つくる」のがおもしろい。
白石和彌 (映画監督)
次々と話題作を発表している日本映画界の若き名匠、
白石和彌監督。20代で映画業界に飛び込み、
体当たりで学んだという「映画づくり」のおもしろさを
たっぷり語っていただきます。聞き手は糸井重里。
映画のたのしみ方がひとつ増えるような、
そんな対談になりました。
映画って「つくる」のがおもしろい。 | 白石和彌 | ほぼ日の學校 (1101.com)
私は映画が好きです。
おもしろい映画、そうでもない映画、観た後、何でおもしろかったのか考えます。
いや、嘘です。
おもしろかったー!
で終わることが多い。
けど、映画を観る前も、後も、映画のことを考えられたら幸せだなーとは思っています。
映画を観る前と後に、映画のことを考えるには、
何が映画をおもしろくしているのか
役者さんのこと
脚本のこと
映画ができるまでの監督やプロデューサーの苦労
どこに何人くらいこの映画のファンがいるのか
など、知らないといけません。
だから、映画のこと、もっと知りたいです。
白石監督は、映画のいろんな工程に興味があるんですね。日本の映画では、口を出すなと言われてしまう照明やカメラについても、昔から、今に至るまで、興味があると言います。
「今に至るまで」という言葉は、二度出てきますね。
ずっと「好き」が続いてることを仕事にできるのは、映画ということ抜きにしてもうらやましい。
途中、糸井さんが、映画のことを世の中の他の出来事や世の中の仕組みなどに置き換えて話そうとしても、映画ではこうですね、映画だとこう考えると思います、と映画に関わる人としての発言に終始します。
20歳くらいまでは、映画製作について学祭に関わるようなイメージをもっていたそうです。その後、助監督時代は、監督のイメージ、脚本の内容を実現するために、「できねーだろ?」と言われ、「やってやるよ!」と、売られたケンカを仲間と買って乗り越えるみたいなノリで、取り組んできたとのこと。和気あいあい、ともちょっと違いますが、仲間と一緒に(真剣に)楽しんできたんだと感じました。
私も、映画が好きで、映像作品に絡みたくて、時々、といっても年に一回くらいですが、エキストラに参加します。現場を見ること、現場にいることが楽しい。待ってる時間も動く人、役者さんを見ることが楽しいです。ほんとに長い時間を待つこともあるので、読書したりして過ごしますが。
ガムテープや毛布が役立つという話、現場を知らないとわからないことですよね。こういう話を聞くと、次にエキストラで撮影現場に行ったときに、そういう目線で現場を見ることができます。
白石さんは、助監督時代から、どうやって映像にすればいいのかわからないような脚本や監督の思いつきを実現するために、できることをやってきたそうです。
映画やTVドラマを見ると、ひどい言い方をすれば、ハリボテ感がある映像に白けてしまったりすることがあります。現実味を感じる映像、感情が大きく振れるシーンは、どうやって撮ったんだろうという想像をするのは楽しそうです。
個人的には、現実の事件を映画に転嫁する話が興味深かったです。
あと凡ミスがある 現実の事件は
これやんなきゃ捕まらなかったのにな
みたいな凡ミスが楽しいんですよ
映画にしづらいんですけど
「この凡ミスはないわ」という感じを
どう面白くするかが実録映画の楽しみ
確かにありますよね。映画で見ると、そんな失敗しねーだろ、と思いますが、現実では、凡ミスから大きな事件になることは多い。そのまま書くと、逆に現実味がなくなるのは、私が仕事で書くような短い記事でも一緒です。
映像だけでなく、わざとらしくなく受け入れられるストーリー作り、展開、場面の描写には、きっと観る人に受け入れられるように、どこか現実と違う表現、順番、見せ方があったんでしょう。陳腐な事象なのに、リアリティを強く感じる場面を見つけたら、その方法を探ることもおもしろそうです。
映画を観る前後に映画を楽しむ視点をもらえました。
最後に、糸井さんが提案してますが、映画監督以外にも、映画に関わる、裏方さんの話が聞きたいですね。話を聞けば、きっともっと映画が楽しくなる。
「ほぼ日の學校」には、授業を「島」というカテゴライズがされていますが、映画は、一つ、島にしてほしい。「本」にまつわる島があるのだから、映画も島が欲しいです。きっと豊かな「島」になると思いますね。
いい歌を詠むため、歌の肥やしにいたします。 「スキ」「フォロー」「サポート」時のお礼メッセージでも一部、歌を詠んでいます。
