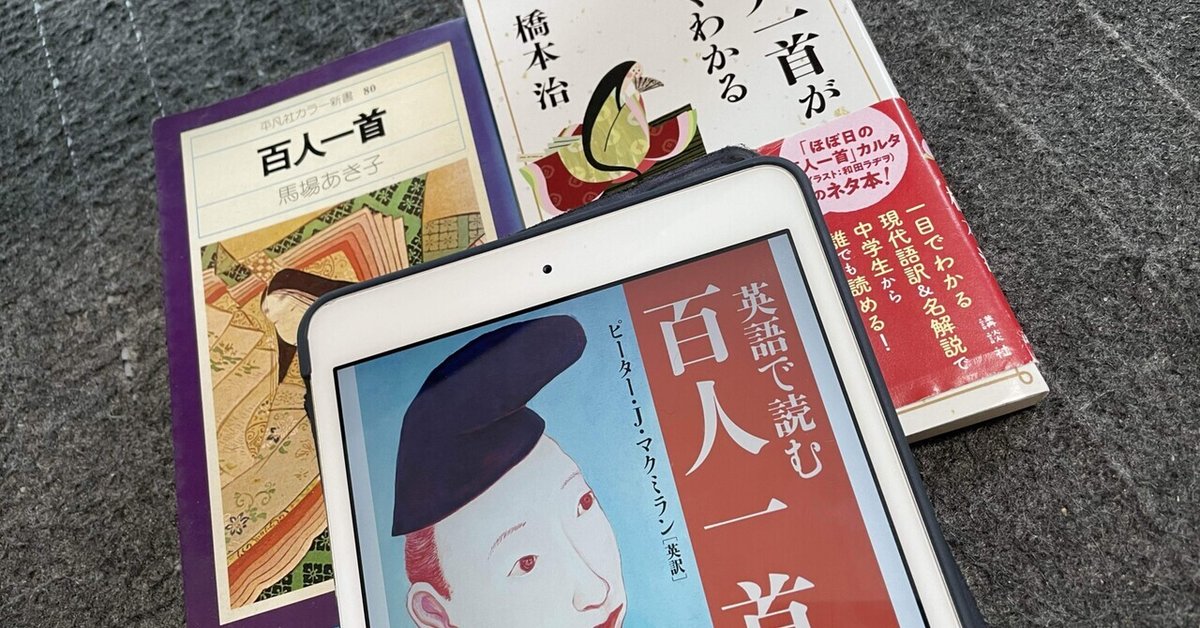
百人一首復習ノート:現代語訳、英訳、解釈とその感想(六九、七〇)
今回のようなシンプルな表現の歌を見て、絵や音楽のようなアプローチが作歌にも活かせるかもしれないという感触があった。
普段、現代語で短歌を詠んでいるのであって、文語に親しみたいわけでも、文語で短歌を詠みたいわけでもない。けど、永く日本人の体に染みついたリズムで、教養ある人が一度は親しんだ(無理やり覚えさせられた)歌に接することには、意味があることかもしれない。
教養としてではなく、自分の作歌の養分と作歌のテクニックという実利を期待して、いまさらながら百人一首を復習してみようと思う。情報は、手元にあった百人一首の本三冊から(『百人一首がよくわかる(橋本治)』『英語で読む百人一首(ピーター・J・マクミラン)』『百人一首 (平凡社カラー新書)(馬場 あき子)』)。
だいたい週一回、まとめている。一つのnoteには、2首ずつ取り上げる。2首ずつ取り上げる理由は、百人一首が、二人ずつのペアが50組あるという作りだから。どうせなら意味のあるペアの形でインプットしたい。歌をまとめて取り上げる作業は、連作を作るアイデアにもなるかもしれない。
六九.能因法師(のういんほうし)
あらし吹く 三室の山の もみぢ葉は
竜田の川の 錦なりけり
(あらしふく みむろのやまの もみじばわ
たつたのかわの にしきなりけり)
現代語訳
嵐だよ 三室の山の紅葉 ああ
見れば竜田の 川は錦だ
英訳
Blown by storm winds,
Mount Mimuro's
autumn leaves have become
the river Tatsuta's
richly hued brocade.
hued / hjúːd(米国英語), hju:d(英国英語)/…色の「hued」は動詞「hue」の過去形、または過去分詞
bro・cade / broʊkéɪd(米国英語), brəʊkéɪd(英国英語)/ 錦(にしき)、金襴(きんらん)
解釈
永承四年内裏歌合の題詠歌。能因最晩年の作品である。三室山は龍田山のこと、古来紅葉の名勝で、花は吉野・紅葉は龍田といわれた歌枕である。紅葉の錦のたとえは珍しくはないが、一首の格調は高く、龍田の紅葉をもう一度典型的にうたい直してみせた感がある。『能因歌枕』などを残し、諸国を旅した作者固有の目がこの歌には出ていないが、むしろ、晴の場の作法に叶ったよみ方としての気韻は高く、なお典型をなしているというべきだろう。
寂しく悲しい三条天皇の「冬の夜の月の歌」の後は、「嵐の歌」です。でもこの嵐は、恐ろしくありません。風がザーッと吹いて、山の紅葉が川に流れ込みます。在原業平は竜田川の紅葉を「からくれなゐ」と赤一色にしてしまっていますが、「錦」と言っている能因法師の「もみぢ葉」は、赤い紅葉と黄色い黄葉がまじったものかもしれません。「強い風で落葉が舞ってるところにいたら、目が痛くてたまらないじゃないか」なんてことは言わないほうがいいでしょう。
感想
もちろん、格調の高さなど、目を惹く歌だから残っているんだろうけど、歌に詠まれている場所、題材は、何度詠んでもいいのかもしれない。それを誰もが共感する、素晴らしい歌にするのは難しいかもしれないが、それでも自分なりの感じ方、捉え方を見つけ出すことで、一首詠めるかもしれない。違う画家が同じ題材、同じ風景を描いて、アプローチを変えることに似てるかもしれない。
七〇.良暹法師(りょうぜんほうし)
さびしさに 宿をたち出でて ながむれば
いづくもおなじ 秋の夕ぐれ
(さびしさに やどをたちいでて ながむれば
いずくもおなじ あきのゆうぐれ)
現代語訳
さびしさに 家を出てみて 眺めれば
どこもおなじさ 秋の夕暮れ
英訳
With a lonely heart,
I step outside my hut
and look around.
Everywhere's the same--
Autumn at dusk.
dusk / dˈʌsk(米国英語)/(たそがれの)薄暗がり、夕やみ
解釈
一首の中で「さびしさ」ということばは、一読した時は感覚的なものさびしさというような意味にとれるが、「いづくもおなじ」という自然への目は、その内がわのしんしんとした孤独の心を反映した自然をみていたのであろう。景と心象とは一体化し、推移し変化するものへの思いがにじんでくる。この何でもないような歌が、ふと読者をとらえるのはそのゆえであろう。
能因法師とペアになるのは良暹法師――比叡山の坊さんだそうですが、詳しいことはわかりません。坊主のペアで、秋の歌のペアで、「派手な秋」と「寂しい秋」の対照です。良暹法師の歌と能因法師の歌の順序を入れ替えると、この歌は三条天皇の寂しい歌に続いて、すごく寂しくなります。でも、能因法師の派手な「もみぢの秋」の後に来ると、寂しさの中に澄んだ美しさが浮かび上がってきます。そういう配置も大切です。
「宿」とありますが、これはべつに、旅に出た時の歌ではありません。平安時代では、「自分の家」も「宿」です。「宿」というのは、「夜を越すところ」という意味なのです。そういう時代に、「マイホーム」という感覚は持てません。定住の感覚がないからです。「家を出て見たら、どこもおなじ秋の夕暮れだった」という歌に寂しさがあるのは、定住の感覚がないからでしょう。ふつうの人がまだそんなことを感じない頃、坊さんの良暹法師は、その放浪感覚を感じていたんですね。
感想
英訳もとてもシンプル。橋本治さんが書いている歌の順番も大事そう。悲しい印象を引きずらない並びもあるだろう。曲の作り方みたいなことも、連作の勉強になるかもしれない。
※引用図書の紹介
『百人一首がよくわかる』
国語の教科書にあるような、文法的に正しい訳ではなく、短歌の長さ程度の軽妙な日本語訳と、短い解説書。
『英語で読む百人一首』
百人一首の英訳。古語や現代語訳より、歌の情景が浮かぶものも多い。
『百人一首 (平凡社カラー新書)』
馬場あき子先生の著作。ただし、教養としての解説であって、歌の解釈は短め。
いい歌を詠むため、歌の肥やしにいたします。 「スキ」「フォロー」「サポート」時のお礼メッセージでも一部、歌を詠んでいます。
