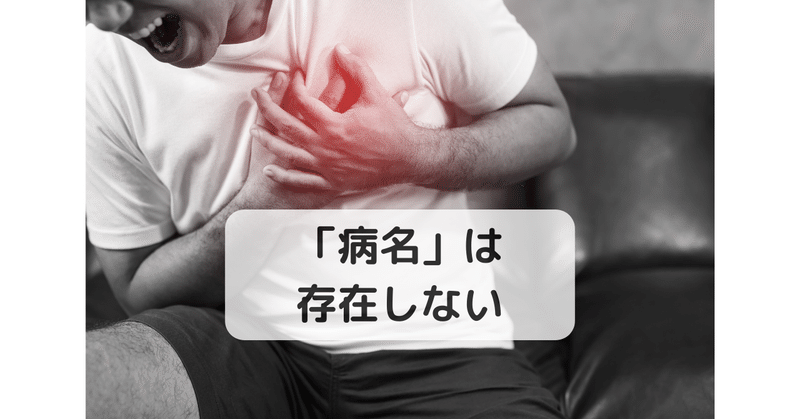
「病名」なんて存在しない。
世間の「病気」のイメージって、「空から鳥の糞が落ちてくる」みたいな、突然、何か運悪く遭遇してしまった感じがありますよね。
それが、Aという病気か、Bという病気か、はたまたXという病気かというのも運次第。
そして、今まで罹った人が少ないと「希少な病気」と言われ、治すのが難しいと「難病」と言われます。
私としては、これらの全部が意味が不明なんですよね。
まず、病気って、降って沸いてくるものではないです。
「菌」とか「ウイルス」由来のときは、そういうニュアンスはわかりますが、大抵の病気は、突然、どこからともなく表れたものではありません。
例外はあれ、基本的には、その人の生活の偏りなどにより、どこかの組織に異変が生じ、それがどこに症状が出たかによって、勝手な病名がつきます。
例えば、「酸素」摂取量が低くて、体のエネルギー生産量が低いと、体のあらやるとこに、「異常」が出る可能性があります。
それを現代医療は、頭に出たら「〇〇病」、内臓に出たら「△△病」などとネーミングをするだけです。
べつにそういう病気がある訳ではないんです。
「酸素不足」という原因が、あるところに症状を起こしただけで、そいういう病気が存在している訳ではないんです。
「難病」という言い方も不可解ですよね。
これは、他の病気は治せるけど、それだけは治せないという人だけが使って良い「単語」です。
「いやいや、あんたたちにとっては、他のも難病ですから!」というわかりやすい突っ込みができてしまうくらい、西洋医学は99%の病気を治せてません。
癌、心臓病、糖尿病、高血圧(←これはそもそも病気か?)、認知症、リウマチ、、、何も治せてないですから。
西洋医学からはすべてを難病と呼んで欲しい。
こんな感じで、別にこの世界には、「病名」というのは本来存在はしません。西洋医療ビジネス的には、「病名」→「対応する薬」というわかりやすい構図にするためにも、病名が必要なんです。
実際に存在するのは、ミネラル不足、血流循環不足、ミトコンドリアの劣化、経絡の滞り、といった原因だけです。
病名は、どこにその症状が出たかというだけで、あまり意味をなさないものです。
病名に惑わされてはいけません。
どんな症状が出たかはヒントになっても、治療としてやることは大体一緒です。
凡事徹底。根本の原因を見極め、基礎をしっかり押さえることで、ほぼすべての病気を予防し、治療することができます。
泣いて喜びます!いただいたお金は、新しい本を買うことに活用して、還元いたします♪
