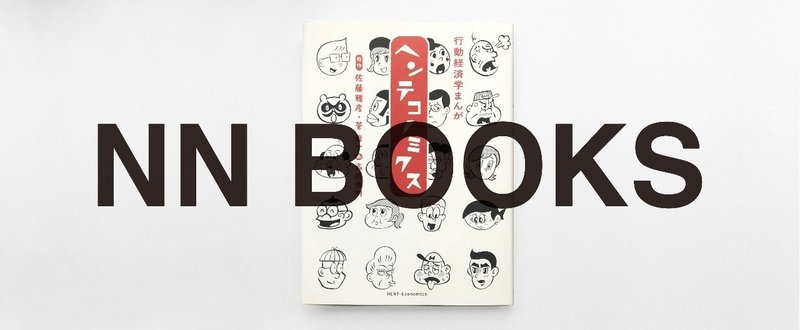
ヘンテコノミクス
みなさん、“行動経済学”を知っていますか?
簡単に言うと、従来の経済学では説明しきれない人間の経済行動を人間の心理の視点から解明しようとする新しい経済学です。今までの経済学というのは、「人間は必ず合理的な経済行動をする」という前提は考えられてきました。
ところが、ぼくもそうですが、“2000円以上かうと送料無料”という文字にノセられて、つい今必要ないものを買ってしまったり(無料による選好の逆転)、クーラー(暖房)の設定は同じ24℃なのに、夏は涼しく、冬は暖かく感じる(参照点依存性)など、ヘンテコなふるまいにあふれています。
今回の推薦書は行動経済学をまんがで学ぶ“ヘンテコノミクス”です。
人は、なぜそれを買うのか。安いから、質がいいから。そんなまっとうな理由だけで、人は行動しない。
そこには、より人間的で、深い原理が横たわっている。この本には、その原理が描かれている。漫画という娯楽の形を借りながら。〜本文より〜
本書には1話〜23話の様々な行動経済学の事例が掲載されています。
たとえば、“報酬が動機を阻害する〜アンダーマイニング効果”というエピソードでは、いつも近所の子供達が家の壁に落書きをされて困っていたおじいさんを主人公に話は進んでいきます。
そのお爺さんは“これからはいたずら描きするごとにお小遣いをあげよう”といたずら描きをするごとに子供たちに小遣いを渡していきます。しかし、数日後もうお金がなくなったと小遣いを渡すのをやめてしまいます。
すると初めは自分たちが楽しむために落書きしていた子供たちが、おじいさんから小遣いをもらっている間に、いつの間にか落書きする目的がお小遣いを貰うことにすり替わってしまい結果として、お爺さんからお小遣いをもらえなくなったことによって子供達は落書きをやめ、おじいさんは静かに暮らすことができました。という結末が描かれていきます。このように自分が好きでしていた行動(内発的動機)に、報酬(外発的動機)を与えられることによってやる気がなくなってしまう現象のことを、「アンダーマイニング効果」と呼ぶそうです。
実は、メジャーリーガーのイチロー選手は、かつて国民栄誉賞を2回も辞退したことがあるそうで、その理由を「今の段階で国家から表彰されると(野球に対する)モチベーションが低下するのではと懸念している」からとコメントしています。
また、“分母によって変わる価値〜感応度逓減(ていげん)性”というエピソードでは、A店ではドライヤーを5,000円で販売していて、距離は少し遠いがB店では4,700円売っている場合は、B店で購入するけれども、これが195,000円のステレオがA店、少し離れた場所のB店では194,700円で売ってた場合では、近くのA店で購入してしまうというストーリーが描かれていきます。これは家や車などの大きな買い物(全体の母数が大きい)をした場合にも起こりますが、同じ金額でも大切に扱ったり邪険にしたりと勝手にその価値を変えてしまう。そのような心の動きを「感応度逓減(ていげん)性」と言うそうです。
ほかにも、財布を落とした時に、一万円札がなくなっているのと、亡くなったお婆ちゃんからお守り代わりのもらった五百円札がなくなってしまっていた場合に金銭的な価値とは異なる、独自の優先順位をつけようとする心の働きを、行動経済学では“心の会計(メンタル・アカウンティング)と呼ぶそうです。
行動経済学を面白おかしく知ることができる本書。文末にはこんな言葉で締めくくられています。
“人間とは、かくもヘンテコな生きものなり。”
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
