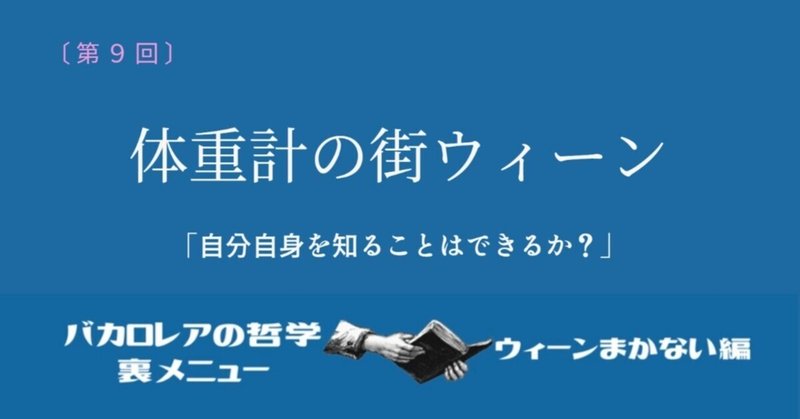
体重計の街ウィーン|『バカロレアの哲学』裏メニュー|ウィーンまかない編
今回の哲学問題「自分自身を知ることはできるか?」
『バカロレアの哲学』の裏メニュー「ウィーンまかない編」。本連載では、著者・坂本尚志さんのウィーンでの生活と、実際に出題されたバカロレアの哲学問題を引き合わせて記録していきます。

シュテファン大聖堂やシェーンブルン宮殿など、ウィーンには名所が数限りなくあります。ウィーンに暮らし始めて、街のあちこちにウィーンゆかりの著名人の像や住居を示すプレートなどがあり、ウィーンの歴史を身近に感じることができました。それが観光都市ウィーンの表の部分だとすれば、今回紹介するのはあまり注目されない裏の部分です。といっても物騒な話ではありません。街角にひっそりとたたずむある機械の話です。
謎の体重計
ウィーンに来てしばらくしてから、路面電車の停留所やバス停の近くにおいてある、あるものが気になり始めました。日本の街中で見たことのないものです。それが体重計でした。
写真を見てもらえばわかるように、機械式の立派な体重計です。大体が公共交通機関の駅や停留所の近くに設置されていますが、街中にぽつんと置かれている場合もあります。体重を測るためには20セント硬貨(約28円)を入れなければなりません。


この体重計のがっちりとしたたたずまいとウィーンの街並みのミスマッチが気になり、体重計を見つけるたびに、私は写真を撮るようになりました。ほとんどがウィーンで見つけたものですが、ザルツブルクのようなウィーン以外の都市にも設置されていました。
モデルはほぼ同じなのですが、少なくとも三色(金、銀、赤)があり、設置された場所によってもかなり印象が変わります。古いものも新しいものもあります。「これは面白い!」と写真を撮っていたのですが、家族には「何が面白いの?」と理解されず、オーストリア人の知人には「体重計? そんなのあったっけ?」とそもそも存在自体が認知されていませんでした。

体重を測っている人は見たことがありません。いつ、だれが、何の目的で設置したのでしょうか?
19世紀オーストリア帝国の技術力
調べてみると、ウィーンのみどころを紹介するウェブサイトに体重計の謎についての説明がありました(https://www.stadtbekannt.at/oeffentliche-personenwaagen/)。このサイトによると、1888年、皇帝フランツ=ヨーゼフ1世の在位40年を記念した博覧会での、オーストリアの工業製品の展示の中にこの体重計が含まれており、その後ウィーン市街に設置されるようになったということです。
今でこそ体重計はコンパクトになり、一家に一台あると言ってもいいでしょうが、当時は自分の体重を正確な数値によって知ることができるというのは、大きな驚きだったことでしょう。公衆の面前で体重を測ることに対する恥じらいやためらいはなかったと、このウェブサイトの筆者は言います。「彼らは、小銭を出せば自分の体重を自分で確かめることができることに感銘を受けた」。機械式の体重計の動きはそれ自体面白いものであったことでしょう。今も体重計は街の一部の風景です。

しかし、使う人がほとんどいない以上、体重計は時代遅れになったように思われます。とはいえ、写真を見るとわかるように、今も体重計はピカピカに磨かれ、路面電車やバス停に鎮座しています(もちろん道端で古びたものもありますが)。
19世紀に考案された体重計は、もう交換部品もないそうです。しかし定期的に維持管理が行われていることで、いまだに使用可能な状態で、あるいはほぼ新品同様の姿で、街の風景を彩っているのです。現在の体重計はユーロ硬貨が使えますが、それが最後のアップデートだったのかもしれません。
体重計の未来
手軽に正確な体重を知ることができる体重計の発明と登場は、わたしたちの身体の状態が、血圧や脈拍、あるいは血液中のさまざまな成分の多寡によって、数値化され、評価される時代の先駆けをなしていたのかもしれません。その意味では、体重計はわたしたちの身体についての知を可視化する技術が、大衆に手の届く形で現れたさきがけのひとつなのでしょう。
歴史的使命を終えた体重計は、ウィーンという都市の絶妙なアクセントになっています。あるいは歴史的な街並みの中の場違いな要素と言えるかもしれません。それでも私は、その丸みを帯びた機械仕掛けの姿になんともいえない愛着を感じてしまいます。
私にとってウィーンは、「体重計の街」といっても過言ではありません。
自分自身を知ることはできるか?
体重に限らず、現在わたしたちの周りには、自分に関するさまざまな数値や情報があふれています。健康診断の結果によって、わたしたちは生活習慣を変えたり、あるいは場合によっては治療を受けたりします。
こうした数値や情報は、わたしたちが自分自身のことを理解するのを助けてくれるように思います。そもそも、わたしたちは自分自身のことをどれだけ知っているのでしょうか。
意識のはたらきによって、わたしたちは自分自身について、あるいは外の世界について知覚することができます。風邪をひいた、怪我をした、あるいは気分がいい、悲しいなど、わたしたちは自分が今どういう状態にあるかを知ることができます。そう考えると、わたしたちは自分自身を知ることができると言えるのかもしれません。
しかし、わたしたちは完全に自分自身の状態を把握しているのでしょうか。たとえば自覚症状のない病気や体の異変、あるいは原因のわからない苛立ちや不安などは、わたしたちの意識による理解を逃れているように思われます。そうした異状は突然現れ、わたしたちの生を根本的に変えてしまうものかもしれません。意識には限界があるのです。
意識の限界を埋め合わせるためには、たとえば医学や心理学、それにもとづく測定や診断の技術を使用することも一つの解決策でしょう。
あるいは、無意識のように、わたしたちの心の中にあるにもかかわらず、その存在を意識できない領域を想定することも、心の働きを理解する助けになるかもしれません。
意識によっては、自分自身を完全に知ることができないのであれば、自己を意識することと、自己を認識する(=知る)ことの間には、埋められない違いがあるのかもしれません。そこからいくつかの問いを立てることができるでしょう。
自己を知るとはどういうことでしょうか。それは、自己を意識することと同じなのでしょうか、違うのでしょうか。もし自己認識と自己意識が違うのであれば、それはどのような点で違うのでしょうか。自分自身を知るためには、意識以外にどのような方法があるのでしょうか。意識以外の自己認識の方法は万能なのでしょうか、それとも限界があるのでしょうか。
街角の体重計の数値は、わたしたちの存在の少なくとも一部を教えてくれます。しかし、体重計がウィーンの風景のひとつの小さな要素にすぎないように、わたしたちの存在もまた、その背後に広大な領域をかかえているのです。自分自身を知るとは、そうした領域に迷い込むことだとも言えるでしょう。
日本実業出版社のnoteです。まだ世に出ていない本の試し読みから日夜闘う編集者の「告白」まで、熱のこもったコンテンツをお届けします。
