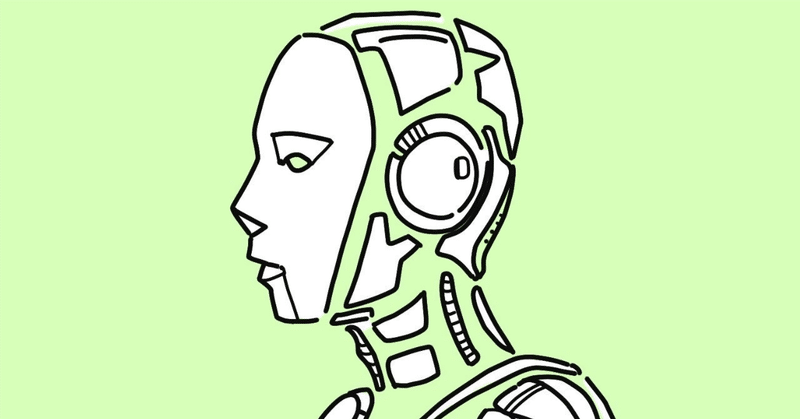
AIイラスト、AI絵師が受け入れられる方法を考える
はじめに
AIイラストはいろいろな意味でお盛り上がってますね。
どちらかというとネガティブな話題のほうが目立つ気がします。
主に著作権侵害や盗作などの問題がありますね。
はっきり言ってAIイラストはほとんどの人に歓迎されていない状況です。
今後AIイラストがどうなるかわかりませんが、どうすれば今よりAIイラストが受け入れられるのか、私なりに考えてみました。
参考にするべきAI
AIを使った製品、サービスは数多くありますが、「NEUTRINO」「Synthesizer V」「Cevio AI」「VOCALOID6」などのAIボーカルの存在は、AIイラストの在り方の参考になると思います。
上記AIボーカルの存在は、AIイラストに比べるとかなり受け入れられていると思います。
AIボーカルとAIイラストの違いを考えると、AIイラストが受け入れられる道が見えてくると思います。
愛用しているAIボーカル
不特定多数の学習をやめる
これは必須ですね。
1番の問題が著作権なので、これは必須です。
著作権フリーの画像だとしても、AIで学習されることは想定されていないでしょうから、別途許可を取るべきです。
イラストレーターにAI学習用のイラストを依頼するというのが、一番クリーンなやり方だと思います。

キャラクター化する
多くのAIボーカルはキャラクター化しています。
これは初音ミクから始まったバーチャルシンガーの文化です。
AI絵師が受け入れられづらい要因として、クリックしただけの人が作者宣言しているというのがあると思います。
AIイラストレーター「絵心アルヨ」みたいなキャラクターとしてパッケージングすることで、クリックしただけの人の絵から、絵心アルヨちゃんの描いた絵になるわけです。
SNSにアップロードするときは、「アルヨちゃんに描いてもらった!」って言って投稿すればいいわけです。
まぁ著作権の所在という問題は残りますが、現状よりは受け入れられるでしょう。
初音ミクの功績は計り知れない
人間が介在する要素を増やす
AIボーカルはすべてが自動なわけではありません。
メロディと歌詞は自分で作る必要があります。(自動作曲ソフトも出てきてはいますが…)
AIイラストもプロンプトを書く必要がありますが、メロディとプロンプトには大きな違いがあります。
それは、メロディには著作権がありますが、プロンプトには著作権が(現状は)ありません。
他人の使ったメロディは使いまわせませんが、他人の使ったプロンプトは使い回せます。
しかも1つのプロンプトで多彩なイラストをかけてしまいます。
AIイラストが、著作権にかかわるような唯一無二の要素を人間が作らないといけないシステムになれば、オリジナル作品として受け入れられると思います。
イラストを描くという行為から乖離しすぎている
AIボーカルにも特有のコツというものがありますが、基本的には通常の作曲、DTMのやり方で使用できます。
一方で、AIイラストを使うときにイラストの知識は不要です。
というより、イラストの知識は役に立ちません。
今まで頑張ってイラストの勉強をしてきた人は、今までの努力が無駄になったと感じるでしょうし、AI絵師をズルいと思うのも当然です。
通常のイラストを描く手順に、なんとかAIを落とし込んでほしいものです。

クリエイターのためのAI
私は音楽を作るときにAIを活用します。
作詞、作曲、編曲は自分でやりますが、ミックスとマスタリングという工程はAIツールを利用しています。
iZotopeの「NEUTRON」と「Ozone」というツールです。
ミックスとマスタリングは専門のエンジニアがやるような難しい工程ですが、AIの力を借りて初心者でも簡単にできます。
AIの力を「借りる」というのが重要だと思います。
上記ツールは自動で80%位のクオリティにしてくれますが、その先は自分自身でやる必要があります。
利便性とクリエイティビティがいいバランスで確保されていると思います。
AIイラストにおいても、ワンクリックで完成品が出てくるものではなく、使用者のクリエイティビティーが加速するようなツールが出てくるといいですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
