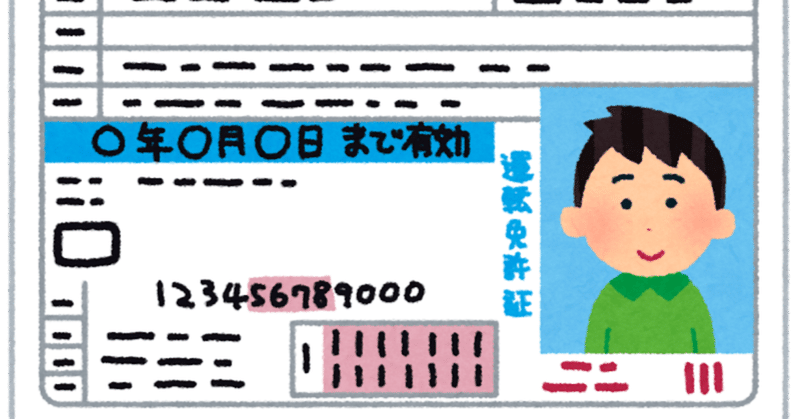
40歳手前で自動車免許を取得した男
2022年、38歳で普通自動車免許を取ろうと考えた。38とかおっさんやんという話は置いておく。今まで1ミリもそんなことは考えたことがなかったのだが、40歳も手前に差し掛かった自分を省みたとき、最近何にも挑戦してないこと気づいたので、今までの自分だったら絶対にやらないことをやろうと決め、自動車免許取得に挑戦することにした。
なんで今まで取らなかったかといえば、シンプルに向いてないという直感があったからだ。元々咄嗟の判断力に欠けており、運動神経も終わっているので、運転が上手くないだろうなという予感はあった。原付の免許は持っていたのだが、車と原付は訳が違う。
今年の6月に、大学生に混じって自動車学校の門をくぐり、MT車はほとんどないらしいからATでいいやと思い、ATを選択し、高い金を払い、説明を聞き、申し込みを済ませて、いよいよ初日の運転ということになった。全体的に話が長い。
初日の運転だが、自分に対する予想は大体あたる。思った通り運転はど下手くそだった。全く感覚が掴めなかった。急勾配を登って降るあたりで先の道路が見えず、どうやって進めばいいのか皆目見当もつかないのだ。教官はもっと先を見ろしか言わないので、先を見てどうすんねんと思いながらあたふたしていると、初日の1コマはあっという間にすぎていた。すでに車校には行きたくなくなった。しかし加齢によってこうなったのかはわからない。元々運動神経は終わっているので、20代で始めたとしても大差なかった説はある。憂鬱な気分だったが、今までやらなかったことをやるというのがテーマなので、続けることにした。
そこから何回か乗ったものの、いつになっても運転の間隔が掴めず、左折も右折もカーブもS字もクランクも、上手くいってるのかいってないのか、なぜできているのかできていないのか、よくわからない状態が続いていた。全過程で脱輪したのはクランクの一回だけで、あとは落ちそう落ちそうと言われてたくらいなのだが、上手くいく理由は言語化できていなかった。
教官の指示がよくわからず、左に寄りすぎとか右によれとか落ちる落ちるとか言われながらひたすら教習をこなしていった。身体感覚を教えなければならないという意味で、車校の教官とは大変な仕事である。
学科はオンラインで受けれるものだったが、50分気を抜かずに聞き続けないといけないシステムだった。気力を振り絞り、かろうじて1日ひとつずつ終わらせていった。
効果測定という仮免前のテストがある。簡単だという噂だが、90点合格で2回も落ちた。2回とも88点という奇跡である。結局3回目で合格だった。
仮免の検定の前にみきわめというものがあった。検定受けていいかどうかかのみきわめである。検定の前日の受けたのだが、これが結構散々だった。発進の確認を忘れる、巻き込み確認を忘れる、S字は落ちかける、という具合である。そんな状態でも、一応みきわめは合格だった。
みきわめの出来が終わっていたので、仮免は実技で当然落ちるものとして、学科の勉強をあまりやっていなかった。当日は受験者が三人いたのだが、番号が二番目で、最初の人の運転に同乗できたので、全てを確認できたのが幸運だった。コースも把握できたし、合図の位置も確認できた。おかげでスムーズに運転でき、技能試験は無事合格だった。問題は学科試験である。合格すると思っていなかったので、待機時間に必死でオンライン問題を解きまくっていた。学科は効果測定より簡単に感じたので、それほど恐れる内容でもなかった。結局は一発で合格だった。3回くらい落ちる予定だったので、どうせ落ちるからといいやと思い、緊張しなかったのが大きかったかもしれない。ちなみに一人だけ学科で不合格だった。普通に勉強しないと落ちる。
1週間後から路上教習だった。一発目から左に寄りすぎ、右に寄りすぎ、車線はみ出そう、などなど言われたい放題だった。
路上教習3回目から教官が変わった。理由は不明である。教官が変わるとテイストも変わるようで、運転中にあれこれ言われて気が散ることがなくなり、運転しやすくなった。その後も何回か人が変わったが、言っていることはよく理解できたので、最初の教官だけよくわからなkった。しかし実際に誰が良かったのかはわからない。気持ちよく運転できるようになっただけで、本質的には最初の教官の方が良かった可能性はあるし、自分が慣れただけの可能性もある。後付けではなんとでも言えるものの、結局は何が良かったのか、本当に分析することは難しい。なんにせよ、教官変更によって乗れる時間が圧倒的に減ったため、免許取得までが長くなったことだけは確かだった。
ここからは乗るのも週1回くらいで、仮免取得が7月だったのに卒検は12月だった。その間はあまりやる気がなく、まあ期間内に卒業できればいいか、くらいの感じだった。不安なく運転できるかな、くらいに車の感覚が掴めてきたのは路上に出て10時間目くらいだったと思う。場内にいるときは左折するのもしんどかったが、人間慣れるものである。この辺からは慣れてきたので特に思い出もない。
ちなみに卒検前の効果測定も2回落ちた。90点合格の試験を89点で2回落ちている。仮免前も合わせると効果測定はトータルで4回落ちた。ギリギリで受かろうとすると落ちるように作られているとしか思えない。そして卒検前に大量に学科が残っていたので気が重くて仕方がなかったが、対面必須のものは自動車学校で受け、後は気力でなんとか終わらせた。高速教習も特に困ることなく終了した。
12月某日。見極めは特に問題なく終わり、卒検の日となった。試験は一発目の組で、とにかく一発アウトだけは避けようと意識した。完璧とはいかなかったが、卒検も無事一発合格だった。修了検定とは異なり卒検は全員受かっていた。合否が出るまでかなり長かったので落ち着かなかった。
卒検から1週間後に本免の筆記試験を受けた。問題集サイトの満点様を2周くらい、市販の問題集を2冊終わらせてから受けたものの、なかなか微妙な感じだった。少なくとも自信を持って受かったとは言えない出来で、免許センターが遠いのでもう一回来るの面倒だな、と思いつつ合格発表を見ると、電光掲示板に自分の受験番号が載っていた。喜びというよりは、ようやく終わってホッとした。6月から自動車学校に行き始めて、取れたのは12月の長丁場だったので、それも仕方がない。ちなみに落ちている人は結構いた。言われるほど簡単とは思えない試験である。仮免よりも、卒研よりも、最終筆記で落ちている人がダントツで多かった。多分2〜3割くらい落ちていた。自分も2000問くらいは解いていったはずだが、それでも見たことない問題があったし、イラスト問題の選択肢がどっちとも取れる気がして、なんとも引っかかる試験だった。
そしてウキウキな解放気分が吹き飛ぶほど待ち時間が長かった。3時間弱待たされ、ようやく写真を撮る時間になり、パシャっとして免許が交付された。写りは微妙だった。
全体を振り返ると、慣れるまでの不安と、効果測定に4回落ちるというやらかしはあったものの、まあまあどんくらいアラフォーでも、自動車免許が取れることは証明できた。苦手なことでも、やり続ければなんとかなるものだ。とはいえ、なかなか難しいというか、しんどい資格だった。ネットではオールストレート合格が当たり前のような風潮になっているが、勉強しなければ普通に落ちるし、実技も仮免辺りは身体感覚が鈍い人はかなり不安になると思う。自分もそうだった。
免許をとって一つ変わったのは、自動車のメーカーがやたらと目に入ってくるようになったことである。人間がいかに興味のない情報を視界から切り捨てて生きているのか、明確に理解することができて、今更ながらに驚いた。
今後車に乗るのかどうかはわからないが、免許取得の一番大きな効用は、この事実に気づいたことだと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
