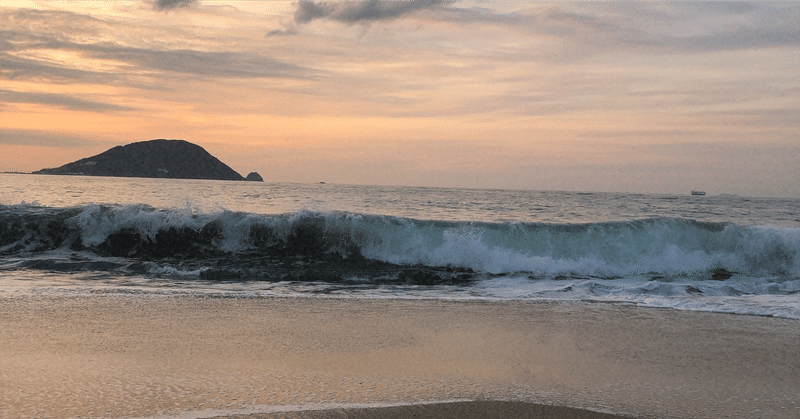
作家の思想を追いかける
平野啓一郎氏の『ある男』『本心』を立て続けに読んだ。数年前に『マチネの終わりに』を読んでいらいの平野作品。
当時『マチネの終わりに』になぜ手を伸ばしたのかはあまり覚えていない。たぶん映画化されて気になったからだと思う。
今回読み始めたのは、平野氏の思想が色濃く小説に反映されているのではと考えたからだ。きっかけは最近刊行された『三島由紀夫論』を本屋で見かけたこと。ぜひ読んでみたいが、文量と値段を考えて買うことが出来ていない。この本を本屋で手に取り、三島由紀夫に大きく影響を受けていることを知った。
三島由紀夫といえば、私にとっては猪瀬直樹氏の『ペルソナ』だ。
猪瀬氏の評伝が好きな私はこの本を何度も読んだ。三島由紀夫自身だけでなく、その思想の背景となった祖父平岡定太郎や、そのボス原敬まで遡って、当時よくそこまで調べ上げることが出来たなと感心した。そして三島作品にはその時代の風潮や、自身がこれまで積み上げてきた思想が色濃く反映されていることを知った。
ここで自分が考えたのは、「自分の思想を小説に込めている作家が今どれくらいいるんだろう」だ。
もちろんどの作家も、自分を形作る思想・考えがあり、それを文学や論考という形で表現しているはずだが、私は小説を読みながら「この人の思想はどこにかかれているんだろう」と考えながら本を読んだことが無かった。単純にその小説の世界に浸る、楽しむ事自体とても素晴らしいし有意義なことだ。そういう時間がとても好きだ。だが、せっかくなら作家がどういう考えを以てこの本を書くことになったのかを知りたいと思うようになった。
そこで三島由紀夫の『金閣寺』を手にした。ちょうど京都旅行をしているときに烏丸御池の大垣書店で。
読み始めると、時代による言葉の使い方のせいなのかスタイルのせいなのか非常に難読だった。何を言いたいのかわからない。主人公は最後に「生きよう」と言った。猪瀬氏はそう言わせた三島の心情を『ペルソナ』で詳細に書いてくれている。こういうことがわかるようになりたいと思った。
そこで現代の作家でさがしてみようということで、平野啓一郎の本を読み始めた。
それぞれの本については別のnoteで書こうと思うが、印象的なのは「分人主義」。
「分人dividual」とは、「個人individual」に代わる新しい人間のモデルとして提唱された概念です。
「個人」は、分割することの出来ない一人の人間であり、その中心には、たった一つの「本当の自分」が存在し、さまざまな仮面(ペルソナ)を使い分けて、社会生活を営むものと考えられています。
これに対し、「分人」は、対人関係ごと、環境ごとに分化した、異なる人格のことです。中心に一つだけ「本当の自分」を認めるのではなく、それら複数の人格すべてを「本当の自分」だと捉えます。この考え方を「分人主義」と呼びます。
職場や職場、家庭でそれぞれの人間関係があり、ソーシャル・メディアのアカウントを持ち、背景の異なる様々な人に触れ、国内外を移動する私たちは、今日、幾つもの「分人」を生きています。
自分自身を、更には自分と他者との関係を、「分人主義」という観点から見つめ直すことで、自分を全肯定する難しさ、全否定してしまう苦しさから解放され、複雑化する先行き不透明な社会を生きるための具体的な足場を築くことが出来ます。

私が読んだ3冊はどうやら後期分人主義に属する。『ある男』では分人主義という概念がよく分かる。出生の悩みを抱える主人公の城戸が一時でもいいから別人になりかわることに恍惚とした感情をいだいたのが印象的だ。『本心』では、主人公朔也だけでなく、彼の母や三崎、そしてイフィーも「さまざまな仮面(ペルソナ)を使い分けて、社会生活を営む」存在として描かれていた。朔也の職業であるリアル・アバターはまさにそれを象徴するようなものだし、バーチャル空間ではアバターをまとい現実世界における「こっちの世界」「あっちの世界」のような格差を超えることが出来ていた。
分人主義という言葉、別の本を並行して読んでいると偶然登場してきた。それが『実験の民主主義』だ。日本を代表する政治思想研究家の宇野重規氏のその本では、現在の民主主義の1人1票はすでに機能していないのではと話しを展開する。自分の思想と全てが同期する政治家や政党を選挙で選べるわけがない。経済、社会保障、教育、外交、安全保障など様々なイシューに対して、それぞれ投票できる仕組みをあげてくれた。まさにこれも分人(民主)主義につながった。
そして今度は分人民主主義を検索してみると、なんとスマートニュースの鈴木健氏の『なめらかな社会とその敵 ──PICSY・分人民主主義・構成的社会契約論 』に出会った。本のタイトルは知っていたがその副題に「分人民主主義」があるとは。
次に読む本が明確になった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
