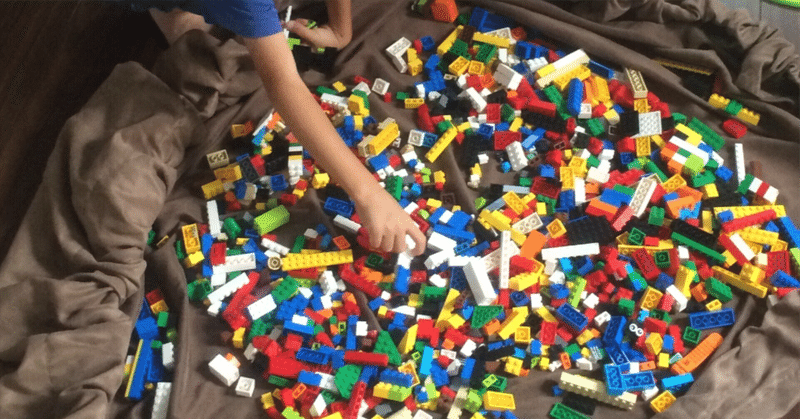
【読書記録】ブロックでなんでもつくる!ビルダーの頭の中
おすすめ度 ★★★★★
レゴのすごい作品見てると、「作った人の頭ん中どうなってるんやろな」と思う。
その頭の中を見せてくれるというすごい本。
こちらも毎日小学生新聞のおすすめ新刊コーナーにのってて、息子が好きそうなので読ませてみた。
最初のページから、カラーでレゴ作品が満載で、興奮する。すごい。
息子とキャッキャしながら見た。
*
有名な作品だから、知っているかもしれないけど例えばこれ↓
本の中身は、ビルダーである三井淳平さんの自伝で、レゴとの出会いから今の仕事に至るまでが書かれている。
とてもテンポが良く、レゴ好きの子に語りかけるような書き方なので、読みやすい。
小学校高学年くらいから、楽しく読めるんじゃないかな。
*
さかなクンの自伝を読んだ時も思ったけれど、その道を極めた人というのはやはり小さい頃からずば抜け具合がずば抜けている。
このかたの場合、勉強もずば抜けている。
受験生だったけど、TVに出る機会があったから挑戦しました。と書かれていて「あらあら、受験はどうしたのかな」と思っていたら、「4月に無事、東京大学に入学できたので」とサラリと書かれていてひっくり返る。
お、おま東大そんなテンションで行けるもんなの…
*
レゴの作品それぞれを楽しく解説してくれる章も面白い。
全然レゴできない私でも、レゴ好きの息子でも面白く読めた。
例えば通天閣を作る時は、四角形のレゴで三角形の構造を作るのが大変だという話をしつつ、
ブロックを斜に組むためのパーツとして「ヒンジ」と呼ばれる角度を変えるパーツがありますが、これを使うと「無理数」と呼ばれる厄介な数字が出てしまいます。
このあと、無理数の説明のためにピタゴラスの定理の話がサラリとなされ、色々計算しながらレゴの的確な位置を決めることの難しさを語っている。
レゴで通天閣つくりました!高さ2.5m超!
— 三井淳平 / Jumpei Mitsui (@Jumpei_Mitsui) November 18, 2020
デフォルメせずに忠実に再現し、通天閣の繊細なトラス構造をうまく表現できたのではないかと思います。
文字部分は関係者に許可いただいてレゴ版にさせていただいています。ご協力いただいた皆様ありがとうございます🙏 pic.twitter.com/d54NNSZb1t
頭の中どうなってんねんと思ったけど、中身みたところで全然わかんない。
他にも、風神雷神図屏風を作る時に日本画らしいボケた感じを出すために3種類の解像度を用意したとか。
マインクラフトのジオラマを作るために、世界観と構造を理解するために100時間プレイしたとか。
レゴ マインクラフトの巨大ジオラマ完成しました!
— 三井淳平 / Jumpei Mitsui (@Jumpei_Mitsui) August 12, 2023
制作期間2か月、推定200kg。
海洋やディープダークを作り込むため、新工法を開発してレゴブロックのみで底上げし、高さを出しています。
昨日のお披露目イベントでは、HIKAKINさんに「思っていた10倍くらいスゴかった」と言っていただけました🙏 pic.twitter.com/Y1P5OS5MQZ
もう、すごすぎて笑ける。楽しい。
あまりに淡々と書いているので、自分も賢くなったような錯覚に陥る。楽しい。
息子とも「やばいよね」「やばい」という賢さゼロの会話をした。楽しい。
*
また、言語化能力の高さにも驚かされる。
頭の中の説明にしても、デザインの視点、アートの視点、試行錯誤の繰り返しとその大切さなど、ひとつひとつ無駄なく構成されている。
まるでレゴを分解して組み立てるような、言語化の仕方だと感じた。
頭の中もレゴみたいになってるんだな。
最後には、「好きを仕事にする」ことへの持論も書かれていて、とても良い内容だった。ちょっと長いけど引用すると
好きなことを仕事にするためには、小中学校で何を勉強すればいいでしょうか?ぼくは、全部やったほうがいいと思っています。それは、小中学校で学ぶことには、基本的なことがひととおり詰まっていると思っているからです。
国語は、仕事相手に仕事の内容をわかりやすく伝えるために必要です。
社会は、自分の仕事が世の中にどう役に立つのかを知るために必要です。
算数は、作るもののサイズやかかる時間を考える時に必要です。
理科は、仕事がうまくいかなかった原因を考えたり、やり方を変えてみたり、考える力を身につけるために必要です。
体育は、仕事をする体力をつけるために必要です。
いいなぁ。こういう押し付けがましくないけど合理性のある話って一番子どもに響く気がする。
大人の私にもめちゃ刺さった。使わせてもらおう。
*
最後に。
この本の「みんなの研究」シリーズは他にもあって、おまけ冊子に他の本も載ってたんだけど、どれも楽しそう。
子どもたちも好きそうだし、他のもトライしてみようかな。
あとでみたメイキングがマジで凄かったのでこれも載せる。
設計図は作らないという著者の、作っては壊し作っては壊しがすごい。ずっとみていられる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
