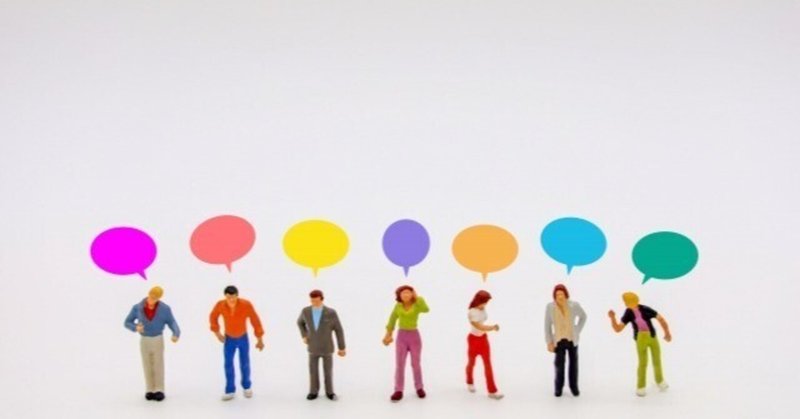
なぜ、方言を考えているのか?
こんにちは、うがいまさみです。
昨日、第3回日本語教師のための方言の会を開催しました。
8月から始めた会ですが、
毎回いろんな出身地の日本語教師が集まって、
自分の体験談やユニークな資料を持ち寄って
のんびりとお話をする会となっております。

今回ご参加くださったのは
三重県、香川県、大阪府、京都府、青森県
に、バックグラウンドをお持ちの先生方です。
(ちなみに私自身は、
実家では津軽弁、学校では仙台弁に接しながら育ちました★)
最近、SNSなどでは出身地ごとに集まって
方言ネタで盛り上がることはありますが、
違う方言話者同士が集まって話す機会は
あまりないように思います。
そこで、日本語教師というカテゴリで
自分の「推し方言」について語ってもらったら
方言に対する新しい見方ができるんじゃない??
と思ったのが、この会発足のきっかけでした。
同じ方言でも、実は
地域や年齢によってずいぶん言葉が違うようですし、
共通語との違い、そして
いわゆる「気づかない方言」などもあるので、
もともと言葉に敏感な日本語教師メンバーの
お話しは毎回大盛り上がりです。

(よく みやぎに いらっしゃいましたねぇ)
なかなかここまで話す宮城県人も、もういないでしょうね。。
私が小さい頃、特に東北地方では、
方言はハズカシイものだと思われていました。
ところが今では、方言女子や方言男子という言葉や
「方言はカワイイよね!」なんて話も聞かれるようになりました。
方言にプラスのイメージが加わったことは、
素直に嬉しかったです。
そして、ここが自分の中でいちばん印象的だった情報ですが、
CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)という
ヨーロッパの言語学習・言語教育のガイドラインの勉強会に参加したとき、
方言や訛りも言語として大切にされていることを知って、
非常に感動したんです。。
なんだかね、大げさかもしれないけど、
これまで訛りを恥じてきた東北の人たちの名誉が
回復されたような気がしたんです。

日本語の共通語の他にも
方言が各地域に住んでいる
外国人と日本人のコミュニケーションの
助けになることがあれば…
いつかはそんなお手伝いが出来たらいいなと思っています。
けれど今は、そんな堅苦しいことは考えず
みんなで楽しく方言の情報交換を
していけたらいいなとポイント思っています。
来月も方言の会を開催予定です。
詳細が決まりましたら、noteでもご案内いたしますね。
それでは、また。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
