
看護師でディレクターの私が、臓器移植をめぐる“命の葛藤”を取材して考えたこと
突然ですが、「臓器移植」と聞いて、どんなイメージを持ちますか?
免許証や保険証の裏にある臓器提供の意思を問う記載などで見たことはあっても、なんだか縁遠い話だと感じる方も少なくないのではないでしょうか。
タイトルの通り、私は以前、看護師として病院で働いていましたが、医療現場の実態を自ら伝えたいとNHKのディレクターに転職しました。
「臓器移植」はエントリーシートに”取材したい”と宣言していたテーマで、2021年とことし、2本の番組を制作しました。
「臓器を提供する側」と「移植を待つ側」、同じ臓器移植でも、真逆の立場から「命の葛藤」について伝えた番組です。
看護師からディレクターになった私が臓器移植をめぐる命の葛藤を取材した経験から、「命と向き合うこと」について、お伝えできたらと思います。
医療現場で感じた「知ってもらうこと」の大切さ
私は看護師として、大学病院の精神科病棟で2年間勤務していました。10代のころ、家族が突然、心の病になったことがきっかけです。
心の病とはなんなのか。そのケアや、周囲の家族への支援について学びたいと、精神科の看護師を目指しました。
病棟で働く中で、たくさんの患者さんや家族と出会いました。いまだにどの方も鮮明に覚えています。
10代、20代の発達障害や統合失調症の患者さん、働き盛りのうつ病の方、認知症の高齢者の方など、世代も病気も本当にさまざまでしたが、みんな複雑な背景や苦悩を抱え苦しんでいることを知りました。
そして、患者さんが入院生活で少しずつ回復し、家庭や社会に戻っていく日々に携わる看護師という仕事に、やりがいを感じていました。
一方で、精神疾患に関する偏見はいまだに残り、患者さんの家族でさえも症状に苦しむ本人の病気を受け入れられないことや、「勤めている会社の理解がない」と患者さんから聞くこともありました。
「どんな病名がついていても、みんな普通の人なのになあ」と感じながらも、外から見ると「精神疾患は少し怖い…」という印象が持たれてしまう現実を突きつけられ、当事者の苦しみと、それに対する社会の認識の差にモヤモヤとした課題意識を感じるようになりました。
看護師として、目の前の患者さんが良くなっていくことにやりがいを感じていたものの、患者さんたちの生きづらさの根底に、社会の偏見や無理解があることを考えると、看護師や医療としてできることの限界も強く感じるようになり、伝えること・知ってもらうことの重要性に意識が向くようになっていきました。
そうした中で頭に浮かんだのは、もともと好きだったドキュメンタリー番組。
特にNHKは、がんの緩和ケアや、うつ病の最新治療など医療の課題に正面から切り込んだ番組が多くあり、「目の前の精神科病棟で起きている実態を知ってもらうだけでも、何かが変わるのではないか」という、今思えば結構無茶な理屈が頭の中で渦巻くようになっていました。
そこで、思い切って当時の上司、看護師長に相談すると「あなた若いんだから、やりたいことやった方がいいわよ!」と、気持ちがいいほどに背中を押してもらい、就職試験を受けることになりました。

伝えることの責任の重さを突きつけられた新人時代
なんとか採用され、最初は静岡放送局に赴任しました。
数ある仕事の中でも、先輩ディレクターの補佐として関わった「在宅でのがんの緩和ケア」の取材が印象に残っています。地域医療が連携し、在宅でも「緩和ケア」を行うという取り組みでした。
こうした先進的な取り組みをテレビで伝えることで、「他の地域でも取り入れようという動きが出るかもしれない」と思うと、転職のモチベーションの1つでもあった「広く伝えることの意義」を改めて感じることができました。
ただ、その取材の中で、ひとつ忘れられないできごとがあります。
在宅で緩和ケアを受けていた80代の女性患者に、デジカメを持ってひとり密着し、治療の日々を撮影していたときのことです。
撮影をはじめて1か月ほどたったある日、患者さんが息を引き取りました。
ご家族は危篤の際に私を呼んで下さり、「撮影しても良い」と言ってくれたのですが、私は戸惑い、どうしていいかわからないまま、結局、亡くなった患者さんにカメラを向けることができませんでした。
地域での緩和ケアの現状を伝えるために取材に入り、ご家族もそのことを望んでいたのに、私はその責任を果たすことができなかったのです。
「起きている事実を伝えること」の責任の重さを心から痛感し、特に人の「生き死に」にかかわることを伝えるには、その人の人生を背負う覚悟を持って取り組まなくてはならない。取材者として、中途半端な自らの姿勢を猛省した経験となりました。
転職当時から考えていた、臓器移植のこと

『臓器移植法の改正。この改正によって命の在り方はどう変わっていくのかとても興味深い。臓器移植の適応が広がったことで新しい生命への道が拓けるというメリットは大いにあると私は思う。しかし脳死となった人の生命の意味、残された家族の思いは計り知れない。臓器を提供する家族、される家族、双方の思いをテレビを通して多くの人に知ってもらうことは、改めて生命について考える大切な機会となり、とても意味のあることだと思う。そうした報道に携わりたいと強く思う』
2009年、NHKの採用試験のためのエントリーシートを書くとき、医療従事者としての視点が生かせないかと、ニュースを見ていました。そこで「臓器移植法の改正」が目にとまり、思うことを書きました。
改正臓器移植法は2010年に施行され、本人の意思がわからなくとも、15歳未満でも、家族の同意があれば臓器提供が可能になりました。
日本の臓器移植において、1つの大きな転換点となる法改正で、当時から「提供する家族」「提供を受ける家族」の思いを知りたいと感じ、シートにも記しています。
そして、ディレクターに転職してちょうど10年、法改正からも10年の節目に、放送を目指して番組の提案書を書き始めました。
記者やプロデューサーと、どんな目線で取材を進めるか議論をする中で気づいたのは、「臓器を提供した側」について、NHKではほとんど伝えられていなかったこと。そこで番組では、ドナー家族に焦点をあてることにしました。
“脳死となった我が子の命” 家族の葛藤
取材に動き出してすぐ、想像もしていなかったことを知りました。臓器提供をした方には、事故や自殺で亡くなったケースが少なくないというデータが出てきたのです。
臓器移植は、時に「命のバトン」などと称され、美談として語り継がれることがありますが、実際は、「“悲しい死の上に成り立っている医療”なのではないだろうか…」という感覚が強まり、その実態を知ることを原動力に取材に走っていきました。
しかし、臓器提供において、その取材は「大切な家族の死」という、ご家族にとっては思い返したくない、つらい経験に踏み込むものです。具体的な話を聞くことは容易ではなく、取材は難航しました。
そんな中で小児救急の医師を通じて出会ったのが、9歳の乃梧くんの臓器提供を決断した、伊藤さん夫婦です。
小学3年生になったばかりの4月に交通事故に遭い、意識が戻らないまま脳死となった乃梧くん。ご夫婦は、「臓器だけでも生きてほしい」という強い願いで提供を決断したと話をしてくれました。

私自身も3児の父です。同年代の子どもがいるひとりとして、我が子が生死をさまよい、「もう助からない」と覚悟して臓器提供を決断したことを想像すると、本当に苦しい気持ちで胸がいっぱいになりました。
そして、看護師として勤務していたときに感じていた医療の限界についても、頭の中で思い返していました。医療は魔法のように全てを救うことはできない、という現実です。
回復して退院した直後に、自ら命を絶ってしてしまった患者さんや、自殺未遂を繰り返し、後遺症で元の生活が送れなくなった患者さん。
成す術なく無力さに打ちひしがれるような思いは鮮明に残っています。
だからこそ、助からない命に直面した伊藤さんご家族の苦しい心境は痛いほど想像ができて、臓器提供をした当時のつらい思いを掘り返すような取材をこのまま進めていいのだろうかと、気持ちが揺らいでいきました。
乱暴な表現ですが、「こんなつらく苦しい思いがあって臓器提供がなされているのならば、いっそのこと移植医療はない方が良いのではないか」と考えることさえありました。

しかしご両親は、臓器提供は「乃梧の体の一部、臓器だけでもどこかで生きてほしい」という願いなのだと教えてくれました。
そして、「最愛の息子の生き様を多くの人に知ってほしい」と本当に丁寧に、乃梧くんが生きた9年の人生を涙ながらに話してくれました。
取材を受けてくださった他のご家族も、亡くなった家族の思い出をかみしめながら、思い返すように話をしてくれました。
伝えることの責任と覚悟
そこで気づかされたのは、臓器提供を決断するまでの時間は「家族がその人と過ごした大切な時間を振り返った時間」だということでした。
だからこそ取材やインタビューそのものが、大切な家族と過ごした思い出を、私もご家族と一緒にタイムスリップしたかのように振り返る時間で、ご家族は「大切な思い出を全て伝えたい」と覚悟をもって話をしてくれるのだと、強く感じるようになりました。
そうであれば、取材者として全てを受け止め、伝えていくことが自分の責任だと私自身も覚悟を決めなくてはならない。
静岡局時代に、ご家族の最期を伝えきれなかったことを思い返し、ご家族の生きた時間を丁寧に聞き、映像に収めていていくことに努めました。
「家族がその人と過ごした大切な時間」=「当たり前だった日常の尊さ」を伝えることで、番組を見た視聴者も自分ごととして、それぞれの「日常の大切さ」を思い返すきっかけになればと思いを込めて、番組を制作しました。
放送後、視聴者からは「臓器提供の背景にこれほどまでに苦しんだご家族の葛藤があったことをはじめて知った」、「毎日を普通に過ごせるありがたさを痛感した」、「決してひと事ではなく、臓器提供のことを家族で話し合おうと思った」などの声が寄せられました。
誰かの臓器をもらって生きる選択
一方で、臓器提供を決断した家族の並大抵ではない思いを知ってしまったからこそ、誰かの臓器を受け取り、移植を受ける側の思いも気になるようになっていました。
そうした思いを抱く中でことし、「臓器あっせんをめぐる事件についての番組をやらないか」とプロデューサーから声をかけられ、今度は「移植を待つ側」の取材を行うことになりました。

この事件の背景にあるのは、臓器移植を受けなければ助からない、移植を待つ患者さんたちの切実な現状です。
慢性的なドナー不足が深刻な日本では、特に腎臓移植の場合、待機期間は平均15年におよび、移植を希望しても叶わないまま亡くなってしまう人も決して少なくないという現実がありました。
いつ移植ができるかわからない中で、命のリミットが迫ってくる恐さ、苦しさは想像できる一方で、臓器提供をめぐる家族の決断の重さを知っているがゆえに“誰かの臓器をもらってでも生きたい”という思いがどんなものなのか、腹落ちしきらない自分もいました。
それを私に教えてくれたのは、腎不全を患い余命宣告を受け、腎臓移植を待っている小沢克年さん(54歳)でした。
2時間にわたるインタビューの中で、最後の最後に心の奥にあった葛藤を言葉にしてくれました。

「(移植で)生き長らえることができるよっていうのと、諦めてもう寿命を迎えるっていうところの、僕は今はざまにいるはずなんですよね。際に。僕が諦めれば、その寿命が尽きるまでっていう、近い将来のことになるし、手術がうまくいけば、それよりかは長生きできるだろうっていう、そこの縁に立っていると思っているので。
だけどそれは本当にいいことなんだろうか、いや、そうじゃないのかっていう/そこに立って悩み続けているし。これからも、いざ手術が終わって、もうちょっと長く生きられるだろうっていうことになっても、生きながらそれは悩み続けるんじゃないかなって」
はじめて知った、移植を待つ患者さんの複雑な心境でした。
「誰かの臓器をもらってまで生きていいのか」と葛藤を抱え、日々「この選択は正しいのだろうか」と苦悩しながら過ごしていたのです。
周囲の“生きてほしい”という願い
さらに、取材を通して知ったのは、 本人の“生きたい”という思いだけでなく、家族や友人など周囲の人の“生きてほしい”という願いが「移植を受ける」という選択に結びついていることでした。
小沢さんも、移植をすると踏み切った理由の1つは、ご家族やラグビー仲間の“生きてほしい”という思いを受けての決断でした。
このとき、ふと、これは臓器提供を決断したご家族の「臓器だけでも生きてほしい」という願いと通ずるものがあると思いました。
「臓器だけでもどこかで生きてほしい」と願い、臓器を提供した家族と、
「誰かの臓器をもらってでも大切な人に生きてほしい」という家族の願いは、状況は全く違えども、なんだか結びついているような気がしたのです。
“命に向き合う葛藤”から教わったこと
臓器提供を決断した家族と、移植を受けなければ助からない状況に置かれた方々の話を聞いて突きつけられたのは、当たり前の日常が、いかに特別で大切かということです。
「本当にそのときは、その時間が特別なものだなんてこれっぽっちも思わなかったですけど、今思えば、そんな日常がすごく大切な時間だったんだなって思います」
臓器提供を決断したご家族のこの言葉が、全てを物語っていると痛感します。
日々忙しく過ごす中で軽んじてしまいがちな“当たり前の日常”ですが、命と向き合った方々の言葉は、「いま大切なことは何か、幸せとは何か」をいま一度考えるきっかけとなりました。
こうしたメッセージが伝わればと、番組を制作しました。
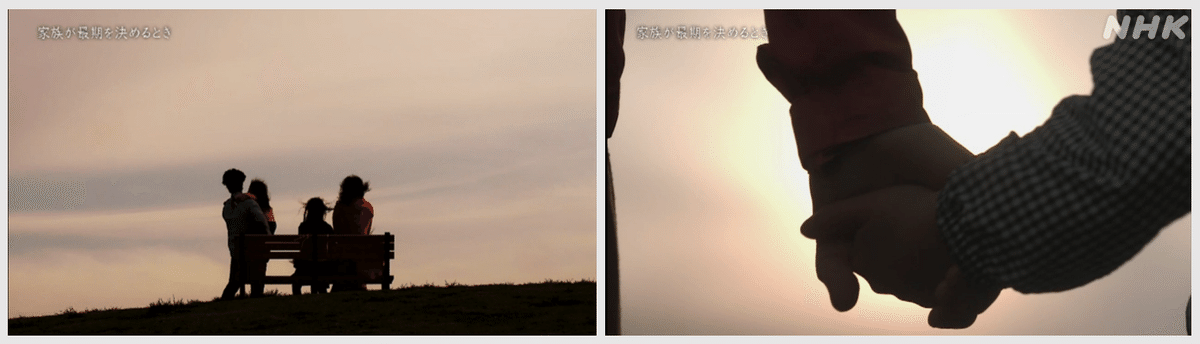
そしてもう1つ、番組を通じて届けたいことがありました。
それは、臓器提供の決断に直面することも、移植が必要になることも、決してひと事ではないということです。
誰しもそんなことは想像もしていないからこそ、自分も含めて何かの事態に直面したとき、冷静に考えることは容易ではないと思います。
だからこそ、公共放送として、そうした状況になったら何が起きるのか、何を準備しておけばいいのかを番組を通して伝えることが大切だと考えています。
仮に臓器提供の決断を迫られたらどうするか、番組やこの記事をご覧いただいたみなさんが家族と話し合ってくれたなら、ディレクター冥利につきると心から思います。
臓器提供の決断のみならず、自分や家族、大切な人の生き死ににかかわるようなことが起こることは決して望まないし、考えたくないものです。しかし、医療現場のスタッフは、日々、生死にかかわる厳しい現実と向き合っています。
私自身もかつて医療に従事してきた一人として、そしてディレクターとして、目をそらしたくなるような厳しい現実があったとしても、そのとき何が起こるのか、何を考えなくてはいけないのかをしっかりと伝え、誰かがそうした事態に直面したときの助けとなるような番組を今後も制作していきたいと思います。
北條 泰成
2010年入局、静岡放送局→報道局ディレクター。「おはよう日本」「首都圏情報ネタドリ」を経て、現在は「クローズアップ現代」や「NHKスペシャル」などを担当。
臓器移植をはじめ、救急医療、医療的ケア児など幅広く医療に関するテーマを取材。看護師・保健師免許あり。
関連記事

