
今、注目の劇団って、どこで見られるの?!
「3年でスズナリ、5年以内に本多劇場進出!!」
「次に来る演劇? 駅前劇場のラインナップ見たら分かるよ」
客席数の少ない劇場から、実力をつけながら観劇ファンの心をつかみ、中劇場、大劇場へと駒を進めていく・・・。誰がそう呼び始めたのかは分かりませんが、東京の演劇界には、『演劇すごろく』なるものがあり、演劇ファンにとっては観劇の際の指針、つくり手にとっては目指すべき劇場の指針となっていました。
2023年現在、すごろくが、消えかけています――
では、今、注目の劇団は一体どこで見ることができるのか。
今回は、たよりとなるものが分かりづらくなった今の演劇界において、新たな指針のひとつになろうとしている『演劇コンテスト』について、ご紹介します。
演劇コンテストとは、いったい何なのか。
運営している人たちは、どんなことを考えているのか。
とある共通点を持つ、3つのコンテスト事業の主催者に集っていただき、それぞれの事業の特徴や、どのような視点で団体を選出しているかを、聞いてみました。
お話を聞かせてくださった方
2008年、若い才能の発掘と育成を目的に開始。日本国内で舞台芸術活動を行う団体・個人を幅広く募集し、選考により決定したアーティストにシアタートラムでの上演機会を提供。公演実施にあたっては、世田谷パブリックシアター支援のもと、会場提供にとどまらない、参加アーティストのさらなるステップアップ、作品の醸成をバックアップします。
公益財団法人せたがや文化財団
大下玲美さん
世田谷パブリックシアタープロデューサー。明治大学文学部文学科演劇学専攻在学中に世田谷パブリックシアターでアシスタントを開始し現在に至る。世田谷パブリックシアター主催演劇公演、青少年向け事業、地域向け事業、人材育成事業など幅広い分野の企画制作を担当。
「次世代を担う芸術家と鑑賞者の育成」というゴールに向けて実施している企画。単に作品の優劣を競うものではなく、せんがわ劇場における舞台芸術活動者の育成支援の出発点として位置づけています。
コンセプトは「出会い」。批評の言葉、観客、アーティスト同士など、さまざまな出会いを提供し、従来のコンクール以上のコミュニケーションを目指しています。
公益財団法人 調布市文化・コミュニティ振興財団
萩原景子さん
調布市せんがわ劇場制作係演劇担当。
大学在学中に演劇をはじめ、小劇場で十数年活動。一時演劇から離れた後、2008年12月より調布市せんがわ劇場に嘱託職員として勤務。以来、演劇事業の企画制作、広報、財務など劇場事業全般に携わる。演劇コンクールは第4回、第12回、第13回を担当のほか、第1回から継続的に関わっている。
安部晴夏さん
調布市せんがわ劇場制作係演劇担当。
2022年7月より現職。日本大学芸術学部演劇学科在学中に舞台制作を学び、小劇場演劇をはじめ現代サーカス、大道芸イベント、ベイビーシアターなどのスタッフを経験。第12回せんがわ劇場演劇コンクールでは一般審査員としてファイナリスト作品の審査に参加した。親子向け演劇公演、小学生ワークショップ企画などを担当。保育士資格保持。
かながわ短編演劇アワード・演劇コンペティション
新しい「演劇」にチャレンジ! かながわ発・かながわオリジナルの演劇アワード。
20分~40分の短編演劇作品を全国から募集。演劇としての表現を拡張し、文化芸術を横断する実験的作品を神奈川から発信していくことを目的とします。
神奈川県
国際文化観光局文化課マグカル推進グループ
松井 寛さん
神奈川県国際文化観光局文化課マグカル推進グループリーダー。これまでに、東京 2020 オリンピックに伴う文化プログラム、文化芸術団体への補助事業などを担当。
渡辺江梨子さん
神奈川県国際文化観光局文化課マグカル推進グループ主任主事。これまでに、神奈川県立青少年センタースタジオHIKARIを舞台芸術団体に無償で提供する「マグカルシアター」や、ミュージカル人材を育成する「マグカル・パフォーミングアーツ・アカデミー(塾長・横内謙介氏)」などの事業を担当。

――いきなりですが、コンテストへの応募数は、どのくらいになるのでしょうか?
せんがわ 30団体前後です。
かながわ うちもです。
世田谷 ばらつきはありますが同じくらいですね。
かながわ 新しいコンセプトを出したタイミングで増える傾向というのはあって、2020年は60団体以上の応募がありました。
せんがわ 応募してくださる団体の作風の傾向は、審査員を務めてくださる方の作風によって変わってくるのですが、毎回、応募してくださる団体数は、同じくらいです。
――改めまして、本日はお集まりいただきありがとうございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
どんな風にはじまったの?
――初めに、それぞれの事業が、どのようなきっかけで始まったのか、ということを聞いていきたいと思います。
シアタートラム・ネクストジェネレーション
-――まずは2008年にスタート、この中では一番長く継続されているシアタートラム・ネクストジェネレーションから教えてください。
世田谷 世田谷パブリックシアターは芸術監督を擁していて、ふたつの劇場で主催の事業を行っています。演劇公演を企画制作するという側面、創造発信型の公共劇場であるという側面が強い。その公共劇場が舞台芸術界の次代を担う若い人材・団体に飛躍の場を提供したい、ということでスタートしています。開始当初、戯曲や個人ではなく、劇場が団体ごと採用するということは特徴だったと思います。
――ネクストジェネレーションは、登竜門としても知られる存在だと感じています。
世田谷 できることに限りはありますが様々な団体の上演に足を運んで劇場スタッフからも積極的に劇団にお声かけをしていたという点は大きかったと思います。
――団体を継続していくために役立つ講座を定期的に開催されるなど、育成に対しての劇場の姿勢は、多くの団体にとって支えになってきたように思います。
世田谷 ありがとうございます。起用した団体の多くがその活動が変遷していくなかで、ミナモザの瀬戸山美咲さん(Vol.3に参加)や、てがみ座の長田育恵さん(Vol.4に参加)のように、主催公演に登場し、アーティストとして第一線で活躍していらっしゃることは、とてもうれしくて、大きな成果のひとつだなと感じています。
せんがわ劇場演劇コンクール
――次は、2010年にスタート。せんがわ劇場演劇コンクールの始まったきっかけを教えてください。
せんがわ せんがわ劇場も劇場主催で演劇作品を発信しているので、創作に関わってもらえるアーティストを発掘したいという思いと、それから、開始当初は地域の町おこし的な面をもっていました。
――町おこし??
せんがわ 調布市内で活動している団体に、調布のシンボルである水木しげるの作品をモチーフにした演劇をつくってもらったんです。その後も少し募集地域を広げたものの、地元ネタのFC東京などをテーマにコンクールをやって、受賞公演をして終了、という流れでした。
ただ、3 回つづけたあと壁にあたってしまったんですね、このままでいいのか。広い意味で若手を支援していくとはどういうことか。1年考えて、コンクール参加をきっかけにせんがわ劇場に関わってもらうという方針を打ち出し、同時に募集地域も全国に変更しました。
――「広い意味で」のところ、もう少し詳しくお聞かせいただけますか?
せんがわ 応募してくださる方は、まだ規模的に小さい団体や、技術面で成熟していない団体も多いんです。主催公演に関わるとベテランの演出家や熟練のスタッフと現場を共にするチャンスもありますし、アウトリーチやワークショップ講師の経験を積めれば、今後の活動にプラスになると思いました。なにより、劇場主催の「親と子のクリスマス・メルヘン」シリーズは、これ以降ずっとコンクール出身者が脚本や演出を手がけています。
そして、ここ数年打ち出しているのは「出会い」です。演劇の第一線に関わる専門審査員、自分たちを知らない新しい観客、同時代に演劇をやろうとしている参加者。仙川にずっと住んでいるけど、お店をやっているとか子育て真っ最中で、演劇なんかめったに見る暇ないよっていう地域の人々。そういういろんな人の目線や言葉との出会いの場をつくることが支援につながるのではないかと。
――確かに、自分たちだけでは出会うことのできない目線ですね。
せんがわ 一昨年からはさらに深めて、団体と専門審査員と(観客から選ばれた)一般審査員が、この座談会の空間くらいの距離感で、それぞれの作品について語ってみようというアフター・ディスカッションという場を設けて、コミュニケーションを取れるようにしています。

かながわ短編演劇アワード
――かながわ短編演劇アワードが今の名称になったのは、2020年ですね。
かながわ 私たちは、他2財団と違って、県が主催のマグカル事業として行っています。文化芸術の魅力で人を惹きつけ地域の賑わいをつくりだすマグネットカルチャー。
2014年に始まった劇王神奈川、かもめ短編演劇祭と変化を続け、今にいたっています。劇作家協会と共催していた劇王を核にしつつ、全国に発信できるものにするにはどうしたらいいだろう、先進的かつ新しいものを観てもらうにはどうしたらいいだろうと。
――どうしたらよいのでしょう??
かながわ できるだけ多様なジャンルの審査委員の方にお願いし、多様な団体にでていただき、多様なものを上演していただくことかと考えています。『演劇』を謳ってはいるが、ダンスもノンバーバルもなんでもあり。去年はダンスに近い公演も受賞しています。
本多劇場が主催していた下北ウェーブという若手支援企画があったのですが、下北ウェーブが終わった年に、企画されていた半澤裕彦さんにかながわ短編演劇アワードのアドバイザーに入っていただき、様々な相談に乗っていただきました。


『審査』について教えて!
――どのように審査されるかということは、応募する団体としては気になる点です。
かながわ 審査委員の方に審査していただく前段階の、事前審査をどうするかということも大事です。舞台芸術担当部長の楫屋と、KAATの制作担当とアドバイザーの半澤さんに入ってもらい、公にしている評価基準をもとに、3人の合議で審査しています。
【審査基準】
・実験性やオリジナリティが感じられるもの
・これまでの演劇観にとらわれない方向性が感じられるもの
・これからの活躍や発展が感じられるもの(年齢制限を設けるものではありません)
かながわ 選んだ段階で各カンパニーの評価もしますが、団体が並んだ段階で、似た特徴を持つカンパニーを選出するべきかどうかというテイストの話もしています。革新的な表現・新しい表現というのは主観も入るので、できるだけ多様な団体を審査委員の方に見ていただけるように。審査委員は、この体制にしてから3年、ほぼ変えてきませんでした。
――変えないことに、意味がある。
かながわ 私たちのカラーを明確にしたいと考えました。最初の段階で審査員をなるべくバラけさせて、多様な人選になるように。最初が大事。そのあと数年は、できるだけ審査委員を変えないようにしようと。審査についての基準を設けてはいますが、審査委員には自由に議論してくださいとお伝えしています。
<演劇コンペティション>
一次審査委員 楫屋一之/半澤裕彦/横山歩
最終審査委員 岩渕貞哉/岡田利規/笠松泰洋/スズキ拓朗/徳永京子/林香菜
<戯曲コンペティション>
一次審査委員 大竹竜平/オノマリコ/河野遥/杉浦一基/半澤裕彦/本橋龍
最終審査委員 市原佐都子/北川陽子/西尾佳織/矢内原美邦
――せんがわ劇場は、毎年、審査員を変えていらっしゃいますね。
せんがわ 私たちの場合は「こういう団体を選びたいです」というメッセージを出しておらず、毎年審査員を変えているので、過去のグランプリ受賞団体の傾向もバラバラに見えるかもしれません。台詞に強度のある審査員に来ていただくと、応募団体も台詞に力を入れている団体が応募してくださる方が多くなるし、フィジカルが強い審査員の場合は、そういう団体が多くなります。
――審査員をどなたにお願いするかで、その年の傾向が決まりますね。
せんがわ その通りです。劇作家・演出家・フィジカルに強いアーティスト・スタッフ・俳優・プロデューサーなど、なるべく多岐にわたる分野から、毎年、この方にお願いするのはどうだろうと、相談しながら選んでいます。ジェンダーと年代が偏らないようにということは、その都度、かなりバランスを見ながら決めています。
高田聖子(俳優)
長田佳代子(舞台美術家)
松井周(劇作家・演出家・サンプル主宰)
三浦直之(劇作家・演出家・ロロ主宰)
徳永京子(演劇ジャーナリスト)
――せんがわ劇場ならではの審査の特徴はありますか?
せんがわ 一次審査、二次審査、本選という流れになるのですが、一次審査がかなり特徴的です。一次審査員はコンクール出身者にお願いしていて、作品の審査だけでなく、せんがわ劇場のアウトリーチ活動で一緒にやっていける人たちかどうかという点も審査のポイントになっています。応募書類に、「5年後にせんがわでどんなことをやってみたいか」という設問があるんですが、その答えをシビアにみているのは、私たち職員よりもむしろ彼らかもしれません。
世田谷 そのあとを見据えるという点は大事ですね。
――シアタートラム・ネクストジェネレーションの審査について教えてください。
世田谷 作品やアーティストを選定する際、シアタートラムという空間で魅力的なものを上演してくれるかどうか、これから飛躍していく団体かどうか、という点など総合的に検討して選ばせていただいています。
――実際に審査されるのはどなたになるのでしょうか?
世田谷 芸術監督とともにプロデューサー含め劇場スタッフと一緒に選びます。シアタートラムで新しくてワクワクする上演をしてくれるかどうか。そういう想像力をもてるかどうかという点も重要です。

シアタートラムの特徴
舞台設備 3尺×6尺束立て床を自由に構成して、様々な形状に舞台、客席を作ることが可能。客席はひな壇形式で後部壁面に電動で格納でき、平土間舞台が可能。
照明設備 劇場内のエリアのどこにでも客席や舞台が自由に設定できる空間になっているため、主舞台の天井にはほぼ等間隔に負荷回路を持ったバトンが8本あり、2本のバトンの間を横行する手動作業ゴンドラによって、フォーカスなどの高所作業が容易にできます。後舞台には4本の美術バトンがあり、照明器具の吊り込みも可能で負荷回路も後ギャラリーから供給できます。前舞台側面のサイドギャラリー、後ギャラリーも器具の吊り込みは容易にできます。
――劇場のプロデューサーが選ぶというのは、他のコンクールとは大きく異なりますね。
世田谷 世田谷パブリックシアターには演劇と舞踊のプロデューサーや制作スタッフが複数名いて、主催公演の企画を芸術監督のもと立案している。実際にクリエイションしたことあるスタッフが上演することを念頭に検討しています。皆で応募書類を読みこんで審査しています。
――今年から、隔年で演劇とフィジカルのコンクールを行うことになったのは、どのような経緯があったのでしょうか?
世田谷 芸術監督が代わり、新たに見直しました。コロナ禍で苦労しているであろう若いアーティストたちにとっての支援を考えた時に、演劇だけでなく舞踊・フィジカルの分野においても、支援が必要だろうと考えました。
参加団体にどのような支援をしているの?
――「選出されたあと・受賞したあと」に、どのようなことが待っているのかということを教えてください。
かながわ 私たちはアワードを開催する劇場が主催者ではない、ということが弱みではありますが、補完するために上演補助として全団体に10万円と神奈川県立青少年センタースタジオHIKARIの上演権、大賞1団体に賞金100万円という、決して少なくない額をお渡ししています。劇場を使うことに関心のない団体も増えているという演劇界の状況に対応できたらと思っています。
ただ、まだこれから整えていかなくてはならないということは考えていて、世田谷パブリックシアターさんやせんがわ劇場さんの取り組みからはいつも学ばせていただいています。
――コンペティションに、22世紀飛翔枠からの選抜があるというのは、高校生にとっては非常に大きいですね。
かながわ KAATで、学校関係者ではない観客に上演を見ていただくということは、未来の舞台芸術を担う存在である高校生にとっても意義のあることと思いますし、観客にも高校生の豊かな表現を紹介したいと思っています。

かながわ 今年からは上位1校に、飛翔枠審査委員の桐山知也さんによるコーチングを行いました。コーチングの稽古場に同行したのですが、高校生がプロの演出家の言葉をその場で吸収し、成長していく姿が印象的でした。
KAATでの上演は審査の対象にはなりませんが、審査委員も大きな関心を寄せてくれています。
――せんがわ劇場はどのように取り組まれていますか?
せんがわ 本選に残った人たちに呼びかけて、ドラマ・エデュケーション・ラボ=DELというグループに参加していただいています。演劇のアウトリーチを中心に、主催事業の劇作・出演・制作・講師として活動していて、先ほどお話ししたクリスマス・メルヘンのほか、市民参加演劇公演、ワークショップなど、せんがわ劇場の演劇事業はDELなしには実現できないですね。
――ここに参加したら、これからも演劇に関わっていけるという環境は、心強いです。
せんがわ DELのメンバーが、一緒に次回以降の演劇コンクールの運営もしています。規模は小さいですが、丁寧にみんなで一緒に話し合いながら細かい点の見直しもしています。みんなコンクール参加経験があるし、劇場の機構や事情もわかっているし、何より自分自身が演劇を創っている。そんな人たちが参加団体の当日アテンドやアフター・ディスカッションのファシリテーターも担当していて、皆さんに驚かれます。こんなコンクールはあまりないんじゃないでしょうか。
――ネクストジェネレーションではどのように取り組まれていますか?
世田谷 カンパニーにとっては、初めて経験する規模の上演になるので、選出したあとから上演に至るまでできる限りのことを一緒に取り組みます。一緒にクリエイションして、一緒に考えて学んで、団体として力を蓄えてほしいと。
前回選出した安住の地の場合、主宰の中村さんに「プレスリリースをつくるときに、アーティストが複数いて多様なアートの魅力がつまっている団体であることを打ち出した方がいいよね」というように、プレスリリースも一緒に作るなどしてカンパニー力を高めていただくということも考えながら進めます。
せんがわ 創作の段階でも、プロデューサー陣が関わっているんですか?
世田谷 はい。カンパニーに必要ならば、プロデューサーも芸術監督も積極的に関わります。安住の地の場合は台本のブラッシュアップなども話し合いました。広報営業もチケッティングも団体と一緒にやってもらうのですが、必ずテクニック面をバックアップして、シアタートラムで上演できるパッケージングになるようにしています。
せんがわ 団体によっては「自分たちでできる!」とぶつかってきたりすることもありそうですね。
世田谷 ありますね。「特殊な形のチラシを作りたい」だったり、「極端に客席数を減らしてアクティングエリアを広げたい」だったり。芸術的な判断はカンパニーとアーティストに任せるけど予算を一緒に見直しましょうという話になります。シビアな部分もありますが、一緒に楽しくやるように努めています。
――プロデューサーとして、長く世田谷パブリックシアターの主催事業に企画運営されている方と一緒に創作できるというのは、貴重な機会になりそうです。
世田谷 部分的に作品製作費を補填するけれどもカンパニーでもしっかり宣伝してチケット収入を生み出して、でもチケットが売れなかったら予算を減らしてみようと相談する。法人化をしてはどうか、とか、税務処理とか契約書や権利の処理などもバックアップしています。
一同 (感嘆の声)
かながわ 世田谷さんは、選出された団体によるアウトリーチ活動はどうなっているんですか?
世田谷 アウトリーチに関しては、クリエイションに専念していて、ネクストジェネレーションでやることはあまりない。公演事業の企画制作とは別に学芸という専門のセクションがあり一年中たくさんのワークショップを実施しています。

せんがわ これだけの数をやられているのは、すごいですね.....。
世田谷 学芸担当は、みんな朝からいくつものチームが区内の施設や学校に出向いていて、なかなか顔を見られません(笑)。アウトリーチに対して世田谷区と連携して地域との関係を密に活動しています。
――結果を残してきたから、理解していただけているんですね。
世田谷 初代の芸術監督の佐藤信さんが最初に掲げた理念は大きいと思います。創造発信型の公共劇場として地域の劇場が人々の生活を豊かにするという点や、舞台芸術の力で人々のコミュニケーションを豊かにするという理念は今も変わらず大切にしています。

安住の地について
――今回お集まりいただいたみなさんには、「安住の地」を選出しているという共通点があります。

――先ほど、世田谷さんが「複数のアーティストがいて作風が固まっていない」とおっしゃっていましたが、どんな点を評価されたのか、安住の地がどういう団体なのかということをお聞かせいただけますでしょうか?
2021年3月 かながわ短編演劇アワード・演劇コンペティションでグランプリ受賞
かながわ 審査委員の徳永京子さんが言っていた話が印象的で。安住の地は 2020年、2021年の2回出場していまして、1回目で「安住の地は演劇を乗り越えようとしている」、2回目は「演劇を壊しにいっている」と。たしかに安住の地はいろいろなジャンルのひとが集まっているアーティスト集団なので、アートの境目を越境していくような感じ、それも軽やかに乗り越えているような感じがあります。
――まさに「既存の演劇にとらわれない方向性を感じられるもの」という、かながわ短編演劇アワードの審査基準ですね。
かながわ 作品で共通しているのは、ディコンストラクション(脱構築)というか、破壊しつつ創造している点。ノマド的というか、軽やかさの一方で土着的な存在感。重みと軽みが交互に出てくるというのがありつつ、形式にはこだわっていて、ポピュラリティがあると思っている。せんがわ劇場で上演された『アーツ』も、存在感ありつつ、あの軽さが面白い。
2022年5月 せんがわ劇場演劇コンクールにてオーディエンス賞 受賞
せんがわ 前回のせんがわ演劇コンクールのときの上演作の話をさせてください――美術展で作品を見ていた男の人が作品に触れてしまった。その事件を発端に、絵画についての、戦時中・現在・古代のシーンが続きます。画家や、美術を見ている人の身体や表情を、舞台上で、見る。『見ている人を見る』。最後の美術家の台詞が印象的なんです。
「この絵だって、跡形もなく消え去るかもしれない。描いたことすら、なかったことになるのかもしれない。でもいいのです。ただ私にできることは、この絵をここに生み出すこと。見ていますか!この先の、遠くない未来の、この絵の前にいる、あなた。絵なんて必要なくなった、近い未来の、あなた。この時代にも、こうして、画家は、いましたよ。この時代にも、こうして、ヒトは、いましたよ」
せんがわ 戦時中命を失った画家の台詞が、今を生きる演劇人に重なります。

せんがわ 「この一瞬のために上演しているんです」ということを、安住の地という団体が叫んでいる台詞のように聞こえました。「今」やりたいという気持ちが作品にも表れていました。
――その、「今」そこにある切実さが、多くの観客の心を捉えて、オーディエンス賞受賞につながったということでしょうか。
2022年12月 シアタートラム・ネクストジェネレーションに選出
世田谷 軽やかさと社会性の同居というのが彼らの特徴の一つだと感じました。アート性が強く、空間に意識が及んでいる点も評価しました。岡本さんと私道さんの力強いアート感と、俳優としてもすぐれているけれど主宰としての中村さんのまじめな人間性とのバランスもいいですよね。
一同 (大いにうなずく)
世田谷 演出家がリーダーだと権力が集中するので、パワーバランスをとるために、俳優が主宰をやっていてすべてを合議制、協議制で行っている。あたらしい劇団のかたちを模索している、劇団のかたちそのものを考えているというのが独特だなと思います。多様性が叫ばれている中で、劇場が起用する団体も、多様なジャンルのアーティストが所属し、新しい集団創作の方法を模索している団体である正解ではないかと。選考の際、安住の地は、満場一致でした。
今後の展望
――たくさんのお話を聞かせていただきありがとうございました。最後に、それぞれのコンクールでの今後の展望を教えてください。
かながわ 私たちは、この事業を通して人材育成をしていくということを標榜している。次の次にどうつながるか。団体のために充実させていきます。
せんがわ DELの皆さんが、これまでに培ってきたもののバトンを、コンクールに参加した若い世代につなげたいという希望を持ってくれています。劇場をつかってどういうふうに演劇をやっていくかを、一緒に、手をつないで考えていけたらいいなと思います。
世田谷 世田谷パブリックシアターの芸術監督に劇団出身の白井が就任し、小劇場であるとか、劇団活動からアーティストを発掘することは必然だなと感じています。演劇のみならず、ダンスやフィジカルにおいてもアーティストの発掘においては、これまで以上に積極的に。ネクストジェネレーションだけでなく、主催公演事業でも若いアーティストの起用、アウトリーチも含めて未来を担う青少年向けの事業も、スタッフのインターンシップにおいても、トータルとして、人材育成のお役に立てることはとにかくつづけていかなくてはと感じています。
――今日はありがとうございました!
(取材日:2023年3月10日)
お話しする中で見えてきたのは、それぞれの事業が、演劇界の才能をしっかりと育てていこう、という思いでした。
その思いは、参加者に届いているのか。
3つのコンテストに参加した安住の地。そのメンバーに、それぞれのコンテストへの印象やメッセージをいただきましたので、ご紹介します。
安住の地からのメッセージ
かながわ短編演劇アワードへ
とにかく「作品に寄り添ってくださる」という印象が強く残っています!
私たち安住の地、第1回目の参加では生卵を舞台上にのせ、第2回目は直径3mのトランポリンを短時間の転換で設置をしました。
ふりかえれば、なんて迷惑な団体なんだ…と反省でいっぱいです。
しかし劇場スタッフと運営チーム皆様の柔軟なサポートがあり、無事に希望通りの作品が発表できました。
当たり前のように対応してくださいましたが、このような手厚い上演は、稀有なことだと身に染みております。本当にありがとうございました!
せんがわ劇場演劇コンクールへ
安住の地初の東京公演を「せんがわ劇場演劇コンクール」にて上演させていただいたことは、団体の歴史の中でも特にありがたかったことの一つです。観劇してくださったお客様と直接話し、厳しい意見も嬉しい感想もいただけたことは、何よりの学びになりました。またせんがわ劇場で公演ができるということで、1年前にお話しさせていただいた観客のみなさんのお顔を思い浮かべながら、わくわくした気持ちで稽古を進めています。私たちは素敵なコンクールに育てていただきました。ありがとうございます。
シアタートラム・ネクストジェネレーションへ
東京で、過去最大級の公演をシアタートラム・ネクストジェネレーションという場で行わせていただいたことは、未だに夢だったのではないかという気がしています。
芸術監督の白井晃さん、大下さんはじめとした劇場のみなさん、スタッフのみなさんには大変お世話になりました。手製の公演を、立派な「興行」にまで引っ張り上げて上げていただき、感謝しています。終演後に「いっぱい勉強して、また戻っておいで」と声をかけていただいたこと、忘れません。思い出す度に「恩返しをするために頑張らなくては!」と力が入る劇場のひとつです。
安住の地の次回作をご紹介!
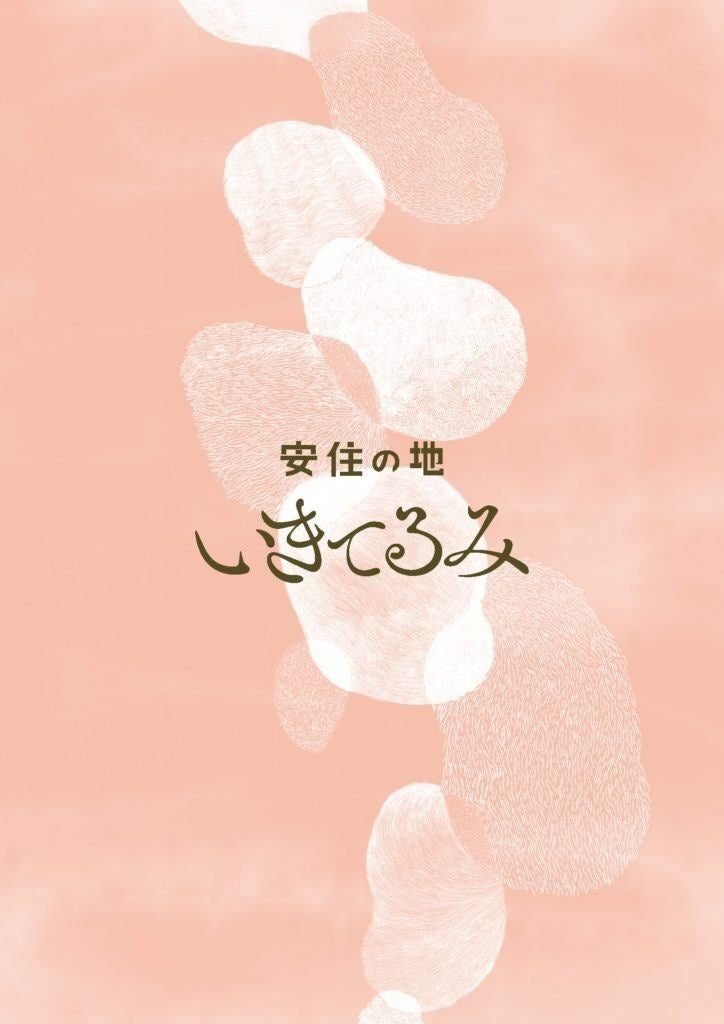
今作「いきてるみ」は、執筆時から想定外のことが多くありました。演出のことを無視して小説で書くと、筆が乗り4章にも及んでしまう。脚本に直して稽古を進めるものの、初めてのことだらけで役者となかなかシーンを立ち上げられない。創作にものすごく時間がかかりました。上演時間も長く、安住の地では珍しく、途中休憩を入れた公演になっています。
「大丈夫かな…」と思って上演した初演、終演後にあるお客様から「今まで見てきた中で一番おもしろい演劇だった」という感想をいただき、予想外過ぎてしばらく呆然としてしまいました。一方で「自分には全然合わなかった」という声もいただき、その感想の振れ幅の大きさにも驚きました。その後いただいたOMS戯曲佳作のお知らせも予想外で、なんだか随分遠くまで連れて行ってくれる作品だなあ、と驚きっぱなしで現在に至ります。
この作品を、せんがわ劇場のお客さんと一緒に楽しんでみたいと思いました。「いきてるみ」が一体どこまで転がっていくのか、目撃していただけると嬉しいです。
第12回せんがわ劇場演劇コンクール オーディエンス賞受賞公演
『いきてるみ』
脚本・演出|私道かぴ
キャスト|中村彩乃、雛野あき、山下裕英、にさわまほ、吟醸ともよ、森脇康貴、沢栁優大/御厨 亮、タナカ・G・ツヨシ
舞台監督|河井 朗(ルサンチカ)、舞台協力|鈴木章友、舞台美術|佐久間優季、照明|河口琢磨、音響|佐藤武紀、衣裳|山井ひなた、ヘアメイク|篁 怜、宣伝美術|横山彰乃、森脇康貴、情報宣伝|日下七海、武田暢輝、制作|中野コナン、加藤七穂
主催|安住の地 共催|(公財)調布市文化・コミュニティ振興財団、京都芸術センター制作支援事業
【上演日時】
2023年5月
26日(金)14:00/19:00
27日(土)13:00/18:00
28日(日)11:00/15:00
会場 調布市せんがわ劇場
前売料金(全席自由席、当日は+500円)
一般:3,500円/U-25:2,000円/高校生以下:1,500円[前売・当日一律料金]/ハンディキャップ 一般:3,000円
取材・構成・文 成島秀和、臼田菜南
17,300名の舞台・美術ファンにお届け中!「おちらしさん」への会員登録もお待ちしています! おちらしさんとは⇒https://note.com/nevula_prise/n/n4ed071575525
