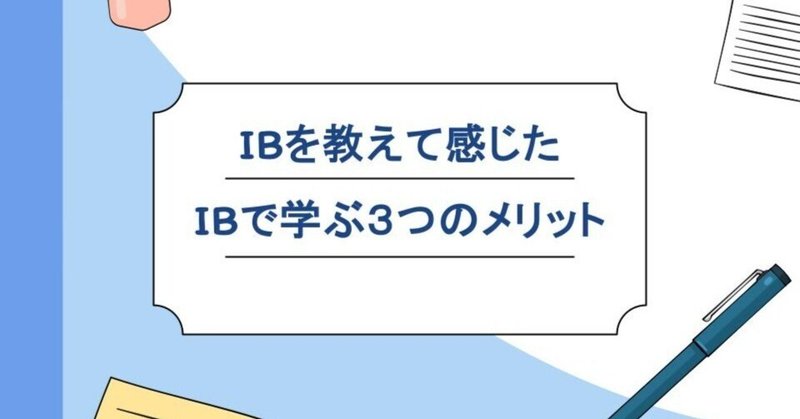
IB(国際バカロレア)を教えて感じた、IBで学ぶ3つのメリット
皆様お世話になってます。小林勇貴です。
IBの基本的なシステムに関しては、文部科学省IB教育推進コンソーシアムや、IB認定校のHP、IB卒業生のブログやYouTubeなど、多く語られるようになってきたかと思います。
全体像を把握するには、文部科学省 IB教育推進コンソーシアムのHPが適していると思いますので、ご存じない方は以下のリンクをご確認ください。https://ibconsortium.mext.go.jp/about-ib/
さて今回は、私自身がIBを教える中で見えてきた、IBで学ぶ3つのメリットをお伝えできればと思います。
メリット1:探求する力を養う
私が教えていたBiology/生物に限らず、IBでは各科目Individual investigation (個人探求)に取り組む必要があります。
以下の表は、生物(Standard Level)における最終評価の内訳です。
いわゆる筆記試験が80%を占め、残りの20%をIndividual investigation (個人探求)が占めている事が分かります。

Individual investigation (個人探求)は、生徒自身が生物に関する問い(Research Question)を立て、実験を通してデータを集め、解析し、6〜12ページの論文にまとめます。
このIndividual investigation (個人探求)の時間は、10時間分しっかりとカリキュラムに組み込まれています。
IBでは、教師を"ファシリテータ/Facilitator"と捉えています。
つまり、生徒に一方的に教え込むのではなく、ヒントを出しながら、寄り添い導いいていく存在であるのだと、私は理解いています。
ですので、このIndividual investigation (個人探求)においては、問いを立てるること、実験手法における安全上の注意点を伝えること、実験に同席し安全を確保すなどサポートはしますが、教員が実験を進め、論文を加筆していくなんてことは絶対にありません。あくまで、学習の主体者は生徒になります。
その他、TOK(知の理論)やEE(課題論文)など、探求する力を養う必須課題も設定されています。
メリット2:英語力を養う
文部科学省は、国際バカロレア機構が協力して、DP(高校生対象プログラム)の一部の科目を日本語でも実施可能とするプログラム(日本語DP)の開発を進めてきました。
これは、ものすごい日本政府の努力と意気込みがあったからこそではないかと、個人的に思っています。
IBによって、英語力が鍛えられるのは言うまでもありません。なぜなら、「日本語DPは、6科目中2科目(通常、グループ2(外国語)に加えて更に1科目)は、英語等で履修することが必要」だからです。

この外国語以外の「1科目」は、IB校によってどの科目に設定しているか異なります。
つまり、英語で実施される「外国語」に加えて、
「音楽」や「美術」を英語で行ってもよいですし、
「数学」や「歴史」を英語で行ってもよいと言うことです。
IB校によっては、「英語」「化学」「数学」の3科目を英語で行っているところもあります。
IB校を選ぶ際には、どの科目を英語で行っているのか、事前に確認しておくことが重要です。
IB生物に関しては、そもそも日本語の教材がほぼありません。つまり、英語の教材を読みこなす力が求められます。(教師側にももちろんその力は求められますし、授業準備も大変です。ですが、私はそこに面白みを感じています。)
なお、教科書はOxford University Press等から数種類発行されています。
以下にリンクを貼っておきますので、ご興味ありましたらご確認ください。
余談ですが、私は5年ほど前、IBに対する興味が溢れ出ており、イギリスにあるOxford University Press本社を訪問した事があります。見ず知らずの私の訪問をを快く受け入れて下さり、とても感謝しています。

数研さんなどが出している、いわゆる「図説」は、日本の誇る素晴らしい教材だと思っており、お見せしたところ、大変感動しておられました。私は英語版にすると相当売れると思っているのですが、、日本の出版社の方とお話しした所によると、なかなか難しい面もあるようです。
メリット3:国際感覚を養う
私は、「英語が喋れること」と「国際感覚があること」は全くの別物だと思っています。
Diversity/多様性には、ジェンダー/gender、人種/race, 年齢/age、民族性/ethnicity, 身体能力/physical abilitiesなどの観点があるとされていますが (Plessis & Bisschoff, 2007)、その多様性を受け入れ、コミュニケーションを取り、共に協働できることが、国際社会で生きていく上で大切なのではないでしょうか。そしてそれは、21世紀ますます必要になってくる能力なのではないでしょうか。
多様性=他者との違い を受け入れるには、自分以外の人の考え方を知り、尊重する必要があると思います。TOK(知の理論)は、他の人の考えを飲み込む試みであると私は捉えています。
TOK(知の理論)は、すべてのIB科目と関わってきます。IB生物においても、もちろん授業の構成要素になります。
他人との違いを尊重する。故に、IBの目指すものが「世界平和」なのだと、私は捉えています。

参照:https://www.ibo.org/globalassets/new-structure/brochures-and-infographics/pdfs/ib-learner-profile-brochure-j.pdf
国際感覚を養うためには、外国の方と関わる実践的な経験も必要です。日本語DPは2科目を(基本的には)英語で行う必要があるので、ほぼ必然的に外国人の先生が担当されることになると思います。外国人の先生と学んでいく中で、新たな「違い」に気づくのではないかと思います。
余談ですが、単に、国際感覚を持ち、いろんな国にたくさんの友達がいた方が人生楽しいのではないか、とも思っています。
英語力と言われても、切り口は様々です。私は、「親友を作れるだけの英語力があったら人生楽しいよね」と、生徒には話していました。
外国人の親友をつくる為には、違いを受け入れられる素養はもちろん必要ですが、語学面でも鍛錬が必要です。
友達が悲しんでる時には励まし、困っている時には相談に乗り、楽しい思い出を語り合った時間が積み重なるからこそ、心の通った「親友」になれるのではないでしょうか。
デメリットも書こうと思っていましたがメリットだけで結構な分量になってしまいました、、続きは次回の記事でお伝えできればと思います。
「こんなことを記事にして欲しい!」など、コメント・ご要望もお待ちしております。引き継ぎどうぞよろしくお願いいたします。
Reference
du Plessis, P., & Bisschoff, T. (2007). Diversity and complexity in the classroom: Valuingracial and cultural diversity. Educational Research and Review, 2(9), 245-254. https://my.uopeople.edu/pluginfile.php/1772960/mod_book/chapter/457728/5710DiversityandComplexity.pdf
♦️本記事は、一般に公開されている情報の範囲内で作成されるよう留意しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
