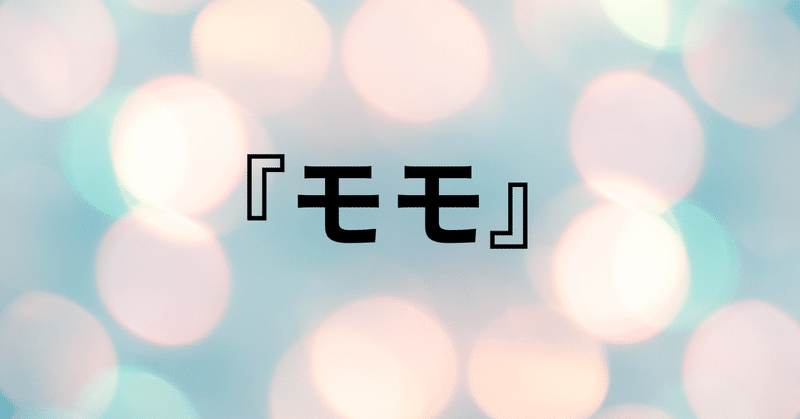
『モモ』
ミヒャエル・エンデ著 『モモ』 大島かおり訳(岩波書店、2005)
私の人生のテーマの中に「時間」がある。
この本を読もうと思ったのも長い時間を必要としたし、
申し訳ない気持ちと戦っていたからだ。
前置きが長いので本のことだけが知りたい方は、
3.あらすじ から読んでいただければと思います。
時間が元に戻ることはない。
過去に我々自身が戻ることは、今のところ不可能であるとされている。
(過去や未来を行き来するような話)
しかし、過去と似たような時間と空間に生きる可能性はある。
私は現代社会を、結構悲観的に見ている方だと思う。
生きるにも死ぬにも大変なこの世界で喜びを見つけるのならば、
そのポジティブな感情を抱く一瞬を逃さなければ良いと思っている。
その一瞬をどうやったら見つけられるかといえば、慌ただしい中で
立ち止まる時間を持つことだ。
多忙な世界で生きる現代人は、立ち止まることを恐れる。
言い方を変えれば恐怖心と喜びは、表裏一体なのではないかと私は思う。
最初の1歩は怖いかもしれないけど、1歩進んでみたら喜びの方が
大きかった!!そんな具合だ。
感想が思ったより長くなってしまったので、
感想を3つのパート「傾聴」、「時間」、「我々の在り方」に分けました。
1.『モモ』を2つの後悔から読めなくなっていた時間
1つ目は、後ろめたい記憶。
小学生の頃、数年学童に行っていた。
学童にあった本棚で初めて、漫画(ドラゴンボール)に出会った。
夏休みなど長期休暇(=ほとんど人がいない時期)は、
お気に入りの本を取り出して、床に積んで読んでいた。
お昼寝の時間もあったので、漫画を読みたい私は時間との勝負。
いつも通り床に座って、本屋漫画を読んでいた時。
先生の1人が『モモ』をおすすめしてきた。
先生の好きな本だから、読んでくれたら嬉しいなぁって感じだったと思う。
当時の私は読まなかった。
本棚にあった本は、全部読んだ気がする。
そういう姿を見ていたからこそ、おすすめしてくれたんだと思う。
先生からは3、4回おすすめされたと思う。
時々、私が選んで床に積んだ本に紛れて『モモ』が入ってたこともあったけど読まなかった。
ハードカバーの分厚い本、開いても多分6歳頃の私には難しかった。
いや、言い訳だな。単に私が頑固者だったんだ。
『モモ』を見かける度に先生の少し悲しそうな、
残念がる顔が今も脳裏に浮かぶ。
それで本を手に取れなかった。
2つ目は、後悔。
タイトルは忘れたけど「時間」の図鑑。
本屋で見つけて超絶テンション上がったのに、その日ケチった。
あと1,000円安かったらなぁ…と。
あとは単純に重いし大きい本だし、どうやって持って帰るんだ?!と。
今はネットで買えるけど、値段が変わってる…!!(今でも高い!!)
とんでもない後悔。
2.ガチで30年ほど経過した
『モモ』を読もうかと最初に思ったのは、著者がミヒャエル・エンデだからだ。
あの『はてしない物語』を書いた大先生!!!!!!!!!!!!!!
それこそ、小さい頃に何度映画を観たことか。
もちろん、本もあります。
美しい装丁をされた、あの赤い本だ。
そしてドイツ語版の本。
ドイツの本は青い、ハードカバーで文章の文字は黒統一でなく、
いくつかの色が使い分けられている。
『モモ』が、あの『モモ』が、また目に入る@本屋。
ついに、本を手にとる。
本棚に並んでいる『モモ』は何種類かあって、文庫本を手にした。
文庫本以外が、高かったものでして(´・ω・`)
「時間」…!!!!
裏表紙を読んで、息が止まりそうになる。
何かが私を猛烈に突き動かした。
爆速(早足)で、自分がまた棚に本を戻す前にレジに向かった。
大きい本屋だから少しレジが遠い…!!
後で気付いたが複数箇所にレジがあった( ^ω^ )
1ページ目から、ページをめくるたびに感動してしまう。
後悔なんぞ、どうでも良い。
今読むべくして、この時が与えられているのだろう。
もし先生とお会い出来て話せるのなら、話してみたい。
さすがに今は「頭の中は恐竜でいっぱい!!」でなくなりましたから。
3.あらすじ
舞台は、廃墟と化した円形劇場にモモが現れるところから始まる。
大人たちは、モモをどうしようかと相談する。
それぞれ裕福ではないので、それぞれの分け与えられるものを与え合う。
だからモモは、暮らすに十分だった。
モモは人の話をよく聴くので、話を聴いてもらうためにも円形劇場には
人が集まる。
モモには特に仲の良い友人が2人いた。
饒舌な若者と、”変わってる”と称されるゆっくり話す老人。
若者は夢を見る、それも貧しい場所で。
いつか大きな家に住むのだ、と。
”変わってる”と称される者は、それを気にしないモモと話す。
モモのこの友人2人は、まったく違うのに仲が良い。
穏やかな日々の中に、灰色の男たちがやってくる。
まずは大人たちのところへ。
「時間を損しているぞ!!」
時間銀行に貯蓄すると言う彼らの言葉に騙され、時間の節約をするようになる。
そんな生活が当たり前になる。
「早くしろ!」
以前より早く仕事も終わって、充実しているはずなのに心は虚しくなる。
忙しい大人たちは、子どもにかまっていられなくなる。
灰色の男の1人から、その正体を聞いたモモだけは灰色の世界に恐怖する。
モモの友人2人。
夢が叶った友人の心は虚しさでいっぱい。
変わった老人はモモを待って黙り込む。
灰色の男たちに恐怖していたモモはカメに会い、
時間を分け与えている賢者に会うこととなる。
みんなを救いたいモモは、この賢者と協力して与えられた1時間の中で
灰色の男たちと奮闘し、世界を元通りにする。
4.感想-傾聴(聴くことについて)
物語のはじめ、この世界の中が穏便だと思われている頃、
モモはほとんど話していない。
相手の話に耳を傾けるだけである。
ケンカをしている2人も、モモに聴いてもらえば解決する。
「モモのところに行ってごらんよ。」と言われる理由は、ここにある。
モモは賢者なわけでもないし、問題解決のための究極的な解決法を相手に
伝えるわけでもない。
話者は話すことによって、己の内面にある自身の答えに辿り着く。
壁打ちテニスや、1人でスカッシュすることに似ているのではないか?
「発する」ことの大切さを、ここでは教えてくれていると思う。
1人でいる時には、頭の中であれこれ1人で考える時間も重要だ。
独り言を言うのは、頭の中が整理されるから良いことだと、何かで読んだことがある(生活に支障のない範囲で)
しかし、自己完結には限界がある。
壁打ち練習ばかり行なっていると、実際の試合では上手くいかない。
相手が打ち返してくることに慣れていないからだ。
そして、自己解決過多は考え方に偏りを生じさせるだろう。
モモは常に傾聴スタイルでいたわけではない。
特に仲の良い友人とは、きちんと会話をしていた。
モモは、きちんと対話していたのだ。
4.1感想-時間(過去、現在、未来)
我が人生のテーマの1つなんで、今回の1冊で全部わかったぜ!!とは
もちろんなりません(´ω`)
現在は過去の連続にもなり得る。
この記事の1文字を打つごとに、それは過去となる。
モモを読んで、時間とは何かということよりも、その費やし方を考えてみた。
ファストフードやカップ麺、確かに便利(開発者の方、尊敬でしかない)
しかし不思議だ。
「すぐに食べられるもの」って、大体健康面においてはネガティブに
とらえられているものが多い。
急かされる現代社会に非常に適していて、しかも美味しいものも多い!!
それなのに、美味しいものほど健康に良くないものが多い気がする。
(食べる時間が速いことも含む)
時間をかけずに簡単に食べられる!!早く食べられる!!
なんとも皮肉な話じゃありませんか。
急げ、急げと言われて、そんなに急かされたところで得るものってなんでしょう?そんなことを考えました。
10秒先だって予想できないのが、人の生命。
生き急ぐ価値とはなんぞ。
「そんな死に急ぐことをしないで。」
毎日、ファストフードばかり食べていたら心配されるかも。
明らか目にすることが出来て、聞くことの出来るものなら
人はそれらをキャッチ出来る。
だが、灰色たちの男たちが我々の本当のところじゃないだろうか。
実際、人が「そんな生き急ぐようなこと…」と気付く時には手遅れなほど、
分かりにくい存在なのだと思う。
急いで、急かされて、ある日プツンと切れてしまう人もいる。
それが多分『モモ』で書かれている、
「致死的退屈症」
これなんだと思う。
様々退屈しのぎのための多忙により、人は収集つかない状態になるほど辟易したり、疲弊した状態に陥るのではないか。
時間はいくらあっても足りない!!けれど、立ち止まる必要性もある。
なんのために時間がそれだけ必要なのか、それさえ考えさせない社会があるから。
時間が貴重であるからこそ、知らない間に”何か”が蔓延しているのではないかと思う。
とはいえ、急がないといけない場面もありますから。
時間は有限なんだから、自分の願うとおりに!!
その行く末もまた、灰色の男たちが教えてくれてます。
反面教師とは、このことか(´・ω・`)
4.2我々の在り方
これは、どれが正解なんて言えない。
でも、虚しさや疑問が生じるのであれば、今の在り方は違うのかもしれない。
理想は、そう願わくば「好きなことして生きていたい。」
そう”なる”ことが出来るのは、そう”ある”ことが可能だという条件が
あってから成立するもの。
『モモ』では物語の最後に、以前のような状態に戻る。
それは、モモがそう望んだからであり、そうあることが出来たから。
作者が後書きで書いているとおり、その未来は分からない。
この物語が書かれたのは、過去のこと。
それでも今読んでいる読者にも教えられることがある。
そして、過去に教えられた良いことは未来へと繋がる可能性がある。
そのために今、こうして記事を長々と書いている。
ここ数年の間に「おうちで○○」の時期に、倫理が流行ったり。
哲学に関するものが、本屋などでも目立つようになった。
何もかもが覆される時、しっかりと考えて取捨選択することが必要とされるだろうから。
そう出来るようになりたい。
『モモ』では、灰色の男たちの速さと影響が描かれている。
本当に私たちを脅かす危機ほど、静かに確実に蔓延する。
そして、気付くには遅いことが多いのではないだろうか。
5.まとめ
レポートみたいな分量…(OωO)
ここまで読んでくれている方ありがとうございます!!!!!本当に。
爆絶まとめると、「この本、めちゃくちゃ良いから読んで!!!!」です。
その理由を細かく、ごちゃごちゃ書いてるのが上記ですので。
あぁ、先生。
恐竜とタートルズで頭がいっぱいだった6歳児には、この良さが分からなかったですよー!!
あの時、素直に読んでいたら「よく分からない本だった」だけが、
頭に残るか、それさえ残らないか。
今まで内心チクリと刺すような記憶があったお陰で、
私は今この本の素晴らしさと美しさに出会えたので大感謝٩( 'ω' )و
ところで。
私ははじめ、灰色の男たちとは”目に見えない何か”を、象徴するもののみかと思っていた。
スマホ(SNSやAI)やゲーム、人と対面して費やす時間や1人という「孤独」の時間を妨げる”何か”だ。
AIに関しては、最近ChatGPTなど話題に尽きない。
前まではAI(Artificial intelligence =人工知能)である限り、人の生み出すことに変わりはないと思っていたけれど、今のデジタル化のそれは人の手から離れているようなところもある。
しかしですよ、しかし。
最後に時間が止まってしまい、己の存在をかけて灰色の男たち同士が
奮闘してる姿を読んだ時には、人間の在り方の化身でもあるようにも思った。
自身が蒔いた種でありながら、それをまったく顧みず、自身が残ることだけのために行動する。
その際、相手がどう思うか、行動するかなんてまるで気にしない。
そうして、1人残らず最後に灰色の男たちは消えていく。
自分が生きるために他者を消し、それが自身の首をしめるのだ。
自身の首を絞めるかどうかはともかく、私は次世代に今より良い空間を残してさりたい。
すでに長文だから自重します。あはははは…
ここまで読んでくれた方、本当にありがとうございます。
読んだことのない方、おすすめですよー٩( 'ω' )و
もうすぐGWだし、読書しましょー
読んでくだり心から感謝します。 サポートいただけたら、今後の記事に役立てたいと考えております。 スキしてくだるのも、サポートもとても喜びます!!!!
