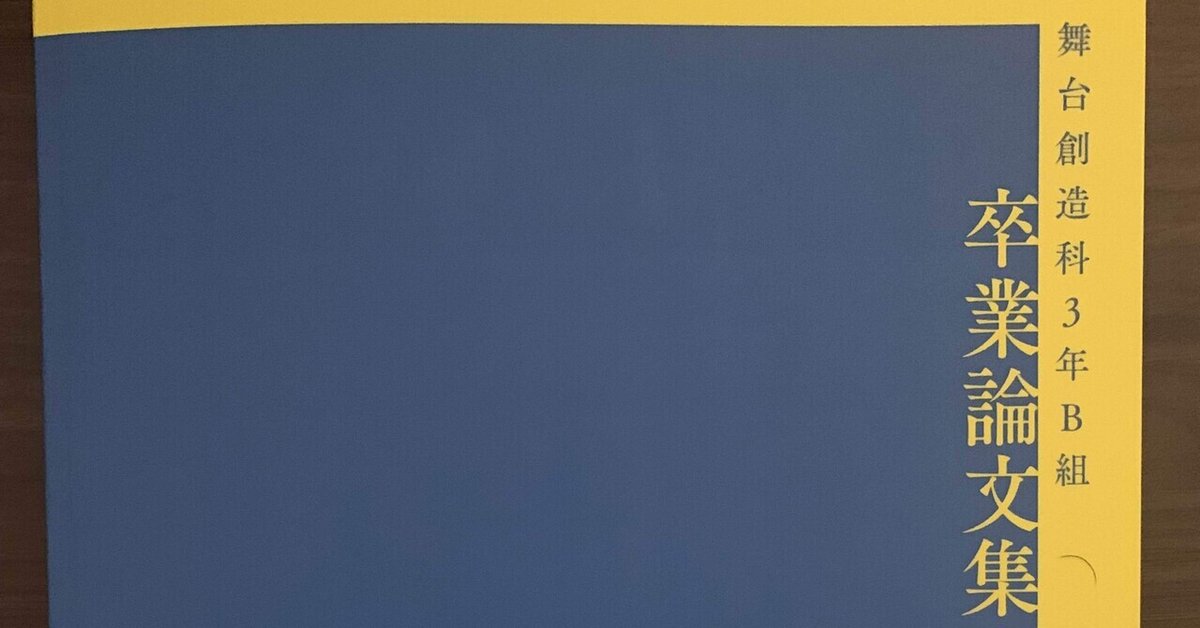
「卒論合同」感想④ 〜X ワイルドスクリーーンバロック〜
引き続き感想を綴ります。今回は訳あって順番が前後しています。
①はこちら。②はこちら。③はこちら。
10-1. 「劇スにおける星摘みカウントについて」 白隼(@shirohayabusa16)氏
今までなかった視点ばかりで非常に面白かった。
「トマトのヘタの数」についての視点は、そもそもそれぞれが「異なる」トマトであるという意識をしていなかったので驚きだった。それと「星摘みカウント」の関連はもう少し考え甲斐のありそうで関心がそそられる問題であるが、それぞれに固有の意味づけがされているという議論は大変興味深かった。
また、「同じ言葉の繰り返し」によって「再生産」が実現するというのも興味深い。『遙かなるエルドラド』における「なぜ、なぜ、なぜ、なぜ、なぜ、なぜ言ってしまうのだ」という華恋演じるアレハンドロのセリフについて、何故「なぜ」が(7回ではなく)6回なのかについて明確な結論を出せないでいたが、本稿で提示された「星摘みカウント」のモデルによって納得がいった。さらに、このモデルによって作中の全てのレヴューに対しかなり説得力のある説明を与えられるであろう。あるいはまた、これを手掛かりに複数のレヴューを関係づけることも可能になるかもしれない。
例えば、4回の繰り返しで場面が転換する点は共通点として挙げられるかもしれない。「狩りのレヴュー」や「魂のレヴュー」がそれである。そう考えると、「最後のセリフ」はそこまでで舞台少女たちが積み上げてきたレヴューをある種の「糧」にして、より高い次元で「再生産」をしているのかもしれない。
個別の話をすると、何度も「5回」で足踏みする「恨みのレヴュー」や完全に主導権をまひるが握る「競演のレヴュー」は解釈一致すぎて面白かった。「繰り返し」の語彙が誰が言ったかに注目して議論してみても面白いかもしれない。
10-2. 「なぜ「私たち」は狂ったように劇場に足を運んでしまったのか〜暗・明転に見る{歌劇}体験〜」 竹内(@akabe_NT)氏
本作は内容もさることながら、それを受け取った観客たちの反応も特筆に値する。作品に魅せられて何度も同じ映画を映画館で見続ける観客たちの姿を、本稿は「パチンコ」をする人になぞらえる。暗転と明転の連続によって脳を刺激するこの映画をパチンコになぞらえる。筆者はギャンブルのことはよくわからないが、さもありなんと感じられる。
では、そこで「賭けられているもの」は何なのか。大袈裟に言ってしまえばそれは「私の人生」なのかもしれない。本作は舞台少女の物語であると同時に、「私たち」の物語でもある。私たちが外部の他者として作品を鑑賞していたところから、本作は物語のレイヤーまで我々を引き下ろす。そうして観客たちの「他者性」を排除したのちに、賭けられたものと重ね合わされた舞台少女たちの運命が「再生産」を経て次の舞台へと向かう。そうした一連の運動を、我々は経験しているのではないだろうか。
観客の行動との関連においてもう一つ指摘しておきたのは、「再演」との関係である。本稿で述べられていたような欲求に基づいて我々が映画を繰り返し鑑賞するとき、我々は彼女たちを再演させていることになる。未来へと歩みを進め始めた少女たちを後ろに引き戻すことになる。このことは、どう解釈すれば良いのだろうか。作品の主題とアンビバレントなものとして受け入れるしかないのか、あるいは両者を一貫性のある仕方で意味づけることができるのか、さらなる解釈が必要であるように感じられる。
10-3. 「劇場版と、前日譚としての#3〜異なる次元を飛び回るということ〜」 ナナミ(@sevenseas_ball)氏
本稿は、舞台#3と劇場版の異同を捉えた上でそれがいかなる意味を持つかについて指摘する。その中でナナミ氏は「ここで劇場版と#3が同じ世界線であるかは重要ではない。異なる次元を飛び回ることは、観客に強い衝撃を与えるためにあると言える。」と述べる。その通りだと思う。舞台の世界とアニメの世界を行き来することによって、我々はより大きな感動を受け取るのだろう。
こうした色彩をさらに強めたのが、(発刊当時は公開前であった)舞台#4であると筆者は考えている。#4は、プロットの下敷き自体は舞台シリーズとはもはや一貫性を有しておらず、むしろアニメシリーズとの一貫性を有していた。しかしながら走駝先生や他のキャラクターたち、あるいは役者の身体性などはやはり舞台シリーズのものを受け継いでいる。したがって#4は、#3まで続いてきた舞台シリーズと劇場版で終幕を迎えたアニメシリーズの両者を取り合わせたものとして見ることができる。こうした「異なる次元の行き来」があってこそ、舞台#4はClimaxを迎えられたのだろうと思う。
そして、とにかく最後の文章がうますぎる。今している全てのことがスタァライトに影響されているということを改めて実感できた。スタァライトに関わる全ての人の熱量が伝わってきた。
10-4. 「演技行為から読み解くワイルドスクリーンバロック」 陣笠狸(@camelo345)
演劇において不可欠なのは、いうまでもなく「演技すること(=to act)」であろう。本稿では、「演技すること」を手掛かりに、ワイルドスクリーンバロックを解きほぐす。舞台少女たちにとって「演じる」ということはどのようであるのかの一端を見ることができた気がして面白かった。
そこにおいてまず触れておきたいのが、露崎まひるの「与えられた役」についてである。彼女は複数の場所で「演じること」と「自然なままでいること」の曖昧さを担わされてきた、と言っても良いだろう。それは、本稿で指摘されたように「競演のレヴュー」内において「普段の」まひるから「舞台上の」まひるへとシームレスに移行していく、あるいは混ざり合っていくというところに代表されている。また、舞台において「それはあなたの台詞?それとも本心?」との台詞を投げかけられたり、普段の柔和な様子でななに近づき「腹パン」を食らわせたりしているのも、こうした曖昧性につながるであろう。彼女の演技の魅力は「自然体でいること」にある、と言っても過言でないかもしれない。
しかしよく考えてみると、「演技すること」と「自然なままでいること」の間に境界は無いのではないかと感じ始める。「演技」をしている間にも私の身体は自然な振る舞いをし続けるし、「普通」に過ごしていても演技をする時がある。本稿でも指摘されている通り、「演技すること」と「行動すること」は共に”to act”であり同じことなのだ。背景が舞台であるか日常の世界であるかの違いしかない。さらに付け加えるなら、演劇における「幕」も"act"と称される。この共通性が何を意味するかは考えられていないが、こちらも(特に「魂のレヴュー」との関連で)考察に値する重要なポイントであろう。
10-5. 「舞台少女らのレヴューにおける強さに関する考察。及び、世界が彼女たちの舞台である証明。」 ぐしゃろごす。(@tehihi)氏
レヴューの勝敗の法則を定式化する試みが説得力のある形で論じられていて、面白かった。自分でもこれに関して考えてみたことはあるが、どうしてもうまくいく変数を見つけたりそれに符合する説明を与えることができなかったので、それに成功している本稿は非常に刺激になった。
まず、「皆殺しのレヴュー」におけるななの位置付けが非常に面白かった。拙稿ではななをキリスト(あるいはメシア)として捉え、「舞台少女たちを導き存在」として解釈したが、「役」や「演技」という視点から見ると、本稿のような解釈が妥当であると感じられた。その上で、テレビアニメと劇場版でのななのポジションの変化をななの「みんなと未来に行きたい」という心情の変化に求め、「狩りのレヴュー」での転換はあくまで純那との関係に限られるとした点も非常に参考になった。
「怨みのレヴュー」における香子の「死ぬ覚悟」は、彼女一人だけ「演劇」の世界から去るということの影響が大きいであろう。本作の最後にもたらされる結論は「世界自体が舞台である」というものであるから実際には離れることは無いのではあるが、卒業を控えた彼女にそう見えることは無理もない。彼女にとって、他の面々と離れて一人京都で日本舞踊へと「戻る」ことは、演劇の世界において「死ぬ」ことであったのだろう。
その他、他のレヴューにおいても、「与えられた役」という観点から考えたこともなかったような解釈が綴られていて、多いに刺激を受けた(が、全て書くと字数が爆発してしまう+完成されていて書かれていることの反復に終始しそうなので、この程度にしておきたい)。
(この記事に関する意見や指摘等があれば、ぜひ筆者(@nebou_June)にお聞かせください。)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
