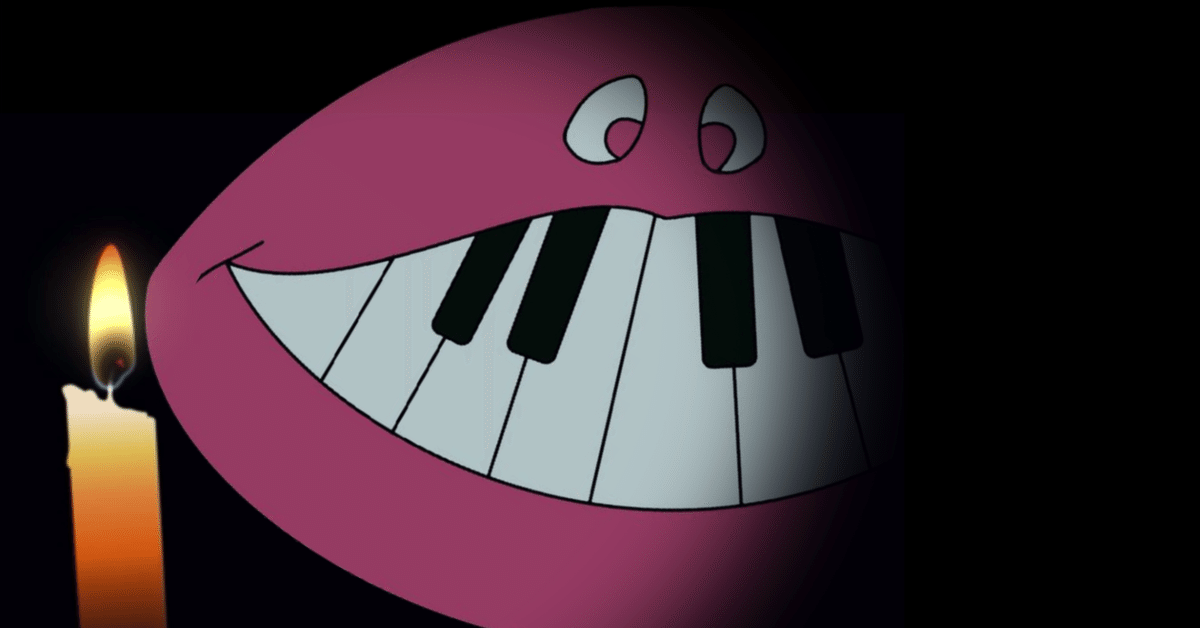
怪談「パップラドンカルメ」
AIのべりすとをいつも玩具にして遊んでいたので、偶には真面目に小説でも書こうかな、と思ってできた作品です。AIに展開してもらいつつ加筆修正して、文体と辻褄合わせを繰り返して出来上がったものです。それでは、ほんへをどうぞ~
「ねぇねぇ、パップラドンカルメって知ってる?あの噂、本当かなぁ?」
「なんだよそれ……聞いたこともないぞ」
「なんかね、知らないけど、最近になって急に出回り始めたらしいよ! すっごく美味しいんだって!」
「ふーん。どんなやつなんだ?」
「それがね……食べた人によると、見た目は白いマシュマロで、味はカスタードだって言ってたんだけど……」
「だけど?」
「食べてみたらスポンジケーキだったとか、キャラメルソースがかかったパンナコッタだったとか、色々あるらしくてさ、全然統一性がないの!」
「そんなのあるわけないだろ?どうせ嘘っぱちだよ」
「でも、気にならない!? 私すごく気になるの!」
「そうか?俺はあんまり興味無いけど」
「えぇ〜!なんでよぉ〜」
「大体、お前もう食ったんじゃないのか?」
「ううん、まだ1回しか食べれてないの。だから他の人の感想も聞きたいしね。」
「はいはい。まぁいいから、早く学校行くぞ」
「むぅ〜……。あっそうだ!今日一緒に帰らない?」
「別に良いけど……」
「やった♪じゃあ約束ね!」
「お、おう……」
僕はそんな噂話を聞いて、またおかしなものが流行り始めたのか、と呆れながらに思った。パップラドンカルメ、さっきの話を聞いても一体何なのか、全くわからない。特徴を聞いても滅茶苦茶で、もはや存在しているかどうかも怪しいものだ。しかしながら、みんな噂している。そんな訳のわからないものに一体どこが惹かれるというのか。理解できない。理解できないことには心底不愉快になる。ならばよろしい。そのパップラドンカルメとやらを解明してやる。デタラメな噂話を吹き消し、この不愉快なわだかまりを取り除いてやろうじゃないか。僕は元来そういう性格だ。
早速、パップラドンカルメというものを、姉にも話してみた。
「へぇ〜。面白いじゃない!私は信じるわよ!」
「本当にいると思うか?パップラドンカルメなんて」
「うーん……正直分からないわ。でも、いなくてもおかしくはないんじゃないかしら? だって、今までに見たことも聞いたこともないものなんですもの。逆にいる方がおかしいくらいじゃないかしら?」
確かに一理ある。パップラドンカルメが存在しないと考えるのは自然だろう。則ち、それは存在すると断言するのは不可能だ。まぁ、そんなことは置いておいて、では、パップラドンカルメが存在すると仮定した場合、噂の発生源はどこか?パップラドンカルメの噂が広まったきっかけはなんなのか?パップラドンカルメの噂の出どころはなんなのだろうか?パップラドンカルメの存在の有無に関わらず、これらを知ることはできるはずだ。
まず、パップラドンカルメの噂についてだが、これはインターネット掲示板に書き込みがあったのが最初であるとされている。しかし、書き込みが行われた時刻は曖昧であり、信憑性は低いと考えられる。その書き込みの内容は、パップラドンカルメを目撃したという人物が現れたというものらしい。目撃した人物によれば、パップラドンカルメは白いマシュマロのような物体だったらしい。その証言を元に、パップラドンカルメは噂になったようだ。
最後に、パップラドンカルメの噂が広まっていった理由についてであるが、これもネットに原因があるらしい。なんでも、とある動画投稿サイトにて、パップラドンカルメを食べてみたという内容のものがアップロードされたそうだ。それからというもの、パップラドンカルメは瞬く間に広まり、人々の心を鷲掴みにしたらしい。
以上が、今現在分かっている情報である。しかし、これ以外にも、もっと多くの情報が出回っている。例えば、パップラドンカルメはどこにあるのか、パップラドンカルメはどんな味なのか、パップラドンカルメはどうやって作られているのかなど、様々な疑問が湧いてくる。これらの謎を解くために、僕はこれから行動に移すつもりだ。
パップラドンカルメを食べるための準備をする。用意するものは、クリーム、スプーン、水筒らしい。これらは全てスーパーで買ってきた。
僕は準備を終えて、家のリビングに集合した。
「これらを使って、これからどうするの?」
姉が尋ねる。
「ええと、この動画によれば、水筒の中に入れてる飲み物を飲み干してから、スプーン一杯ほどのクリームを入れて振ると、できる…らしい。」
僕は説明をしながら、メモ通りにやってみた。
カランカランカラン……! 僕は思わず、驚いて声を上げてしまった。なぜなら、目の前にはパップラドンカルメ?いや、それらしきものが入っていからだ。その形状は、マシュマロを想像させ、少し焦げ目がついていた。色は白色。匂いは仄かに甘く感じられた。見た目はとてもいいのだが、食べるとなると話は別である。
「姉ちゃん、これ食べてみてよ」
僕の姉の好奇心はかなり旺盛なほうで、大抵のことは楽しんでくれるのだ。だが、僕の姉の反応は予想していたよりも薄かった。
「へぇ、こんなのがパップラドンカルメ?量が少ないわね」
彼女はパクっと一口食べた。すると、次の瞬間、 パァーンッ!! 突然、破裂音が聞こえた。一体何が起こったんだ?と不思議に思っているうちに、姉の姿が見えなくなった。
僕は急いで辺りを見渡したがどこにもいない。しかし、何か物音がしたので振り返ってみると、そこには姉が倒れていて、彼女の体はみるみる溶けていくところだった。まるで、チョコレートフォンデュみたいに、ドロリとした液状になっていたのだ。しかもそれは、床一面に広がるのではなく、徐々に集まってきて、一つの大きな山を形成し始めた。やがてその塊の中から、人の形をした何かが出てきた。
目はぐりぐりと光り、鼻は無く、口は耳の近くまで裂けていた。服は着ておらず、代わりに白い布のようなものをまとっている。そして、大きくてやたらに平べったい顔が特徴的だ。こいつは姉ではない。直感的にそう思った。きっとこいつが、あの有名な未確認お菓子物体の正体に違いない。
それは僕に向かって近づいてきた。僕は身動きが取れない。もうダメかと思い、死を受け入れる覚悟をした。しかし、謎の怪物は何もせず、ただ僕の横を通り過ぎて行った。
僕はホッとして胸を撫で下ろしたが、よく考えるとおかしいことに気がついた。なぜこいつは何もしてこなかったのだろうか?姉をドロドロに溶かした奴だぞ?普通なら殺そうとするはずだろう。もしかしたら、こいつに殺意は無いのかもしれない。それなら、姉は一体どうなってしまったんだ?僕は恐這いる恐る、自分の腕を確認した。なんともなっていないようだった。では、どうして姉だけ溶かされてしまったのだろう。考えに考えて僕はその答えを見つけることができなかったが、そんなことで僕は諦めたりはしない。
あの未確認お菓子物体の正体を暴いて、姉さんを取り返してやる。あのドロドロの這い跡がわずかに床に残っているので、僕はその跡をたどっていくことにした。するとそこには、小さな扉がった。なんだろう、こんな扉あったかな?開けてみても中は何の変哲もなかった。でも僕は安心できなかった。どこかに隠し部屋のような場所があるのではないかと、探し回ってみた。しかし結局見つからず、諦めることにした。
しかし、そこでまた一つ不思議なものを見つけた。部屋の壁に貼ってあった一枚の写真だ。それはどうやら家族写真らしく、三人写っていた。一人はもちろん僕の姉。もう一人は恐らく、パップラドンカルメ(仮)であると思われる。顔が大きすぎてあまりにもアンバランスだ。問題は残りの一人なのだが、これは僕ではなかった。その人物は男で姉よりは若干の年下に見受けられた。全く知らない男性だ。彼は一体誰なんだ?姉との関係は何なのか?ますます分からなくなってきたが、今は置いておこう。そうして後ろを振り返った瞬間、例の奴が立っていた。
僕は慌てて逃げようとしたが、足を踏み外してしまい転んでしまった。そしてすぐに起き上がって走ったが間に合わず、奴は僕の体を覆いかぶさってきた。体中を締め付けられる痛みで、呼吸が苦しくなる。そして次第に意識が遠退いていった。
僕はゆっくりと目を覚ました。ここは一体どこだろう。僕は仰向けになって寝ており、天井には無数のシミができていた。この光景を見ただけで、とても気持ち悪く感じられた。周りは壁で囲まれているようだ。しかし、窓が無いせいで今いる場所は暗くてほとんど何も見えない。どうしたものかと考えていると、微かに音が聞こえてきた。
コツ、コツ、コツン……
靴の音だ。誰かが近づいてくる音である。その正体を確かめるために、僕は急いで音の鳴るほうへ向かった。そこにはドアがあって、その向こうには廊下。一つの小部屋に繋がっているのを発見した。そこに入ってみると、そこには僕の家があった。家具の位置などから見て、ここが僕の家で間違いないと思う。しかし、明らかにおかしいことが一つある。玄関から入ってすぐ目の前にある居間の様子が、以前とは少し異なっていたのだ。テレビとソファーの間には、様々な種類のカップラーメンが乱雑に積みあがっていて、壁にはガラスケースに入った高級なお菓子が飾られていた。その中身がプリンとクッキーであることを見て、えも言われぬ気持になってきた。まあそれはいいとして、もう一つ気になることが。それは居間に置かれた時計だった。時刻が狂っているのだ。現在の時刻が午後二時だというのに、針は五時過ぎを指し示している。カチカチと正確に動いているし、壊れているわけでもなさそうなのに…それにしてもどうして僕はここに来てしまったのだろうか。結局姉の姿も見えないし。あのお菓子物体と一体何の関係があるのだろうか?そういえば、さっき入ってきた入り口にまだ鍵をかけていない。このままだと危険だと思い急いで戻ろうとしたが、その時、ガチャリという音が響いた。
振り返ると、例の奴ががそこにいた。あの大きな顔と口はいつ見てもびっくりする。今度は驚きのあまり立ちすくんでいたが、やおら僕の前に立ち止まったかと思いきや、何か静かにしゃべり始めた。
「お前の望みは何だ」と、彼は問いかけてきた。僕は意味がわからなかったので、しばらく黙り込んで相手の様子を見ていたが、相手は何もする気配を見せないので、恐縮しながら、恐る恐る答えた。
「姉さんを返してほしい」
すると奴は僕に質問を続けた。
「その答えは本当にそれで正しいのか」といったような内容のものだった。
僕は正直に答えるのが正しいことだと確信していたので、迷わず答え続けた。
「そうだ。姉さんを返してほしい。」
「君が望んでいるのは姉さんを取り戻すことなのか?」
「そう言っているだろう。姉さんはどこにいるんだ?」
「君の姉は生きているよ。でも、姉を返すことはできない。だけど、姉はここにはいないんだ。君は姉のことをどう思っているんだい?君は姉のことを取り戻そうとしている。君が欲しいものは、本当にそれなのかい?本当はもっと別のものじゃないのか」
「言っている意味が分からない。生きているんなら返すことはできるはずだろ?早く返せよ!」
彼は何も言わず、僕の顔を見つめ続けているだけだった。まるで心を読んでいるかのような視線に耐えられず、思わず顔を伏せた。彼はそんな様子の僕を見ながらこう呟く。
――本当のところ、君は自分の姉が嫌いなんだろう?……
何を言っている?この男は一体何を言ってるんだ?確かに姉はヒステリックな面があるけれど、だからといって嫌いになるほどではないぞ?僕の疑問にはお構いなしとばかりに話は続いていく。
―違うかい?君の考えている通りだよ。人間は醜いものだ。他人よりも自分を優先し、自分が大事。そうやって他者を貶め、自分を正当化しているだけだ。その行いはやがてエスカレートしていき、ついには自らの手で命を奪ってしまうことも珍しくはない。自分の家族であっても、例外はない。むしろ身近にいる存在だからこそ、より深くまで堕ちてしまう。自分の姉もそういう類の存在ではないのか?彼女は昔からそうだっただろう?いつも人の顔色を窺って生きていたんじゃないかな?周りの人たちが機嫌よくしてくれるかどうかによって自分の価値が決まると思っていて、少しでも機嫌を損ねればすぐに捨てられると思って……
「一体何が言いたいんだ!」
と僕は尋ねた。彼の話に納得がいかなかったのだ。
――君が今までやってきたのはそういうことだよ。彼女のためと思ってやっていたことでも、結局自分の都合のためだったんじゃないのかな?そして今も、彼女がいない世界では生きる希望が無いと考えているから、何とかしようと必死になっているだけなのかもしれない。だって君はずっと、彼女と二人きりで暮らしてきたじゃないか。それはつまりどういうことかわかるかい?君にとって、彼女の存在は必要不可欠だったというわけさ。まあそれも無理もないよね。君が彼女を嫌っていないはずがない。なぜなら彼女は、君にとってはただの重荷にしかならなかったからだ。その重さに耐え切れなくなって、いつの日か捨ててしまおうと考えたこともあるだろう?でもできなかった。君は怖かったんだろう?その事実を認めることが。認めたくないのなら、それをなかったことにして誤魔化すしかない。そのために……。
「うるさい!さっきから何をごたごたと話しているんだ!僕の答えになっていないじゃないか!僕は姉を返せと言っているんだ!」
――やっぱりそうなんだな。じゃあ改めて訊こう。なぜ君は彼女を返してもらおうと思ったんだ?君と姉さんの間には、特に深い絆があったわけではないだろ?君と彼女の関係は、血が繋がっているだけの赤の他人同士に過ぎない。しかも、片方はそのことに気が付いていなかった。なのにどうして君は彼女に固執するんだい?姉がいるべき場所はどこなのか考えてみてほしい。君の隣に立っていたその人は、いったい誰だい?
頭がおかしくなりそうだ。奴の言っていることが滅茶苦茶なはずなのに、図星を突かれた気分になってくる。姉はもしかして帰ってくるのを望んでいないんじゃないのか?いままで姉と過ごしてきた時間は?僕にとって姉の存在は?そもそもどうして姉を取り返したがっていたのか?そんなネガティブな考えが脳に埋め尽くされていく。奴はまた口を開いた。
――君はまだ迷っているようだ。本当の答えがまだ見つかっていない。君の心の中に存在する迷いこそが答えなんだ。だから君は迷わなくてはならない。
僕は再び黙り込んだ。奴の言葉にはなんだか説得力があった。確かに僕は姉のことを考えていたようで全く考えてなどいなかったんだと思う。姉がどうとかではなくて、僕自身がどうしたいか、ということが重要なはずではないか?そうだよな。でも考えてようやくわかった。僕は空っぽだ。姉さんがいないのなら生きている意味なんて無いよな。僕はもう何も考える必要がなくなったと思った。僕は静かに目を閉じた。
目が覚めると、家のリビングだった。姉もいる。スプーンと水筒があって、まるで何事もなかったようにそこにあった。
「大丈夫?」と姉が言った。
「あんた、私がパップラドンカルメを食べたと思ったらいきなり倒れちゃうからびっくりしちゃった」
そうか、あれは夢だったのか。
姉が僕を見つめている。僕はその目を見てこう告げた。
―姉さんは僕と一緒にいたほうがいいよな? すると姉は一瞬不思議そうな顔をしてから笑顔になり、僕の手を掴んで ―うん、私もそのつもりだよ。だって私はあなたのお姉ちゃんだからね。
と言った。
「そういえばパップラドンカルメを食べてみて、どんな味がした?」
「えっとねー、よくわかんない。」
「うん、まぁ、それでいいと思うよ」
「なんか、どうでもよさそうね。」
「いやいや、ただ、分からなかったら、分からないでいいのさ。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
