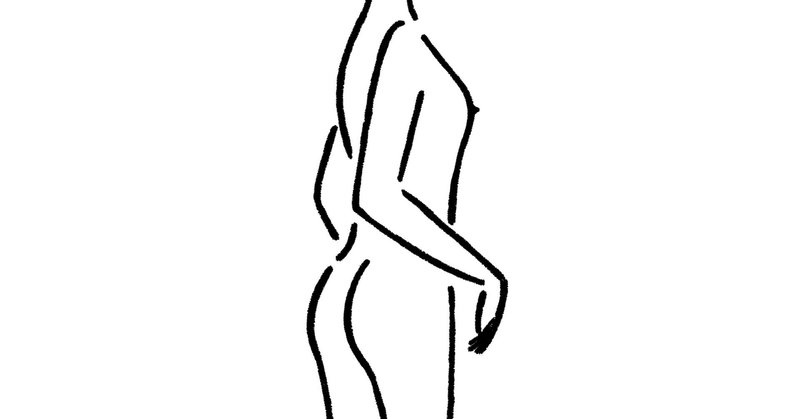
面影 (ポラ列から始まる百合②)
「私、真帆ちゃんのことがずっと好きだったみたい」
しおりがそう言ったのは、高等部に上がってすぐのことだった。わたしやしおりのような、中等部から持ち上がりの生徒と、高等部から入学してきた女の子たちがすこしずつ打ち解け始めたころ。しおりとはクラスが離れてしまい、新しい顔ぶれが物珍しかったのもあって、そのころのわたしは高校入学組とつるむことが多くなっていた。
小学校を出てすぐ女子校にはいったわたしたちと比べて、中学まで共学だった女の子たちは他校に彼氏がいる子も多く、社交的で大人っぽく見えた。まだ付き合いの浅いうちから「真帆」と呼び捨てにされること、それが乱暴な感じではなくごく自然な親しみを込めた言い方であること、そういう新鮮な空気で接してくれる新しい友人たちに夢中で、しおりとの付き合いがすこし希薄になっていたのかもしれない。
「わたしも好きだよ?」
「そういうのじゃなくて」
そのころからしおりは、外でも目立つほど背が高かった。運動部ではないもののスポーツが好きで、スカートから短いソックスへとまっすぐに伸びた脚はいつも日に焼けていた。中学の頃は長かったくせの強い髪を切ったばかりで、ちょっとした取り巻きのような子たちに囲まれているところをときどき見かけるようになっていた。
女の子が女の子を好きになる。そういうことがあるのは中学のころからとっくに知っていたし、まるでセットみたいに扱われる二人組なら学校のあちこちにいた。しおりを囲むようになった女の子たちが、まるで王子さまを見るような目をしおりに向けるとき、反対にわたしの気持ちは冷めていた。ぜんぜん冴えないおじさん先生に熱を上げる子がいるように、女子校特有の風邪みたいなものだと思っていた。
わたしたちはいつか男のひとを好きになる。でも、いまは周りに男の子がいないから、予行練習として手近な身代わりに熱を上げている。アイドルに熱狂するグループも、こそこそ漫画を回し読みしているグループも、それぞれが行き場のない熱を発散しているけれど、この場所を出れば憑き物が落ちたみたいにあたりまえの恋をするのだろう。
そう疑いなく信じ込むくらい、あのころのわたしは狭い世界を知ったつもりで生きていた。
傲慢なわたしの前で、目を泳がせて言葉を紡ごうとするしおりの姿はとてもいじらしく見えた。まつ毛が長いから、瞬きが増えたのも落ち着きなく視線が動くのもありありと見えてしまう。あちこちの運動部から誘われているのに、わたしと同じ合唱部を辞めようとしないしおり。委員会で遅くなったわたしを、ただ一緒に帰るためだけに待っていてくれるしおり。新しい人間関係に惹かれたとき、馴れたつながりはほんのすこし疎ましいときもあった。けれど、たくさんの女の子が欲しがっているしおりの視線の先に自分がいることを意識したときに、わたしの胸はずるい高揚感で満たされた。
「どういう好き?」
うんとやさしい声を意識して、わたしは尋ねた。
「うまく言えないけど……」
煮え切らないしおりの態度にじれる気持ちを抑えながら、確かな言葉をただ待つだけの甘やかな時間。ひとの気配がほかにない教室で、生まれて初めて他人から好意を向けられたわたしは有頂天だった。
「特別に、なりたい」
絞り出すようにしおりがそう言ったときの、満たされた感覚を覚えている。
オープンショーのあとは、間をあけずに次の演目がはじまる。隣の席にいるしおりの表情をうかがうことはできないけれど、手拍子がどことなくぎこちない。そう感じてしまうのもまた、わたしの傲慢や期待の表れかもしれない。誰かの胸に自分が大きな存在として残っていると思い込むなんて恥ずかしい。狭い世界のなかで、しおりの関心を惹いて良い気になっていたわたしは、そういう自意識を隠したがるつまらない大人になっていた。周りの客たちから外れないように、リズムとタイミングを合わせて手を叩く。
過去の気配に飲まれてしまいそうで、救いを求めるように舞台へと目を向けた。踊り子の白い肌に映える深紅の着物。つややかに赤い唇。舞台に現れたときはきゅっと端を上げていた唇が、演目が進むにつれて薄く開かれる。愛らしさの際立つ表情は次第に蠱惑的なものへと変わり、表情やしぐさのひとつひとつが客たちの視線を集めて離さない。踊り子の息が上がると、濡れた舌のちいさな震えまでもが見て取れる。やがて露わになるすべらかな肌や、普段日にあたらない場所を飾るうすい体毛へと視線を這わせるうちに、踊り子としおりを重ねてしまう自分がいた。
いっしょに帰ること。休日に遊ぶこと。ほかの子たちとはすこし違う態度を向けたり、名前で呼んだりすること。どれもすでに済ませていたわたしたちにとって、あらためて「特別」になるのは簡単ではないことだった。しおりの取り巻きのことを考えると、関係に名前をつけて公言するのはわたしの気が進まなかった。しおりは「真帆ちゃんとのことは、私たちが知っていればそれでいい」と言った。
「高等部になってから、真帆ちゃんが離れていくみたいで寂しかったの。でも、いまは平気」
そう言って、本当にすっきりした表情で笑っていた。女の子たちに囲まれているしおりが、通りかかったわたしに小さく手を振ったとき。部活のパート練習が終わったタイミングで、アルトの集まりから抜け出してきたしおりから「何話してたの」と拗ねた声で尋ねられたとき。しおりから向けられる優遇やささやかな独占欲が、なんのとりえもないわたしを良いもののように思わせてくれた。
キスは、してしまえば簡単だった。わたしたちのどちらも経験はなかったけれど、唇を合わせるだけのことだからそう難しいことではない。困ったのは、そうするのに適した場所を知らないということだった。
しおりはふたりの関係が変わってからすぐにそうしたいそぶりを見せはじめていた。学校からの帰り道、電車に乗ってしまえばわたしたちは降りる駅が違うから、しおりは妙に寄り道をしたがった。カラオケボックスやプリクラの中で、意味ありげにしおりが黙るとき、わたしは気づかないふりをしてやり過ごしていた。ひとの目につくのがとにかく怖かった。
だから、わたしたちがはじめてそれをしたのは、ショッピングモールの中にある女子トイレの個室の中だった。先に立っていたしおりがわたしの手を引いて、同じ個室の中に引っ張り込んだのだ。辺りを行き交う足音に注意を向けながら、ふれあった唇は気が付くとどちらも小さく笑っていた。声を立てないように。しずかに息を零して。
それから、ちょうどいいトイレがあれば同じ個室に入り、キスをするのが習慣のようになった。しおりははじめ、学校のトイレでもそういうことをしたがったけれど、わたしが絶対に応じなかった。汚いトイレでもだめで、公園や駅のトイレは問題外。ずいぶんわがままを言ったけれど、しおりは学校の外にある清潔なトイレをちゃんと見つけてくれた。個室のカギを閉めた瞬間の、安堵としずかな興奮。まるでこわれやすいものを扱うように、そっと肩に置かれるしおりの手。ただ合わせただけの唇から自分とはちがう体温が伝わったとき、くすぐったいような、泣きたいような不思議な気持ちになったことを覚えている。
「ボタン外してもいい?」
隣の個室から出て行った足音が遠ざかるのを確かめてしおりがそう言ったとき、わたしたちはもう一年生ではなかった。すこしずつ見え始めたお互いの進路は交わりそうもなく、しおりは時折思いつめたようなため息をつくことがあった。肩まで伸びた髪をきつく結んだ横顔がすずしくて、向き合う時よりもただ見ているときに、わたしの胸はひそかに高鳴った。
「どうして?」
「真帆ちゃんのこともっとよく見たいから」
ひるまずに言葉を続けるしおりの視線が、わたしの襟元に注がれている。唾をのめば喉の動きでわかってしまいそうで、わたしの呼吸が浅くなる。
「嫌。しおりが先に見せて」
動揺を隠して顎を上げる。しばらく見つめあったあと、さきに目をそらしたのはしおりのほうだった。両手を首の後ろに回すと、パチン、とリボンの留め具を外す音がかすかに聞こえた。小麦色の長い指が上から順番にボタンを外す。ためらうようにゆっくり息を吐いたあと、シャツの前を開いて恥ずかしそうに目を伏せた。肌着を身に着けていないので、藍色の下着に包まれた胸が目の前にあらわれる。日に焼けていない肌が、緊張のせいかふつふつと粟立っている。
クラスが同じころはプールの授業もあった。宿泊行事でお風呂に入ったことだってある。体育の着替えなら日常茶飯事。恥じらう理由が見当たらないのに、しおりの緊張が移ったようにわたしにも汗が滲んでいた。立ったままの足がぐらぐらとするのをこらえて、そっとしおりに手を伸ばす。何も言えなかったのは、他人の話し声が近づいていたからだ。おしゃべりをしながら入ってきた二人組がわたしたちのいる個室の前を通り過ぎ、それぞれの鍵がまわる音がした。一方の個室から擬音装置の水音が流れ始め、それに便乗するようにもう一方からは控えめな排尿音が聞こえてくる。重なる音に隠れるようにして、しおりの背中に回した手でぎこちなくホックを外した。着たままのシャツを取り払うことはできなくて、ブラだけを上にずらす。締め付けを解かれた乳房が、ほっと息をつくように柔らかくこぼれ出た。ふくらみにきざまれたワイヤーのあとをなぞると、シャツを広げたままのしおりの手にぎゅっと力がこもる。いつもかすかに感じていた柔軟剤の香りが、汗と混ざって濃く漂う。二人組の話し声が遠ざかるまで、むきだしにされたしおりの胸をじっと眺めていた。
(似ているわけじゃないのに)
踊り子の肌には、下着のあとなど見当たらない。膝頭に残る青や黄色の痣が、華やかな踊りの裏で積み上げられたストイックな鍛錬をうかがわせているものの、夢をみせてくれる体は生々しいようでいて慎重に生活感を排している。体つきも見せ方も、あの日のしおりと目の前の踊り子はまったく違う。それなのに、踊り子の体にかつてのしおりを見てしまう。
いまそばにいるしおりは、舞台を見てなにを思うのだろう。ふたたび顔を出す、期待のような思い上がりを打ち消したくて、逃げ込むように踊り子の体へとわたしの心がすがりつく。モニュメントのように静止する踊り子の体。不自然なはずの姿勢が、しなやかな筋肉に流れるような起伏をつくりだす。天に向けて伸びたつま先や、体を支える細腕が、体勢をかえるたびに緊張と弛緩を繰り返す。のぼせてゆく頭のなかで、果たされなかった約束の記憶がそっとふたを開けた。(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
