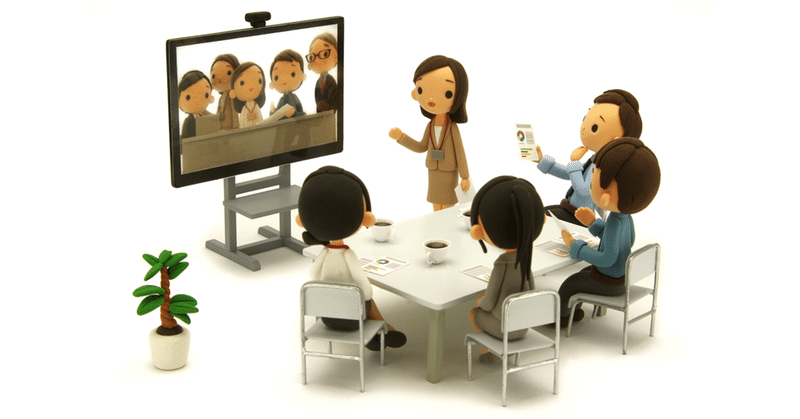
中原教授の「オンライン授業10か条」メモ。
zoomとかmiroとか、その他の色々なオンラインツールが、ニーズの高まりを受けて話題になり、活用が進んでいる。
そんな中、ボク自身はそれらのツールとほぼ無縁の生活を送り、仕事的にも今しばらく、特に導入・活用の予定は無さそう…。
とはいえ、これだけテレワーク、リモートワークが進む社会で、全く無知なままでいることに流石に焦りを覚えるし、自分だけでなく、今後は我が子がオンライン授業を受ける機会も出てくるかも知れないし、というか必然的にそんな流れは更に加速する事が自明の理。
そんな気持ちが着々と醸成されていた中で、
先日、購読(≒登録のみ)していたメルマガの紹介記事の中に、オンライン教育に関連したタイトルの記事があって、なんとなく目に止まったので、珍しくクリックしてみた。
普段は、殆どノーチェックで「全てゴミ箱に直行」というのが実情の中で、珍しく目が留まった今回の記事のタイトルは、
祝!オンラインでの授業、無事スタートできました!
:経験学習でつかんだ「オンライン授業10か条」!?
立教大学経営学部 中原研究室の、
中原教授が書かれていたブログのエントリーでした。
オンラインツールに無縁と書いたボクですが、
先般、妻の繋がりでちょっとだけzoomを使ってお話をする機会があった。
ただ、初めての事だし、用意した簡単な資料を見ながら話したので、
思えば「聞く側」の顔もリアクションも全く見れていませんでした。
しかも、zoom自体がほぼ初めてだったので、
チャットすら見れていない事に途中で気付いて、
後で見ようと思っていたけどミーティングが修了して見れなくなり…。
無知さの反省と恥ずかしさとに襲われたのも、今回のクリックに至った動機だと思います。笑
*****
オンライン授業の10か条。
さて、本題ですが、ほぼ丸ごと引用した感じですが、自分用のメモ的な意味合いが強いので、原文とは各所表現が変わっています。
原文はもっと丁寧なので、ご興味がある方はリンクから原文もご覧ください。
1.15分で、ひと区切り!
15分をひとつのモジュールとして考える。
15分をひとつの「目安」に、細切れにレクチャーを行い、その合間合間には、必ず、何らかのグループワークを入れたり、発問をするなどして、集中力をもたせ、注意資源を集める。
※メリハリのないオンライン授業(会議)だと、
昼ご飯を食べたあとに感じる眠気をただちに誘発する。
2.参加者には、とにかく「反応」を求める
1)挙手ボタンをもとめる
2)ビデオ映像でのジェスチャーをしてもらう
3)マイクを使っての発話をふる
4)投票ボタンを使う
5)チャットを用いる
などなど、相手に反応を求める方法は多々ある。
とにかく参加者に「反応」を求めることを実践する。
意外に使えるのは、チャット。
何か思いついたことがあればどんどん書くように促しておくと、チャットに意見が流れる。
これを拾いながら話すと、インタラクティブになる。
なぜ、チャットに流れている文章を「ひろう」とうまくいくか?
チャットに書き込む人は、自分の「考え」を敢えて外に出している人であり、逆にいえば「考えていない人(や考えのない人)を指名することが避けられる」から。
これは、オンラインでの学びに非常に有効な点で、かつ得意な点。
通常の授業では「頭に浮かんだ疑問でも、外にだすことは希」、なぜなら、授業が中断してしまうから。
だから、余程の事がないと挙手しない。
しかしチャットは、「頭に浮かんで、かつ授業を中断させる程のことではないこと」を「見える化」することが出来る。
当然、ここに指名を行えば「考えている人」に指名することになる為に、上手くいく。
3.メインディッシュは7割、バッファは「多め」に!
対面でも同じだが、教える方はどうしても詰め込みすぎる傾向がある。
オンライン授業では、さらに詰め込みすぎに注意が必要。
なぜなら「2.相手にはとにかく反応を求める」ので、そのやりとりに時間がかかるから。
※伝達内容は、おそらく全体時間の7割程度でよく、目的の打ち込み、質疑などに加え、バッファ時間を多めにとすると、メインディッシュは7割くらいにおさえ、質疑などの時間を多めにとるとよい。
4.チームティーチングが出来ると安心!
zoomの操作を代行する人や、アシスタントがいると、万が一、通信障害や機材トラブルがあっても代わりに進めて貰える。
5.コミュニケーションチャネルを「複数」をもつ!
トラブルが発生した時に、参加者と連絡のとれる別手段を用意する。
LINEやKintoneなど複数のコミュニケーションチャネルを持っておくと安心。
またメインが落ちてしまった時にどう続行するかも予め決めておくといい。
例)最悪の場合は「LINEの音声通話」で授業を続行する、など。
※オンラインでは「接続性を高めること」が重要。
6.備えあれば憂いなし!
マウスやイヤホンなど、LANも含めて無線のツールには有線など、あるいはバッテリーの確保など、備えあれば憂いなし。
7.情報環境をセットアップ:「無線」よりも有線接続!
家族がおのおの使用していると、無線の容量を超えていることが。
有線接続など含めたチェックと見直し。
8.グループワークは「手続き」を明瞭に!
ブレークアウトセッション(参加者を小人数に分けて、それぞれで話し合ってもらう機能)で、グループワークを行う時は、とにかく指示を明確にする。
1.チームとしては何分間、個人としては何分間で
2.誰が司会者になって
3.誰がタイムキーパーをして
4.何を話し合い
5.どのようなアウトプットを出すのか
グループワークは進行・ルールを理解して貰ったうえで行うこと。
この指示を「ゆるめ」にしてしまうと、グループワークにお見合いが生じるので注意。
例)チームに分かれて自己紹介
時間は25分あります(1人5分)
①誕生日が一番12月に近い人が「司会役」
②誕生日が1月に近い人から自己紹介
・お名前
・どんな仕事をしているか
・なぜここにいるか
・ここでどんな成長がしたいか
・得意なことはなにか?
・苦手なことはなにか?
③1人終わったら拍手
④時間が余ったらお互いの仕事に質問をし合う
ブレイクアウト!
9.いつもの「1.5倍」テンションを盛れ!
メディアに映る時には「やりすぎくらい」がちょうどいい。
1.5倍くらいテンションを盛っても、メディアを通して見るとおそらく普通くらい。
10.自分が学ぶことを楽しむ
新型コロナウィルスとの闘いは、
おそらく「短距離走」ではなく「マラソン」になる。
ZOOMフリークとかではなくても、やむなく実践する中で、経験学習しながら、オンライン教育を学び取ることに「腹をくくった」。
いざ実践してみると、意外に楽しく、学びも多いとのこと。
これは教育界全体も、社会全体にも言えることだと思う。
*****
オンライン授業に関するその他の記事
以上、中原教授がブログに書かれていた10か条について、自分用に書いてみました。
表現や語尾が若干ぶっきらぼうな箇所も多いですが、原文はもっと丁寧に書かれていて、分かり易いです。
また、中原淳研究室のブログでは、この他にもオンライン授業に関する記事が多数掲載されていましたので、実施をお考えの方にも、とても参考になるかなと思いました。
当面、授業は元より会議でも自分が何か発信する側になることは無さそうだけど、参加者になることはあるかも知れないし、いざ当事者になった時に、焦らずに出来るよう心に留め置きたいと思います。
***追記***
同ブログの最新のエントリーで、これまで中原教授が公開されてきたオンライン授業のノウハウ・経験について、1つのスライドにまとめたものを7日間限定で無償公開(ダウンロード可能)してくださるそうです。
“僕や僕のゼミ生(中原ゼミ)が試行錯誤しつつ、僕のブログで公開してきたオンライン授業のノウハウ、そして、立教大学大学院 経営学研究科 リーダーシップ開発コースの教職員がつみあげてきた経験を【ひとつのスライド】にまとめました。このスライドを無償でダウンロードいただけるようにいたしました!”
ちばみに、サーバーの負荷の関係で7日間限定とのことです。
ご興味がある方は、下記リンクのブログ記事からダウンロードしてみてはいかがでしょうか。
(ダウンロードしてみたところ、30MBでした。)
以上、ナツキのパパでした。
過去のボクは昭和の固定観念や慣習に縛られ、自分や家族を苦しめていた事に気付きました。今は、同じ想いや苦しみを感じる人が少しでも減るように、拙い言葉ではありますが微力ながら、経験を通じた想いを社会に伝えていけたらと思っていますので、応援して頂けましたら嬉しいです。
