
ツタンカーメンに会いに
研究調査のためにエジプト南部の町ルクソールに何度か脚を運んだことがあります。かつて、ワセト、あるいはテーベの名で知られ、百門の都と呼ばれた壮大な宗教都市でした。
調査といっても、ちょっとした確認作業のようなものです。あの神殿のあの壁のレリーフを撮影して論文に載せてみよう、と。私は考古学者ではないので、チームではなく、いつも独りです。学生時代はお金が無かったので、少しでも節約するのが板についていました。カイロの空港に降りて暑い風に迎えられると、少し気が引き締まったものです。迎えの人もガイドさんもいません。私を待っているのは、決まって客引きのタクシー運転手さんたちです。ソーリー、ソーリーと言いながらその人影を潜り抜けようとします。彼らにも生活がありますから、簡単に引き下がりません。かといって、一人一人に頭を下げて断るとキリがないのです。そうして、必然と彼らを無視して進むという心苦しい欠礼からエジプトの旅は始まります。ターミナルからずいぶん離れたところにある公共バス停まで行くと、すっかり汗が吹き出ます。ホッして見渡すと私以外、外国人の姿はありません。

渋滞の末に騒々しいカイロ都心にたどり着くと、私は徒歩で安宿を目指しました。中心部のそういう宿は、なぜかフランスとイギリスの影響下にあった頃の古い建物の上階にあることが多かったように思います。見た目は立派ですが、ガランとしたロビーは薄暗く、蛇腹のドアを自分でガラガラと開けて入るエレベータは、いかにも骨董品のようで、とても頼りありません。そして、時差を取り戻すために私は泥のように眠りました。翌朝、近所のモスクのスピーカーから流れる悪意のないけたたましい礼拝と通りを行き交う車のクラクションの大合唱で目が覚めます。

礼拝の号令(アーザーン)が轟くと、びっくりして強制的に起こされる。2004年に撮影
そうして、荷物の中でぺしゃんこになったヨレヨレのシャツを引っ張り出してエジプト考古庁に向かいます。国内の遺跡に自由に入れる許可証を発行してもらうためです。パスポートと大学からの推薦状を持参しますが、すんなり通してもらったことはありません。初日はだいたい徒労で終わります。二日目にまた同じ場所の同じ人物に会いにいきます。「またか、しつこいな」と思われたらしめたもので、許可証を執拗にねだります。相手が根負けするまでそこに居座るのです。私の孤独な調査は、そんな神経の消耗戦で始めるより他ありませんでした。許可証は決まって限定的なものでした。すべての場所に自由に行き来できるわけではありません。それでも、お金と力のない私にとっては欠けがえのない切符でした。
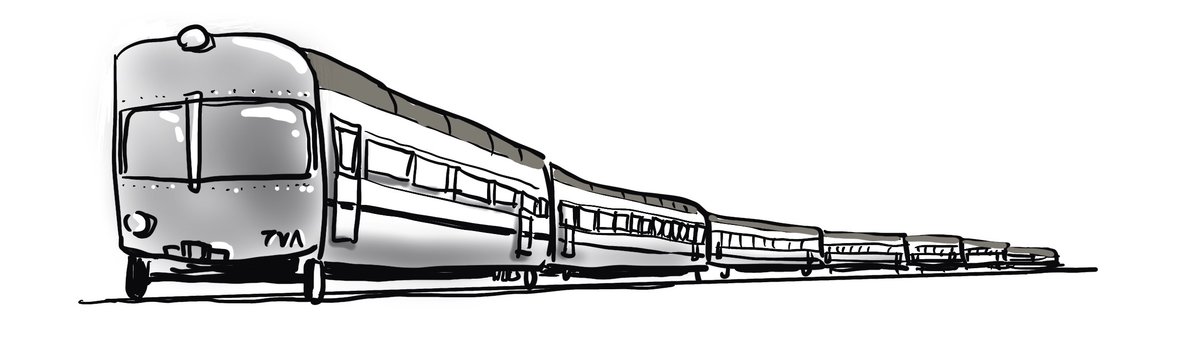
ルクソールの風はカイロよりずっと優しい気がします。山が近くに見えるからかもしれません。ヨボヨボだった足取りは、すっかり元気を取り戻し、慣れた手順で遺跡を巡ります。ナイル川を挟んだ両岸に遺跡は点在しますが、墓地のある西岸の方が落ち着きます。生者より死者の方が紳士的だと思うのは私だけでしょうか。いちいち渡河するのは面倒なので、東岸の神殿で写真を散々撮ったあとはさっさと西岸に向かうことにしていました。そこで、空き家を借りて二週間ほど滞在するのです。自炊をして好きなものを食べると、緩いお腹も回復してきます。ここで私はようやく自由を得ます。自転車を借りて。

重い荷物を引きずる私が乗るのは、もちろん白い客船ではなくて、
左端に見えるような年季の入った地元住民の船。ここから西岸に渡る
かつて西岸には累代の王が建造した大神殿が林立していました。この地が首府だった新王国時代(紀元前16世紀〜11世紀)には、王は谷奥の秘密の岩窟墓に埋葬されるようになりました。というのも、ピラミッドのように追悼施設と墓が一緒では、容易に盗掘されてしまうからです。西岸の神殿群は、墓から切り離された礼拝所の役割を果たしました。一般に葬祭殿と呼ばれます。私は南北数キロに渡って並ぶ葬祭殿を自転車で毎日巡りました。凍らしたペットボトルの水がどんどん減って、朝にはずっしり重かったリュックサックが心細いほど軽くなっていきます。私は何を食べていたのでしょう。妙に塩っ辛いポテトチップス以外、あまり良く覚えていません。遺跡に夢中になってずっと自転車を漕ぎ、食事を抜いていた気がします。汗と一緒に日焼け止めが蒸発するような匂いを思い出します。今思えば、若く無謀な独りよがりでした。

ふつう、急ぎ足の観光バスはこの場所に停まらずに、王家の谷へ向かう。
守衛さんと私だけの静かな時間。気を抜くと、バクシーシ(お布施という名のチップ)を要求される。
汗まみれの小汚い私はどう見てもお金がないのに、容赦がない
ずっと会えずにいる人がいます。かつて、ルクソールには30人以上の王が眠っていましたが、皆消えてしまったか、カイロの博物館に移されました。でも、たったひとり、この町を三千年以上見守ってきた王がいます。それがツタンカーメンです。王家の谷の大発見は誰もが知る有名な話ですが、彼のミイラだけは唯一、本来の場所で保存されているのです。十代で亡くなった彼のこじんまりした墓には、夥しい副葬品がギュウギュウに納められていました。今は、石棺の中のミイラは首から下を覆う布しかありません。昔からこの墓の話が好きだった私は、内部の様子やミイラの顔をよく覚えています。実際に行ったことはないけれど、会ったことがあるような気がしてなりません。ところが、残念ながら、ツタンカーメンと私の研究テーマはあまり関連がありませんでした。彼の墓を実際に訪れることは優先順位が低かったのです。それに、私の許可証では彼に会うことはできませんでした。

右の山裾には神官や官僚の墓が800基も残ると言われる。村の住民は古くから盗掘を生業にしてきたが、今では政府の施策によって移住させられてしまった
言うまでもなく、ツタンカーメンは世界中の関心を集め、観光客が絶え間なく訪れます。ドル箱である彼の墓の入場料は、一般外国人は300エジプトポンド(およそ2000円)です。学生の私でも頑張ればなんとかなる値段ではあります。でも、すぐ隣にあってずっと壮麗なラムセス6世の墓の入場料が40ポンド(一般現地人)ですから、すっかり現地の物価水準に慣れた私は容易に手が出ませんでした。いつか会える。だって、エジプトの研究をしているんだもの。そんな期待だけで満足しようとしていたのだと思います。それと、ほんの少しの後ろめたさもありました。あまりに多くの人が訪れるために、墓内の温度と湿度の管理が難しく、危機的だと耳にしていたのです。若い自分には、譲れない倫理観を自負するような生意気なところがありました。大型の観光バスが真横を通り過ぎる中、その黒い排気を吸わされるたびに毒づきながら自転車を漕いでいくうちに、私は本と死者以外の誰とも話さない穴のような存在になって、知らず知らずに何かに飲み込まれていきました。一日の終わりに鼻をかめば、塵で真っ黒だったのをよく覚えています。エジプトに行くたびに、そんなことを繰り返しました。

私は遥か向こうの緑の耕作地帯を越えて通った。厳しい暑さのなか、自転車で訪れる人は他にいない
ツタンカーメンはどんな人だったのでしょう。少なくとも、私のような偏屈者ではなかったと思います。彼はあまりに早く亡くなりましたから。それでも、短い生涯で一度改名をしたことが判っています。彼が王になる直前、前代未聞の思想上の大変革があって、エジプトは混迷を極めました。そこから再び元の世界へ戻すための努力を彼は強いられたのです。彼が残した碑文は、「両土(エジプト)の混沌を排除し、秩序が戻った」と伝えます。ところが、その復興半ばでこの世を去ったために、後世の人たちは彼を革命残滓とみなし、正史から揉み消しました。そうして、彼の存在とともに墓も忘れ去られた経緯があります。

ラムセス二世の名前が残るが、様式は明らかにずっと以前のもの。
ツタンカーメンと王妃アンクエスエンアメンが捧げたものをラムセスが横取りしたと考えられる
留学から日本に帰った私は、研究をあまりしなくなりました。他に生活の糧を求めてから随分経ちます。お金は相変わらずありません。そして、世界中が新型コロナウィルスによって大混乱して、旅はますます遠くなっていきます。どうやら、ツタンカーメンに会うきっかけをすっかり失ってしまったようです。何度もあんなに近くまで行ったのに。二十一世紀に私がここで悔しがっていることを彼は何とも思っていないでしょうね。でも、あの乗り心地の悪い自転車もでこぼこした道や生ぬるいペットボトルも忘れられないのです。青々とした畑と白い砂漠の間に立つ葬祭殿をいつかまた走ってみたい。そして、若かった自分を拾って、山の向こうにある300ポンドの小さな王墓へ連れて行ってあげたいと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
