
ビジネスの世界から教育の世界を逆照射!~オンラインイベントを開催して~アップグレード版
前回noteに書いた記事のアップグレード版です。
さらに私の気付きを付け加えました。
1 お招きした塔本さんの略歴

略歴
地元広島から大阪の大学へ、そして大手銀行へ勤務。部次長など8年のマネジメント職を務めた後、25年務めた銀行を退職し、フリーランスの道へ。様々な経験を経て現在、起業家の資金調達支援のフリーランスCFOとして活躍されている。グロービス経営大学院大学経営学修士MBA取得。
もうちょっと加筆すると
ビジネス畑を歩いてこられたベテラン銀行マン。
↓
マネジメント職にもついて、さらにスキルアップしようと
グロービス経営大学院大学で学び直し。
↓
猛烈な刺激を受ける
↓
価値観の転換
↓
退職してフリーランス
↓
東北で起業チャレンジ!
↓
多忙な起業生活を考え直し、一年間の充電の後、再起動
↓
組織に属さず、起業家のスタートアップのサポートやアドバイスを行っている。
大手銀行マンでの高収入で安定した生活を捨てて、自分のやりたいことを追い求めてきた塔本さんの生き方は、いわゆる安定職の教員にとって、非常に刺激になるに違いないし、将来、転職が当たり前になる時代を生きる生徒にとっても非常に有益な話になるに違いない、と思って企画しました。
2 塔本さんを変えたグロービス経営大学院大学での学び

銀行マンとして学び直しのために通ったグロービス経営大学院大学での学びは非常に刺激的だったとお話しになっていました。
●やりたいからやっている!という熱量の高い人の集まり。
●いろんなバックグラウンド、価値観を持っている人の集まり。
●組織の一員、パーツでしかない自分の存在を再認識。
●「君の志は何なのだ?」と3年間問われ続けた。
私はこの、「君の志は何なのだ?」と問われづづけたというところが、すごく刺さりました。私も、仕事に忙殺されながら、一体自分の目指すものは?と考えることがあります。
しかし、職場が異動になり、そこで安定的に働いていると、その志は固まるのですが、また別の職場になると、それがスクラップされて、また再構築に時間がかかります。
でも、果たして「自分」自身の「志」とは何なのだろう・・・とずっと疑問なのです。
その疑問を解くには、多様な人と語り合うこと・・・にヒントがありそうです。
3 ファシリテーションとは?

そしてグロービス経営大学院大学での学びの様子から、私自身の「ファシリテーション観」がまたアップグレードされました。
●みんなが小学校時代の児童のように手を挙げる。
●当てて欲しくて仕方が無い。発言権の取り合い。
●はったりOK。誰も怒らない。
●安心安全な場であることの証。
●講師はいつも評価される。評価が悪かったら再研修。
●学びのパターンは「Fact整理」「課題議論」「まとめ」
●コンテンツは自由な議論が許されてるが、実は細かく設計されている。
●講師=ファシリテーターは自分が場を支配しようとしてはいけない。場を信じて身を委ねる方が良い。
「安心安全な場作り」というのは前提条件なのですね。それなくして対話は成り立たないとすれば、「安心安全な場づくり」をする力量が必要です。教科指導の前にクラス経営力が必要ですね。
もっといえば、「安心安全な場づくり」が困難な実態の現場では、対話型授業はかなりな力量が求められるということになるかと思います。
対話的授業を授業で本気で取り入れようと思ったら、教員の側も評価されてしかるべき・・・だし、その評価する側もその力量を持っていないといけないですね。(ビジネスの場と同等に考えるものではありませんが)
そしてファシリテーションはやっぱり、深い教材研究が根底にないとどんな話題も切り返しができないものなんだ、と思いました。
細かい設計というところでは、いろいろな授業スタイルに慣れてないといけないな、と思いました。一斉授業とか講義式授業とか、昨今批判的に見られますが、それもきちんと成立させる力があった方が良いですね。もちろん、ICTも使えて、その場その場でもっとも適切なやり方をカスタマイズする力が必要だと思いました。
ああ・・・なんて難易度が高いのか・・・。
4 起業する人に必要な資質・能力
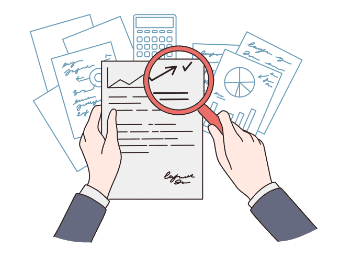
この質問をしたのは私ですが、本当に示唆に富んでいました。
●謙虚であること。他人をリスペクトできる人。
安心安全な場を作ることができるので、人が集まってくる。
多様な人が集まると問題解決もできる。
●グリット力=やり抜く力・粘る力
やめなければ失敗ではない。
しかし引き際の判断は必要。
現在、総合的な探究の時間でいろんな取り組みをしていて、実際に新しいプロジェクトに生徒が取り組んだりしているようですが、一体、どういう力が必要なんだろう、社会を見る目なのか、分析力なのか、プレゼン力なのか・・・・と悩んでいました。
でも結局、チームを作る力、やり抜く力ってこれからの困難な課題を解決するにはもっとも重視する力なのではないか、と思いました。
そして、成功する人の条件は
●山に登り続ける人
●その理由を持っている人
●ある意味、勇気を持って撤退できる人
と言われました。私自身に、山に登り続ける理由はあるのか、それは空疎なものではないのか、考えさせられました。
5 併走する人に必要な心構え

塔本さんは、起業家のアドバイザー。
山登りでいうところのシェルパ。
●主役になりたがる人は駄目。
●まずは相手がどんな人かを観察する。しばらくはずっと我慢して聞く。
●相手から受け取る。
●どこに行きたいのかを確認する。
●困難なこと、失敗、チャレンジを支え続ける。
今現在、ある生徒の個人添削をしていますが、まさに当てはまりました。生徒をしっかりまずは観察して、何を求め、何を考えているのか、受け取ることから出発しています。
参考にしたいと思います。
6 これからの時代の生き方
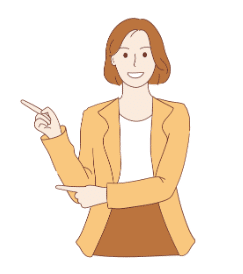
変化の激しい時代。副業解禁の時代。
今後の働き方はどうなるのか、尋ねました。
●副業解禁も、起業も国策=国の方針だから、今後は重要な働き方。
●職業的流動性は高まっていく。
●一つの会社にだけ勤めているとチャレンジ精神に乏しいと評価されかねない状況になるかも。
●一つの経験しか無いというのは、ハンディになるかも。
●みんなで同じ事ができることは最も効率が良かった。しかし、時代は変わった。多様性を生かして、個人個人になにが良いのか、何が売れるのかを考える時代になった。
教育現場にも非常に刺激になるお話しでした。
生徒が生きていく未来に、どういう教育が必要なのか、また考えていきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
