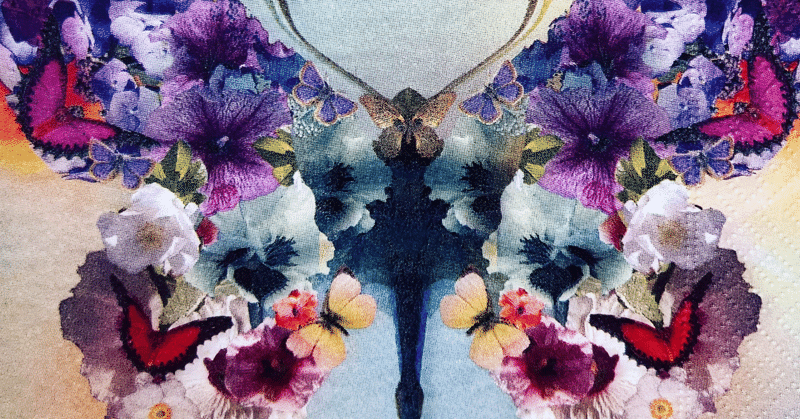
歌、そして言葉の力〜落語とオペラの融合『蝶々夫人』
ヨーロッパを中心に世界9カ国で『蝶々夫人』を歌ってきたソプラノの百々あずさがプロデュースする本公演は、落語家の春風亭愛橋を演出に迎え、日本の伝統芸能である落語と西洋芸術であるオペラの融合を目指したものだ。オペラはしばしば歌舞伎と比較されて語られるし、また、能と融合させた舞台も近年ではつくられており、日本と西洋の芸術を組み合わせるという発想自体はそれほど新しいものではない。その中で落語に関しては、オペラの物語を落語でやるとか、その逆はしばしばみられるが、本公演はオペラの舞台の中に落語を溶け込ませようという点で非常にユニークだった。
鑑賞前には、完全な「語りの芸」である落語と、「音楽」でドラマを表そうとするオペラとの相性はそれほど良くはないのではないか、と思っていたのだが、実際に観てみるとその懸念は杞憂だった。まず、渋谷区文化総合センター大和田の伝承ホールという「場」がいい。木の壁で囲まれたこのホールは伝統芸能の公演などによく使われるが、『蝶々夫人』の舞台となっている「日本」を強く感じさせることで、セットがなくても自然にドラマの世界に入り込める効果があったと思う。そして、開演前には民謡やお囃子などが流されていたのだが、よく聴いてみるとこれが『蝶々夫人』でプッチーニが使っている「さくらさくら」や「豊年節」ではないか!蝶々さんたちが普段歌い、また耳にしていたメロディを聴くことで、よりドラマの臨場感が増していく仕掛けだ。
まず開幕前に、結婚式に出席した書記官が蝶々さんの幼馴染という設定の「書記官の思い出」という落語が披露される。そしてお馴染みのオペラ『蝶々夫人』が始まるのだが、簡潔な舞台の上でオーソドックスな衣裳を身につけた歌手陣が、落語で使われる手拭いと扇子を、お盆やグラス、位牌、キセルなどさまざまな小道具に見立てて演じていく。この試みは、なかなかよかった。そして、劇中、いくつかの説明的な場面(例えば、第2幕でシャープレスが蝶々さんにピンカートンからの手紙を読んで聞かせるところ)などを愛橋が落語にして語ることで、テンポ良くストーリーを動かしていく。こうしたいくつかの試みによって、オペラの舞台に落語がすんなりと溶け込み、また落語の語りがオペラのドラマをより加速させる効果を上げていた。
もちろん、本公演の成功はそうした新規な仕掛け、だけが理由ではない。当然そこに歌手たちの優れたパフォーマンスがあったからこそ、だ。『蝶々夫人』はプリマドンナ・オペラの中でも特にソプラノに負担の大きい作品(なにしろ第1幕の登場シーンから最後まで出ずっぱりなのだから!)。百々あずさはこの役を掌中のものとしているだけあり、終始素晴らしい歌唱を聴かせてくれた。私はいつも、蝶々さんという人は、確かに純粋な人なのだろうけれど、何が魅力なのかよくわからないなあ、と思っていた(プッチーニのような男性からするととても魅力的なのだろうけれど←皮肉w)。しかし今回の百々の蝶々さんの可愛かったこと!明るくて素直で、そして聞かん気なところもある、本当にチャーミングな女の子なのだ。これは百々が、「蝶々さん」というキャラクターに与えられた音楽をきちんと理解し、またそれを表現するための正統的な技術を身につけているからこそ表現し得たのだろう。いつも「これだけはない!」と思ってしまう子どもをすんなり手放してしまうシーンでも、彼女の心の中にある「愛」がそれほど大きかったのだ(あの人がおっしゃるなら従わなければならない)ということがすんなりと納得できた。やはりオペラは「歌」ですべてを描いてこそ、という当たり前の、しかしもっとも大切なことを改めて痛感した。
他の出演陣もベテラン揃いで、みな聴きごたえのある演奏を披露。中ではゴローの寺田宗永が好演で、今度は別の舞台でもこの役で聴いてみたいと思わせた。またいつもながら小埜寺美樹の「オーケストラが聴こえてくるピアノ」は文句のつけようがない出来ばえ。プッチーニの音楽をピアノ1台で表現する腕前には毎回脱帽しかない。
最小限の仕立てで大きな効果を上げてみせた今回の『蝶々夫人』。歌手プロデュースの舞台としては成功だったと言っていいのではないだろうか。
2022年11月8日、渋谷区文化総合センダー大和田 伝承ホール。
皆様から頂戴したサポートは執筆のための取材費や資料費等にあてさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします!
