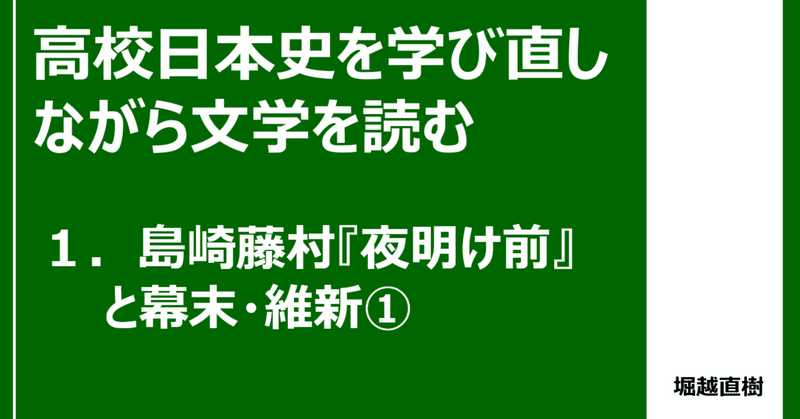
島崎藤村『夜明け前』と幕末・維新①【高校日本史を学び直しながら文学を読む 1】
「木曾路はすべて山の中である」という書き出しではじまる島崎藤村の『夜明け前』は、藤村の実の父である島崎正樹を主人公のモデルとし、中山道の宿場町である木曾の馬籠を舞台にしています。幕末から明治維新期において、主人公の青山半蔵が何を夢見て、その期待がどのように崩れ去っていくのかが描かれています。
『夜明け前』は本格的な歴史小説であり、幕末・維新期の日本史の知識があると深く楽しむことができます。また、『夜明け前』に限らず、幕末・維新期は歴史小説・ドラマ・漫画・アニメ・ゲームなどの題材として、とても人気のある時代です。しかし、人気のある時代でありながら、その複雑な時代状況の概要を理解している人はあまり多くはないのではないかという印象を僕は持っています。幕末・維新期を扱うコンテンツの多くが、特定の人物を中心に歴史をみていく流れになっていて、時代の全体像を理解することは難しいのではないかと思います。
今回は、高等学校で僕がおこなっている幕末・維新期の日本史の授業の一端を紹介します。それによって文学などをより楽しめる人が増えることにつながれば幸いです。
江戸幕府には鎖国体制とよばれる外交の基本的な枠組みがありました。この枠組みは17世紀半ばに整えられましたが、鎖国といっても対外的な通信や通商がなくなったわけではありません。当初は、キリスト教の布教と貿易の両方を行うポルトガルとの国交を断絶し、そのかわりにオランダとの交易を開始する、という部分が主眼に置かれていました。また、鎖国という言葉は、オランダ商館医として来日したドイツ人医師のケンペルの『日本誌』の一部を、19世紀初頭に志筑忠雄という人物が『鎖国諭』として訳出したことによってはじめて使用されるようになりました。
幕府が限定的な対外関係を明確に意識するようになったのは、18世紀末以降のことです。シベリア進出をはたし、北太平洋にも目を向けるようになっていたロシアが1792年にラクスマンを派遣して通商を求めてくるなど、欧米列強が日本に接近しはじめ、幕府は対外関係の見直しを迫られるようになりました。その際に、幕府は鎖国体制を祖法(代々受け継いできた法)とみなし、それを守ろうという認識が徐々にできあがっていったのです。
アヘン戦争(1840~42年)で清がイギリスに敗北したことにより、江戸幕府や諸藩は海防問題への関心を高めました。しかし、幕府には鎖国体制自体を捨てる気はありませんでした。1844年にオランダ国王が開国を勧告してきましたが、オランダは通商国(民間商船と貿易のみを行う国)であり、通信国(国書のやり取りによって国交が結ばれている国)ではないとして勧告を無視しました。1846年にはアメリカ使節ビッドルが浦賀に来航して通商を要求してきましたが、幕府は鎖国を理由に退去を要求しました。
ビッドルに続き、アメリカは1853年に再度艦隊を派遣します。ペリーの来航です。アメリカは1848年にカリフォルニアを獲得したことで領土が太平洋岸に到達しており、その後は中国貿易の拡大を求めていました。中国貿易のために日本近海を往来する自国民が増えると予想されること、また捕鯨船が太平洋で活動するようになっていたことから、アメリカは燃料・食糧などの補給地として日本を利用しようと考えていました。
ペリー艦隊は太平洋を横断してきたわけではありません。大西洋とインド洋ルートを通って8か月もかけて日本に到達しました。日本への海上交通路が確保できておらず、イギリスが開拓した航路を利用させてもらい、食糧と燃料を購入する必要があったからです。ペリーは浦賀に到達する前に琉球の那覇に立ち寄っています。日本が要求に応じない場合は、琉球を基地にしようと考えていたからです。ペリーは日本の開国をみずからの使命と考えていましたが、深刻な問題も抱えていました。補給をイギリスに頼らなければならない状況であり、いくら大砲を備えた軍艦があるといっても、江戸城を占拠できるような軍事力までは備えていません。そもそも大統領のフィルモアからは日本との交戦を禁止されていました。
幕府は出島を通じてペリー来航の情報を早くから得ていました。そのため、外国船の来航自体は幕府にとって大きな衝撃とは言えませんでした。それでも幕府は、アヘン戦争以降の世界情勢の把握により西洋列強のアジア侵略を脅威と認識しており、条約締結を容認しました。1854年にペリーが再来航した際に、老中阿部正弘のもとで日米和親条約が締結されます。
さて、この条約により何が変わったのか、また変わらなかったのか、内容をみながら考えてみましょう。下田(伊豆国)と箱館(蝦夷地)の2港が開港され、日本が薪水・石炭や食糧を提供することを認めました。しかし、アメリカとの自由貿易は認めていません。これらを考えれば、対外政策を転換する契機となったことから「開国」と呼ぶことはできるかもしれませんが、祖法としての鎖国(朝鮮・琉球との通信関係、オランダ・中国との通商関係以外は原則認めない)が完全に放棄されたわけではない、という言い方もできるでしょう。それでは、幕府側の外交交渉の勝利と言えるかというと、それほど単純ではありません。日米和親条約には「一方的な最恵国待遇のアメリカへの付与」という内容もありました。これは、日本が将来別の国と条約を結び、その国に有利な権利を与えたとき、最恵国待遇を認められているアメリカは、自動的に日本からその権利を得ることができる、というものです。最恵国待遇がアメリカには認められて日本には認められていないことから、これは不平等な規定です。あとで確認する日米修好通商条約における不平等な規定ばかりが注目されることが多いのですが、すでに和親条約の段階で不平等な規定が存在したのです。
欧米列強の外交使節の制度と儀礼は、19世紀初頭の「ウィーン規則」によって定められていました。これは近代国際法と呼ばれ、幕末・維新期には、清で翻訳されて「万国公法」という名称になったものが日本にもたらされることになります。西洋による当時の国際法では、世界の民族と国家が三つに区分されていました。一つ目は「文明国」で、国際法上の主体性が認められた欧米の国々です。二つ目は「半開国」で、主権を制限され、文明国からは対等に扱われない国です。三つ目は「未開」で、最初に発見ないし開拓した文明国が占拠し、植民地としてよいと認識された地域です。日米和親条約によって、日本は「半開国」として明確に位置づけられたとみることができます。対等な関係であれば最恵国待遇を相互に認めるという国際法の知識は、おそらく当時の幕府にはなかったと考えられます。
日米和親条約にもとづき下田に赴任したアメリカ総領事ハリスは、自由貿易を認める内容の通商条約締結を強く幕府に要求しました。老中の堀田正睦は通商条約調印を決意し、ハリスとの交渉にあたった幕臣には積極開国論の岩瀬忠震もいました。しかし、水戸藩の徳川斉昭などが反対派していたため、堀田は孝明天皇の勅許(条約調印の承諾)を得ることで意見の統一を図ろうとしました。水戸藩では、徳川光圀による『大日本史』編纂の過程で「水戸学」と呼ばれる儒学が形成され、18世紀以降に朱子学を軸としながら神道や国学などを取り入れたものは特に「後期水戸学」と呼びます。後期水戸学の代表的人物である会沢安(正志斎)や藤田東湖らを抜擢したのが徳川斉昭です。徳川斉昭は攘夷論(外国人排斥諭)の中心でしたが、条約勅許の要請後は、いわれなく「打ち払い」(戦争)は不可能という意見を朝廷に送っています。しかし、強硬な攘夷主義者であった孝明天皇は、幕府の要請を拒絶し、打ち払いも辞さないという意向を示しました。公家の中にも貿易開始反対派のグループが存在しました。
1858年、アロー戦争でイギリス・フランスが清をやぶると、ハリスは英仏の軍事的脅威を説きながら、イギリスが日本に来航する前に自由貿易を認めてしまった方がよいと脅してきました。堀田が江戸へ戻った直後に大老になった井伊直弼は、これに屈し、勅許が得られないまま日米修好通商条約に調印しました。開港場・開市場の設定、自由貿易の原則の他に、領事裁判権の承認(日本人に対して法を犯したアメリカ人はアメリカの領事裁判所で裁判する)、関税率は日米の協議により定める協定関税制(日本の関税自主権の欠如)という不平等な内容が含まれていました。幕府はこれらの条文によりどのような問題が起こり得るのかを正確に理解できておらず、不平等条約を強制されたという意識はなかったようです。一方で、アヘンの輸入を禁止したこと、外国人居留地を設定して外国人による日本国内の自由な旅行を認めないことなど、清が結んだ条約よりも有利な規定も盛り込まれており、これらは日本側の外交交渉の結果と言えます。
1859年、横浜・長崎・箱館の3港で貿易が開始されると、日本の貿易額が急速に増大しました。取引額は横浜が圧倒的に多く、対日貿易の主導権を握ったのはイギリスでした。1861年に南北戦争がはじまったこともあって、アメリカは後退していました。輸出品は生糸・茶・蚕卵紙など半製品や食料品が多く、輸入品は毛織物・綿織物などの工業製品が大半を占めていました。最大の輸出品となった生糸を生産する製糸業が急速に発展しましたが、京都西陣・桐生・足利などの絹織物業は、原料生糸の不足と価格高騰により打撃を受けています。また、イギリスから安価で綿織物が輸入されたことで、綿作・綿織物業が動揺しました。
貿易による流通機構の変化、大幅な輸出超過など複数の理由により、急激な物価上昇がおこっています。これにより、下級武士や都市で生活する庶民は生活が苦しくなり、一揆・打ちこわし、攘夷運動の経済的背景となりました。また、幕府や欧米諸国への反発が強まる一方で、条約調印に反対の意思を示した孝明天皇や朝廷への支持が広まっていきました。
『夜明け前』は中山道の一部である木曾路の宿場を主な舞台にし、そこで庄屋・本陣・問屋を兼ねていた青山半蔵を主人公としています。半蔵は若い頃から学問を好み、国学に心ひかれていました。本居宣長、平田篤胤など、国学の先人が残していったものを想像するような青年のもとに、黒船のうわさが伝わるところから、この大長編小説は始まっていきます。
ここで少し、国学について説明しておきます。国学は、和歌を中心とした古典研究からおこりました。それまでの和歌の解釈が、一部の人たちによる秘伝で伝えられてきたのに対し、文献の正確な解読・相互批判などによる古典研究が江戸時代に進んでいきました。それらの研究を通じて、儒教や仏教などの外来思想が入る前の日本古来の道(古道)を明らかにしようとするのが国学です。
国学の大成者とされる本居宣長の思想には、「もののあはれ」論と「古道」論という二つの核があります。「もののあはれ」論では、儒教や仏教の影響が強かったために道徳や宗教の観点から文学を論じる傾向を批判し、人間の感情表現こそが文学の本質であると説きました。「古道」論では、日本には『古事記』のように神々に包まれた人間の真実を伝える伝承があるとし、天照大御神が生まれた「皇国」と、「異国」との差異を強調していきました。アマテラスから委任されているから朝廷に支配権があり、その朝廷からの委任によって将軍や大名が領土領民を支配していると宣長は説き、将軍権力の正統性の根拠を示そうとしました。このような「大政委任論」は幕末の政治史に大きな影響を与えることになります。
宣長の思想は、宣長の没後の門人を自称した平田篤胤によって神学として発展していきました。日本だけに『古事記』のような「古伝」が残っているのは、万国の始まりの地が日本であったからだと考え、極端ともいえる日本中心主義につながっていきました。また、篤胤の特徴として、それまでの文芸的・考証的な国学に入り込めなかった庶民や地域の神職層を開拓した点が重要です。古典の解釈だけでなく、それを身近な話と関連させていくことで、国学普及の基盤を広げていったのです。地域社会の人々の連携により著作が刊行されたという事実をみると、江戸の思想家の中でも特筆すべき人物の一人であることはまちがいないでしょう。
以上のような国学の知識があると、「すべて山の中」と冒頭で記された木曾路に暮らす青年が平田派国学に傾倒していった背景が理解できて、物語が読みやすくなるはずです。
平田派国学は、平田篤胤の生前よりも没後の方が門人を増やしていきました。平田篤胤の養子の銕胤(かねたね)は、遠方の門人から書簡で寄せられる疑問に、篤胤の著述を引用しながら回答するなど、丁寧な活動を続けていました。平田派国学の門人は各地で活動を活発化させていきます。
『夜明け前』の主人公の青山半蔵は、木曾の馬籠で庄屋・本陣・問屋を兼ねています。都市部と木曾路を比べると、情報が入ってくるスピードにはズレがあるのですが、それでも本陣にはある程度身分の高い人が宿泊することもあって、貴重な話を耳にすることもあります。しかも、京都の政局が重要度を増す幕末において、京都の情報が江戸よりも早く、江戸の情報が京都よりも早く入ってくることがあるのです。この地理的条件が、『夜明け前』を面白くしていることは間違い無いでしょう。
ペリー来航などの話はもちろん木曾路にも入ってきました。国政について意見を述べることを許されていなかった身分の人であっても、国を揺るがす事態に無関心ではいられず、国の行く末を我がこととしてとらえる意識は、身分を問わず高まっていきました。さらに、日米修好通商条約をはじめとする安政の通商条約締結によって朝廷と幕府の対立が生じると、日本のあるべき姿を考えようとする多くの人々の存在を背景に、平田派国学が飛躍的に普及しました。
開港後の横浜では、輸出品を扱う売込商、輸入品を扱う引取商などが居留地で外国人商人と貿易をおこなうようになりました。『夜明け前』では木曾路にもこうした動向が及んだことが記されています。第一部の第四章では木曾路の商人ら4名が馬籠を立って横浜に向かうエピソードが出てきます。かなりの冒険とも思われましたが、持参した生糸に横浜の貿易商が破格の値をつけたと書かれています。
②に続く
※主要参考文献は最後にまとめて記します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
