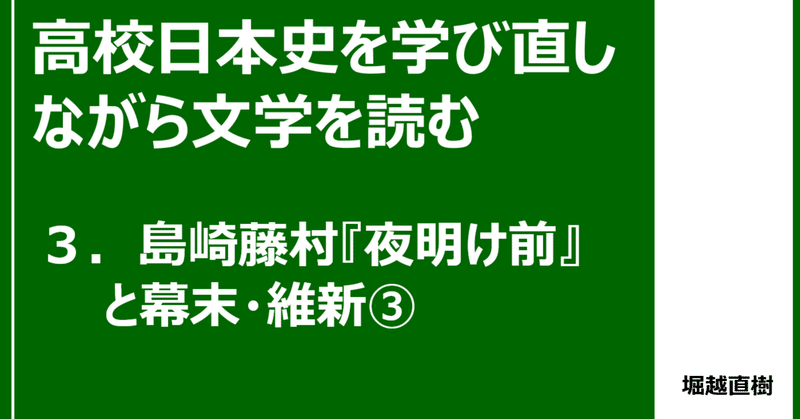
島崎藤村『夜明け前』と幕末・維新③【高校日本史を学び直しながら文学を読む3】
対幕府強硬派においては、いまだ朝敵の扱いを受けている長州藩は公然と行動できず、薩摩藩の西郷隆盛・大久保利通らが中心でした。西郷・大久保らは、クーデター方式という、かなり強引な手法を選択します。在京兵力に勝る薩摩藩が、土佐藩・越前藩・尾張藩・安芸藩の同意を得た上で、五藩で御所を封鎖し、徳川慶喜抜きで新政府を発足させるというクーデター案です。公議政体派のキーパーソンであった土佐藩の後藤象二郎が同意した背景には、薩摩藩の在京兵力の圧力も考えられますが、天皇中心の新しい国家体制を創設するために人心を覚醒させるショック療法に後藤が同意したとも考えられます。
1867年12月9日、御所を軍事的に制圧した上で、幕府の廃止、摂政・関白の廃止、総裁・議定・参与の三職からなる中央政府の発足が宣言されました。いわゆる王政復古の大号令です。三職には、皇族、公卿、藩主・前藩主、藩士が任じられ、徳川慶喜を排除した公議政体の性格が示されました。
同日夜に小御所で三職会議(小御所会議)が開かれました。ここで徳川慶喜に対して内大臣の辞退(辞官)と領地の大部分の返還(納地)を求めることが決定されました。会議の席上、土佐藩の前藩主であった山内豊信が、クーデターを非難しながら、徳川慶喜を評議の席に加えるべきであると主張したことがよく知られています。
西郷・大久保らはクーデター決行後も、旧幕府・会津藩・桑名藩の動きを注視していました。もし、決定内容に反発するような行動をみせるのであれば打倒してしまおうと機会をうかがっていたとみてよいでしょう。しかし、徳川慶喜は激昂していた兵をなだめながら、松平容保・松平定敬の両者を連れて、二条城から大坂城へと移動しました。西郷・大久保らのもくろみははずれ、むしろ山内豊信らが徳川慶喜の議定就任の手続きをすすめ、三職会議でもこれが承認されました。
こうした中、旧幕府側の庄内藩が江戸の薩摩藩邸を焼打ちする事件がおこります。この事件には、西郷隆盛の指示を受けた薩摩藩士が、江戸市中や関東各地で挑発行動を開始していたことが関係していると考えられています。1868年、大坂でも旧幕府が薩摩藩の陰謀に武力で決することを表明して京都に進軍し、鳥羽・伏見の戦いがはじまりました。戊辰戦争と呼ばれる一連の内戦のはじまりです。新政府は迎え撃つ薩長軍に錦の御旗を授け、徳川軍を「朝敵」とします。ところで、これまで「討幕派」という言葉を意図的に避けてきましたが、旧幕府勢力を武力で討とうとする集団が明確なかたちであらわれるのはこのタイミングだと思います。この戦いは新政府軍の勝利となり、慶喜は江戸に逃亡し、見捨てられた幕府軍は四散しました。
新政府は有栖川宮熾仁親王を東征大総督として征東軍を派遣しますが、実質的に指揮をとったのは参謀についた西郷隆盛ら薩長の藩士でした。征東軍には、豪農や豪商がみずから組織した草莽隊も加わっていました。その一つで相楽総三を隊長とする赤報隊は東山道の先鋒をつとめ、新政府の許可を得て年貢半減を布告しながら進軍しました。しかし、新政府は年貢半減を公式文書のかたちでは残しておらず、のちに年貢半減令を取り消して相楽ら赤報隊の幹部を処刑しました(偽官軍事件)。『夜明け前』第二部では、この偽官軍事件についての記述が出てきます。主人公の青山半蔵は、赤報隊に金二十両を提供しますが、そのことで取り調べを受けています。半蔵は、同じ平田派国学の門人である浅見景蔵に対して、「景蔵さん、君も気をつけて行って来たまえ。相良惣三に同情があると見た地方の有志は、全部呼び出して取り調べる―それがお役所の方針らしいから。」と声をかけています。新政府に貢献しようとした草莽隊に対して容赦ない弾圧が加えられたことは、半蔵の心理状況に大きな影響を与えたと考えられます。
戊辰戦争が続く中、1868年1月に政府は列国に新政権の樹立を通告し、3月には五箇条の誓文を公布しています。公議世論の尊重や開国和親など、新政府の方針が示されました。これにより『夜明け前』の主人公である青山半蔵の気持ちは高揚しています。「それは新帝が人民に誓われた五つの言葉より成る。万機公論に決せよ、上下心を一にせよ、官武一途はもとより庶民に至るまでおのおのその志を遂げよ、旧来の陋習を破って天地の公道に基づけ、知識を世界に求め大いに皇基を振起せよ、とある。それこそ、万民のために書かれたものだ。」とあります。「古代復帰」を願う平田派国学の門人として、天皇が百官・諸侯を率いて新政を誓うという神国国家スタイルに興奮するのは理解できます。しかし、戊辰戦争中に出されたこの五箇条の誓文が、はたして半蔵の期待に沿うようなかたちで実現するでしょうか。薩長主体の新政府軍は、内外の支持が得られなければ、戦争の勝敗がどう転ぶかわからないという不安定な状況でこの政治方針を発表しました。きこえのよい言葉を並べなければ、内外の支持を得ることはできません。同時期に民衆に対して出した五榜の掲示には魅力的な言葉が並ぶどころか、幕府の民衆支配の方針を引き継ぐ内容が示されていたことは、政府の意図を知る上でも重要です。
また、同年閏4月には政体書を公布し、権力を集中させた太政官のもとでの三権分立、官吏公選制などを示しました。兼官禁止も規定されていましたが、あちこちで破られていたこともあり、政体書はアメリカ合衆国憲法の「皮相な模倣」と否定的な評価を受けることが多くなっています。近代国家が「急造」される中、「皮相な模倣」は政体書以降もあちこちでみられるようになります。
徳川慶喜は江戸城を出て上野寛永寺に引きこもり、恭順の方針をとりました。最終的に、慶喜の身柄を水戸藩にあずけること、江戸城をあけわたすことを条件に交渉が成立し、西郷隆盛は総攻撃の中止を指示しました(江戸無血開城、1868年4月)。慶喜の処分が寛大になった背景には、征東軍の深刻な資金不足、世直し一揆の頻発など、不安定な状況がありました。
江戸開城後も戦争は終わらず、新政府は会津藩征討を東北諸藩に命じました。しかし、会津藩への寛大な処分を求めていた藩は命令に従わず、5月に奥羽越列藩同盟を結成します。その後、激戦が展開されますが、7月に新政府軍が越後を制圧し、東北戦争でも列藩同盟軍と会津藩が降伏して9月にこの地域の戦争が事実上終わりました。
8月に品川沖を旧幕府艦隊が出航し、北上して約3000名で蝦夷地を占領しました。総裁となった榎本武揚は、蝦夷地の開拓経営を新政府に嘆願しますが認められず、箱館の五稜郭にたてこもって、北上した新政府軍と戦いますが、1869年5月には降伏しました。これにより、戊辰戦争が終了しました。
青山半蔵が待望していた新しい時代が幕を開けました。1868年9月には明治と改元するとともに一世一元の制を定めています。半蔵ら馬籠の人々もすぐに明治維新の潮流の渦に巻き込まれて行きました。1869年1月、薩摩・長州・土佐・肥前の4藩主が版籍奉還を上表し、続いて多くの藩がこれにならいました。これにより、全国の土地(版図)と人民(戸籍)を、新政府の支配下に置くことになりました。成立直後の新政府は基盤が弱く、中央集権化による強力な国家建設をめざしていました。そのためには幕藩体制の解体が必要でした。幕藩体制とは、幕府と諸藩が全国の大部分の土地と人民を支配する体制のことです。幕府はすでに解体されていましたが、諸藩はなお存続しており、そこへの介入として版籍奉還をおこなわせたわけです。しかし、版籍奉還によって目的が達成されたわけではありません。藩の名前は残り、旧藩主は知藩事と名前を変えましたが同じ人物が任命され、藩の伝統は残ったままでした。何よりも、租税と軍事の権限が諸藩に残ったままという点だけをみても、藩の支配が温存されたとみることができるでしょう。
1871年、薩摩・長州・土佐の3藩に兵を提供させて親兵とし、これを軍事的圧力として用いつつ、廃藩置県を断行しました。知藩事は罷免されて東京への移住を命じられ、中央から府知事・県令が派遣されました。これにより、中央集権化が大きく進展したと言えます。廃藩置県は、大名家にとって不利益ばかりをもたらすものではありませんでした。大名家の多くは財政が逼迫しており、財政の観点からみれば幕藩体制というのは明らかな限界を迎えていました。廃藩置県により、各藩の負債を新政府が引き継ぎました。藩にかわって、豪商などからの負債を新政府がしっかり返済したわけではなく、大部分は踏み倒されて行きました。廃藩置県というのは、全国規模の財政整理策でもあったのです。
廃藩置県後は、税収の安定が政府の課題でした。政府は旧来の年貢負担者に地券を交付して土地所有権を認めました。これにより土地は地券所有者が自由に処分できる私有財産という認識になり、近代の資本主義経済につながる制度に変わりました。1873年に地租改正条例を公布して地租改正に着手していきます。その骨子は、納税主体は村から地券所有者へ、課税基準は収穫高から地価(3%)へ、納入方法は金納に一本化、というものでした。近世領主制のもとでの年貢納入は、村請制と呼ばれるシステムをとっていました。年貢は村を単位とし、村内部での年貢負担の割り付けと徴収は村役人の仕事であり、農民個々人の負担のあり方にまで領主側は介入しないのが原則でした。地租改正は、個人を徴税単位とし、それまでの住民を、日本国民として性格づけるために決定的な意味を担った政策であったと言えます。この地租改正事業の中心は、地価の決定にありました。地価の「3%」という数字だけをみると少ないように錯覚してしまいますが、政府はこれまでの歳入を減らさない方針を立てたので、各地域で地価を高く設定して、それを押し付けてきました。新政府に期待していた人からしてみれば、江戸時代と変わらない負担に憤慨したことでしょう。各地で地租改正反対一揆がおこっています。
地域によっては江戸時代と変わらないどころかマイナスであると感じた人も多かったようです。村が共同で利用していた入会地が、所有権不明という理由で国に接収されてしまったのです。その影響を大きく受けたのが木曾谷の住民でした。木材を多く産出していた木曾の山は尾張藩が森林保護をおこなっていましたが、住民が自由に立ち入ることができる開放林も多く、建築材・薪炭材・干し草・木の実などの採取、木材加工による収入など、住民の生活に欠かせないものになっていました。住民による雑木伐採により、ヒノキ・アスナロなどの木曾五木と呼ばれた保護対象の樹木が保たれたとも考えられています。政府はそのような地域の実情を考慮せず、全国一律に藩有林を国有林としてしまいました。山林に住む人々の生活は困窮し、住民による請願運動がおこなわれました(木曾山林事件)。戸長となっていた青山半蔵は嘆願書のとりまとめに尽力しますが、そのことが原因で戸長を免職となります。
半蔵は働き盛りの時期に大きな挫折を味わい、「御一心がこんなことでいいのか。」と漏らします。その後は村の子どもたちに読み書きを教えていましたが、一念発起して上京し、国学仲間のつてで教部省に出仕します。
王政復古の大号令後、祭政一致を確立するために神祇祭祀が重視されていました。初期の明治政府は「復古」と「維新」という二つの相反する理念をもって出発したと言えますが、この二つの理念を調和させるために用いられたのが「神武創業」という言葉であり、祭政一致体制、すなわち天皇親政体制の創出がめざされていました。そのために多くの国学者が動員され、国学者が主導する形で神祇官が再興されました。1868年には神仏分離令が出て、日本の歴史上長い期間続いてきた神仏習合を否定しています。さらに、1870年には大教宣布の詔が出て、伊勢神宮を頂点とする神社制度や、皇室行事を中心とする国家の祝祭日が定められました。
神道国教化の動きに刺激され、仏教を排撃する廃仏毀釈の動きが各地でおきました。神官や国学者が中心になって、寺院・仏像・仏具などを破壊する動きです。こうした廃仏毀釈運動や政府の強引な政策への民衆の反発もあり、神道国教化は結局実現しませんでした。
仏教界では、浄土真宗本願寺派の島地黙雷のように、欧米諸国にならった信教の自由の考え方によって神道国教化を批判し、仏教を近代化に適合したものにしようとする運動をおこす者もあらわれました。
神道国教化政策が後退していく中、神祇官は1871に神祇省と改組された後に廃止され、かわって設置された教部省では、神道だけでなく仏教も動員して神仏合同で人民教化にあたる政策へと変化していました。しかし、政治と宗教の分離を求める批判の声が各所から出ることで、教部省も追い込まれていきます。
青山半蔵は東京に出て教部省に勤めることで、国学の衰退を目の当たりにしてしまいます。また、大陸の思想の影響をかつて本居宣長は「漢意(からごころ)」と表現しましたが、今は西洋にあこがれ、それを模倣する傾向が強く、「漢意」が「洋意」に変わっただけではないかと半蔵は感じてしまうのです。廃仏の急先鋒に国学者が多数いたことは事実ですが、廃仏が国学のすべてのようにとらえられることで国学そのものが衰退してしまう状況は、半蔵を深く悲しませました。
憂国の情に突き動かされた半蔵は、自身のおもいを歌にして扇子に記し、その扇子を明治天皇の輿に投げ入れることで不敬罪に問われます。その後、岐阜県飛騨一宮水無神社の宮司を数年つとめた後、馬籠に帰郷しますが、青山のような旧家の屋台骨は傾いていき、平田派国学がめざした復古は馬籠にもたらされなかったという現実と向き合う日々を送ることになります。国学がめざした素直な心は求められず、かつての攘夷は大きく異なるものに変貌し、西洋的な生活様式や思想を取り入れる「文明開化」が進む中で、半蔵は「維新」というものが自身の思い描いた「夜明け」ではなかったことを思い知らされるのです。
絶望した半蔵は精神を病み、家の菩提寺を放火するなどの奇行がみられたことで、家中につくられた座敷牢に閉じ込められました。その座敷牢の中で半蔵が56歳の生涯を終えることで、この物語も終わります。
さて、ここまで幕末・維新の歴史を概観しながら、『夜明け前』をみてきました。主人公の心情などを中心に生涯を追い、歴史は背景として描くという文学ではなく、歴史をかなり網羅的に描いている大長編です。高校教科書の幕末・維新の分野はすべて関連ページであり、完全に読み飛ばせるページは1ページもありません。そのため、高校での僕の授業内容を用いた日本史の解説がとても長くなりました。「高校日本史を学び直しながら文学を読む」というシリーズの最初に持ってきましたが、おそらく文字数は最長になるのではないかと思います。幕末・維新期というのは、特定の人物とその周辺にくわしい人はいるのですが、全体像を理解している人が少ないという印象を抱いていたので、少し力を入れて解説しました。
この物語の主人公である青山半蔵は島崎藤村の父・島崎正樹をモデルとし、かなり父の歴史が再現されていると言えます。物語に出てくる四男の和助は、島崎藤村(本名は島崎春樹)がモデルですが、学問好きであることから東京に遊学させたものの、英学校進学を希望したことで父を落胆させています。その島崎藤村が1929〜35年に『中央公論』にて連載した小説が『夜明け前』なのですが、なぜ藤村は最後の大長編小説のモデルに父を選んだのでしょうか。また、近代文学を代表する作品の一つと評価される『夜明け前』の刊行から数年後の1941年、「生きて虜囚の辱を受けず」という一節で知られ、陸軍大臣東条英機が示達したことで玉砕や自決の原因となったと言われる「戦陣訓」の文案作成に島崎藤村が参画したのはなぜでしょうか。このあたりを理解するためには、さらに昭和の歴史的背景を知る必要がありそうですが、今回はここまでとしましょう。
主要参考文献
・島崎藤村『夜明け前(全4冊)』(岩波文庫)
・高校教科書『日本史探究』(実教出版)
・町田明広『攘夷の幕末史』(講談社現代新書)
・井上勝生『幕末・維新』(シリーズ日本近現代史①、岩波新書)
・須田努『幕末社会』(岩波新書)
・家近良樹『孝明天皇と「一会桑」』(講談社学術文庫)
・知野文哉『「坂本龍馬」の誕生』(人文書院)
・三谷博『維新史再考』(NHKブックス)
・久住真也『王政復古』(講談社現代新書)
・青山忠正『明治維新』(日本近世の歴史6 吉川弘文館)
・奥田晴樹『維新と開化』(日本近代の歴史1 吉川弘文館)
・小林和幸編『明治史講義【テーマ編】』(ちくま新書)
・山口輝臣・福家崇洋編『思想史講義【明治篇Ⅰ】』(ちくま新書)
・山口輝臣編『はじめての明治史』(ちくまプリマー新書)
・成田龍一『近現代日本史との対話【幕末・維新−戦前編】』(集英社新書)
・小風秀雅編『大学の日本史 4近代』(山川出版社)
・田尻祐一郎『江戸の思想史』(中公新書)
・辻本雅史『江戸の学びと思想家たち』(岩波新書)
・國學院大學日本文化研究所編『歴史で読む国学』(ぺりかん社)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
