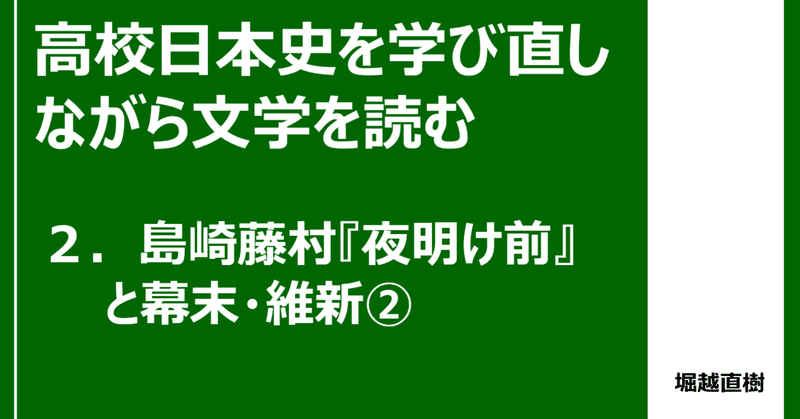
島崎藤村『夜明け前』と幕末・維新②【高校日本史を学び直しながら文学を読む 2】
幕府が勅許のないまま日米修好通商条約の調印を強行したことに反発した孝明天皇は、1858年、水戸藩に密勅を送り、幕政改革を迫りました。改革案の内容は、現状の問題に対して、多くの大名が集まって話し合っていこうという、連合政権的な路線を示すものでした。朝廷が幕府を介さずに一部の藩と結びついたという事実は、「権威」的存在が「権力」をも高め、幕府に対抗する政治勢力となり得ることを示していました。これは幕藩体制下ではあってはならないことであり、その事実を知った井伊直弼は幕府の政策を批判する勢力への徹底的な弾圧をおこなうようになりました。徳川斉昭(水戸藩)・松平慶永(越前藩)・島津斉彬(薩摩藩)などの一橋派(一橋慶喜を推す雄藩諸侯ら)を処罰し、開国論者の橋本左内、老中暗殺など過激な計画を立てていた吉田松陰を逮捕するなどの弾圧を加えました。この弾圧は、安政の大獄と呼ばれます。しかし、これにより尊王攘夷論者の井伊直弼への反発が高まり、水戸藩を脱藩した浪士らにより、1860年、井伊は江戸城桜田門外で暗殺されました(桜田門外の変)。
幕政における実質的な最高責任者とも言える大老が浪士に暗殺されたことで、幕府の権威は失墜しました。そのような状況下で、老中安藤信正は朝廷の権威を借りるかたちで幕府権威の回復をめざします。この政策路線は「公武合体」路線と呼ばれ、孝明天皇の妹和宮と14代将軍徳川家茂との結婚が実現しています。
ところで、高校の日本史の授業において、薩摩藩などの「公武合体派」と長州藩などの「尊王攘夷派」のように、二項対立をつくることで複雑な幕末の歴史をわかりやすく整理しようとするケースがよくみられました。しかし、これは正確な説明ではありません。そもそも公武合体は政策路線であって派閥ではありません。また、攘夷論者の孝明天皇が公武合体路線を受け入れているように、両者は二項対立どころか、共存し相互補完が可能なものです。さらに、薩摩藩も長州藩も藩内で様々な考え方が存在していて複雑な状況なので、ひとつの派閥として説明するのは不可能です。
町田明広『攘夷の幕末史』(講談社現代新書、2010年)では、多くの人々が攘夷論者であったと説明しています。通商条約を容認して武備を備えた後に海外侵略をおこなおうとし、無謀な攘夷は否定する「大攘夷」と、通商条約を即時破棄して対外戦争も辞さないという「小攘夷(破約攘夷)」のように、攘夷の解釈による対立が存在していたことを示し、「公武合体」と「尊王攘夷」を二項対立的に配置する図式については批判しています。
さて、安藤信正の公武合体路線に話を戻しますが、和宮と家茂の結婚の交換条件として、近い将来の破約攘夷を幕府が約束しました。この約束により幕府はのちに追い込まれることになります。安藤信正は朝廷との関係改善を進めたにもかかわらず、幕府の都合で朝廷の権威を利用したとして一部の過激な尊王攘夷論者から反発を受け、1862年、水戸藩を脱藩した浪士らによって坂下門外で襲われ(坂下門外の変)、失脚しました。
薩摩藩では藩主の父の島津久光が、朝廷の意向を利用して幕政に介入する動きをみせます。1862年に上京し、勅使の大原重徳とともに江戸に向かい、公武合体のための改革を幕府に要求しました。幕府はこれを受け入れて、一橋派の幕政参加を認め、一橋慶喜と松平慶永が幕政を主導する立場となりました(文久の改革)。この改革の中で、参勤交代の江戸出府を3年に1回としています。諸藩の財政負担を減らし、諸藩の軍制改革を促そうとするねらいですが、大名統制の根幹とも言える参勤交代を緩和したことで、統制力を緩めることにつながりました。幕府と藩の関係が形骸化している現状を、幕府が自覚していたとみることもできるかもしれません。
長州藩では、長井雅楽という人物が「航海遠略策」を打ち出していました。これは、通商条約を容認しつつ、その先に日本中心の東アジア秩序をつくる構想でした。「大攘夷」主義と言えるものです。それに対し、桂小五郎・高杉晋作・久坂玄瑞らのグループは「破約攘夷(小攘夷)」を主張して長井の献策に反発し、長州藩の方針は破約攘夷に転換していきました。長州藩は破約攘夷派の公家を味方につけて京都の主導権を握り、1862年には勅使三条実美を江戸へ派遣し、徳川家茂と一橋慶喜を上洛させ、攘夷の実行を約束させました。
幕府は1863年5月10日を期に攘夷を決行するよう諸藩に命じますが、攘夷という言葉の解釈は立場により異なっており、下関海峡を通過した外国船を長州藩が砲撃した事件(長州藩外国船砲撃事件)以外には目立った動きはほぼみられませんでした。その後、長州藩と三条実美らは、天皇親征のための軍議をおこなうなど、幕府の軍事指揮権を否定するような動きをみせますが、直後の八月十八日の政変により状況は一変します。長州藩と三条実美らの公卿が京都から追放されたこの政変は、薩摩藩と会津藩が主導したと説明されることが多いですが、三条実美の排除をねらっていた孝明天皇の動きも見逃せません。孝明天皇は攘夷を望んでいましたが、天皇が将軍に国政を委任しているという大政委任論を肯定する立場であり、幕府を追い込むようなかたちでの攘夷を認めることはできませんでした。
政変後、島津久光は、一橋慶喜、松平慶永(春嶽)、会津藩の松平容保、宇和島藩の伊達宗城、土佐藩の山内容堂との合議を朝廷のもとでおこなって国政を協議・決定することを提案しました(参与会議)。しかし、外様の島津久光による幕政への介入に対して、幕閣の強い不信感がありました。また、孝明天皇の意向に応じて横浜港閉鎖を主張する一橋慶喜と、それを受け入れられない薩摩・越前との対立があり、慶喜は参与会議を解体に追い込みます。その後は、朝廷のもとで、一橋慶喜、京都守護職の松平容保(会津藩)、京都所司代の松平定敬(桑名藩)という水戸徳川家の血筋でつながったトリオ、いわゆる「一会桑(いっかいそう)」が国政の重要な部分を掌握しました。
1864年、勢力挽回をめざしていた長州藩士が、京都の池田屋で、京都守護職配下の新選組に襲撃される事件がおこりました(池田屋事件)。長州藩はこれをきっかけとして京都に進撃しますが、薩摩・会津・桑名などの諸藩にやぶれました(禁門の変)。さらに、イギリス・フランス・アメリカ・オランダの四か国連合艦隊が下関を攻撃しました(四国艦隊下関砲撃事件)。この四国艦隊下関砲撃事件というのは、横浜港を閉鎖しようと考えていた天皇・幕府への警告です。言葉ではなく軍事行動によって、「通商条約を守り、自由貿易を続けろ」という圧力をかけてきたのです。攻撃先が下関であったことから、長州藩外国船砲撃事件への報復という意味もあったかもしれませんが、それは主目的ではありません。
軍事的敗北を重ねた長州藩は、一連の過程で破約攘夷の方針を放棄するにいたります。禁門の変の罪を問う幕府軍には戦わずして屈服しました(第1次長州征討)。
イギリス・フランス・アメリカ・オランダは、条約の勅許と関税率引き下げなどを要求してきました。禁裏守衛総督という立場にあった一橋慶喜が朝廷と交渉した結果、1865年、孝明天皇がついに条約勅許を決断しました。この一連の経過は、天皇といえどもその見解は絶対ではなく変化し得るということを明らかにすると同時に、一橋慶喜を中心とする「一会桑」が、天皇を取り込んで朝廷との一体化を進めつつあることを示していました。
「一会桑」が存在感を増す中、幕府と薩摩藩の関係は悪化していきました。1862年、横浜近辺の生麦村を通行していた島津久光一行に接触したイギリス人を薩摩藩士が殺傷してしまう事件がおこっていました(生麦事件)。翌年、その報復として鹿児島をおそったイギリス艦隊と薩摩藩が戦い(薩英戦争)、欧米列強の軍事力の強大さを痛感したことにより、西郷隆盛や大久保利通らを指導者として洋式軍備の強力な軍隊をつくり上げていきます。一方、第1次長州征討で屈服した長州藩では、高杉晋作らが再び藩の主導権を握るようになっていました。高杉が組織した奇兵隊は、藩の正規軍と異なり、武士以外の百姓・町人も含まれていました。グラバー商会などイギリスの商人から武器を密輸して軍備を強化しており、最新のライフル銃などがあれば世界水準の近代歩兵を有志の兵士でつくることが可能だという認識も高杉にはありました。
こうした長州藩の動きに対し、幕府は再び長州征討を計画しますが、薩摩藩はこれに従わずに密かに長州藩を支援しました。薩摩藩としては、朝廷のもとで雄藩(有力な藩)の連合政権による新しい政府(公議政体)を実現したいと考えていたため、慶喜ら一会桑が朝廷を取り込んで公議政体への妨害を続けるならば、兵力を用いてでもその動きを排除しなければならないと考えるようになっていました。さらに薩長両藩は、1866年、幕府に対抗する同盟を秘密裡に結びました(薩長同盟)。
薩長同盟の仲介役の一人であった坂本龍馬に触れておきます。歴史上の人物の中でも上位の人気を誇る人物ですが、その一方で、歴史の教科書に掲載するほどの人物ではないのではないかという意見も存在します。坂本龍馬は、関連史料の信頼性を批判的に検討するという歴史学の基本プロセスを経ていない状態のまま、歴史小説やドラマが大ヒットしてイメージが固定化されてきたという経緯があると思います。「船中八策」から龍馬が壮大なスケールで世界をみていたことがわかる、龍馬が西郷隆盛を一喝した、などは小説やドラマによってつくられたイメージであり、専門的な歴史研究者の中でそういうことを言う人はおそらくいません。このような話をし過ぎると龍馬ファンをがっかりさせてしまうのかもしれませんが、でも一歩踏み出して「龍馬のイメージに人々は何を託そうとしてきたのだろうか」という思想史的考察をすれば、より坂本龍馬を深く楽しめるのではないかと個人的には感じています。一歩踏み出したい人には、知野文哉『「坂本龍馬」の誕生』(人文書院)がおすすめです。
話を戻しましょう。薩摩藩などが非協力の動きをみせていたにもかかわらず、幕府は長州征討を開始します(第2次長州征討)。しかし、西洋式軍備を備えた長州軍に幕府軍は各地で敗北しました。14代将軍徳川家茂が大坂城で病死したことを理由に、幕府は戦闘を停止しています。
政争の激化、物価高騰による生活苦などから、各地で世直し一揆や打ちこわしがおこっていました。また、1867年後半には「ええじゃないか」の乱舞もありました。伊勢神宮のお札が降ったということで、各地で民衆が熱狂的な乱舞をおこなったのです。特定の日を「遊び日」(休日)に設定して、男女が異装して路上に繰り出すという点では、現代でも似たようなものがある気がしますが、当時のええじゃないかには世直しの期待が込められており、支配層に危機感を抱かせる力を持っていました。
徳川(一橋)慶喜が15代将軍に就任しますが、将軍になっても江戸に行くわけではなく、京都や大坂に滞在し続けます。そのため、江戸の人々にとっては親しみを感じる将軍とは言えなかったようです。孝明天皇の信任を得ていた慶喜は、フランス公使ロッシュの支援を受けながら軍制の西洋化を中心とする大胆な幕政改革に着手しました。高校の日本史では、イギリスが薩長に接近して、フランスが幕府に接近したと説明することが多いかもしれません。誤りとは言えないのですが、もう少し細かいところまでみていくと、実際はもっと複雑な関係があります。イギリス公使のパークスは幕府に対する信頼もあったので、幕府と雄藩とで公議政体を実現すればよいと考えていました。薩長へ積極的に接近した若手通訳官のアーネスト・サトウの行動をパークスが黙認していた、というのが正確な情報ではないかと思います。また、フランス公使のロッシュが幕府を支援したのは事実ですが、フランス本国としてはベトナム支配の方が優先順位は高く、日本に対するロッシュの動きを支援していたとは言えません。
1866年、孝明天皇が急死します。悪性の天然痘が死因とされていますが、かつては毒殺説が論じられたこともあります。幕末における大きなターニングポイントの一つになったからこそ、毒殺説が出たのでしょう。これにより徳川慶喜が大きな後ろ盾を失い、明治天皇即位後、公家の岩倉具視が急速に力を強めました。岩倉らが薩長両藩とともに、将軍職廃止や天皇親政を武力を用いてでも実現しようとうする対幕府強硬策を計画するようになります。そして、1867年10月14日に討幕の密勅が薩長両藩に下されました。「密勅」とありますが、まだ元服前であった明治天皇が父である孝明天皇の意志に反する討幕を命じるとは考えにくく、当時の摂政も討幕派ではなく幕府派と言った方がよい人物だったので、これは岩倉具視ら一部の公家主導の詔書と考えるのが妥当です。
一方、土佐藩の後藤象二郎は、徳川将軍家を残しながら天皇のもとで公議政体を実現しようと考えていました。朝廷と幕府がわかれて政治権力が複数あるのが問題であって、天皇のもとで、徳川将軍家・雄藩・公家が集まって国政を協議していけばよいという公議政体論です。後藤象二郎は前土佐藩主の山内豊信(容堂)の承認を得た上で、この考えを建白しました。慶喜はこの建白を受け入れて大政奉還を朝廷に申し入れ、朝廷はそれを認めました。「大政奉還」を理解するためには、前提知識として「大政委任論」を理解している必要があります。天皇から委任されていた国政権を、天皇に返上します、というのが大政奉還の意味です。この日は討幕の密勅と同日の10月14日でした。
朝廷が大政奉還を受け入れた以上は、対幕府強硬派が即時に討幕する理由が失われます(ただし、対幕府強硬派は将来的な挙兵を考えていましたが、即時挙兵は断念していたようです)。慶喜は、対幕府強硬派の機先を制して大政奉還をおこない、幕府は消滅しても、天皇のもとで実施される公議政体における有力者として徳川家が温存される、という方向を自ら選択したと言えます。後藤象二郎らは徳川慶喜を無条件で新政府に加えることに何の疑問も持っていませんでしたが、徳川慶喜抜きの新政府をめざしていた岩倉具視や西郷隆盛・大久保利通らの対幕府強硬派は、別の策を練っていました。
さて、複雑な幕末の歴史について説明してきましたが、『夜明け前』では高校の日本史で学ぶような知識がたくさん出てきます。日米和親条約、日米修好通商条約(神奈川条約)、安政の大獄、桜田門外の変、和宮と家茂の結婚、公武合体、坂下門外の変、航海遠略策、破約攘夷、文久の改革、参勤交代の緩和、生麦事件、第1次長州征討、池田屋事件、禁門の変(蛤御門の変)、孝明天皇の条約勅許、第2次長州征討、薩長同盟、ええじゃないか、大政奉還などが『夜明け前』の第一部に登場します。
激動の幕末史が木曾の馬籠にも影響を及ぼす中、青山半蔵は平田派国学の門人として自分に何ができるかを考え、行動します。半蔵が水戸学と国学の違いを考察する場面はなかなか興味深いものです。勤王の志があるという点では共通するものの、神道を敬いながら儒教まで崇める水戸学の傾向は、国学者からみれば「漢意(からごころ)」のまじったものであると述べています。「漢意」とは、中華思想を正当化したり、物事を虚飾で飾り立てたりする態度のことで、宣長はそれを排し、人間本来の「真心」による生活が古道にかなうものと考えていました。半蔵は、宣長が方向性を示してくれたと感謝しています。
『夜明け前』第一部では、水戸藩の政争に敗れた藤田小四郎らによる天狗党の乱にかなりの字数を割いていますが、水戸学に影響を受けた人々の中からは実際に一部の過激な尊王攘夷論者が出ていました。物語の中では、平田派国学の門人の中から、過激な攘夷論を尊王論と切り離して考えるべきという意見も出てきます。一方で、等持院に安置してある足利将軍の木像の首を抜き取るという乱暴な事件(等持院事件)をおこした平田派国学の門人もいました。
薩長に対する批判も出てきます。半蔵の妻(お民)の兄である寿平次は、航海遠略策→破約攘夷→イギリスと結びつく、という長州藩の変遷に一貫性がないとし、外国との結びつきで力をつけた薩長を批判しています。
第一部の終盤、誠実多感な主人公は、大政奉還の知らせをきいて歓びに満たされます。平田派国学の門人としての願望、そして宿場で様々な仕事に従事し武家に奉公してきた家の一人として、新しい時代への希望が膨らんでいきました。
③に続く
※主要参考文献は最後にまとめて記します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
