
映画『帰ってきたムッソリーニ』(原題:Sono Tornato)(2018・伊):イタリア文化会館・試写会レビュー
0. はじめに
2019年9月11日、筆者は、東京・九段下のイタリア文化会館にて開催された『帰ってきたムッソリーニ』(Sono tornato)(2018・伊)の試写会に参加した。

(公式フライヤー)
こちらの映画は、今年春のイタリア映画祭において上映されたもの。
日本では、2019年9月20日より、公開予定である。
監督ミニエーロは、ドイツにおいて2015年に公開された映画『帰ってきたヒトラー』(Er ist wieder da)に着想を得て、本作を製作した。
もし現代において、ファシスト党を主導した独裁者ベニート・ムッソリーニが生き返ったら?という、とんでも設定に基づいてストーリーは展開する。
1. ムッソリーニとは
そもそも、ファシズム(ファッショ(fascio; 結束、連帯)+イズム)はどのようにして生まれたのであろうか。
第一次世界大戦後、戦勝国のイタリアは、パリ講和会議に参加したものの、満足な合意に至ることができなかった。
国内では不満が高まるとともに、財政面でも外交面でも国内政治は混迷を極めていた。
そのために、議会制民主主義でもなく、プロレタリアート独裁でもない、第三の道としてのファシスト党が登場した。
ファシズムとは、議会主義、資本主義の危機の際に出現する反民主主義、反社会主義、反革命の暴力的な独裁政治とその運動として定義される。
ファシスト党の党首であったムッソリーニは、改革を希求する労働者からも、また秩序維持を期待する上層階級からも支持を得て勢力を拡大していった。
ムッソリーニは軍事力を所有し、様々な政策を強行していった。
当初、ファシスト党の勢力はそれほど評価されていなかったが、ムッソリーニによる1922年10月末のローマ進軍が成功すると、ファシスト党は、事実上の単独政権となっていく。
ムッソリーニは、国家や社会のためには個人の自由の犠牲をいとわないということを意味する「全体主義」のもと、様々な政策を正当化するとともに、1926年にはファシスト党以外の政党を作ることが禁止された。
1929年の世界恐慌により、世界中が不況に喘ぐようになると、ムッソリーニは、かつて古代ローマ帝国が支配していた地中海を「我らの海」として回復するために、エチオピアに進軍した。
1935年に始まったこの戦闘では、イタリア軍は、毒ガスや飛行機を使用してエチオピアを圧倒して、結果的にエリトリア、ソマリアも含めた「イタリア領東アフリカ」を形成した。
これを機に国際的な孤立を深めたイタリアは1937年に国際連盟から脱退し、共に国際連盟から脱退していたドイツ、日本と協定を結んだ。
1940年6月、イタリアはドイツと共に英仏に参戦するも、イタリアは苦戦を強いられていた。
国内ではムッソリーニに対する不満が高まり、1943年7月のファシズム代表議会の結果、彼は逮捕された。
ドイツに占領されていた中北部ではレジスタンス(抵抗闘争)の動きが活発化し、最終的に、連合軍とレジスタンスによって、イタリアはドイツ支配から解放された。
1945年、パルチザンとの攻防を続けていたムッソリーニは、ついに捕らえられ銃殺、その遺体は、ミラノのロレート広場に吊るされた。
参考:濱口忠大「第4章 「大国」をめざして」『はじめて学ぶイタリアの歴史と文化』ミネルヴァ書房、2016年、104-129頁。
2. 『帰ってきたヒトラー』(2015・独)との比較
序文でも触れたとおり、こちらの映画は、『帰ってきたヒトラー』というドイツ映画に着想を得て作られている。
大まかな流れから細部の演出に至るまで、『帰ってきたヒトラー』を倣っている部分もあれば、イタリアらしさが現れている部分もある。
どちらの映画も、売れない映像作家が、過去の独裁者とともに、国中の人々にインタビューをして回る場面からストーリーは展開する。

(公式フライヤーより、以下引用画像は公式フライヤーより掲載したもの)
『帰ってきたヒトラー』においては、ヒトラーの扮装をした役者が街中を歩くと、笑う人がいる一方で、ヒトラーの姿をした役者に激昂する人もいた。
本作の場合でも、銃を持って「出て行け!」と言った人もいたが(この人はさすがに役者かもしれない)、総じて、ヒトラー版より、本作では、イタリア人がムッソリーニを好意的に、というより面白がって受け入れていたとのことであった。

どちらの場合においても、スマートフォンで過去の独裁者と自撮りをする人々も次々と現れ、彼らはアイドルのようにもみくちゃにされている。
一方で、本作においてイタリアらしさが前面に出ていると言えるのは、次の3つであろう。
まず一つ目に、ローマという都市を効果的に使っていること。
1930年代にムッソリーニが、ローマに作った建築物は今でも残っており、本作の各場面において登場する。
本作冒頭で、足にロープをつけたまま(ムッソリーニは処刑された後、さかさに吊るされた)生き返り、新聞屋さんに保護された後、ムッソリーニが真っ先に向かったのは、観光地化したかつての我が家であった。
このシーンは、清朝最後の皇帝・溥儀を描いたベルトルッチ監督の映画『ラスト・エンペラー』のラストシーンにおいて、観光地化した紫禁城に溥儀が出てくる場面に似ているように感じた。

偉大なるローマ帝国を想起させる古代ローマの遺跡や青い空も注目である。
二つ目に挙げられるのは、登場人物のファッション(特に女性)の華やかさや、バールや車の小汚さ。
エンドロールを見ていたら、その中に、ミラノ発の高級ブランド・アルマーニ(Armani)の名前があった。
ジョルジオ・アルマーニがブランドを立ち上げたのは、戦後であるが、作中でムッソリーニが来ていた黒シャツはひょっとしてアルマーニなのかなと思いを馳せた(そうではなくて、他の登場人物が着ていたスーツかもしれない)。
三つ目は、作中で使用されるイタリアの歌である。
試写会の後行われた小田原琳教授(東京外国語大学)の解説の中で、指摘されていたことであるが、テレビ局のプロデューサーが視聴率アップを願って『小さな黒い顔』を歌うシーンがある。
『小さな黒い顔』とは、1936年にイタリアがエチオピア帝国を侵略した際に、イタリアがエチオピアを文明化するという内容を軽快なリズムに合わせて歌った曲である。
ムッソリーニを大々的に取り上げようとするテレビ局の幹部がこの歌を歌っていることからも、他国民・多民族の排斥を正当化する歴史の繰り返しが暗示されているようにも思われる。
また、本作の中では、何度かヴェルディ作のオペラ『椿姫』の劇中歌『乾杯の歌』が何度も流れる。
『乾杯の歌』は、「皆で喜びの時を分かち合おう」ということを朗らかに歌った歌であるとともに、何よりもヴェルディは、19世紀後半に活躍したイタリアで愛される作曲家である。
『帰ってきたヒトラー』の予告編を見た方はお気づきかもしれないが、ヒトラー版の中では、ドイツで愛される作曲家であるワーグナー作曲の『ワルキューレ』が使われている(ヒトラーは、ワーグナーに心酔していた)。
このような国民的作曲家は、国粋主義の称揚のために効果的に使用されていたのであった。
3. 家族愛→愛国心
『帰ってきたヒトラー』において、ヒトラーが初めてインターネットを使うシーンがある。
そこでヒトラーは、wikipediaを見て、「インテルネッツ、アーリア人の知の結集」と言って感涙にむせび泣く。
ところが、同じく初めてインターネットを使ったムッソリーニが、一番に検索したのは、一緒に処刑された恋人の名前であった。
懐かしい彼女の写真を見て「彼女は、私のせいで死んだんだ」(1945年当時、独裁者の愛人ということで一緒にムッソリーニと一緒に殺された)と目頭を抑える。

また本作ではスマートフォンを使って恋愛指南をするムッソリーニなど、独裁者の人間らしい場面がコミカルに描かれている。
しかしながら、それと同時に、「自分が愛する者以外の者」に対するムッソリーニの態度は厳しい。
ムッソリーニがテレビ番組で演説するシーンでは、その背景に子供を肩車するムッソリーニの写真が使われている。
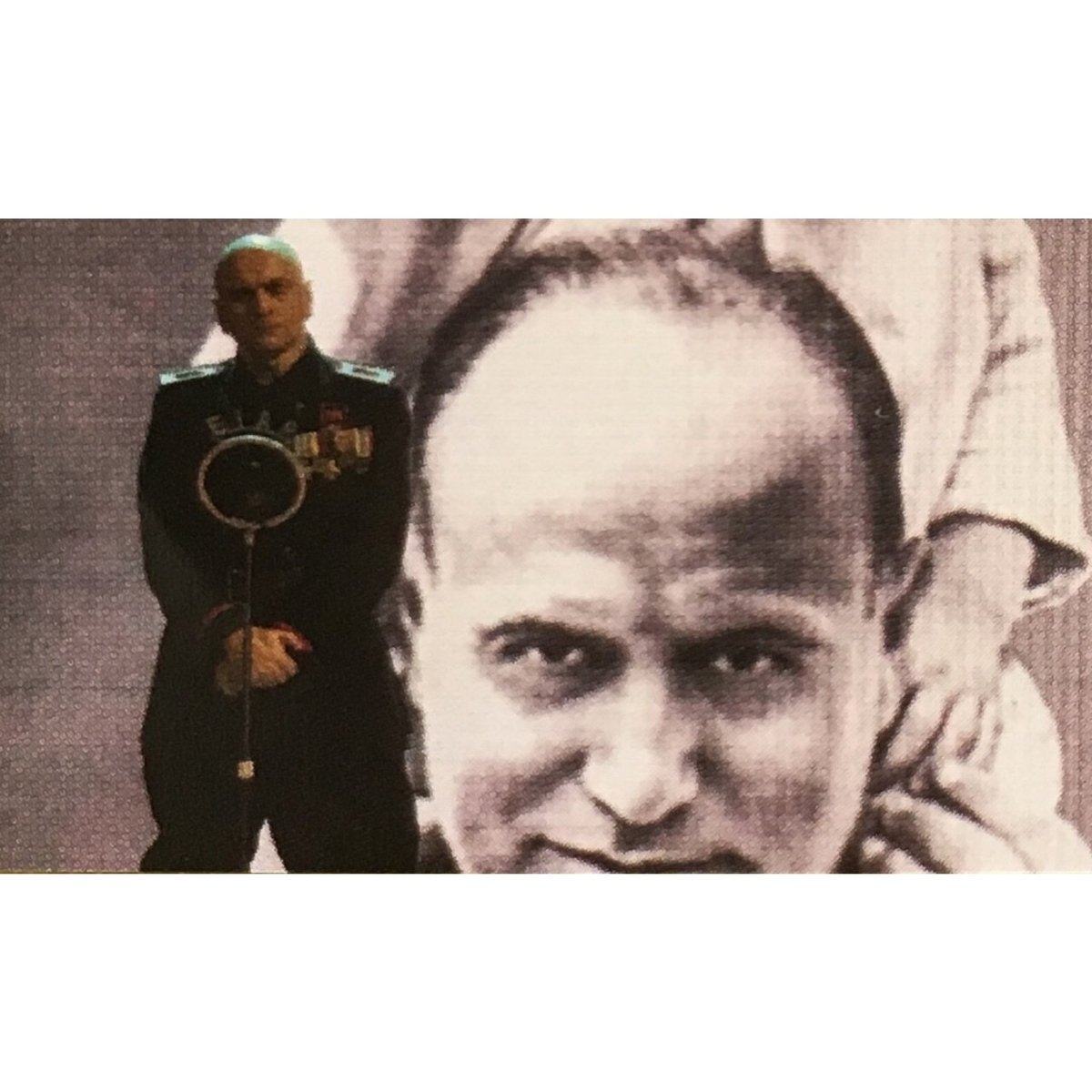
(フライヤーの写真より、子供の部分が見切れている)
ムッソリーニは、イタリア国民の父としてのイメージをプロパガンダするとともに、それ以外の者たちを徹底的に排除しようとした。
我が子を守る父のように。
特にイタリアはファミリーを大事にする国である。
その家族愛が、逆にその他の人を傷つけるむき出しの刃になっているのではないだろうか、と考えさせられるセリフが本作にはいくつかあったのである。
4. 笑っていいのか、笑ってはいけないのか
さて、最後の章に入る。
我々は、この生き返ったムッソリーニを笑っていいのか、いけないのか。
作品を見終わった後に考えるべき課題であろう。
作中には実際に街を歩くイタリア人のインタビュー映像が使われ(本人から許可が出た人に関してはそのまま、出なかった人にはモザイクがかかっている)、今を生きるイタリア人の政治観が語られる。
そこでは、移民に対する不満や政治家に対する失望感・不信感、将来に対する不安など、イタリア人のやり場のない感情が噴出している。
「国民の罪は忘却だ」とか「私がファシズムを作ったのではない。国民の心の中にファシズムの精神があったのだ」という台詞を作中で残したムッソリーニ。
彼は、約70年後の情勢を瞬く間に把握し、メディアの力を借りて自分が次なる指導者となろうとする。

つまり、人々にとっては、ムッソリーニでもタピオカでもなんでも良い、とにかく明確に自分たちを導いてくれる「正解」があれば良かったのである。
「あの頭のイカれたムッソリーニのコスプレ野郎!」と笑っていた人が、ムッソリーニを好きになっていく。
『帰ってきたヒトラー』や本作の独裁者たちは、主人公でありながらリトマス紙のようなものに過ぎない。
彼らを通して、我々は主人公として、歴史をどのように考え、これからどうするべきか考えるような狙いがあるように思われる。
幸いなことに、インターネットや交通手段の発展により、21世紀を生きる私たちと世界はどんどん近くなり、情報は手に入りやすくなっている。
例えば、イタリア人の若者の間では、チュニジアにルーツを持つラッパー・ガリ(Ghali)がその優れた音楽的センスとファッションが話題になるなど、文化の面から、多様性というものを学びとることができる。
(最も、イタリア人の女の子の間では、BTSが人気である)
過去を繰り返さないためには、自分とは違う人を理解する努力をし、その上で一人一人が行動・発言を考えることであろう。
また、九段下の駅から試写会の会場となったイタリア文化会館に行くまでに、靖国神社のそばを通ることになるため、日本の戦後についても否応無しに考えさせられた。
1930年代に日独伊三国協定を結び、国際社会から悪の枢軸国と言われた国のうち、ドイツとイタリアは、過去の独裁者を映画にし、人々に問いを投げかけた。
悪い冗談であるが、今の日本では、『帰ってきた◯◯』という作品を作ることは不可能であろう。
実際に作る作らないをおいておくとしても、なぜ不可能なのか、その理由を私たちが考えること自体には意味があることかもしれない。
『帰ってきたムッソリーニ』(原題:Sono tornato)
監督:ルカ・ミニエーロ
主演:マッシモ・ポポリツィオ(ムッソリーニ)、フランク・マターノ(映像作家カナレッティ)、
2019年9月20日より順次公開
全国各地の公開スケジュール→★
公式ホームページ:finefilms.co.jp/imback
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
