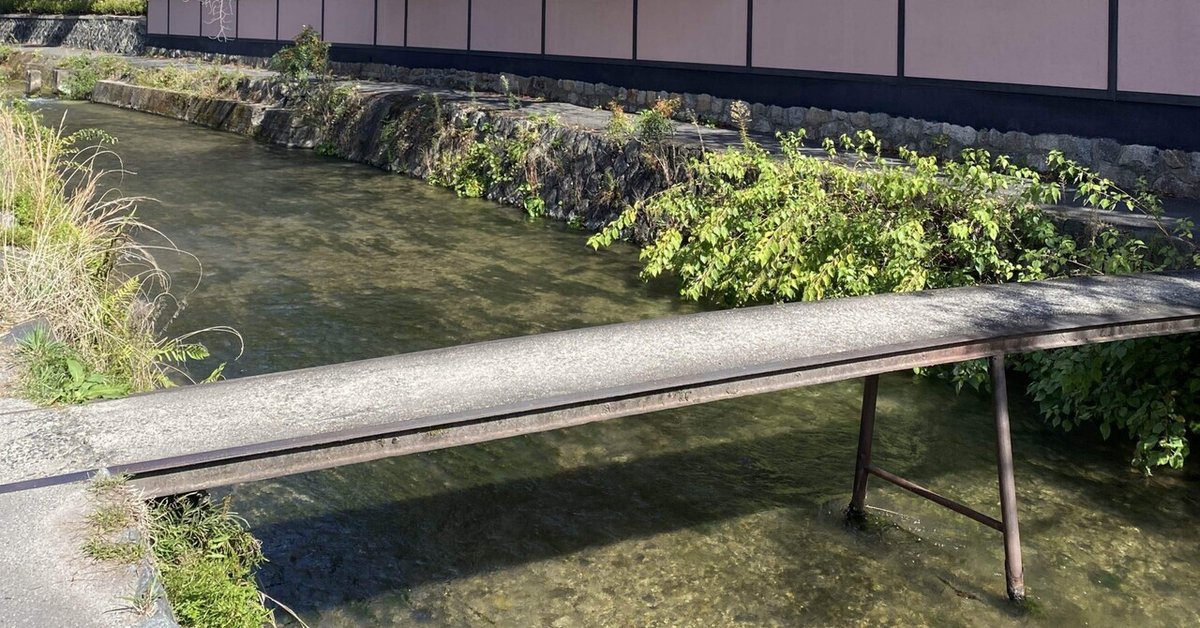
「エンタメとその対岸にいるもの」(短歌研究2023年4月号)
短歌研究2022年12月号には、次号予告として「多角的分析『成長するエンタメ短歌』」という特集名が掲載されている。その後、1月号を見ると当該の特集は掲載されておらず、エンタメ短歌はどこかへ消えた。
その後2月号から連続企画と題し山田航、渡辺祐真(スケザネ)による特集「新時代『現代短歌2.0』」が始まるが、これが「エンタメ短歌」として当初企画されていたものなのかは分からない。予告が最終的に本編と大きく変わることはどのジャンルでもよくあるし、特に気にする話でもないのだけれど。あり得たかもしれない「エンタメ短歌」への分析について、せっかくなのでここで少し考えてみたい。
エンタメ短歌、とはなにか。近年、短歌研究社を中心に推められている『ホスト万葉集』『アイドル歌会』などの、エンターテイメント業界への短歌文化の輸出(逆に言えば、エンタメ文脈の短歌文化への輸入)のことを指すのであれば内容はわかりやすい。
個々の企画についてはそれぞれリアルイベントや紙面での特集が組まれているし、逆に言えばこれらはそもそも企画がなければ存在しないムーブメントであるので、一通りの振り返りが済んだ時点で言及すべき点は少ない。
(もう少し長期スパンで考えれば、職業詠としての「ホスト」や「アイドル」の分析を詳しくできるかもしれないが、それはそれぞれご興味のある方がやればいいだろう。また、今後もエンタメ業界の一コンテンツのあり方として、色々な職能の人に「歌を詠んでもらう」というのはますます定着していくのではないだろうか。余談おわり。)
ここでとりあげたいのは、エンタメ業界の短歌、ではなくて、短歌の中でエンタメ性が強いとされるもの、のカテゴリとして使われる「エンタメ短歌」の文脈のことでした。
短歌研究2月号、渡辺祐真(スケザネ)の「短歌と考える現代」の第一回。既存の短歌への評価を純文学=芥川賞的なものを軸としていると捉え、直木賞に相当するような「エンターテイメント性の高い短歌を作っている歌人を歌壇的に位置づけることが難しくなっている」と言う田村元の記事(短歌研究2022年12月号「短歌ブームについて」)を踏まえて、「エンターテイメント的短歌と純文学的短歌」について考察している。
この「エンターテイメント的短歌」「純文学的短歌」という区分は、ある
程度戦術の区分に応用できるように思う。
SNSでバズる短歌は、一読して意味が分かりやすいものが多く、エンタ
ーテイメント性に富むものが多い。一方で、純文学的短歌の代表には、川野
芽生のような古語を活かした歌人や、平岡直子のような一読しても意味が判
然としない歌を得意とする歌人が挙げられる。
川野・平岡の二人を並べて文体・レトリックの難解さ=純文学的短歌、と置くのは興味深かった。それがアングルとして適切かどうかはさておき、その後の西行と定家を引いて「僧侶の持つおおらかな境地から多くの人々が安心して心を預けられる西行、自らの美意識を持ち、確固たる世界観を築いた定家。短歌に二つの極があるとすれば、まさにこの二人の態度であり、先の区分もこうした大きな方向性の中にあると思う」と、エンタメ/純文学の線引きを、大衆的な分かりやすさに対する、確固たるレトリックや世界観の在りよう、と区分するのは分かりやすい視点に思える。
田村にしても、スケザネにしても、この「エンタメ/純文学」の区分に対して、作品としての優劣を以て使用しているわけではなく、本人たちもその点は明言している。不用意にこの分類を当てはめようとすると、どうしてもヒエラルキー的な上下が発生するからだ。
「エンタメ」の用法でいうと、阿木津英はさらに明確に、商業的に成功したものを指して「エンタメ短歌」として言及している。角川『短歌』の年間回顧記事の中で、木下龍也の『あなたのための短歌集』と、木下自身の商業的なプロモーションに対して阿木津はこのように発言する。
恵まれた容姿と多少(失礼だが)の短歌技術を武器に、有名になりたい、金を稼ぎたいという率直な欲望を動力として、数年間にわたる弛まぬ諸種の努力とアイデアを積み重ねた、本格的エンタメ系短歌の出現だ。
木下について、真っ先に容姿について言及しているところが、世代を感じさせて興味深い。文章全体のアイロニーについてどのくらい真面目に受け取ればいいのか分からなくて困るけれども、興味深いテキストなのは間違いないのでぜひ全文を読んでください。
阿木津の論では、名が売れて、商業的に稼げるエンタメ系短歌、に対して「稼げそうもないし、多数決では評価できないので、名も現れそうにない。」芸術としての短歌が位置づけられ、また、「芸術とは人間精神の本質にもとづくもので、高みを目指して限りがない。」とも述べている。
商業的に成功した歌集を「エンタメ」的なものとして考えたとき、「エンタメ」でない側にあるのは何なのだろうか。阿木津は「エンタメ」と「芸術」を相反するものとして置いたけれども、エンタメを志向しないものをすべて「芸術」の範疇に入れるには、阿木津の論調は芸術に対してかなりストイックなように映る。
こと短歌の話に限って言うけれども、『エンタメではないもの』の大多数は、だからといって文学的なもの(阿木津の言う「芸術としての短歌」)を志向しているようには見えない。
それならばまず短歌のなかで文学性と大衆性を対置した上で、大衆性の延長線に「エンタメ短歌」を位置づけるほうが多少わかりやすく見えるのではないだろうか。そうすると話は結局、先の田村・スケザネのロジックに戻る。
さらに言えば、一部の求道的な(阿木津の言うような?)「文学的短歌」を除けば、短歌においての「エンタメでないもの」の大多数は、自ら方法論を選び、商業的な成立を目指した「エンタメ短歌」に比べて、結局のところ、既に価値観の確立された安全圏にいるのではないか、という意地の悪い見方もできるだろう。
ラベルは常に外から与えられるものではあるが、制作者として最初からエンタメ/純文学のような区切りを前提に作品を作るのは、場合によっては危険なことかもしれない。
例えば、新人賞の傾向や選考委員に合わせて応募作をチューニングする、といった程度のことは今でも普通に行われている話であって、芥川賞(仮)や直木賞(仮)が並立した場合、予めそれぞれに焦点を合わせた作品の住み分けがなされるだろう。ラベルによる分類と住み分けは、読者にとっての入り口が分かりやすくなる半面、長期的に見ればジャンルの間口そのものを狭くするリスクもある。
これはあくまで個人的な感覚の話ではあるが。
わたしには、自らの創作活動や問題意識ついて、広い意味での現代短歌の末端に連なるものであるという自負や矜持が(これでも多少なりともは)ある。ただ、己の創作について、自らそれを「文学である」や「芸術的な営為である」と言ってしまえるほどには、わたしは短歌をとりまく環境について、無邪気に振舞うことはとてもできない。
あるいは、各々の創作という営為それこそが文学的なもの、芸術的なものである、というような実践主義的な精神論をここでは用いるべきだろうか。ある程度の年数と実績を積んだ方々にとってはもはや自明すぎて、いまさら言語化するような話ではないのかもしれない。それでも私たちは折に触れ思い出し、問い直すことが必要なのではないだろうか。
文学とは何か。あなたは、どうお考えですか?
(短歌研究2023年4月号掲載分をレイアウト修正の上掲載。)
いいなと思ったら応援しよう!

