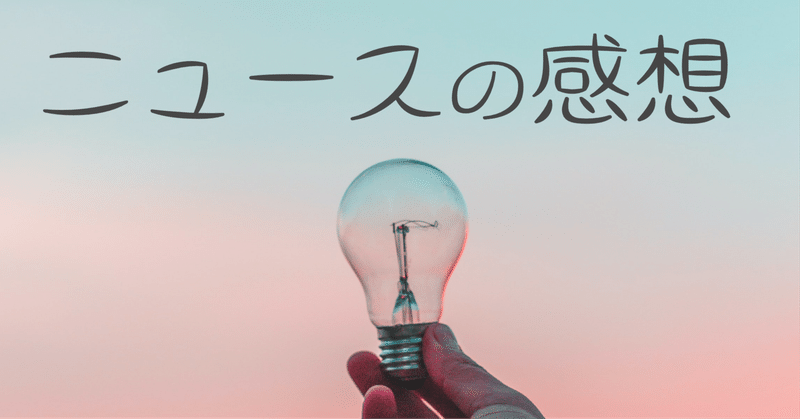
「ゆるブラック」と言う言葉に思ったことなど
2013年に新語・流行語大賞のトップ10に入った「ブラック企業」は、長時間労働やパワハラが横行し、働きたくない企業の代名詞となった。この10年で人への投資に対する認識も高まり、「ホワイト企業」が増える一方、緩すぎて成長機会を見いだせない「ゆるブラック」なる言葉も出てきた。働きやすく、働きがいのある職場の追求は続く。
「ゆるブラック」と言うのは、仕事が緩すぎて成長機会を見いだせない職場を表す言葉のようです。我々は言葉だけで物事を理解するわけではありませんが、このように新しい言葉が生まれることで、新しい問題意識が形成されることが多々あります。
『ブラック会社に勤めてるんだが、もう俺は限界かもしれない』という映画の公開が2009年で、2chにスレッドが経ったのは2007年だと考えると、00年代の後半あたりには「ブラック企業」という言葉は一般に認知されていたのだと思います。そして、上記記事によると10年代以降年々、残業時間の低下や、有給取得率の上昇など日本の職場はホワイト化が進んでいるとのことです。
それがすべてとは言わないですが上記のようなホワイト化の一因として、ハードワークを強制されたり、ハラスメントが横行する職場を「ブラック企業」と言語化し、社会問題化したことが挙げられるのではないかと思います。
そう考えると「ブラック企業」と言う言葉が生まれ、社会問題が認識され、それが多少なりとも改善されたからこそ「ゆるブラック」という、「過労」「ハラスメント」と言うわかり易い問題ではなく、「やりがい」や「自己成長」と言う抽象的な問題が言語化されたのかもしれないですね。
「ゆるブラック」と言う言葉が生まれたことによって、職場の問題はブラックとホワイトの単純な二元論から一歩進んだのではないかと思います。そういった意味で私はこの言葉が生まれたことをポジティブに捉えています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
