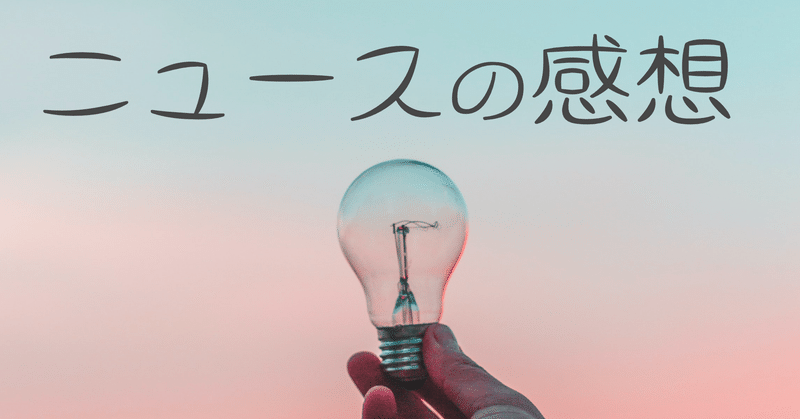
「新しい資本主義」提言案に思う
賃上げを促す税制は第2次安倍晋三政権下の13年度に導入されて以来、見直しが繰り返されてきた。当初は企業規模にかかわらず給与総額が増えれば優遇税制を適用したが、18~20年度は働き続ける人の賃上げに力点を置き、継続雇用している人の給与総額を増やした場合に税額控除すると明確にした。(上記記事より抜粋)
賃上げを促す税制は13年度から導入されているのですが、いまいち効果が出ていない政策です。そこに対して優遇する賃金の支払い方を変更する今回の対応はあまり意味がないのではないでしょうか。
賃金が上がらない背景には生産性の低さがあると言われています。いまいち効果のなかった政策にそれっぽい名前を付けてリニューアルするよりも、生産性の低さへの手当を優先する方が効果的な気がします。
ということで、生産性を上げる政策についてちょっと考えてみようと思ったのですが、パッと思いついた「最低賃金上げ」などは以前どっかに書いたので、他にないかなぁと上記記事を見ていたところ以下のような記載がありました。
野村証券の美和卓チーフエコノミストは「日本では依然として再分配の強化よりも成長戦略を重視すべきだと考える」と指摘。「税制を活用した一律の賃上げ促進策よりも、労働市場改革、特に雇用流動化の促進やリカレント教育の支援を通じた労働生産性引き上げ策のほうが望ましいのではないか」と語る。(上記記事より抜粋)
労働市場の改革、特に雇用流動性の促進は適材適所が実現されるため、社会全体の生産性が向上します。ちょっとこれについて考えてみようと思います。
雇用流動性の促進について
促進するためには雇用流動性が低い原因を見つける必要があります。
その原因をまずは、労働者が転職に及び腰になる理由から考えてみようと思います。新しい人間関係が面倒だとか、今より給与が下がったら嫌だとか、そもそも入れる会社があるのかなどの理由が考えられますがこれらは結局のところ、会社に入ることが難しいことが原因です。
転職に及び腰になる理由 = 就職が難しい
では、逆に企業が社員の採用に及び腰になる理由について考えてみます。例えば採用した人が不幸にも企業風土に合わず生産性が低いとします。現状では、だからと言って簡単に解雇することはできないので、その人の生産性を上げるための施策をコストをかけて色々と行うことになります。それで生産性が上がればいいのですが、そもそも企業風土と合わない場合は生産性が低いまま働いてもらうしかなくなります。
なので、日本企業では解雇が容易でないため、長期にわたって高い生産性で働いてくれるのかと慎重に採用を行わざるを得なくなります。
採用に及び腰になる理由 = 解雇が難しい
と言うことで、解雇を簡単にすれば企業が採用に積極的になり、雇用流動性が促進され、アンマッチな企業で働いている労働者は、更に適した企業に簡単に移動できるため社会全体の生産性が上がると考えられます。
ただ、そうなると現在よりも更に実力主義の社会になるので、リスキリングや、さらにそこから漏れる人へのフォローも丁寧に行う必要があると思います。
まぁ、分配政策に傾いている現状で、「解雇を簡単に!!」なんて言ったら、夏の参院選に勝てなくなるのでどの政党も絶対言わないでしょうけどね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
