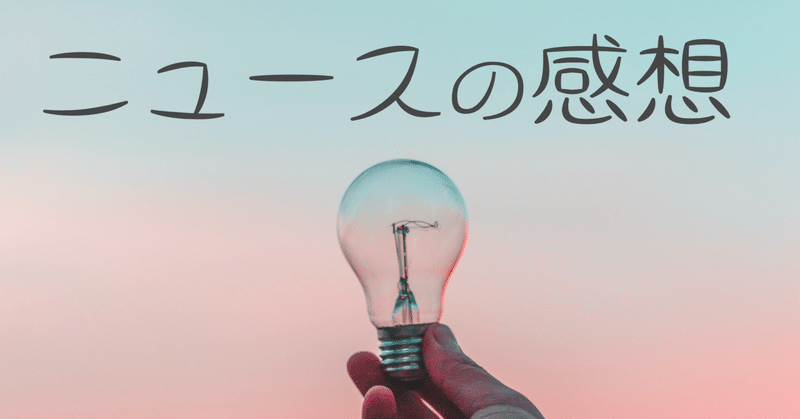
タマゴが映す「安いニッポン」に思う
鶏卵の消費者物価指数(2020年=100)は21年が102.4。1985年と比べると10%上昇したが、総合指数は16%も上がっている。鶏卵が物価の優等生といわれるゆえんだ。
スーパーでタマゴは特売商品の常連だ。かさばる上に割れやすい。だから、お客が別の店に行かない、というのが狙いだ。最近でも都内の店で10個入りMサイズが148円で売られていた。こんな古典的な手法でタマゴは重宝されるのだ。
タマゴが特売の常連になる理由が、買ったら他のお店に行き辛くなるためだというのは面白いですね。
上記の記事ではタマゴの値段が他の商品と比べて上がっていない理由を「過剰生産」と「過剰店舗」の2つの原因から説明していました。
過剰生産
卵価が下がると国から補助金が出るため、メーカーとしては過剰生産することのデメリットが少ないです、よってタマゴは過剰生産されることになります。過剰生産されるということは、需要が供給よりも多くなるので値段が下がることにつながります。
過剰店舗
理由は分からないですが、日本は他の国と比べて人当りの小売店の数が多いです、一つの商圏内に複数の小売店(スーパー)が乱立しているのは実感としても理解できると思います。これによって小売店通りの競争が激化します。
また、徒歩圏内に2つの店舗があったとすれば値段の安いお店に行くという消費者が多いため、競争が激化した状態にある小売店は生き残るために値下げを行います。
まとめ
この流れをまとめると、消費者はお金が無いので、安く買い物をすましたい、小売店は生き残るために値下げを行う必要がある、メーカーは卵価が下がっても補助金が出るので過剰生産のデメリットが少なく、値下げに答えられる。となり、だれも悪くないのにみんな貧しくなるという図式が出来上がるわけです。
上記の記事ですが、鶏卵だけにチキンレースという言葉を使いたいがために、「合成の誤謬」(部分最適化)という言葉を使っている感じが、なんか好印象でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
