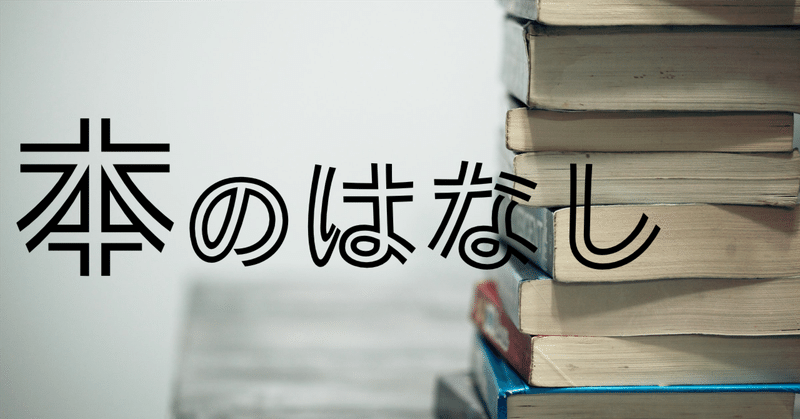
浅田 次郎著『地下鉄に乗って』を読んで思ったことなど
30年前の小説に対して時代錯誤と言うのはちょっと違うと思うので、言い換えるならば『地下鉄に乗って』は90年代前半という時代だからこそ楽しめた作品だといえる。
石田純一が「不倫は文化だ」と(そのままズバリとは言っていないらしいが)言ったのが、1996年だそうだけど、確かにあの時代90年代まではそれを言ってもある程度は許容される、よく言えば大らかさが、悪く言えば無神経さがあったと思う。
では何故30年経った現代はどうだろうか?
不倫をした芸能人は一定期間干されるのが通例になっている、理由は視聴者がその芸能人をみていて見ていて不快感を感じるからだからだそうだ。この不快について妄想してみると、これは被害者(例えば配偶者とか、相手の配偶者)等に視聴者が共感するからなんじゃないだろうか?
理由もなく日本人の共感力が上がったとは考えづらいのでこの理由をちょっと考えてみたい。一つ私が思い至った原因はストーリーが多様になったことだ。
30年前に我々が目にしていた、ストーリーはかなり限られていた、もちろん本を読む人なんかは多様性のあるストーリが摂取できていただろうけど、本を読まないならメディアはTVで、TVは放送枠の制限と利益を生む必要があることから、マス向けの娯楽を提供せざるとえなかった。言い換えれば、90年代に一般大衆が触れるストーリーは画一的だったと言える。
それが、インターネットの発展で個人が自身の考えや経験を発信できるようになり、動画配信サービスによって見切れない量の動画コンテンツも供給されるようになった。メディアもマスだけでなく小さな集団に対して娯楽を提供するようになった。言い換えれば、現代は一般大衆が触れるストーリーが多様になったと言える。
ストーリーというものは強力で、人は摂取したストーリーで出来上がっていると言っても過言ではない。そこに多様性がもたらされることで我々は不倫の裏にいる被害者の感情までも、既に知ってしまっている(正確にはそう思い込んでいる場合が多い)。だから、ストーリーが多様になった今、我々は昔以上に、人を慮ることが出来るし他人の痛みがわかる(と思っている)、同時に加害者に不快感を覚えるのではないだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
