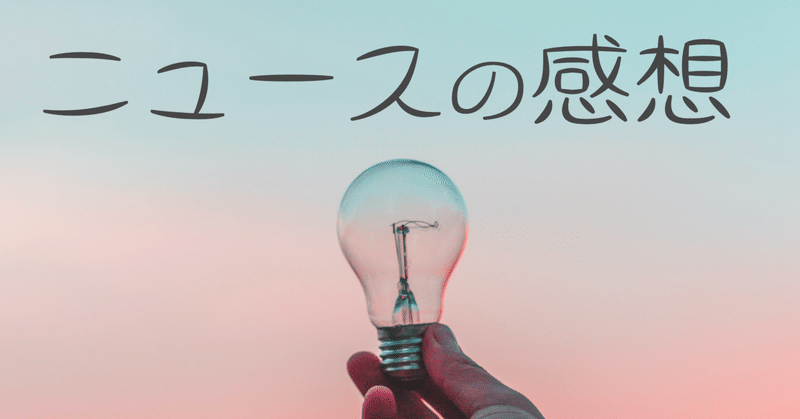
賃上げは生産性の向上に寄与するか?
労働生産性の引き上げに向けた期待を担うのが、22年春季労使交渉における岸田文雄首相の3%程度の賃上げ要請だ。
本稿では、賃金上昇が生産性を上げるかという視点から、高賃金が労働者の生産性上昇をもたらすメカニズムについて、完全競争市場の典型的なモデルと労働経済学の「効率賃金仮説」のモデルを用いて検討する。
と難しい感じに書いてあったので、ざっくりまとめつつ自身の理解を深めておこうと思います。
完全競争市場とは?
まず、完全競争市場って何ぞや?経済人の市場版みたいな感じ?などと思っていたので調べてみました。
市場に需要者と供給者とがきわめて多数存在していて、彼らが自らの需要量または供給量を変化させることによっては市場価格を動かすことができない場合の市場状況をいう。完全競争市場では、個々の需要者あるいは供給者は市場価格で自らの望むだけの量をいくらでも需要したり供給したりすることができる。
例えば、自分がパン屋だったとして作ったら作っただけ売れる。しかもいくら作っても、それが原因でパンが値下がりすることはないというワンダーランドなわけです。ただこれ、経済分析をする際には必要な一つの仮定だそうです。まぁ、色々細かい話してたら分析進まねぇっす。ってことなんだと理解。
何で賃上げで生産性が上がるのか?
完全競争市場
完全競争の状態で、時給1000円のパン職人100人が1個100円のパンを1時間に1000個作っているとすれば、3%の賃上げすると時給が1030円になるので、雇用を守るためには、1時間に1030個のパンを作る必要があります。つまり賃上げした分生産性(個人の時間当たりの生産量)が上がるわけです。あくまで完全競争のモデルであってこまごました現実を考えなくていいから言える話ではありますけどね。
同じく、時給1000円のパン職人100人が1個100円のパンを1時間に1000個作っている場合で、3%の賃上げをしたがパンの焼き上げ時間がボトルネックになって生産量を増やせない場合、完全競争では市場価格を動かせないのでパン職人を減らすしかパン屋が生き残る道はないわけです。人数をxとして計算すると以下のように97.087…になります。
$$
\begin{array}{}\frac{1030x}{1000} &= &100 \\\ x &=& \frac{100\times1000}{1030} \\\ x &=& 97.087…\end{array}
$$
職人を3名減らすことで生産性(個人の時間当たりの生産量)が上がり、パン屋を守ることができました。
と言うことで、完全競争市場であれば生産性は上がるわけです。ただこれ、考え方的には面白いですが、あまり現実的とは言えなさそうです。
効率賃金仮説
「労働経済学の効率賃金仮説のモデル」は賃金が上がったら労働者は頑張るという話なんですが、自分だけではなく全体が上がることによってその効果は無くなるということが書かれていたと読み取りました。
72の法則
よく複利の話で出てくる72の法則というのがあります。72を年利のパーセントで割ると、元本が2倍になる年数が分かるというものです。
生産性の向上にはあまり効果のない3%の賃上げですが、24年で年収が倍になると思うと悪くない気がします。まぁ、そんなに続けないんでしょうけど。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
