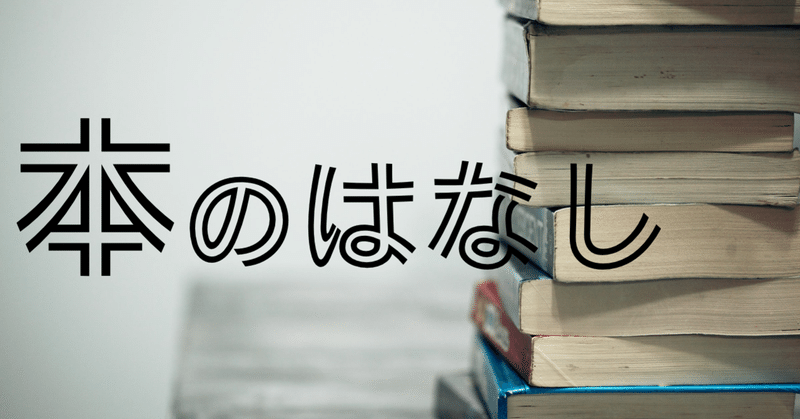
若林 正恭著『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』キューバを読んで思った、本を読む理由
若林 正恭著『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』キューバの序章的なところまで。
— なにがし (@72gashi) November 12, 2021
知ることは動揺を鎮めるというのは、私が本を読む大きな理由。もわっと思ってることが明文化されて腑に落ちる瞬間が最高に気持ちいいし、その後は少しだけ生き辛さが軽減するんだからやめられない。#読書感想
20代前半ぐらいまでは、本を読む理由といえば物語を楽しむためでした。けれども、20代の中盤ぐらいに、自分がもやっとなんとなく思っていることが、本で言語化されていることがあって、それから本を読む理由の半分ぐらいは、そういった本に出会うためになりました。
そういった本を読むと、変な表現ですが、その概念を応用することができるようになるので、ストックを溜めておくと何かが起こった時に色々な方法で出来事を解釈することができるようになります。
なので、知ることは動悸を鎮めるという表現は正鵠を得ているなと思った次第です。
若林 正恭著『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』キューバ(58%まで)
— なにがし (@72gashi) November 17, 2021
著者が感じている気持ち悪さは、友情空間の消滅によって、愛情空間と貨幣空間が接していることで解釈はできるけど、解決はできない。ただ、これも知っていると動悸を鎮めることぐらいはできるかもしれない。#読書感想
著者はキューバで一番お薦めの観光名所として、マレコン通り沿いの人々の顔を挙げていて、そこにはamistad(血が通った関係)がずらーっと並んでいたと書いています。それとは対照的に、東京のことは灰色の街と表現しています。また同じように、キューバではコネが大事で、日本ではお金(資本主義の競争で勝つこと)が大事だと書いています。
本の受け売りですが、私たちを取り巻く世界を「愛情空間」・「友情空間」・「貨幣空間」の3つに分けて考えると、グローバル化の流れの中で日本では「友情空間」が消滅している人が多くみられるようになってきました。
それを感じ取っている著者は東京を「灰色の街」と呼び、キューバ、マレコン通りに自分の周りから失われた「友情空間」を見たのではないでしょうか。
と言った感じで、キューバには東京にはない血が通った関係があるんだよな、とかふわっと感じていることについて、概念を適用することで心を鎮めることができます。
人によっては他人と話したり、本以外のメディアからの方が情報を摂り易かったりするんでしょうけど、私にとっては本が最も効率が良いので本を読んでいるというわけです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
