7つのウヌボレ

ある夜、散歩していると、街灯の下で探し物をする人に出会う。
鍵を落としたので家に帰れずに困っていると言う。
一緒に捜すが、落とし物は見つからない。
そこで、この近くで落としたのは確かなのかと確認すると、
落としたのは他の場所だが暗くて何も見えない、
だから街灯近くの明るいところで捜しているのだと。
これは社会心理学者の小堺井敏晶さんが
大学の授業でよく取り上げるたとえ話だそうです。
ここで「街灯」に譬えられているのは常識です。
いまは「常識」とされていることも
時代や場所によって変わります。
その時々に大勢をしめる人間の都合でつくられ、
広まった考え方が「常識」といえるでしょう。
ヒトラーやスターリンは当時国民から支持されましたが、
後世は独裁者と非難されるようになりました。
同じように今の「常識」だけで今私のいま生きている社会の
善悪を判断するのは難しいことが分かります。
これは社会だけで無く、
自分を評価するときにもあてはまるでしょう。
良識あるひとは、
自己反省も出来るのでは?
と思われるかも知れませんが、
私たちが自己評価するときの
常識や良識は本当に信頼できるものでしょうか?
惚れて眺めりゃあばたもえくぼともいわれます。
他人からみれば欠点にしか思えないことも、
惚れてみると、よくみえてしまう、ということですね。
どんな良識ある人も、それは同じでしょう。
ハンナアーレントといえば
ナチズムを批判した『全体主義の起源』で知らされる
女性思想家です。
20世紀を代表する哲学者ハイデガーと
愛人関係であったことも知られています。
ハイデガーはナチスに入党していた経歴があり、
アーレントとしては最も許せない言動をしたはずの人でも、
惚れた人のことは悪くみれなかったのかも知れません。
大学者の良識も曇らせてしまうのは、
この「惚れた」ということですね。
私たちが一番惚れているのは
他でもない自分自身です。それが自惚れです。
自己反省には「自惚れ」のバイアスがかかるために、
その評価はとても甘くなりがちです。
この自惚れ心を分析すると7通りになると言われます。
これを七慢といわれます。
慢は慢心の慢。自惚れ心のことです。
慢、過慢、慢過慢、我慢、増上慢、卑下慢、邪慢の7つです。
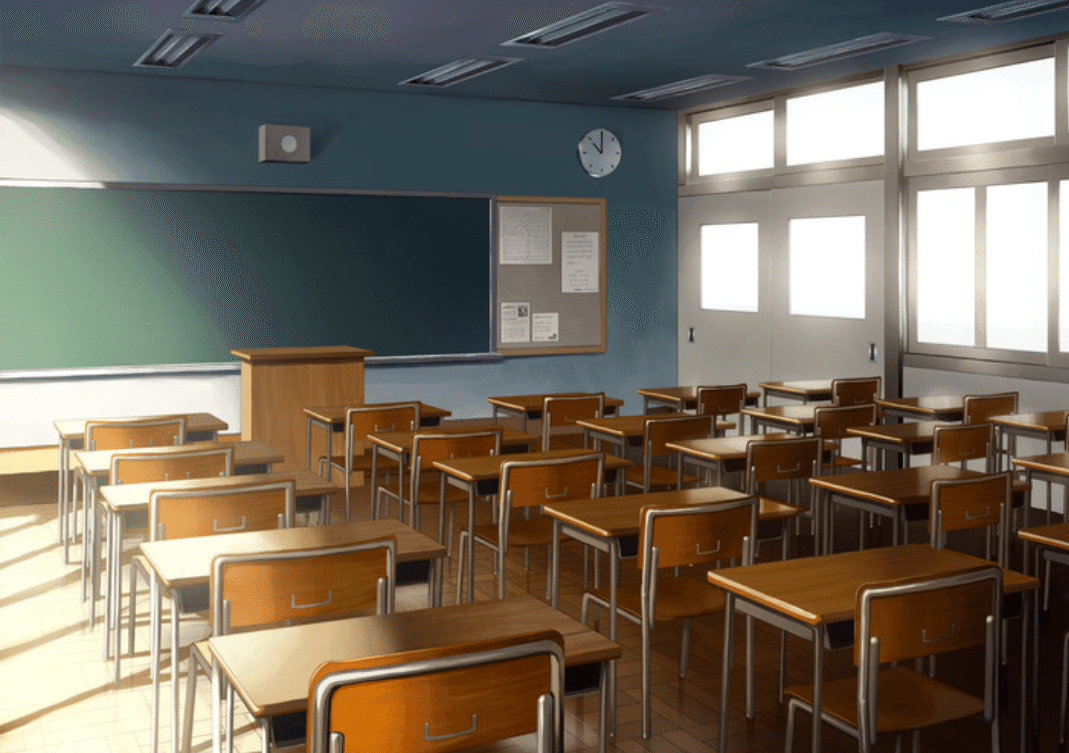
「慢」は自分より劣った相手に対して自惚れる心です。
テストの点数で自分は70点、友人は60点だったとすると
「どうだオレの方が上だろう」と見下すような心です。
そう思うのは当然じゃ無いかと思うかも知れませんが、
心の中で相手を踏みつけている、
とても人には言えない心でしょう。
つぎの「過慢」は自分と同じ程度の人に対しても
自惚れる心です。
テストの点数が同じでも、本当はオレの方が上だと思う心です。
「慢過慢」はテストで自分は70点友人は90点だった場合でも、
素直に相手が優れていると認められず、
おれの方が上だと思う心です。
あいつは塾に通って、毎日寝ずに勉強して90点。
おれは部活もやりながら、一夜漬けで勉強して70点。
条件が同じなら断然オレの方が上だと思ったりします。
あるいは「あいつは勉強は出来るかもしれないが、
スポーツはまるでだめじゃないか、その点おれは両方出来るから」
などと、相手のよいところは見ないようにして、
自分に有利なところを他から引っ張ってきて、
なんとか相手の上に立とうとする心です。
「我慢」はくすぐられても笑わないように我慢するとか、
暑さを我慢するという忍耐のことではありません。
自分の考えは正しい、間違いないと
どこまでも我を押し通そうとする心です。
「はっても黒豆」ということわざがあります。
床に落ちている黒いものをさして
「あれは虫だ」「黒豆だ」と言い争っていたところ、
黒いものが動き出したので虫だとハッキリしましたが、
「黒豆」だと主張していた男は
「はっても黒豆だ」と言ったはったそうです。
こんなのを「我慢」といいます。
「増上慢」とは悟ってもいないのに
悟ったと自惚れる心です。

「卑下慢」とは
未熟者ですが、何も出来ないものですが、
腐女子です、腐男子ですと卑下しながら
「本当にお前はどうしようもないな」
「腐ってるな」と言われると腹が立ってくる心です。
本心からそう思ってはいないからでしょう。
不祥事をおこした会社の社長や役員が
「申し訳ありませんでした」と深々と頭を下げますが、
心の中では「どうして私が」と思う心です。
そして「どうだ私ほど頭の低い者はないだろう」と
自惚れる心です。
「邪慢」とは自惚れる価値の無いことを自惚れることです。
テストで20点とってしまった、授業の単位を落としてしまった、
留年したとか、それを友達に見せびらかしたり、
ツイートしたりする心です。
刑務所の中では前科の回数が自慢の種になるそうですが、
そんなのを邪慢といいます。
能力が高い人ほど「慢過慢」より上の高慢になりやすく、
そうでないひとは卑下して自惚れ、
慢心から離れて自分をみることが出来ません。
これが私たちの常識を曇らせる「慢心」です。
常識の枠に囚われていると、
本当の自分の姿は見えてこないのかも知れません。
「常識」という街灯が照らす限界を知って、
自分や世界を見直してみる必要があるのかも知れません。
参考図書:小堺井敏晶『社会心理学講義』
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
