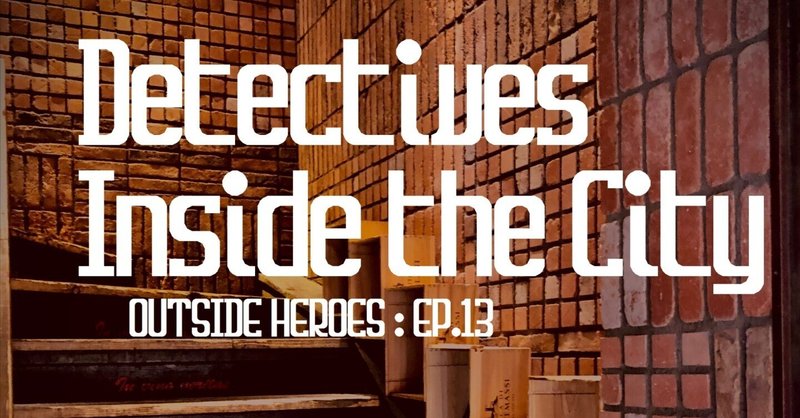
アウトサイド ヒーローズ:エピソード13-6
ディテクティブズ インサイド シティ 昼下がりのカガミハラ・フォート・サイト第4地区、歓楽街の片隅に店を構えるミュータント・バー“止まり木”。スピーカーから音量を絞ってゆったりと流れる、旧文明期のラグタイム。
耳を澄ませると壁掛け時計の秒針が時を刻む音が聞こえてくるようだった。アンティーク調の店内には客の姿も、女給たちの姿もなかった……カウンター席に腰掛けるスーツ姿の女性と、向かい合って座る女主人以外は。
「……ふう、美味しかった! ありがとうございますチドリさん、お店が休みなのに」
「ふふふ。せっかく様子を見に来てくれたんだもの」
食後のコーヒーをすすったアマネがカップをソーサーに戻しながら言うと、グラスを磨いていたチドリが微笑む。
「でも、うちのお店の料理もミール・ジェネレータで作ってるから、軍警察の食堂と変わらないと思うんだけど……?」
「えーっ、違いますよぉ!」
チドリの言葉に、アマネは笑う。
「あんなに殺風景なところで食べてたら、ご飯の味なんてどうでもよくなっちゃいますよ! 毎食毎食そんなだったから、もうそろそろしんどくなってきちゃってて……」
「あら、あら」
巡回判事の愚痴を聞いて、チドリが小さく笑う。食器を受け取ってカウンターの後ろに片付ける女主人の背中を見ながら、アマネはカウンターテーブルに頬杖をついた。
「あーあ、早く収まらないかなあ、“ミュータント風邪”」
「そうねえ。こればっかりは待つしかないから。今は補助金をもらえてるから、お店はなんとかなってるんだけど……」
蓋を閉じたピアノを見やって、女主人は小さくため息をつく。休業が続き、ショーを開けないのは歌姫にとって苦痛に近いのだろう。
「病院でも、新しい治療法を研究してるって話は聞くんですけどね。……あっ」
「えっ?」
思い出したように声をあげるアマネに、チドリは片付けの手をとめて振り返る。
「チドリさんは何か知りませんか? よく効く薬が出回っているって噂……」
「うーん、そうね……残念だけど、聞いたことはないかな」
「そっかあ……」
アマネは腕組みして「はあ……」と深くため息をつく。チドリは模造麦茶のグラスをカウンターに置いた。
「そういう噂話、キリシマさんなら詳しく知ってるかもしれないわね」
「うーん、探偵さんかぁ」
「あら、アマネちゃんは苦手なの、キリシマさんのこと?」
巡回判事は口を“へ”の字に曲げて「むうう」と唸っている。
「苦手っていうか、なんというか、私の方が探偵さんから避けられてるというか……ところであの人、お店が開かなかったらどうやって仕事してるんですか?」
「どうなのかしらねぇ。最近はよく、あちこちに行っているみたいだけど……あら」
乾いたドアベルの音が鳴る。店に入ってきたのは、洒落っ気のある派手なシャツにスーツを重ねた、義腕の探偵だった。
「チドリさん、ただいま戻りましたよ……っと」
キリシマはカウンターに陣取るアマネの顔を見て、ぎくりとして立ち止まる。
「どうかしましたか、キリシマ探偵」
「い、いや、どうもこうもあるわけではないんですがね。へへへ、失礼しますよ……」
巡回判事に白い目を向けられると、探偵はぎこちなく笑いながら店の奥にそそくさと引っ込んでいく。
「やっぱり、怪しい……」
「まあ、まあ。常連さんと店子さんだから、仲良くしてほしいのだけれど……」
チドリの言葉に、アマネはハッとして振り返った。
「ごめんなさい、私もちょっと、余裕がなかったのかも」
「余裕、って?」
チドリが尋ねかけた時、巡回判事の携帯端末機が鋭い呼び出し音を鳴らす。
「あっ、わっ、ちょっと待って……!」
慌てて通話回線を開く。表示画面には“軍警察 要請”の文字。同期していた軍警察の無線連絡網に、一斉に送信された出動要請だった。
「『第4地区周辺の捜査員に出動要請。現在、中央通り300番地近辺で暴徒が現れたとの通報を受けています。被疑者はミュータントの男性、長い尾と腕を振り回し、周辺の建物などを破壊しているとの事。第4地区周辺の捜査員は至急、応援に向かってください。繰り返します……』」
アマネはインカム耳に押し込むと通話回線を開いたまま、携帯端末機をポケットに仕舞いこんだ。
「それじゃあチドリさん、そろそろ行きますね」
「ええ。最近物騒だものね。気をつけて……」
「ありがとうございます」
立ち上がりかけたアマネはチドリの言葉に礼を言い、小さく手を振ると店を飛び出した。
扉が閉まると、チドリは小さくため息をつく。グラスを拭く作業に戻ろうとした時、カウンターの裏に置いていた通話端末機が呼び出し音を鳴らす。
「はい……あら、メカヘッドさん?」
受話器を耳に当てながら、チドリの眼差しは鋭いものに変わっていった。……すなわち歌姫としての顔から、PMCの社長としての顔へ。
「……わかったわ。みんなにも、お願いしてみる」
カガミハラ第4地区の大通りに集まった、軍警察の警備車両。通りを塞ぐバリケードの中、粘液に覆われたミュータントが鋭い声をあげた。鞭のようにしなる尻尾を振り回すと、周囲を囲んでいた透明のシールドをしたたかに打ちつける。
「うわっ!」
盾を持っていた警ら隊員が押されて怯むと、周囲の隊員たちが慌ててミュータントを押し返した。
「やめなさい!」
盾の壁の後ろから、黒髪の壮年男性が拡声器を使って叫ぶ。通報を受けて現場に駆け付けた一般捜査課のクロキ課長だった。
「KyaaaAAAhOoooh!」
盾の壁にはじき返されたミュータントは目を血走らせて牙を剥きだし、甲高い声で吼える。店のガラス窓がビリビリと音を立てて震え、血管が浮き出るかのような亀裂が走った。
「クソ、話が通じねえ……」
素早く盾の裏に引っ込んだクロキが歯噛みしてこぼす。捜査員の一人が、暴徒鎮圧用の拳銃をホルスターから引き抜いた。
「課長、発砲許可を!」
「許可する!」
引き金に指をかけると乾いた炸裂音と共に放たれたゴム弾が、ミュータントに向かって飛ぶ。弾丸は粘液の層を貫くが硬質化した皮膚に遮られ、跳ね返されてアスファルトに転がった。
「何だと!」
「ShyaAAAhOOOOOoooH!」
暴徒化したミュータントは鋭く吼えると口を開き、長い舌を伸ばした。舌は矢のような勢いで空を飛び、警ら隊の構えるシールドに槍のように突き刺さった。
「ひいいいいっ!」
「ビビるな! 距離を取って囲みなおせ!」
悲鳴をあげ、ざわめく隊員たち。クロキ課長は怒鳴りつけると、包囲網を作り直させた。
「クソ! どうする……」
「か、課長、駐屯軍本隊に支援要請を……」
手にしていたシールドに穴をあけられ、すっかり腰が抜けた隊員がすがるように言う。クロキは額に青筋を走らせながら吼えた。
「タワケか!」
「ひ、ひいい……」
「一般人相手に何考えてやがる……!」
すっかり縮こまった隊員に、クロキは苦虫を噛みしめたような顔で怒鳴った。
……とは言うものの、勿論このままにしておく訳にはいかない。
この数日間で連発している、ミュータントが暴徒化する事件。被疑者たちに関連性は見えず、今のところ原因は不明。
“ミュータント風邪”の流行によってミュータントたちに多くの偏見や敵意の目が向けられている中、この暴徒たちは大きな問題だった。
下手に高圧的な手段を取ることで、ミュータントに向けられる批判を強めることになってはよろしくない。だが、ならばどうすればいい……?
クロキ課長が警ら隊の作ったバリケードの中で立ち往生していると、ポケットに入れていた携帯端末が呼び出し音を鳴らす。
「誰だ、こんな時に……」
イライラしながら端末機を取り出すと、画面に表示された発信者名は“たわけ”だった。クロキは舌打ちをしながら、通話回線を開く。
「メカヘッド!」
「『はい、課長』」
回線の向こうから、ヘラヘラした声が返ってくる。
「はい、じゃねえんだタワケ! 動けるならさっさと応援に」
「『はい、向かわせてます! 安心してください、イチジョー副署長に話は通してありますから!』」
「はあ?」
メカヘッド巡査曹長が説明を軽く吹っ飛ばしながら元気よく答えるのを聞いて、課長は思わず威嚇するように訊き返した。
「何だって? 許可? どういうことだ、おい!」
怒りと呆れと困惑が混ざった声を聞き、メカヘッドは楽しそうに笑う。
「『ミュータントを制するには、ミュータントの力を使うのが一番ですよ、課長』」
「どういう事だ! 何をする気……ん?」
軍靴の足音が聞こえてくる。吼えるように怒鳴っていたクロキが驚いて周囲を見回すと、軍警察のバリケードを更に取り囲んで、黒尽くめの軍装を身につけた一団が集まっていた。
「こいつらは……?」
「軍警察一般捜査課長のクロキ警部三佐ですね」
「あ、ああ。そちらは……」
黒尽くめの集団の、リーダーと思しき男がクロキ課長に向けて敬礼する。クロキも反射的に敬礼を返した。
「我々は民間軍事企業“イレギュラーズ”所属の対ミュータント戦闘チームです! 地域貢献を目的に、軍警察の支援に入らせていただきます!」
銀色の手袋をした“イレギュラーズ”リーダー格の男は、クロキに敬礼したまま説明を続ける。
「あ、ああ……」
メカヘッドから最低限の連絡を受けていたクロキ課長が困惑混じりの相づちを打つと、リーダーは“イレギュラーズ”の隊員たちに向かって叫んだ。
「総員、作戦開始だ!」
(続)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
