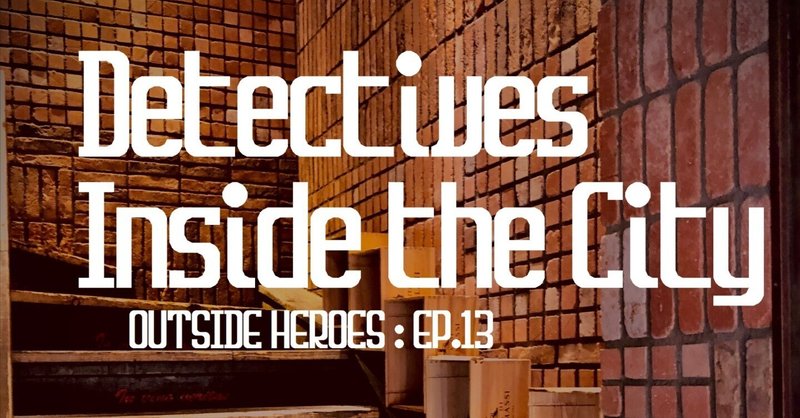
アウトサイド ヒーローズ:エピソード13-8
ディテクティブズ インサイド シティ児童公園の木立を揺らして舞い上がるとアパルトマンの屋根を飛ぶ、薄ピンク色の風。湿気を含み始めた晩春の空気を裂いて屋根の波を走っていき、路地裏に飛び込むと、つむじ風はピンク色の光の粒子となって消え去った。
「……ふう」
渦巻く風が消えた先、物陰の薄汚れたゴミ箱の上に立つのは、ぱりっとしたスーツに身を包んだ若い娘。ナゴヤ・セントラルの上級捜査官であることを示す、星型に開いた花のバッジが胸に輝いた。
管区の保安官・軍警察組織を監査する権限を持つ保安局直属のハイキャリア、巡回判事。普段の言動からは想像し難いが、滝アマネはその最年少任命記録を更新した俊才なのである。
「よっ、と」
足元に気をつけながらゴミ箱を飛び降りると、アマネは手に持った金属製のスティックを胸ポケットに収めた。
暴走ミュータントをなんとかしなきゃ、って問題は、“イレギュラーズ”のお陰でひとまずは何とかなりそうだ。その代わり“イレギュラーズ”の指導顧問を兼ねているメカヘッドは、しばらく軍警察とのダブルワークで身動きが取れなくなるだろうけど。
と、なると……
「ここからは、私一人でやるしかないか。さて……」
物陰から顔を出す。繁華街の片隅、レンガ造りの店に目を光らせる。
「……ひい、ひい」
しばらくするとやって来たのは息を切らせ、足をもつれさせながら走る、スーツ姿の男だった。男は勢いよく金属製のドアを開け、転がり込むように店の中に入っていった。
ミュータント・バー“止まり木”の重い扉が閉まると、昼前のホールに大きな音が響く。店に入ってきたキリシマは両膝に手を当てて、激しく空気を吐き出していた。
「ひい……はあ……」
「あらあらキリシマさん、どうなさったんです、そんなに慌てて」
顔を上げるとカウンターから心配そうにこちらを見つめる、黒いドレスの女主人と目が合った。
女給たちは掃除の手を止めて、心配と不信感をないまぜにしたような表情でこちらを見ている。……不信感の方が割合は多いようにも思えるが。
「はあ、はあ……あはは、すいませんチドリさん、大丈夫ですよ」
探偵は跳ね上がるように上体を起こすと、気丈に胸を張ってみせた。
「ホントですか?」
音もなく扉を開き、背後に立っていたアマネが声をかけると、キリシマは「ぎゃっ!」と短い悲鳴をあげてとび上がった。
「……なんだぁ、刑事さんか。驚かさないでくださいよ!」
「あら、これは失礼」
巡回判事はしれっと、さほど失礼さなど感じる素振りもなく返した。
「てっきり、何かとんでもないことをしでかして、慌てて逃げ出してきたと思ってました」
「根も葉もない中傷はやめてください! さすがにそれは、越権行為ではないのですか?」
「あら、これは失礼しました」
アマネの言葉に、キリシマは噛みつくように言い返す。巡回判事はこれにも動じず、カウンター席のスツールにさっさと腰かけた。
「おいおい刑事さん、まだ“止まり木”は営業自粛中ですぜ」
「いいんですぅ、これはチドリさんが好意でお昼ご飯を分けてくれてるんですから!」
すましてうそぶく巡回判事の前にドミグラスソースがかけられたオムライスが置かれた。湯気とともに広がる、ソースと玉子の香り。配膳した、灰色の外骨格をまとう女給が頭を下げる。
「ごゆっくりどうぞ」
「ありがとうございます! いただきまーす!」
手を合わせて元気に言うとアマネはスプーンで黄金色の小山を削り取って、大きく開いた口に放り込んだ。
薄焼き卵に包まれた熱々のピラフとソースが絡み合い、コクのある旨味と甘味と酸味が口の中に広がる。
「はふ、はう……美味しーい!」
「こんなの、店ひらいてるのと変わんないじゃねーか……」
呆れた表情でつぶやくキリシマに、アマネは「ちっ、ちっ、ちっ……」と舌打ちをして持っていたスプーンを小さく振ってみせた。
「ホールを私一人が使ってるのと、お客さんで一杯になっているんじゃ全然違いますー」
「そりゃ、まあ、そうかもしれないですがね……」
釈然としない顔のまま返す探偵を後目に、アマネはガツガツとオムライスをむさぼりはじめる。
「あむ、あむ……うふふ! チドリさん、美味しいですね、これ!」
棚に収まっていたグラスの個数を確認していたチドリが、振り返って微笑む。
「ありがとう、アマネちゃん。ミール・ジェネレータのレシピを色々調べてたら、たまたまできちゃったんだけど……。評判がいいなら、レギュラーメニューにするのもいいかもしれないわね」
「レギュラーに入れてくださいよ、これ! 絶対、また食べたいです!」
そう言って夢中で食べるアマネを見ていると、キリシマの胃袋が低くうなった。チドリが面白そうに笑う。
「あら、あら!」
「ははは、お恥ずかしい……」
探偵は鳴き声をあげる腹に手を当てて笑う。朝から色々あって……本当に色々とあって結局、飯を食べそびれていたのだった。
「キリシマさんもいかがです? “ピラフのオムライス”」
「……ありがとうございます、いただきます」
頭を下げて、アマネから2人分離れたカウンター席につく。腰を落ち着けるとすぐに女給がやってきて、水の入ったグラスとオムライスの皿を目の前に置いていった。
「ごゆっくりどうぞ」
「ありがとう、ございます」
先ほどまでオムライスをほおばるアマネを白けた目で見ていた身としては、少し居心地が悪い。探偵はぎこちなく礼を言うと、スプーンを手に取った。こんもりとしたオムライスを崩し、一口。
「……うまい」
様子をうかがっていたアマネが、ニコニコしながらうなずく。
「でしょう! そうでしょう!」
「ええ、こいつはいいや。チドリさん、確かにレギュラーいけますよ、これ!」
「それはよかったわ」
チドリは微笑んで返した後、小さく「ふう」とため息をつく。
「あとは、“ミュータント風邪”が落ち着いてくれればいいのだけど……」
誰に言うでもなく呟いた後、カウンター席に腰かけている巡回判事と探偵から向けられる心配そうな視線に気づいて、チドリは慌てて両手をパタパタと動かした。
「ごめんなさい、お店は大丈夫なのよ。ただ、なかなか“ミュータント風邪”がおさまらないのがもどかしくて。……最近は、別の問題も起きているみたいだし」
「急に暴れ出す、ミュータント……」
チドリのつぶやきにアマネが言葉を重ねると、キリシマはぎくりとしてスプーンを持つ手をとめた。
「あれは、“ミュータント風邪”の症状じゃないらしいですけどねぇ」
「でも、このタイミングで騒ぎになるのはちょっとつらいわね。まだ原因もわかっていないし……」
「そっちも早く、落ち着いてくれたらいいんですけど……」
チドリとアマネが話し合っている間、黙りこくったキリシマは食べかけのオムライスをじっと見つめていた。
「……ごめんなさい、愚痴につき合わせちゃって。それじゃあ、私は部屋に戻っているわね。食べ終わったら、食器は返却口に置いていってもらったらいいから」
「わかりました。ありがとうございます、チドリさん」
チドリは軽く会釈をすると、店の奥に引っ込んでいく。アマネは料理を平らげると、スツールに腰かけたまま上体を大きく伸ばした。
「うーん、困ったものよね。探偵さん、それで……」
物思いにふけっていたキリシマは、急に呼びかけられるとびくりと背筋を伸ばす。
「えっ、ええ、はあ、そうですね」
「ちょっと、大丈夫ですか? ボーっとしちゃって」
「えっ、ははは! 大丈夫ですよ、ははははは……」
探偵はわざとらしく笑った。巡回判事は相手の腹の底をのぞき込もうとするように、真っ黒い瞳を向けている。
「ふーん……?」
「大丈夫、大丈夫ですから! ……あっ、ところで何か言いかけてましたけど、どうしたんです?」
露骨に話題をそらそうとするキリシマ。アマネは「ふう……」と深呼吸すると、目の前の相手に鋭い目を向けた。
「ええと……刑事さん?」
「まず、お断りしておきますが、私はいわゆる“刑事”ではありません。巡回判事といいまして、軍警察の皆さんや保安官の方々を監査し、監督することが主な職務です。保安局に所属していますので保安官区では捜査権もありますが、軍警察が管轄するカガミハラでは捜査権も持っているわけではないので……」
「は、はあ……?」
女給たちもホールの掃除を済ませてバックヤードに引っ込んでいた。二人が黙ると、掛け時計の秒針が時を刻む音が妙に大きく、ホールに響く。
「それで……それが何か?」
「私は今、事件を追っています」
アマネはキリシマから目を離さずに話を続ける。
「この町を騒がせている……ミュータント連続狂暴化事件です」
「事件?」
探偵はことさらあっけらかんとした調子で返して、肩をすくめる。
「ミュータントが暴れている背後には、何か人為的な問題がある、と?」
「そうです。そして、どの事件も、原因は同じ……これを」
巡回判事は携帯端末を取り出すと、探偵にも見えるようにカウンターテーブルの上に置いた。
画面に表示されているのは、錆びついた塗料缶が転がる工場の裏手。汚れたアスファルトの地面に転がっていたのは……白いラベルが貼られた、ガラス製の小さな茶色いアンプルだった。
「こ、これは……?」
「オーサカ・セントラル・サイトの製薬会社が作った、“ミュータント風邪”の特効薬です」
(続)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
