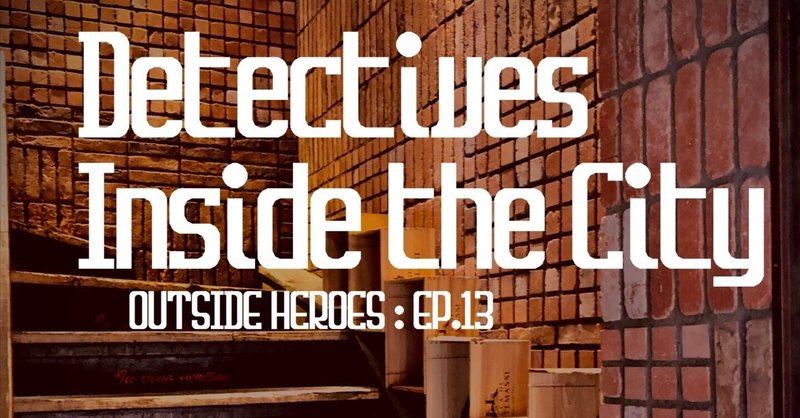
アウトサイド ヒーローズ:エピソード13-3
ディテクティブズ インサイド シティ「『済まないアマネ、しばらくカガミハラには行けなくなった』」
長距離通話端末の受話器から響く、青年の声。
「『今週末には交代するって話だったけど……』」
後ろで騒いでいる子どもたちの声が漏れ聞こえてくる。アマネの帰りを待ちわびている……というよりも、しばらくナカツガワの町から外に出られないことが不満でたまらないようだった。
「『おい、アキ、リン、ちょっと待って!』」
通話回線の向こうの子どもたちは、ますます元気に声をあげる。なんとかなだめすかそうとする青年の声を聞いて、アマネは「あはは」と笑った。
彼には悪いが、普段は落ち着き払っている男が、慌てふためいて子どもたちの面倒を見ている絵面を想像すると、何とも微笑ましい。
「仕方ないよね、“ミュータント風邪”が大流行りしてるんだもの」
そう、“重篤化因子”を持つミュータントの命をあっさりと奪う感染症が、流行りの風邪が広まるのと大差ないようなハイペースで広がっているのだ。ミュータントたちが暮らす町ナカツガワ・コロニーが、病禍が収まるまで門扉を閉ざすのも、仕方のないことだろう。
「『そうなんだよなあ、説明してるんだが、なかなか……あっ、こら!』」
「ん、レンジ君?」
青年の声が途切れる。どうやら、子どもたちが通話端末の受話器を奪い取ったようだった。ガサゴソと物が転がり、布がこすれ合う音が続いた後、子どもたちの元気な声が耳に突き刺さる。
「『おーい、アマ姉ちゃん!』」
「『ねえ、聞こえてる? もしもーし!』」
「はいはい、聞こえてるわよ、アキ君、リンちゃん」
アマネが応えると、子どもたちはキャッキャと笑い声をあげる。
「『今週はカガミハラに行けないなんて、退屈だよー!』」
「『アマ姉ちゃん、なんかお土産買ってきてよー!』」
「もう、アキ君ったらちゃっかりしてるんだから……いいよ、“ミュータント風邪”が収まってからね」
「『やったあ、絶対だよ!』」
「『待ってるからね、アマネお姉さん!』」
喜んで声をあげる子どもたち。どうやらスピーカー通話にしていたようで、後ろから「もうそろそろ、いいか……」と受話器を返すように促す青年の声が聞こえてきた。
「『はーい』」
「『じゃあ、アマ姉ちゃん、ばいばーい!』」
子どもたちが受話器を手放すと、再び青年の声に切り替わる。
「『やれやれ……まあ、こっちはこんな感じだ。今のところ、“ミュータント風邪”も入って来てないから、子どもたちも怖がっているというより不満ばっかりでなぁ……』」
「ふふふ」
手を焼いている様子がありありと聞き取れるため息に、アマネは思わず笑ってしまう。
「『本当はアマネの代わりに、俺がそっちに行っていた方が良かったんだろうけど……』」
「レンジ君はナカツガワのヒーローで、私はカガミハラを中心にしたこの辺り全部を担当してる巡回判事なんだもの、役割分担としたら、これが普通でしょ」
「『そういうことじゃなくて……』」
レンジが受話器の向こう側でモゴモゴと言っている。アマネが自らの正体を周囲に隠していることを知っているからこそ、はっきりとは言えない。その心遣いがありがたかった。
「私は大丈夫だから。それに、今からナカツガワに戻って、もしウイルスを持ち帰っちゃったら大変でしょう?」
「『それも、そうなんだが……気をつけろよ?』」
「ありがとう。レンジ君も子どもたちのお世話、頑張ってね」
「『おい、おい……それじゃあ、な』」
ふつりと通話回線が切れる。静かになった受話器を端末機の本体に戻すと、アマネは「ふう……」とため息をついた。
途端に耳に入ってくるキーボードの打鍵音、打ち合わせをするささやき声。カガミハラ軍警察庁、一般捜査課の事務室は退勤時間も迫っているというのに、仕事を続ける捜査官たちが右往左往していた。
「ご連絡は済みましたかな、巡回判事殿」
そして目の前には芝居っけたっぷりに胸を反らし、こちらにコーヒーカップを差し出してくる機械頭の男。
「ありがとうございます高岩巡査曹長、長距離回線を使わせていただいて……どうも」
「親しみを持ってメカヘッドと呼んでいただきたいのですがねえ」
機械頭の男の愚痴を聞き流し、アマネはすまし顔でコーヒーカップを受け取った。ちびりとすすると目を白黒させる。
「あっつい!」
「おや、巡回判事殿はネコ舌でいらっしゃいましたか」
「それにこれ、コーヒーじゃなくてムギ茶じゃないですか!」
「おやおや、コーヒーなどとは申し上げておりませんが? こんな遅い時間にカフェインを摂るのはよろしくなかろう、というただの老婆心ですが、不愉快な思いをさせてしまっては申し訳ない」
「あー、もう、この……!」
ぺらぺらと言葉を連ねるメカヘッドに、アマネが顔を真っ赤にして震えている。少し離れた席に腰かけていた課長が鋭い眼光で男を睨むと、メカヘッドは「ははは……」とごまかし笑いを漏らしながら両手をこすり合わせた。
「申し訳ありません。すぐに新しいコーヒーを」
「結構ですっ!」
巡回判事はぷりぷりしながら、少しずつ模造麦茶をすする。一般捜査課長はメカヘッドを睨んだまま口をパクパクと動かした。
“し”、“ま”、“つ”、“しょ”。
より上位の組織から派遣されてきた監査役をおちょくって笑っていれば、当然の結果だろう。むしろ始末書で済めば御の字といったところか。……メカヘッドは、先の事は考えないことにした。
「ええと、その……お疲れ様です、こんな大変な時期に」
「本当ですよ、まさか“ミュータント風邪”なんてものがいきなり流行りだすなんて!」
アマネはそう言うと、随分冷えてきた模造麦茶をぐい、と飲み干した。
「おかげでしばらくナカツガワに帰れなくなってしまったので、これを機会にカガミハラ軍警察のお仕事っぷりを、しっかり拝見させていただきます」
鋭い視線と共に、カップをメカヘッドに突き返す。
「……主に、高岩巡査曹長の素行についてですが」
「え、ええっ、俺ですか? そんな、こんなに真面目に仕事に励んでいるというのに。ねえ課長……」
ちらりと見やると、課長はそしらぬ顔でそっぽを向いた。もちろん、他の捜査官たちも顔を背ける。
「そんなあ……」
もみ手をしながら居心地悪そうに身体をくねらせるメカヘッドに、アマネはずいと顔を近づけた。
「だいたいあなた、叩いたら出るホコリが多すぎます。これまでにも数々の独断専行、無断の独自捜査に、法に触れるような行為も……」
「それは、全てきっちり報告しておりますし、内部には始末書という形で」
「事後報告で説明責任を果たしているとお思いですか! まあ、説明をできなかった事情があったことも、わからなくもありませんが……」
アマネはぴしゃりと一喝したあと、少し譲歩するように言葉を濁す。
この機械頭刑事は全く持って信用がおけないし、実際にこれまでも散々“やらかして”きた。……けれどもその“やらかし”にも理由があったし、それがなければ解決しなかった事件も、防ぎきれなかった惨劇も沢山あったに違いない。
……もちろん、だからと言って放置しておいていいわけではない。巡回判事・滝アマネはそう考える。
「そうなんですよ! こちらとしても内密で事を進めるのは本来許されることではないと思ってはいるのですが、機密性と確実性を確保するためにどうしても仕方がないと、毎回断腸の思いでですね……」
「高岩巡査曹長」
「あ、はい」
調子に乗って再び捲し立て始めたメカヘッドを、アマネがぎろりと睨みつけた。機械頭の不良刑事は、ぎくりとして背筋を伸ばす。
「あなたの起こしてきた数々の問題行為は功績や、あるいは昇進差し止めの措置と引き換えに帳消しになっているわけではありませんよ。だいたい、最近の事件でも反社会組織の内通者を保」
「わあっ! わあっ!」
メカヘッド巡査曹長は慌てふためいて、両手をぱたぱたと振り回す。どうやら、キリシマ探偵の一件はまだ課長にも伝えていない事柄らしかった。
「ええとですね、その、“入院患者の付き添い”につきましては、今はまだ様子を見ておこうというか、えー……」
知らんぷりを決め込んでいる課長をチラチラと気にしながら、もごもごと口の中で言う不良刑事。巡回判事はため息をついた。
「……まあ、いいでしょう。しばらく時間はありますから、じっくり見させていただきます。今日はもう遅いですし……あれ?」
夕焼け雲が濃紺の夜闇に呑まれようとしている窓の外を見やると、大通りを走る人影に気づいてアマネは言葉を切った。
「どうしました?」
「いえ、そこをキリシマさんが通っていって」
「よく見えましたねえ、こんな暗い中で」
釣られて窓を見たメカヘッドが、感心して声を上げる。
夕方から夜へと切り替わる、陽の光が去って街灯りもつかぬ、最も暗い瞬間。黄昏時とはよく言ったものだ。オフィスビルの階上からでは、通りを歩く人の顔は判然としなかった。……常人にとっては。
「そうですねえ、気のせいだったのかも。……では、失礼しますね」
「はい、それでは巡回判事殿、しばらくご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくおねがいしますね」
慇懃無礼な声を背中に浴びながら、滝アマネは一般捜査課の事務所を出る。
脳裏には、大股で通りを歩き去っていくキリシマ探偵の、何かに追われているような表情が妙に生々しくこびりついていた。
滝アマネは常人を装いながら、文明崩壊後の世界を生きるミュータントである。食肉目の獣に近い構造をした彼女の特殊な眼球は、闇の中で僅かな光を手掛かりに、蠢く者の姿を鮮明に捉えるのだ。
(続)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
