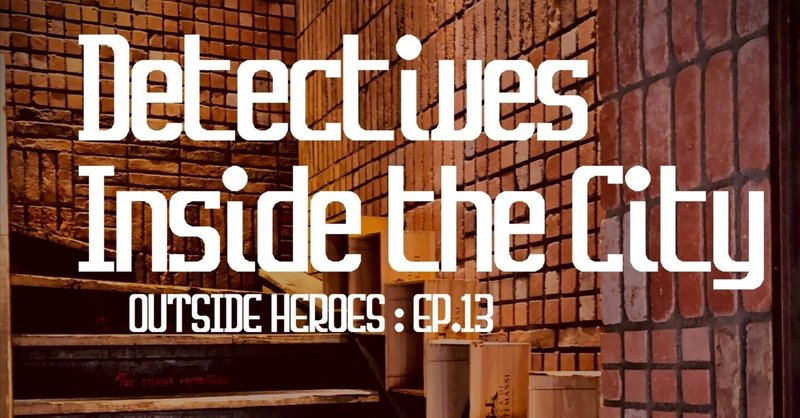
アウトサイド ヒーローズ:エピソード13-14(エピローグ)
ディテクティブ インサイド シティ「ごちそうさまでした!」
真っ白いベッドの上でキシメン・ヌードルを勢いよくすすっていたアマネが、空になったボウルをテーブルに置いた。きびきびと歩き回りながら病室の片付けをしていたナースが、入院患者の声を聞いて振り返る。
「あら、もう食べちゃったんですか!」
「えへへ、昨日は一日点滴だけだったから、つい……」
アマネは恥ずかしそうに笑いながら、空の食器を手渡した。小柄なナースは微笑んでボウルを受け取り、入り口近くに停めていたワゴンに載せる。
「食欲があるのは大変結構なんですけどね。回復しきってるわけじゃないんですから」
「はーい、気をつけます」
ナースの言葉に、巡回判事はいたずらがばれた子どものように返した。
「まったく……結構、危ない状態で運ばれてきたんですよ、巡回判事さん。こんなに早く元気になるなんて、ちょっと信じられないくらいなんですから。もっと自分の身体をいたわって……あら!」
早口で小言を漏らし続けていたナースは、ワゴンに置いていた自らのメモに気づいて声を上げる。
「何か、ありました?」
「面会の希望が入っていたの、お伝えするのをすっかり忘れてました!」
「面会……いつですか?」
ナースはメモを取り上げ、パラパラと手繰った。
「あと30分以内です。面会希望者の名前は、ええと……」
慌ててしらべている間にアマネは手鏡を使い、さっさと前髪を整えていた。入院着と後ろ髪の乱れも手早く直して、にっこりと笑う。
「できました!」
間髪入れずに響くノックの音。ナースは患者を一瞥した後、慌てて病室の扉を開けた。にゅうと顔を出したのは濡れるような黒髪の、強面の中年男性だった。
「失礼しますよ」
胸元に輝くナゴヤ・セントラル防衛軍の階級を示すバッヂと、軍警察所属を表す徽章。ナースは目を丸くして直立した。軍の看護学校を出ているため、反射的に体が動いてしまうのだろう。
「ご苦労様です!」
「ナースさんの方こそ、ご苦労様です。私のことは、お気になさらず」
強面の男性は穏やかな表情でナースに伝えると、ベッドの上のアマネに声をかけた。
「巡回判事殿、大変でしたな! まさか路上で倒れるとは……」
「えっ! 巡回判事? この子が……?」
ナースは目を白黒させながら、軍警察のお偉方と思われる男性と若き巡回判事を交互に見やった。巡回判事・滝アマネはばつがわるそうに笑う。
「えへへ、ありがとうございます、クロキ課長。ちょっと調子が悪かったところを、無理しすぎちゃいまして」
「“ミュータント風邪”は油断していると危ないですからね。それにしても、ミュータントじゃない方でも重症化するとは……」
「あはは……」
「問題は重症化する因子を持っているかどうかですからね。ミュータントの特徴が出ているかどうかは関係ないんですよ」
気を取り直したナースが説明すると、言葉を濁して笑っていたアマネはホッとため息をついた。
「まあ、油断大敵ってことですね。ところで、クロキ課長はどうして面会に?」
「どうして、って……」
クロキは困ったように笑い、後ろ手に持っていたカードと小さな花束を差し出した。ナースが「まあ!」と楽しそうな声を漏らす。
「巡回判事殿の監査期間終了の記念に、一般捜査課一同からです。……入院見舞いになってしまいましたけどね」
「ありがとうございます」
アマネが花束を受け取ると、クロキ課長は病室を軽く見回した後、自らの仕事に戻っていたナースに声をかけた。
「ところでナースさん、ホソノ医師はどちらへ?」
「ホソノ先生は、一昨日“帰られました”」
ナースは淡々と応えた。
「アマネさん……巡回判事様の診察と処置をした後、“ひとまずの役割は果たした”とおっしゃられまして……」
「そうか」
クロキ課長は短く答える。宿直室に住み込みで働いていたドクター・ホソノが帰る先は自宅ではなく、軍警察が用意した社会復帰支援施設だった。
「今回の“ミュータント風邪”を治療することに多大な功績があったとのことで、是非お話してみたかったが……」
「怪しいルートで薬を仕入れて、その責任を全部背負いましたからねえ。私もお陰で助かりましたが……」
「施設に戻されるのは仕方なし、か……」
むっつりとつぶやくクロキ。アマネは目覚めた時には既に結着を見ていた問題について、今さらキリシマ探偵の名前を出すわけにもいかず、言葉を探しながら課長の顔を見ていた。
「ええと……あっ、そうだ、カードもありましたよね! ありがとうございます」
「いやあ、お恥ずかしい話ですが無骨者ばかりで、気の利いた言葉などは書けませんでしたが……」
頭をかくクロキ課長。カードに書かれた捜査員たちの寄せ書きに目を落とすと、アマネはくすりと笑った。
「ふふっ」
「どうしました?」
「いえ、これ。なんだかおかしくなっちゃって」
カードの隅に書かれた、真面目な見舞いのコメント。その下に、メカヘッドの署名があった。
「『お前たち、死ぬ気で逃げろ! 死ぬ気で闘え!』」
軍警察の再先任巡査曹長にしてPMC“イレギュラーズ”の軍事顧問・メカヘッドが通話回線越しに怒鳴る。
「『これは演習だから、どうやっても死なん! だから……安心して死んで来い!』」
「んな、無茶苦茶な……」
インカムから飛んでくるとんでもない言葉に、有鱗ミュータントの新兵が愚痴る。
遠くで鳴り響く破裂音。乱れて散らばる軍靴の音。鬨の声……のち、野太い悲鳴。
簡略化された造形の建物が並ぶカガミハラ基地の演習場は、戦場のようなひりついた空気で満たされていた。
「ナマ言ってんじゃねえぞルーキー!」
隣で小銃のマガジンを交換しながら、銀色のグローブをつけた小隊長が吼える。
「テメエの歓迎会をやってやろうってんだ、気合い入れろ!」
「そんなぁ……」
「『第2班、ミワ隊、全滅!』」
演習のオペレーターにしてチューター(教官役)のメカヘッドが容赦なく戦況を告げる。
「『残りは第1班、カジロ隊! いいか、これは新兵だけの演習じゃない! 生存レコードを更新しなけりゃ、全員に追加訓練だからな!』」
「ちくしょう、チューターのやつ、こっちの話も聞いてやがるな! ……ほらよルーキー!」
カジロは吐き捨てるように言うと、新人に銃を手渡した。
「テメエの分もやっといた! 次からは自分でなんとかしろよ!」
「オ、オスッ!」
「じゃあ……死にに行くぞお前ら!」
「そんな、カジロ班長も大げさな……」
新兵がそう言った途端、盾代わりにしていたコンクリート造りの壁が粉々になって弾けた。数人の班員が、衝撃を浴びて吹っ飛んでいく……負傷判定を下すまでもなく、演習からのリタイアは確実だろう。
「きゃあああ!」
新兵は少女のような悲鳴をあげる。壁に開いた大穴から現れたのは、鈍い銀色の装甲に身を纏った人影……
「どうも、新人さん。確か、クサカ君といったか」
全身に走るラインが、青から金へとグラデーションしながら光る。隙のない身の構えと気迫とは裏腹に、装甲スーツを身にまとった男の声は驚くほど穏やかだった。
刃のような牙と強固な鱗、堂々とした体躯を持つはずのルーキーは、目の前の男から放たれるプレッシャーにすっかり縮みあがっている。
「ひゃ、ひゃい!」
「先日は大いに暴れ、相当な強さだったと聞いている。……だから俺も、本気でいくとしよう」
両の握りこぶしから、踏みしめた両脚から電光が走った。
「おおおお手柔らかに、お願いします……」
「構えろ、ルーキー!」
怯えながら口走る新人の声に、かぶせるようにカジロ班長が叫ぶ。
生き残っていた班員たちは装甲スーツの男を取り囲み、銃を突きつけていた。
「オラアッ!」
引鉄に指をかけようとした時、装甲スーツは電光の尾を描きながら腕を振り抜いた。パワーアシストをのせて加速した砂粒が丸い軌道を描いて飛び、極小の散弾となって包囲していた班員たちの銃を撃ち抜く。
「クソッ、ナイフだ!」
班員たちはあっさりと銃を捨て、刃先にマーキング塗料がべったりとついた演習用ナイフを構えた。
「動け、動き回れ! とにかく逃げろ!」
ナイフを構えながら演習場内を走り回る班員たち。銀色のパワードスーツは稲妻のように走り、一人、また一人と打ち倒していく。
「ルーキー、お前も走れ!」
カジロは腰を抜かしていた新兵の手を持って引き上げると、並んで走り出した。
「ともかく時間を稼ぐんだ! ワンチャン仕留めようだなんて考えるなよ!」
「考えてないっすよ、とてもじゃないけど、そんなこと!」
新兵は必死になって走りながら、班長に怒鳴り返す。
「それより先輩こそ、両手から出る電気ショックでなんとかしてくださいよ!」
「あの人相手に効くわけねえだろ!」
言い合いながら走る二人の目の前に、地響きを立てて落下してきたもの。砂煙の中、電光が火花を散らす。
「ひっ……」
悲鳴をあげる間もなく、新兵の視界が真っ暗になった。ちくしょう、とんだ就職祝いじゃないか。
「お前さんも随分な目にあったな。詫びといっちゃあ何だが、新しい勤め先の“ツテ”を紹介しようと思ってなぁ。なかなかいい職場だと思うぜ……」
ヘラヘラとした調子で“イレギュラーズ”への就職を斡旋してきた男の声を思い出し、毒づきながらジャノメは意識を失った。
ランチタイムの営業時間も終わりに近づいた、ミュータント・バー“止まり木”。午後の穏やかな空気に、ピアニストが指慣らしに奏でるエチュードが溶ける。ホールの片隅、薄暗いボックス席にスーツ姿の男が収まっていた。
背中を丸めながら、小型端末機に向かう。レトロスタイルのキーボードは、一文字打つたびに乾いた音を立てた。
「……ふう」
コーヒーをすする。画面に表示された文章に目を走らせて、一息つく。
打ち込んでいたのは、誰に見せるでもない報告書。非合法取引シンジケート“ブラフマー”構成員のジョウジ・キリシマがオーサカ・セントラル・サイトの製薬会社が死蔵していた薬品を非正規のルートで買い付け、カガミハラ・フォート・サイトの医師に秘密裡に売りつけた事件の、嘘偽りない一部始終。
「“ミュータント風邪”が落ち着いたら、また施設に戻ろうと思っていたんだ」
老医師の言葉を思い出す。最後の暴走ミュータント……クサカがカガミハラ軍病棟に運び込まれた次の日、いつもの取引場所にやってきたドクター・ホソノは、キリシマが回収した特効薬を受け取った後、ぽつりぽつりと話していた。
「久しぶりに“外”に出て、患者を診るのは楽しかった。こんな大変な案件に出会って、四苦八苦するのも、やりがいがあって楽しいものだ。ただ……」
細身の医師はうらぶれた地下休憩所のベンチに腰掛けると、小さな肩を丸めてため息をつく。
「どうしても私は、外の世界でやっていける気がしなくてね。これまではそんなこと、考えもしなかった。ただ目標のためにがむしゃらになって……」
足元に落とした視線は、どこか遠くを見ているようだった。
「充実していた。夢があった。ただ、ひたすらに楽しかった」
キリシマは閉じた口元を固く締めて、ただ黙っている。
「けれどねぇ、施設に入って色々見聞きするうちに、自分のやったことが色々な人を苦しめたことがよくわかったんだ。身近な人を傷つけ、苦しめてきたことも。……それでも、私は楽しかったし……私の生き方は、これ以外にはないだろう。だから、私は塀の中に戻った方がいいんですよ」
「ホソノ先生、あなたは、それで……」
尋ねかけた言葉が途切れた。ぽつり、ぽつりと話しているうちに、ホソノ医師の背筋は伸び、目には光が戻ってきていたからだ。
少し寂しそうに、けれども穏やかな笑顔を浮かべて、ベンチに腰かけていた老医師は探偵を見上げる。
「ええ。もし世の中に役に立つことがあれば、その部分だけ私を使ってくれたらいい。少なくとも今は、自分にそんな力が少しでもあることを、とてもありがたく思っているのです」
壁掛け時計が、ゆっくりと鐘を鳴らす。物思いにふけっていたキリシマは顔を上げ、再び手元に置いていた端末を見た。
「俺は……」
脳裡に浮かぶのは、薄桃色の肌をした娘のあどけない笑顔。
遠くでドアベルが乾いた音を立てる。
「いらっしゃいませ、ようこそ“止まり木”へ……えっ? あら、そうなんですね。少々お待ちください……」
対応に出る女給の声。探偵が右から左へと、ぼんやりと聞き流していると、
「キリシマさーん」
入口付近で客と話し込んでいた四つ目の女給が、手を振りながらこちらに駆けてくる。
「お客さん、探偵さんにご用事ですって!」
「おーう、ありがとうよ、よっちゃん」
キリシマ探偵はこたえると、報告書のファイルを閉じた。
深呼吸、背伸び。そして両肩をごきり、と鳴らす。
「さて、それじゃ、お仕事しますかね……!」
(エピソード13;ディテクティブズ インサイド シティ 了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
