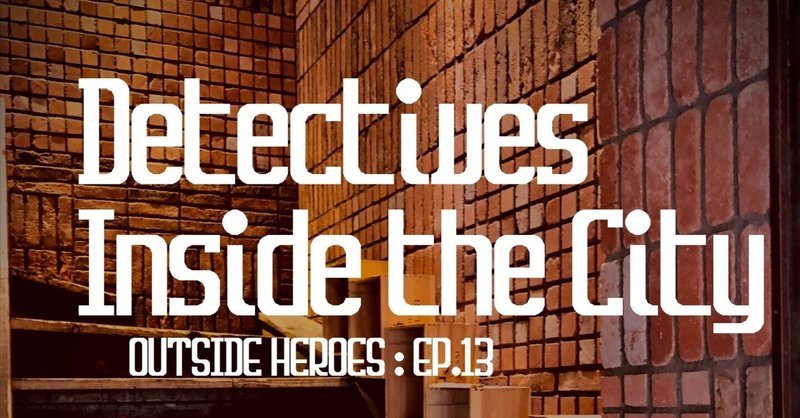
アウトサイド ヒーローズ:エピソード13-10
ディテクティブズ インサイド シティ「どうしたんだい、お昼ご飯はまだ……」
「しらばっくれんな!」
薄っぺらな模造タタミ・シートが敷かれた室内に上がり込むと、息子は激しくがなりたてた。
「探偵を使っただろう! テメエ何しやがんだ、このクソババア!」
若干呂律の怪しい悪態とともに吐き出される、酒臭い息。大柄な体がわずかに揺れている。昼間から相当呑んでいるようだった。
「すまなかったねえ、勝手に話して……」
「うるさい、うるさい!」
男はわめきちらしながら腕を振り回した。母親が持って帰ってきたランチボックスを吹っ飛ばす。タタミ・シートの上を転がるライスボール。落ちたボトルから蓋が弾け飛び、ミソ・スープが茶色の染みを作った。息子はむずかる子どものように、泣きの混じったうめき声をあげながら地団駄を踏みながら母親の居室で暴れ回る。
「ババア、俺の事を探り回りやがって! なんでだよ、クソ! ……うっ」
ひとしきり暴れると吐き気を催し、男は固まった。流し台に駆け込むと「うええ」とえずいた。胃袋に溜まっていたものがまき散らされる、不快な音が響く。
病床の母親は体を起こして、丸くなっている息子の背中を見つめた。
「あなた……」
「……辞めたことを、知られたくなかった」
荒れた喉から絞り出すように、息子が言葉を吐き出す。
「どうして、あんなに頑張っていたのに……?」
「ミュータントの子はミュータントだって……真人間の後輩にバカにされて、ついカッとなっちまって、暴れて……ボスにも詰められて、職場にいられなくなって……」
「あなたは頑張っているわよ、ミュータントだし、父親もいなくても、こんな私の子どもでも、普通の仕事につけたんだもの」
尋ねられた息子は、流し台にしがみつくようにしながら、訥々と話し始める。母親ははげまそうと声をかけるが、それが却って彼の逆鱗に触れた。
「うるさい! うるさいんだよ! そんな話、聞きたいわけじゃない! ……うぷ」
息子は怒鳴り声をあげた後、再び流し台に向かってえずいた。胃の中身は一回目でほとんど出し切っていたようで、吐き出されたのは苦しい息遣いと咳払いばかりだった。
「あの……」
掛ける言葉が見つからず、母親がうろたえる。息子は頭を抱え、噛み合わせた牙をギリギリと軋ませながら、小さくなっている母を睨んでいた。
「もういい! 何も聞きたくない! ……ぎ、ぎぎぎぎ!」
「大丈夫かい?」
「うるさい、飲み過ぎただけだ!」
うめき声をあげていた息子は頭を抱えながら吐き捨てるように吼えると、床に置かれていたマグカップを拾い上げた。
「あっ」
母親がとめる間もなくカップを傾けて、薬が溶かしこまれた白湯を一気にあおった。青い顔の息子は、人心地ついたようで深く息を吐き出した。
「ハーッ! ……出かけてくる。今日は、メシはいらない」
大柄な男は母親に視線を向けることなく言い捨てると、ふらつきながら部屋を出ていった。
激しく音を立てて扉が閉じられる。取り残された母親は、床にぶちまけられた昼食をぼんやりと見つめていた。
黒く垂れこめていた雲の中で低く雷が唸ったかと思うと、重い雫がぽつりぽつりとアスファルトを打ち始めた。
晩春の雨が降り始めた昼前のカガミハラ市街地、繁華街の第4地区。雨は瞬く間に勢いを増し、屋根や地面を激しく叩いていく。
傘も持たずに、軽い気持ちで第1地区の宿舎を飛び出したアマネは歩いているうちにすっかりずぶぬれになっていた。下着はもちろん、靴も、ストッキングの足裏もすっかり水びたしになってしまっている。
「やっちゃったなあ……」
雨の量は増え続け、アスファルトのところどころにできた水溜まりはいよいよ小川になり始めていた。足首まで水に浸かるのも構わず、しぶきをあげながらアマネは小走りで路地を進む。
こうなってしまっては仕方ない、さっさと“止まり木”に入ってしまおう。店に着いたら、シャワーは貸してもらえる、かな……
「あっ」
縁石の段差を越えようとして、足を持ち上げた時に感じるめまい。バランスを崩したアマネは、咄嗟に街灯のポールにしがみついた。
水溜まりに反射するオレンジ色の灯りが視界に二つ、三つと重なって揺れる。
「ああ……」
頭が割れるかのような痛みに襲われて、アマネは呻く。
足に踏ん張りがきかない。全身がひどく重く、だるく、力が入らないような感覚。額に手を当てると、雨に濡れた中で妙に熱く、顔全体が火照っているようだった。
「これ、は……」
よろめきながら歩くと、足裏がアスファルトを踏む感触が頭に響く。
これは、間違いないだろう。急に発症する、風邪のような症状。そして一気に重症化する。やがて患者をむしばみ、死に至らしめる……話には聞いていた“ミュータント風邪”の重症化事例。
“ミュータント風邪”の特効薬にまつわる事件を追いかけていて、まさか自分が身をもって味わうとは。
アマネは頭を抱えながら、“止まり木”めざして歩き続けた。
「ああああああ! がああああああ!」
雨に煙る町の中、獣のような叫び声が響く。そして鈍い衝突音。街灯のポールが溶けた飴細工のようにぐにゃりと曲がり、オレンジ色の灯りは数回明滅するとかき消えた。
「うあああああああ!」
街灯の支柱を折って暴れ、雄たけびをあげるのは巨漢のミュータント。全身を覆う鱗は急速に発達して棘のように尖り、牙も、爪も鋭く伸びてむき出しになっていた。血走った目は焦点が合わず、細長い瞳孔が自動機械のようにぐりぐりと動いていた。
鱗の鎧の下に筋肉が詰まった腕を振り回すとゴミ箱は叩き潰され、看板は吹き飛び、壁にヒビが入った。鱗の隙間からじわりと血が滲み、降り続ける雨に洗い流されていく。
「『とまれ! とまりなさい!』」
スピーカーからの叫び声。雨の中動く人垣。軍警察の警ら隊が展開し、狂暴化するミュータントの周囲にシールドの壁を張り巡らせていた。
「『ミュータントの方、落ち着いて! 声が聞こえていますか? 返事を』」
「あああああああああああ!」
クロキ課長が拡声器で呼びかけ続けるが、巨漢のミュータントには聞こえていないようだった。大きな口を開けて吼えると、シールドの壁に向けて突っ走る。
勢いよく人垣に突っ込むと、容易く数人を弾き飛ばした。
「うわああ!」
「『くそ、鎮圧弾発砲許可! 総員構え、撃て!』」
崩れたスクラムの中から次々と銃口が突き出し、暴徒鎮圧用のゴム弾が放たれた。
大口径の銃弾は硬質の鱗に次々と命中し、はじき返されてアスファルトに散らばった。ミュータントは振り向きもせずに走り去り、路地の中に消えていく。
「くそ、逃した!」
ずぶぬれになったクロキ課長は悔しそうに拡声器を投げ捨てると、通信端末機を取り出して通話回線を開いた。
「……イレギュラーズ、後は頼む!」
降りしきる雨が黒尽くめの軍装をしとどに濡らす。インカムからの声を聞きながら、PMC“イレギュラーズ”の部隊リーダー・カジロは路地の先を睨みつけていた。
「了解……と言ったものの……」
両肩に重くのしかかる雨水を手で払い落し、リーダーはため息をつく。
「どうしたもんかな……来るぞ!」
路地の先で重い物が激しくぶつかる音。カジロはシールドを構えて展開していた“イレギュラーズ”の社員たちに檄を飛ばした。
「総員、構え! 吹っ飛ばされたくなければな!」
家々の壁をえぐり飛ばし、道端に出されていたゴミ箱やドラム缶を弾き飛ばし、踏みつぶしながら筋肉の塊が突っ込んでくる。“イレギュラーズ”の盾持ち部隊は縦横に密着し、遥か太古のファランクスのごとく障壁を築き上げた。
「がああああああああ!」
雄たけびをあげながら突っ込んでくる暴走ミュータント。盾の壁一層目をめくり上げ、二層目を貫通し、三層目を突き崩すが、四層目は破られる寸前で持ちこたえた。
盾持ちの社員たちに取り囲まれ、暴走ミュータントは吼える。
「あああおおおお!」
「いいぞ、このまま押し込め!」
カジロが隊員たちに指示を飛ばす。重層の防壁を作っていた盾持ち部隊たちは、ミュータントを中心に閉じ込めて円陣を組む。周囲の隊員たちはミュータントに向けて銃を構えていた。
「トリモチ弾、撃て!」
一斉に放たれる特殊弾。盾の壁と押し合いを続けていたミュータントに命中すると、高粘度の塊になって腕や体にまとわりついた。
「やった!」
カジロがガッツポーズを作って叫ぶ。
「確保……」
「がああああああああ!」
「何!」
盾持ちの隊員たちの緊張が解けた隙をついて、暴走ミュータントが吼える。周囲の盾を巻き込んで固まりついたトリモチもろとも腕を振り回すと、隊員たちが吹っ飛んだ。
「クソ、これで動けるのかよ! 撃て! 今度はゴム弾だ!」
トリモチでくっつけられたシールドは、今や暴走ミュータントの武器であり盾になっていた。暴徒鎮圧用のゴム弾を弾き飛ばし、応戦する隊員たちを殴り飛ばしてミュータントは吼えた。
「があああ!」
「なんだよ、この筋肉オバケはよ!」
警棒を腰のホルスターから抜き出しながらカジロがこぼす。インカムがザリザリと音を立て、通話回線が再び開いた。闘いをモニターしていた、クロキ課長だった。
「『カジロ君、電気を使う技は使えないのか?』」
「無茶言わないでくださいよ、どこぞのヒーローじゃあるまいし!」
カジロは警棒を構え、カジロに言い返しながら駆けだした。
「こんな雨の中、感電しちまいますよ……っとおお!」
警棒を振り抜く。暴走ミュータントの腕に容易く弾き飛ばされると、カジロは大きく後ろに飛びのいた。
「やっぱり、こんなんじゃハナシにならねえか! クソ、来いやオラアア!」
カジロは叫び声をあげ、暴走ミュータントをひきつけて走り出した。一目散に走りに走り、細い路地に飛び込んだ。
「がああ、ああああああ!」
ミュータントは雄たけびを上げながら腕を振り回し、周囲の壁を突き崩す。引っかかっていたシールドが次々とめくれて、硬化したトリモチから剥がれ落ちた。
「ひっ、ひいっ、うおおおお!」
カジロは悲鳴をあげながら、拳の雨を逃れて走る。細い路地を走り抜け、反対のブロックに飛び出すと大声で叫んだ。
「ミワ、今だ! やれ!」
(続)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
