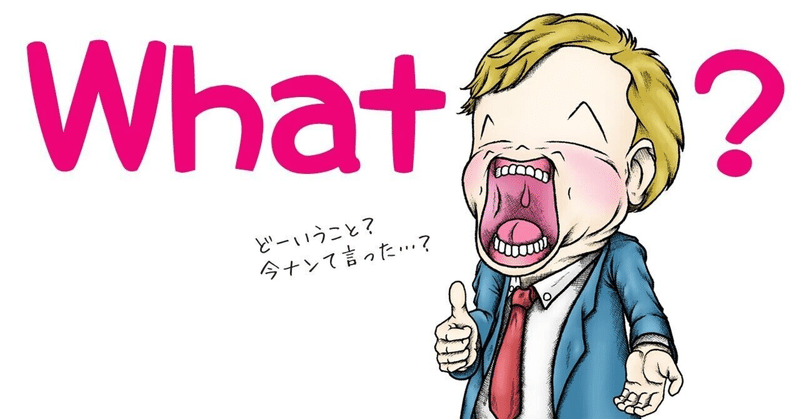
上場とM&A、M&Aの相手などで株価が大きく変わってくる理由
結論としては、買う側の目的と考え方が異なるから。
当たり前か。。
どの立場にしても、それが投資になるということは同じ。
なのでリターンを期待する。
期待するリターンの時間軸、大小などによって、株価の考え方は変わってくる。
上場の場合、市場に流通させた株式は転売されることが前提。
なので、株価変動への期待に対して値段がつけられる。
買収した企業をより高値で手放すことで利益を生み出すのが投資目的である、M&AにおけるPEファンドの立ち位置と似ている。
但し、上場株式市場での投資家とPEファンドは時間軸と期待するリターンの大きさに違いがある。
以前にPEファンドを運営する会社の上場は、短期的な株価の上昇を期待する上場株式の投資家と、中長期的な運用でより大きなリターンを得たいファンド自体の投資家との利害が反する可能性があるために珍しい、ということを書いたがそれと同じ。
時間軸と期待リターンの大きさに違いがあるため、それによっていくらなら投資しても良いという価格への違いが生じる。
時間軸が違うと必要なリターンが変わる。
年間10%の利回りを実現しようと考えたとして、1回の投資なら1回で10%を実現しないといけないが、10回の投資ならそれぞれ1%のリターンで足りる。
時間軸が短ければ、必要なリターンは小さくなるので、その分高い株価が許容されやすい。
M&Aで事業会社に譲渡した場合は、上場やPEファンドのように転売が前提とされない。
なので、取得したものをより高く売ろうということではなく、取得した事業が創出する利益を通じて投資のリターンを得る。
リターンを期待する時間軸が、上場<PEファンド<事業会社、という順になる。
リターンまでの期待時間軸が短いと高価格を許容しやすくなる。
上記の不等号順は高価格のつきにくい順とも概ね一致してくる。
ということで、上場とM&Aで価格が変わってくるのはそのような背景。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
