
【奇譚】南米唯一の君主制の起源 奴隷堕ちしたアフリカの王子、新大陸で奴隷たちの王になる
はじめに
歴史を紐解けば、奴隷から身を起こして君主になった人間は少なくない。その例として、エジプトのマムルーク朝や北インドの奴隷王朝の一部君主、(伝説上の存在ではあるが)第6代ローマ王セルウィウス・トゥッリウスが挙げられる。さすがに奴隷ほど低い身分からはそう頻繁には出ないが、貧農の末子として生まれて明朝を開闢した朱元璋(=洪武帝)など、賤民からの劇的な成り上がりを遂げた例はかなり多い。
逆に、生まれながらの君主一族が奴隷身分に転落した事例もある。具体的には、人身売買業者に捕らえられたイースター島の伝統的支配層や、靖康の変ののちに「洗衣院」と呼ばれる金王朝の官営売春施設に収容されて性奴隷として奉仕させられた宋王朝の女性皇族ら、イギリスのヴィクトリア女王に気に入られたエグバド族の王族サラ・フォーブス・ボネッタが挙げられる。
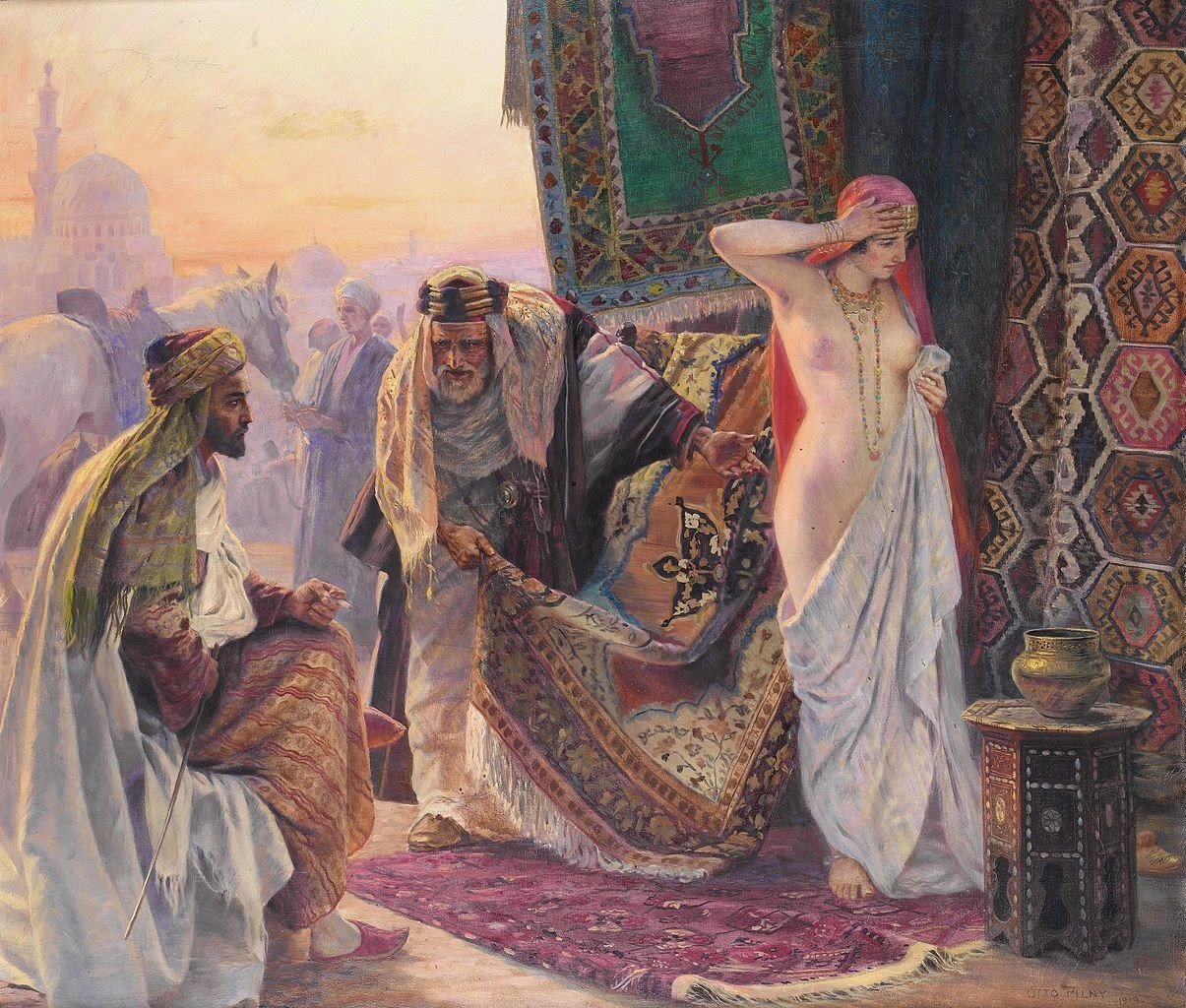
では、これら二つを併せた、生まれながらの君主一族が一時奴隷に身を落とした後に玉座に即いた事例はどうか。歴史上の実例をただちに挙げられる人はほとんどいないのではなかろうか。
歴史上の実例ではなく、伝説や民話、小説・漫画・ゲームなどの創作物の物語でもよいからそのような展開の例を示せと言われたとき、多くの人々が第一に思い浮かべるものは何だろうか。――おそらくは、国民的RPGシリーズの第5作目『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』の物語を思い浮かべる方が相当数にのぼるに違いない(1992年発売のレトロゲームなので遠慮なしに重大なネタバレをしてしまったが、もしも未プレイかつ今後プレイしようと思っていた方がおられたら申し訳ない)。
とある村長の息子である主人公が、魔物に拉致されて奴隷に身を落とす。のちに彼は自身がグランバニアの王子であるという出生の秘密を知り、叔父から王位を譲り受ける。――これ以上のネタバレを回避しつつ説明すれば、こんな展開を含むストーリーだ。
具体例がこれ一つだけではあまりに寂しすぎるので、もう一つ、伝説中の事例を挙げておく。『カンボジア王朝年代記』に語られるソコンナボット(Sokonthabat)王を弑逆したスダチ・コーン(Sdec Kon)という自称王は、一伝承によると、ソコンナボットの王子であったが、赤子の際に大魚に飲み込まれた後、奴隷夫婦に育てられ、父とは知らずに戦ったのだという。
このように、君主家という最上層階級に生まれて、奴隷という最下層階級への転落を経て玉座を得るという流れは、貴種流離譚の中でもかなり極端なタイプである。しかし、これはけっして創作物や架空の伝説・民話などの中だけの出来事ではない――。
アフリカ系ボリビア人の「王」
南米大陸の中央部に位置する国、ボリビア。かつての正式な国名は「ボリビア共和国」だったが、それを2009年に「ボリビア多民族国」へと改めた。では、どうして国名を変更する必要があったのか。

©David Liuzzo
ボリビアは、ケチュア人やアイマラ人、ヨーロッパ系や混血系など、多様な民族が同居する多民族国家である。「多民族」という語句を採り入れたのは、単一民族国家ではないことを強調するためだと推察できよう。しかし、なにゆえ「共和」という語句を削除する必要があったのだろうか。
「共和」削除との関連性は明らかでないが、実は、現在のボリビアには王が君臨している。といっても、王制に移行して「ボリビア国王」が誕生したわけではない。国内に抱える多くの民族のなかの一民族が、王を持つことを公認されたのである。
モチベーション維持・向上のために、ちょっとでも面白いとお感じになったらスキやフォローやシェアや投げ銭をしちくり~

