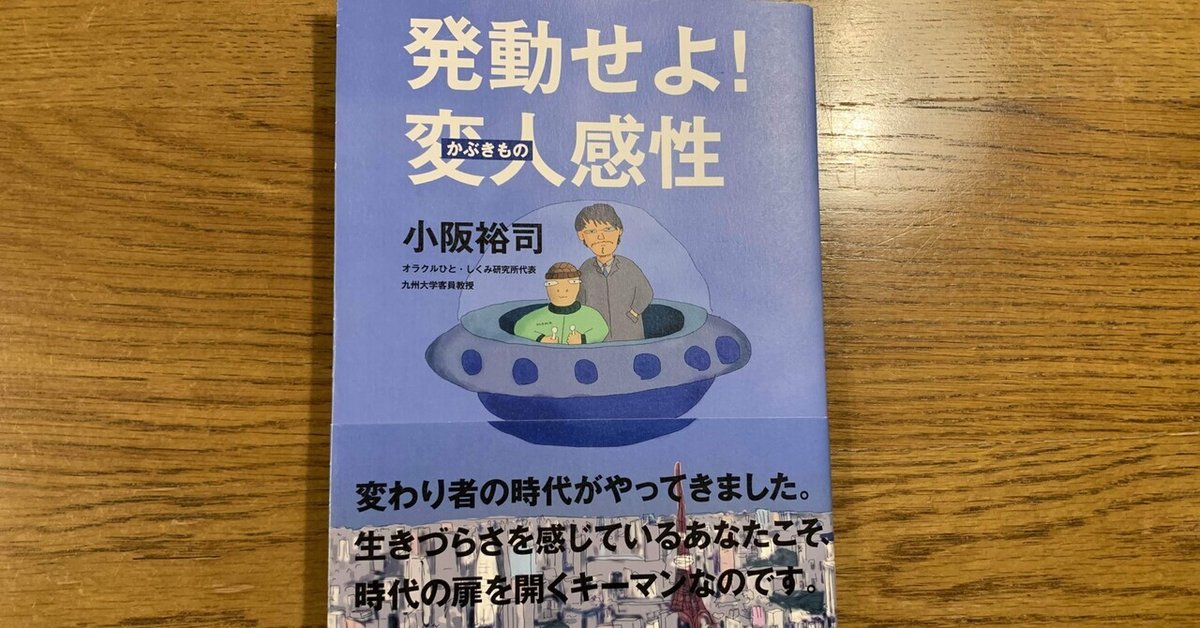
時代は偏差値から変差値へ-『発動せよ!変人(かぶきもの)感性』を読んで
以前から「考材シリーズ」が好きで『組織にいながら、自由に働く』を読みひっそりフォローさせていただいていた楽天大学 仲山がくちょ。
先月から #オンライン読書会開発部 がスタートし、参加しています。(ついに明日が最終回!)
がくちょが少し前にSNSでシェアされていたことで気になったのがこちらの本。
その名も『発動せよ!変人(かぶきもの)感性』。
「できない」「変」に悩んだ私の子ども時代
「変わってる」「浮いてる」「変」は、たいていネガティブな意味で使われることが多いです。
私の両親は村社会で静かに暮らすものの、ふたりとも内心「周りに無理にあわせなくていい」「自分の好きを大事に」という考え方をしていました。
そのため、特に勉強しなさいとか習い事をしいられることもなく「全部平均点より凸凹があっていいじゃん」とか進路についても特に口出しされたこともありません。「自分のやりたいことをやればいい」と言ってくれたので、かなりのびのびと育ててくれた気がします。
学生時代に美術を少し勉強した母は、母自身が万年ショートヘアにパンツスタイル、メンズっぽい感じを好んでいました。
そのため外見の面で、私も子どもの頃は母の好みのショートヘアに原色の服。
田舎では、見た目でも静かに浮く(笑)。
↓ 20代の頃の私の母

↓ 原色の服。たとえばこんな感じとか(笑)

少年のようだったので「おとこおんなー」「ブス」「バーカ」などと言われることも多く、また男子のケンカに巻き込まれることも多い子どもでした。一番痛かった記憶があるのが、顔面に回し蹴りを食らったとき(笑)。
そのうえ、運動も苦手、算数も苦手という弱点も重なり、「できない」扱いもされやすかった。とりあえずコンプレックスのかたまり。
また小学校高学年で反抗期が来て、当時の担任の先生には、いちいち反抗し結構迷惑をかけた気がします。廊下にも何度も立たされたりと、ちょっとした問題児でした。(一方でその先生とだけは、いまだに年賀状のやり取りをしています。)
その後、中学に入り、きっかけがあってスイッチがはいり、成績があがると周りの見方がガラッと変わるという経験があったりします。
そんな感じで、子どもの頃からいまに至るまで「できない」「変な人」という扱いはそれなりにしてきた気がします。
気になる本の内容は?
本の話に戻ると、この本はビジネス「絵本」という、これまた変わった装丁。
周囲から浮く人がなぜ浮くのか?
普通の人が疑問を持たずに受け入れてしまうモノやコトに違和感を覚えるからという話からスタートします。
その変人性につながる視点や感覚がどこから生まれるのか?という話では、源泉となるのは「感性」という話。
感性が豊かかどうかにいちばん影響するのは幼少期の過ごし方なんだとか。
息子にも「なんで?」「どうして?」と聞かれまくっていて、毎度答えを絞り出したり、なんでかね〜?と話をするようにしているのですが、これが大事らしいです。私自身も「なんで?」「どうして?」と聞きまくって、祖母や両親に答えてもらったり、いろいろ日常の体験を通じて教えてくれた気がします。
感性が豊かな人が「変わり者」と呼ばれ、生きづらい思いをするのはなぜか?
「常識」「当然」「絶対」という言葉を掲げ、「考えること」や「感じること」をさぼっているひとが大勢いるということ。この「同調圧力」で、「協調性をもて」「空気を読め」となる。
日本が物質的に豊かな国になるためには効率性と生産性が重視されてきて、指示に従い、結果を出すのがよいとされ、規律に従わない、はみだす人は矯正される教育方針がとられた。
ただ物質的に充足した日本がこれからどこに向かうのか?
考えない、感じない人たちの努力はどこに向かうのでしょう?ということ、
その壁を乗り越えるのに感性の時代が来ているということが絵とともに書かれています。
個人の好きにフォーカスするとターゲットが限定される、なんて古くさい人たちは言うかもしれませんが、確固たる購買動機があるぶん低価格競争とは無縁。
むしろ特定多数に圧倒的な支持を受けられる。
ワンアンドオンリーの競合優位性が生まれるんです。
(小阪裕司(2014),『発動せよ!変人(かぶきもの)感性』プレジデント社 p.44より)
上の引用は中にちょこっと出てきた話。
私もいま特定多数から支持されるという方向から考える ファンベースをしていることもあり、ここまでの流れをうんうんと思いながら読みました。
感性の豊かさを育てるには?
私自身も今、育児中。
自分自身も凸凹だらけなので、子どもにも好きな事をのびのびと楽しんでもらえるといいな~と思っています。
本の中で感性を育てる「原体験」についての話も紹介されています。
夕陽をみたことがない子どもが増えているという現象を挙げましょう。
教育現場で問題になっているのですが、授業で「夕陽の美しさ」をとりあげると、夕陽を見たことがないと答える子どもが少なからずいるそうです。
(中略)
単純に彼らは「夕陽は美しいものである」と認識する原体験を持っていないだけなのです。
たとえば幼少期にお母さんと散歩しながら夕陽をながめ、「きれいだね」「ほら、ススキにキラキラ反射しているよ」と感性のスイッチを押してもらっていれば、その日から夕陽を見るたびに「夕陽はきれいなもの」という感性が育まれます。
しかし、親との関わりが少なく、こうした原体験を持たない子どもたちが増えているため、夕陽の美しさどころか、夕陽の存在さえ認識していない子どもが増えているんです。
このお話からも分かるように、変差値の源泉となる感性はスイッチを押すほど養われます。
(小阪裕司(2014),『発動せよ!変人(かぶきもの)感性』プレジデント社 p.98-99より)
山に囲まれた地方で育った私は、冬の日に山並に夕陽が落ちていくところや、天使のはしごがでているところをよく眺めていました。車に乗っているときに母ときれいだねぇ~なんて話もしたなと思いだしたり。
↓ 家族で車で北海道に出かけたときの函館の夕焼け

「できない人」のレッテルを超えるには?
正直私自身、算数が苦手だったり、運動も苦手だったりして小学生の頃は完全に「できない人」のレッテルを貼られていました。高学年の頃に球技でボールが落下しそこにいた先生含めて笑われ悔し泣きしたこともありました。
「できない人」と言われてきたから思うのですが、最初から「できない」と周りに扱われ続けると「自分にはできない」とか「自分なんかどうせ」みたいな方向にいきがち、というか私はそうでした。
このセルフイメージを乗り越えるのにすごく苦しんだ気がします。
教育現場で行われている測定方法では限られたインテリジェンスしかはかることができません。
それなのに、できる人、できない人のレッテルを貼り、それを生徒たちに信じこませてしまう。
非常に恐ろしい行為だと思うんです。対抗手段はひとつ。
自分を信じることです。
学校の成績が悪かったって気にすることはない。
たまたま自分のインテリジェンスが学校教育とは別のところにあると信じることが大切だし、それは実際にそうなのです。(p.108-109)
はかりやすいモノサシではかるほうがわかりやすい。
だから、周りにしても本人も「できる」「できない」とか「既存のモノサシ」で他人と比較して一喜一憂します。
勉強ができるできない、運動ができるできない、かわいいかわいくない、モテるモテない、お金があるない…とかとか目に見えるものを手に入れること=幸せだと思ってしまう。
子どもの頃は「いつか見返したい」と思い、「見返す」(人と比べて)というものにがんじがらめになっていました。
だからかなり苦しかった。たとえ努力し手に入れても、比較をし続けているから心はずっと満たされない。
私はたまたまその価値観で臨んだ就職活動でもがき苦しんで、人からみてどうか?でなく、自分が好きと思えそうでかつ合いそうな広報という道に進み、その中でもさらにもがきまくって、この近年でちょっとずつ解放されつつある気がします。
これは本当にある意味「呪い」みたいなものだなと思います。
「呪い」を解くには、本来の大事にしたいものや、個々がもつ「よさ」に目を向け、のばしていくということ。
私には周りや常識を跳ね返せるほど激しい強さはないけれど、「変人」=「かぶき者」として心のままに進んでいきたいなと思える一冊でした。
小学校高学年の頃の私に手渡してあげたいなぁ。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
