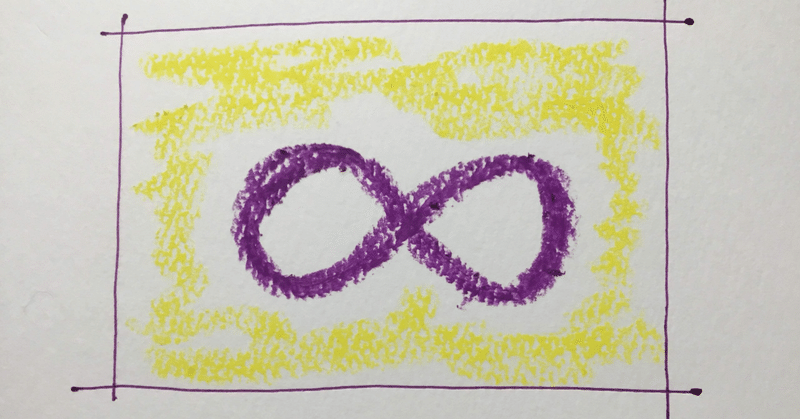
読み聞かせの際に、どのように子どもに問いかけるか?「ブルームの分類法」を参考に その3
前回まで、「ブルームの分類法」とはなんぞや、また、どのように子どもへの読み聞かせの際の問いかけに活用できるかについて、考えてみました。
今回は、その「ブルーム」シリーズ最終回です。
お話がない本にも…問いかけ次第で使い方は無限大!
子どもに好きな本を選ばせると、図鑑のようにお話がない本を持ってくることもありますが、その場合も、問いかけの仕方によって、楽しみ方が無限に広がるのではないかと思います。
例えば、「ノンタン・タータンの遊び図鑑」(偕成社)と言う本は次男(4歳)のお気に入りの1冊ですが、ある時期、毎晩のように食べ物の絵が描かれているページを読みたいとせがまれることがありました。「読む」と言っても、このページには文字はほとんど書かれておらず、食べ物の絵が描かれているのみ。はじめは、次男が絵を指さして、私がその名前を言って..の繰り返しだったのですが、次第に、絵に基づいて、親子(長男も含めて3人)で毎回クイズや質問を出し合うのが習慣となりました。正直に言うと、「またこのページか…まさにデジャヴュ!もうネタがない」とゲンナリする事もありましたが、「ブルームの分類法」に基づいて質問のレベルを行き来することで、意外にもクイズや質問のネタは尽きず、本のポテンシャルは問いかけの仕方次第(素材の料理の仕方次第、とでも言うのでしょうか)であると痛感したものです。
とりわけ、食べ物というのは、子どもにとって身近であり関心の高い題材であるため、「「あ」がつく食べ物」あるいは「「りんりんりんりんりん」ってなあに?(答えは「りんご」)と言った言葉にフォーカスした問い/なぞなぞから、「次に日本に行ったら食べたい物ランキング」や「(家族のメンバー)が好きそうな食べ物」と言ったような個人化した問いかけ、さらには「体にいいランチ。5グループの食べ物を一つずつ選ぶ(現地校で栄養バランスについて学んだ時に、穀物、タンパク源、ビタミン等、5グループが揃った食生活を送るよう習ったそう)」とか「意志力が必要な食べ物(「がまくんとかえるくんシリーズ」の「クッキー」というお話より。あまりに美味しそうで誘惑に抗いがたいクッキーをこれ以上食べないように、意志力が必要だと話したことから)」と言ったように、他の作品や学校生活とのつながりを持たせて問いかけることもできるかと思います。
とはいえ、楽しむことが一番。臨機応変な対応を!
とはいえ、もちろん四六時中「ブルームの分類法」といった事について考えながら日常生活を送っているわけではもちろんなく(!)、実際には、読み聞かせの際の問いかけの量も内容も、その日の子どもと自分自身の気分や体調、本の長さや内容によって、臨機応変に行うようにしています。ほとんど問いかけをせずに、私が一方通行的に読んだり、逆に、子どもに本を読ませて私は聞き役に徹することもあります。親子ともども、「毎回絶対にこのようにやらなければいけない」と身構えず、あくまで楽しむことが一番大切だと思っています。
「楽しむ」と言う点では、読み聞かせの際にひたすら「ナンセンス」を極めるという場合もあります。例えば、いつも読んでいる本の文末を全て否定形で終わらせる(例えば、「おじいさんは山へしばかりに行き…ませんでした。おばあさんは川へ洗濯に行き…ませんでした。」)、子ども達から募集して登場人物の名前を変える(例:さる->さru "ru"の発音を英語風に)、頻出するキーワードを反対から読んでみる(例:きびだんご->ごんだびき)、本の登場人物の声色をいつもと全く違うものに変えてみる(例:鬼の声が意外にかわいい、鬼は実は物語に描かれているほどそんなに悪いやつではないのかもしれないと思わせてみる)、あえて絵が示す内容と全く異なるストーリーを作ってみるなど、思いっきりふざけてみるのも、本がもたらしてくれる楽しみ方の一つだと思っています。
継承語に限らず、家庭内で子どもが母語や外国語を学ぶ過程を親が見守れるのは、長いようで短い時間("Longest Shortest Time")だと言えるかもしれません。すでに、子ども達の関心は、家庭での時間から、友達との時間に移行しているなと感じることも多々あります。「読み聞かせ」と言う形で子ども達と関われるのはあと何年ぐらいなのかわかりませんが、たとえ「読み聞かせ」を卒業したとしても、本を介した家族間のコミュニケーションが続いてくれればと願うばかりです。
補足:本を媒介とした社会的対話を促すような読み聞かせの方法は「ダイアロジック・リーディング(Dialogic Reading)」と呼ばれています。その意義と効果、具体的なやり方が書かれた一般書として、「思考力・読解力・伝える力が伸びる ハーバードで学んだ最高の読み聞かせ(加藤映子、かんき出版)」という本は、やさしくかつ具体的に書かれていて、参考になるかと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
