
【4/27 #日めくりクラシック音楽 】今日はロシアの作曲家:アレクサンドル・スクリャービンの命日(1915年)~交響曲第4番「法悦の詩」~
こんにちは、名古屋クラシック音楽堂(@nagoyaclassicca)です。今日の #日めくりクラシック音楽 では、1915年4月27日に命日を迎えたロシアの作曲家、アレクサンドル・ニコラエヴィチ・スクリャービンの交響曲第4番「法悦の詩」をご紹介します。
アレクサンドル・ニコラエヴィチ・スクリャービンとは?

アレクサンドル・ニコラエヴィチ・スクリャービン(1872-1915)は、ロシアの作曲家、ピアノ奏者。
生地のモスクワ音楽院に学ぶ(同期生にラフマニノフがいる)。モスクワやヨーロッパ各地で演奏活動を繰り広げる一方、ショパンの影響の濃い《ピアノ協奏曲》(1897年−1898年)などを発表。
1898年母校のピアノ教授となるが5年後に辞任。このころからニーチェに傾倒し、作品は徐々に複雑な書法をとった。
1905年ブリュッセルでロシアの神秘思想家H.P.ブラバツキー〔1831-1891〕の神智学を知り、神秘主義的傾向を深める。
以後,いわゆる〈神秘和音〉を含む独自の和声語法の探求を進め,管弦楽曲《法悦の詩》(1905年−1907年)や《ピアノ・ソナタ第5番》(1907年)、《同第9番・黒ミサ》(1911年−1913年)などが書かれた。
第5番以降のピアノ・ソナタはすべて単一楽章となり、ソナタ形式の枠組みも崩れる。
また管弦楽曲《プロメテ》(1908年−1910年)では、鍵盤の操作によって色彩を映し出す〈色光オルガン〉を用いて和声と色彩との統合が試みられ、未完に終わった《神秘劇》ではこれに舞踊や香りをも加え、五感すべての融合が意図されている。
アレクサンドル・スクリャービン:交響曲第4番「法悦の詩」
『法悦の詩』は、1908年にアレクサンドル・スクリャービンが《交響曲第4番》作品54として完成させた作品。
スクリャービンが神秘主義に傾倒した後期の代表作として知られている。日本語の「法悦」は意訳であり、原語のまま「エクスタシー」として理解するとよい。
この標題の意図については、性的な絶頂を表すと考えるほかに、宗教的な悦びを表す、あるいは両者を包含しているという解釈もある。
この曲が発表された当時、あまりにも官能性に満ちていることから、ロシア正教などから強い批判が上がったという。
オルガン、ハープ、チェレスタなどを含めた四管編成の大オーケストラによる単一楽章の楽曲であり、自由な形式の交響詩とみなされていた時期もあるが、拡張されたソナタ形式をとっている。
それまでの3曲の交響曲とは異なり、決まった調性を持っていない。その代わりに、神秘主義に傾倒して以降のスクリャービンの作品で頻繁に用いられる神秘和音を完成させた。
それでは、今日はこの辺で🎶
「#なごクラ」という東海4県のクラシック音楽演奏会をご紹介&徹底応援するプロジェクトを始めました。
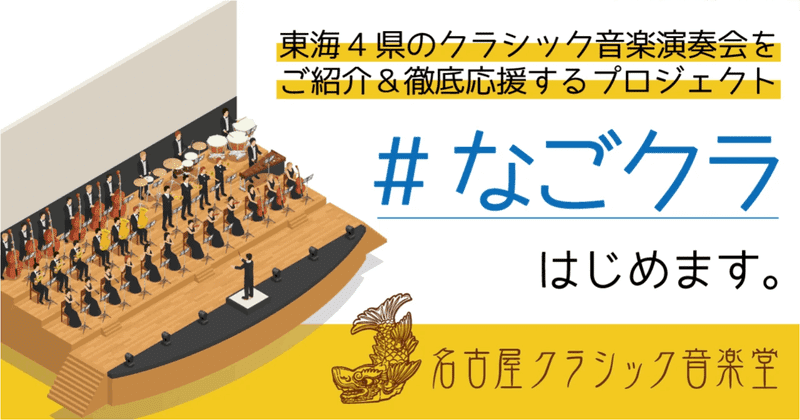
このプロジェクトは東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)で開催されるクラシック音楽の演奏会・コンサート・リサイタル・講演会などをひたすらご紹介するというもの。
まずは、名古屋クラシック音楽堂のTwitterにて、だいたい2週間~1カ月先のクラシック音楽演奏会の情報を、ハッシュタグ #なごクラ を付けてツイートしていきます。
聴きに行くコンサートの計画を立てるのにご活用ください。またクラシック音楽演奏会の主催者やホール、演奏家など関係者の皆様からも情報を募集しています。掲載ご希望の方は名古屋クラシック音楽堂のTwitterのDMでご一報ください。
名古屋クラシック音楽堂はTwitterでもクラシック音楽の情報を発信しております🎶

名古屋クラシック音楽堂のTwitterでは、『クラシック音楽を誰もが楽しめる原動力になる』をビジョンとし、名古屋を中心とした東海4県のコンサートや演奏家の情報 #なごくら 、その日にちなんだ作曲家や演奏家の曲を紹介する #日めくりクラシック音楽 、人気のクラシック音楽動画やクラシック音楽関連ニュースを毎日ご紹介。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
